インタビュー
イノベーション研究 第23回 大阪ガス
大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- 公開日:2014/11/26
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第23回は、大阪ガス株式会社の松本毅氏にご登場いただきます。松本氏は、大阪ガスのイノベーション推進を、オープン・イノベーションという方法で進めます。
オープン・イノベーションは、古くは通産省が主導した産官学のさまざまな国家プロジェクトから、近年ではP&GのConnect & Developmentがその代表的な例として挙げられることが多い概念です。カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロウ氏によって提唱されましたが、その新しさ故、まだ精緻な定義が確立されておらず、世界中で研究が盛んに行われています。
そんなオープン・イノベーションを、組織の名称にして、2008年以来徹底して推進しているのが、松本氏です。どんな背景で、どんな考え方で、実際にどう推進して、どんな成果が出ているのか? 未開・未踏の分野であるからこそ、興味は尽きません。では早速、松本氏のイノベーションストーリーをご覧ください。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- オープン・イノベーションの3つの成果 スピードアップ、レベルアップ、コストダウン
- ニーズを把握し、マッチング会にかけ 提案されたシーズを精査、部門に伝達
- 5年間で286件のニーズを社外公開 提案、活用に繋がったのが140件
- 母体となっているのはMOTスクール
- IH調理器でガス業界が息も絶え絶えに イノベーションを起こす新たな仕組みを
- 最初のブレークスルー 食べ物の旨みを科学的に測定する
- 技術開発部門の探索依頼を待たず 自らテーマを創出する試みに着手
- 総括
オープン・イノベーションの3つの成果 スピードアップ、レベルアップ、コストダウン
イノベーションといえば、組織内の知を組み換え、まったく新しい価値を生み出すこと。そんな認識が世間の通り相場ではないだろうか。発表されるまでは、社内でも一部の人しか知らない極秘プロジェクトだった……。筆者も、そんなイノベーション事例をいくつも取材してきた。
がしかし、そうした“常識”が昨今、壊れつつある。イノベーションを起こすために足りないものは何か。自分たちは何を必要としているか。そうした「課題=ニーズ」を大胆にも社外に公開した上で、それに応えてくれた他組織の力を借りて成し遂げる事例がにわかに増えているのだ。名付けて「オープン・イノベーション」という。
それに最も力を入れている企業の1つが、大阪ガスだ。2008年9月から模索し始め、2009年4月から具体的なニーズの社外公開を開始、2010年4月には同社技術戦略部内にオープン・イノベーション室という組織まで設けた。
その仕事に一貫して取り組んでいるのが、開設以来、室長をつとめる松本毅氏である。室員は他に2人いるが、いずれも兼務であり、専任者は松本氏のみだ。本人が話す。「背景には製品ライフサイクルの短縮と技術の複雑化があります。従来のやり方では、高性能の製品を市場にタイミングよく投入していくことが非常に難しくなったのです。自前にこだわることをやめ、これまで関係がなかった異分野・異業種のなかから最適な知のパートナーを見つけ出すことが、今ほど求められている時代はありません」
オープン・イノベーションの効果についてはこう説明する。「技術開発や製品化のスピードアップ、製品の性能のレベルアップ、コストダウンという3つのメリットが享受できます。社内だけでは成し遂げられないイノベーションが実現、あるいは促進されるわけです」
ニーズを把握し、マッチング会にかけ 提案されたシーズを精査、部門に伝達
では、同社はどのような仕組みでオープン・イノベーション(以下、OI)を推進しているのか。
舞台となるのは、グループ会社も含めた同社の技術開発部門である。具体的には、業務用および工業用の技術開発を行うエネルギー技術部、同家庭用の商品技術開発部、同インフラ用の導管部、基礎研究を行う研究所など、8組織に分かれる。
やり方は結構アナログ的だ。それらの組織内で行われる幹部会議から、その下のチーム単位の会議、グループ単位の会議に至るまで、松本氏自らが出向き、今何に困っているのか、それはどんな技術や研究があれば解決するのか、をヒアリングして回るところからすべてが始まる。加えて、OI室の活動内容と実績も説明する。大阪ガスではこうした組織横断型の会合を「キャラバン」と呼ぶ。もちろん、このキャラバンを実施しなくても、技術開発部門からOI室に技術探索依頼が入ることもある。
そうやって収集した課題(ニーズ)を東京、大阪などで定期的に開く技術マッチング会にかける。東京では電気通信大学の産学官連携センターの主催、大阪では大阪商工会議所の共催という形だ。「集まっていただくのは、企業、大学、そして公的研究機関に勤務するエンジニアや研究者です。さらに重要なメンバーがいます。技術の目利き役となってくれるコーディネーターです。東京と大阪の2拠点に関しては、事務局に、企業や大学の研究室を100集めるだけではなく、優秀な目利き役100人も集めてくれるようお願いしています。100組織の技術を知り尽くしている目利き役を100人集めることができれば、100かける100で合計1万組織にわれわれのニーズが伝わることになるからです」
こうした目利き役は行政や大学から報酬を得て大手企業に紹介することをミッションとしているため、積極的に紹介していただける。したがって、企業が手当を払う必要がない。会場に関しても、東京は電通大、大阪では大阪商工会議所が用意してくれる。
それ以外に、OI室が独自に特許や文献等を調べ、あるいは既存の人脈を使い、適切な技術や研究成果を保有していそうな企業や大学、研究機関に当たりをつける。「この仕事を担当する前は、大阪ガスグループで、日本発のMOT(Management of Technology=技術経営)スクールの立ち上げとその事業化の仕事に従事していたので、技術の目利きやコーディネーターの知り合いが国内外にたくさんおり、その人脈が大いに役立っています」
そうやって得られたシーズ(技術や研究)をOI室が精査し、有望なものを技術開発部門に知らせる。各エンジニア、研究者が興味を示せば、引き合わせをして共同開発や共同研究がスタートするという仕組みだ。
5年間で286件のニーズを社外公開 提案、活用に繋がったのが140件
この仕組みがスタートした2009年度から2013年度までの5年間で、286件のニーズが社外に公開され、それに対して外部から約3000件の提案があった。それらをOI室が精査した結果、3分の1にあたる約1100件を社内に紹介、うち140件が何らかの活用に繋がっているという。最初の286に対して140だから半分だ。かなり高い確率といえるだろう。「今まで自分たちが見つけられなかったような技術を見つけてくれた、欠けていた“ピース”がはまり、頓挫していた研究が再スタートできた、といった声が寄せられ、大変喜ばれています。2012年度までは研究開発段階のニーズに対するシーズを探るものが多かったのですが、2013年度からは商品開発に代表される事業化に向けた段階のものが主流になってきました」
商品化の代表例が、新たな水素製造装置の開発だ。
大阪ガスは独自のコア技術である触媒技術を生かした「HYSERVE(ハイサーブ)」と名付けた水素製造装置を製品化していた。新たなエネルギー源として水素に世界的な注目が集まるなか、このシリーズの輸出を考えたが、グローバル市場には手ごわいライバル社の製品がひしめいている。そこで勝つためには、装置自体をもっとコンパクト化してコストダウンを図る必要があった。
社内でプロジェクトを立ち上げ、その課題に挑戦したが、なかなかうまくいかなかった。10%程度のコンパクト化しか実現できなかったのだ。「何とかならないか」と、OI室に問い合わせが入った。
松本氏が担当部署に出向き、ヒアリングを行ったところ、熱交換器が鍵を握っているらしいということが分かった。熱交換器の性能が上がればコンパクト化できる。また、1つの装置に10台以上入っている熱交換器の数も減らすことができるので、目標が実現できそうだということが分かったのだ。
熱交換器のイノベーションというニーズが社外に公開されると、ある中小企業が手を挙げた。OI室のお膳立てによるマッチングが成功、共同開発が始まった。
開発は成功した。従来より性能が向上してコンパクト化に成功した。その結果、10台以上必要だった熱交換器の数を、大幅に減らすことができた。。結果、コストが従来の50%となり、大きさも40%減が実現したのである。新製品は「HYSERVE-300」と名付けられ、2013年10月から販売されている。また、建設中の新しい水素ステーションにも搭載される予定だ。
母体となっているのはMOTスクール
このOI室は、どのような経緯で設置されたのだろうか。
先ほども少し触れたが、それは室長をつとめる松本氏のキャリアと大きな関係がある。
松本氏はエンジニア出身であり、大阪ガス入社後は凍結粉砕機の開発や薄膜型ガスセンサーの研究開発などに携わった。特に後者は高性能化による改善改良を実現して誤報対策には成功した。ただ、この新規事業化は、技術は素晴らしかったのに、パートナー選びに失敗、新規事業としては花開かなかった。その失敗から、松本氏は「技術を確実にビジネスに結びつけるための人材育成」の必要性を痛感、社内に提案したのがMOT教育の実施である。
幸い、技術統括のトップの思いとも重なったこともあり、とんとん拍子に話が進み、2002年10月、日本初のMOTスクールが大阪市内に立ち上がる。運営主体は大阪ガスの子会社、アイさぽーとで、松本氏は同社取締役MOT事業本部長となった。
このスクールは企業内大学ではなく、受講生は社内、社外どちらでもよい。しかも、教鞭を執る講師は、MOT概論を担当する松本氏を除き、ほとんどが他社あるいは大学の研究者たちだった。「私が全体のカリキュラム作成と、担当講師の人選を担当しました。そういう意味ではオープン・イノベーション型でした。しかもここで培ったネットワークと目利きの力が今、大きく役立っているわけです」
IH調理器でガス業界が息も絶え絶えに イノベーションを起こす新たな仕組みを
この事業があたり、2004年に東京校、2006年に名古屋校が相次ぎ開校。全国10校体制にして、MOT教育を日本にきちんと根付かせようと、福岡校開校の準備に取り掛かっていた矢先、松本氏は本社に呼び戻され、技術戦略部への異動を命じられる。2008年9月のことである。「その頃は、電力会社のオール電化攻勢で、IH(Induction Heating=電磁誘導加熱)調理器の売れ行きが非常に伸びていて、ガス業界が惨憺たる状況でした。異動の理由は、MOTで他社のイノベーションを支援している場合ではない。大阪ガス社内でイノベーションを促進させる仕組みを考えろ、ということでした」
MOTスクールでも、イノベーションの講義を重視していた。それも、オープン・イノベーションの考え方を複数の研究者やコンサルタントが行っていたのだ。MOTスクールで教えられていた内容を自分が実践すればいい。松本氏はこう考えた。
ただ最初は、社内になかなか理解してもらえなかった。2つの壁があった。1つは、「オープン」なんて滅相もない、自分たちですべて実践、解決することが組織の地力を強くするという内製重視の考え方である。特に研究部門にそういう認識が強かった。もう1つ、大学への基礎研究委託に代表されるように、「オープン・イノベーションはすでにやっている」という反応もあった。
逆風のなか、とにかく実績を出すしかなかった。MOTスクールの社内修了生に会っては、課題を聞き出す。外部の知を使ってそれを解決した。そんな実例を積み重ねつつ、その成果を社内にキャラバンする活動が続いた。
最初のブレークスルー 食べ物の旨みを科学的に測定する
転機がやってきた。評判を聞きつけたエネルギー技術部の部長がやってきて、こう相談を持ちかけたのだ。「ガスで調理した食べ物の旨みを科学的に評価できないか。それができれば、IH調理器に一泡吹かせてやることができそうだ」
松本氏はまず当たりをつけた。食べ物の味の評価手法は豊かな食文化をもつヨーロッパにありそうだと。ドイツに技術開発を委託している企業があり、その日本支社が東京にある。その社長もMOTスクール時代に知り合い、かなり親しかった。ヨーロッパの技術探索を依頼したところ、こんな答えが返ってきた。「松本さん、灯台下暗しですよ。九州大学に、世界初の味覚センサーを作った都甲潔(とこう きよし)という有名な教授がいます」
すぐに繋いでもらい、相談元の部長と共に九大に向かった。教授と部長は意気投合し、その場で共同研究契約を結んだ。間もなく、ガス調理をした食べ物の旨みが科学的に実証できるようになった。現在では、同社のエネルギー技術研究所内に、旨みと健康性という二面からガス調理の効用を研究する「おいしさ・健康調理ラボラトリー」が開設されるところまで、おいしさに関する研究は発展している。
技術開発部門の探索依頼を待たず 自らテーマを創出する試みに着手
2014年度から、OI室は新たな課題に取り組んでいる。技術開発部門からの提案や探索依頼を待たずに、自分たちでイノベーションのテーマを作ろうとしているのだ。「研究開発部門も自分たちでテーマを作ろうとしていますが、今まで散々やってきた周辺領域でやってしまう。そうしたやり方では駄目なんです。自分たちが強みとする領域でテーマを作り、商品化までこぎつけたものの、市場性がまったくない。そういうリニアモデルによる失敗が非常に多い。われわれが模索しているのはそれとは対極のやり方で、ユーザー基点のイノベーションを目指したテーマ創出なのです」
具体的に何をやるのかと松本氏に問うと、大阪ガスを含め、異業種の研究者やエンジニアが一堂に会し、最初に技術ありきではなく、社会に生み出す新しい価値とそれを実現するビジネスモデルから議論していく「異分野ワークショップ」だ、という答えが返ってきた。「これこそ究極のオープン・イノベーションです。本田技研工業の『ワイガヤ』(役職や年齢を超えて、気軽にワイワイガヤガヤ話し合うこと)は有名です。うちでも相当やっていますが、それは社内ワイガヤ。私がこれからやろうとしているのは、『異分野ワイガヤ』です」
ここまで来ると、一企業の範疇を超え、国家戦略にも繋がる話に思えてくる。アベノミクス第三の矢である成長戦略の核がまさにイノベーション創出だ。大阪ガスが仕掛ける異分野ワイガヤから企業横断型イノベーションの成功例が1つでも、そして一刻も早く現れることを期待したい。
総括
松本氏のオープン・イノベーションのストーリー、いかがでしたか。
いつものようにイノベーション研究モデルの領域をイメージしながら総括をします(図表01参照)。
図表01 イノベーション研究モデル
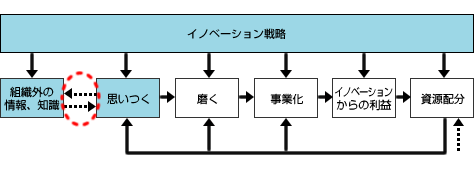
注目するのは「イノベーション戦略」、「組織外の情報・知識」と「思いつく」の間の領域の2つです。では、順を追って松本氏のオープン・イノベーションのストーリーを振り返ってみます。
閉じていることとは?
閉じていることの強さ
松本氏が実践しているのはオープン・イノベーションです。その本質は『開き』『繋がる』ということにあります。その対極は『クローズド』であり『閉じている』ということでしょう。私はNHKの「プロジェクトX」をワクワクしながら観ていた世代ですが、そこでは、『ヤミ研』とか『under the table』といった『クローズド』概念のなかでのイノベーションが数多く見られます。組織の公式の承認がなされず、限られた情報や知識しか活用できず、潤沢な資金などもってのほか。閉じた世界のなかでコミュニケーションが繰り返されます。
そのほとんどのエピソードに共通するのは、組織からある種見放されたことからくる逆説的なエネルギーの大きさでしょうか。「いつかは絶対に成し遂げてやる」「冗談じゃない。俺はそんなことのために研究してきたわけじゃない」「誰がなんと言おうと、私の考えは変わらない」「これこそが、私のライフワークだ」「自分のためじゃない。人のため、社会のため、そして未来の子供たちのためにやっているんだ」こんな心の叫びが錯綜していたと思います。
執念。いえ、執念をも超え、情念の域に達しているほどのエネルギー。閉じられていることで、個人の内部に根ざすエネルギーが逆に激しく昇華していくようなイメージが湧きます。閉じていることは強い。合目的的で共通の利害がある場合は尚更でしょう。
では、なぜ松本氏はオープン化に舵を切ったのでしょうか? 松本氏は製品ライフサイクルの短縮と技術の複雑化が背景にあったと語っています。消費者のニーズやウォンツは多様化し、十把ひとからげの商品・サービスでは市場は受け入れてくれません。ITは加速度的に進展し、顧客とのコミュニケーション手法は簡便化してその容易性を増し、一方、必要な技術の領域は飛躍的に増えています。企業一社が単独で保有できる資源は制約され、活用できる技術は急速に限定的になっています。技術を、【組織が労働力、資本、原材料、情報を、価値の高い製品やサービスに変えるプロセス。製造・マーケティング・投資・マネジメントなども包含する】と捉え直すと、尚更その傾向が強まっていることに気付かざるを得ません。
閉じていることはある種の強さを生みますが、21世紀の現代においては閉じているだけでは前に進めないのです。
開かれていることとは?
開かれた共同体を創る
では、開かれているということは何を意味するのでしょうか?
開くことは、繋がることともいえるでしょう。では何が繋がるのか? オープン・イノベーションの場合、社内のニーズと社外の技術が繋がる、ということになります。組織内外の知が繋がり、組み換えされ、新しい知が創出され、まったく新しい価値が創出されるのです。
では、組織内外の知が繋がるとは一体どういうことなのか? それは、組織内外の脳が繋がるということだと理解します。ひとりの脳を点とイメージしてみます。点は点に過ぎない。ふたりと繋がると線ができます。脳と脳が繋がり、線が生まれるのです。では、3人だとどうでしょう? 3人の脳、つまり点が繋がると、三角形ができます。三角形の面積は、お互いの距離が離れていれば離れているほど大きくなります。社内の同じ目的や目標をもち、同じ意思決定の基準値のなかで働いている人同士の繋がりよりは、社外の人との繋がりの方が『離れている』ということができます。離れている同士が繋がると、その三角形や多角形の面積は飛躍的に大きくなります。開かれているということは、閉じていることと異なる意味や強さをもっているということです。
松本氏は、こういった『開かれている』状態がもつ強さを、ニーズと技術の繋がりを超えて、課題設定そのものにも活用しようとしています。『異分野ワイガヤ』と名付けられたそれは、異業種・異分野のエンジニアや研究者、マーケッターなどの、点ではなく線、線ではなく面、面ではなく立体の脳の繋がりを創ろうとする試みともいえるでしょう。そこでは個人や企業の立場や制約を超えた、今後の日本や世界を見据えた談論風発でワイガヤの議論がなされていくに違いありません。まさに野中郁次郎教授の提唱するイノベーションを育む『開かれた共同体』を、極めて実践的な方法で推進しているといっても過言ではないでしょう。
オープン・イノベーション
それは『慣行の外に出る』仕組み
イノベーションの開祖はオーストリアの経済学者、ヨーゼフ・シュンペーターと言われています。今から100年以上前の1912年に、その著書『経済政策の理論』のなかで、イノベーションとは新結合である、と述べています。と同時に、新結合の遂行のため、慣行の領域の外に出る必要性を説いています。その際に、固定的思考習慣に陥ることや、普及の際に社会の抵抗を受けるような困難に直面する、とも語っています。
同様のことはほとんどの経済学者、経営学者も言及しています。ドラッカーは、新事業は既存の事業と分離して組織する必要があると説明し、既存の事業とは異なるシステム、ルール、評価基準が必要だと主張しています。『イノベーションのジレンマ』のなかでクリステンセンは、「バリューネットワーク」という概念を提唱します。「バリューネットワーク」とは、企業が顧客のニーズを認識し、対応し、問題を解決し、資源を調達し、競争相手に対抗し、利潤を追求する枠組みのことです。価値の測定基準がネットワークによって異なることに気付かないことが失敗に繋がるとし、企業は需要に合わせた能力・組織構造・企業文化を形成するが、そのこと自体がジレンマに陥っていると訴えたのです。
代表的な経済・経営学者3人は、イノベーションの生成過程の特徴に関してほぼ同じことを言っています。それは、『慣行の外に出る必要性』です。
松本氏のオープン・イノベーションの活動を振り返ってみると、まさに『慣行の外に出る』ことを実践していることが分かります。自社のニーズ、言わば弱みを社外に伝えることは、慣行の外の極みといっていいでしょう。NIH(Not Invented Here)症候群に侵されていると思われる多くの日本企業にとっては、ニーズの公開など絶対にありえないことなのかもしれません。しかし、慣行のなかにいると必ず固定的習慣に陥ります。ごく自然に慣行のなかのシステム、ルール、評価基準で物事を考えてしまいます。バリューネットワークにはまり、既存の価値の測定基準ですべてを評価してしまいます。自社のフレーミングに脳が拘泥してしまうのです。
それらを取り払うにはどうしたらいいのか? そう、『慣行の外に出る』以外に方法はないのです。それを、松本氏は、大阪ガスというプラットフォームの上で、オープン・イノベーションという形で推進しているのです。
Connect & Development という概念で、近年、オープン・イノベーションを加速させている世界的に有名な企業があります。P&Gです。そのオープン・イノベーションの責任者が松本氏を訪問し、詳細なヒアリングをした上で、大阪ガスのオープン・イノベーションの方法を導入しているそうです。松本氏のオープン・イノベーション戦略は、世界から注目されているのです。大阪ガスのオープン・イノベーション自体が、オープンに日本や世界中に広がり、繋がっていくに違いありません。
【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】
PROFILE
松本 毅(まつもと たけし)氏

1981年大阪ガス株式会社入社。凍結粉砕機の開発、薄膜型ガスセンサー研究開発に携わり、技術企画室課長、人事部・担当部長を務める。日本初のMOTスクール設立。株式会社アイさぽーと取締役MOT事業本部長。2008年9月大阪ガス株式会社オープン・イノベーション担当部長。2010年4月よりオープン・イノベーション室 室長。
大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻科 招聘教授、大阪工業大学工学部技術マネジメント学科 客員教授を兼任。
一般社団法人 「Japan Innovation Network」 理事
公益財団法人 大阪産業振興機構 特別参与
大阪市イノベーション促進評議会 委員 「大阪イノベーションハブ」
京都大学デザインイノベーション拠点 フェロー
文部科学省 科学技術・学術審議会 「総合政策特別委員会」 委員
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で