インタビュー
イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- 公開日:2013/08/28
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第8回は、ソニー生命保険株式会社(以下、ソニー生命)名誉会長の安藤国威氏にご登場いただきます。なぜ、ソニーが金融機関である生命保険会社をつくったのか? なぜ、既存の生命保険のやり方とことごとく異なるやり方を選んだのか? なぜ、圧倒的に不利な闘いに敢えて挑んだのか? 安藤氏が語るこれらのなぜに対する答えこそ、今の日本に必要とされていることかもしれません。今でこそ、ソニー銀行やセブン銀行など、異業界から参入してきた金融機関は珍しくありませんが、そのことが非常に困難だった昭和50年代にさかのぼっていただき、さっそく安藤氏に語っていただきましょう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 盛田昭夫の夢、金融機関をもつこと
- サンディエゴのホテルで「これ、翻訳してくれ」
- 「余人をもって代えがたい」と盛田さんから口説かれる
- 27人 VS 35万人! 量的には圧倒的に不利だが…
- 本邦初!男性が保険を売る ライフプランナー制度
- レッド・オーシャンを尻目に 悠々とブルー・オーシャンへ
- 総括
盛田昭夫の夢、金融機関をもつこと
ソニー生命(当時はソニー・プルデンシャル生命)が設立されたのは今をさかのぼること34年前の1979年のことである。
それは二つの意味で画期的なことであった。
まず一つは、ソニーという事業会社(メーカー)が設立した金融機関だったこと。当時は金融機関に対する政府の規制が今よりずっと厳しく、護送船団方式が維持されていた。門外漢の事業会社による金融機関設立など監督官庁の大蔵省が許すはずがなく、唯一、ある流通企業が外資との合弁で設立した例があるだけだった。
もう一つは、ソニー生命のビジネスモデルが、これまでの生命保険業界の常識を180度、覆すものであったこと。当時、生命保険の営業は「生保レディ」と呼ばれる保険外交員が行っていたが、ソニー生命は、金融や経済の知識を兼ね備えた生命保険のプロフェッショナルを「ライフプランナー」と名付け、大卒男子を中途採用・育成するようにしたことだ。しかも、販売する保険商品も新しく、年齢や家族の数などによってあらかじめ決められているパッケージ型ではなく、本人や家族のニーズを汲み取って設計するオーダーメイド型のものであった。
シュンペーターによれば、イノベーションには次の5つが該当する。すなわち、(1)新しいプロダクトの導入、(2)新しい生産手段の導入、(3)新しいマーケットの発見、(4)新しい原料や半製品の導入、(5)新しい組織の導入、である。このうち、ソニー生命という会社の設立は、(1)、(3)および(5)にかかわっている。もし同社が既存生保と同じようなビジネスモデルで出発していたら、ソニーが単に新事業に進出したというレベルの“画期的なこと”に過ぎず、イノベーションとまでは言えなかっただろう。それを成し遂げたのが後にパソコンのVAIO事業などを手がけ、ソニーの社長として辣腕をふるった安藤国威氏その人である。
その安藤氏がいう。「盛田さん(編注:盛田昭夫氏。ソニー創業者の一人)は銀行をもつのが夢だったんです」と。しかし、前述したように大蔵省は認可せず、いろいろなアイデアを検討したものの、ソニー銀行は文字通り夢と消えた。ただし、銀行に限定せず、金融機関ということならば、生保、それも外資との合弁なら可能性があった。1975年、セゾングループと米オールステート社との合弁によって西武オールステート生命が現に設立されていたからだ。
チャンスは思わぬところからやってきた。1976年4月、アメリカ最大の生命保険会社、プルデンシャルの会長であるドン・マクノートン氏が当時会長だった盛田氏を訪ねてソニーにやってきたのだ。両氏は旧知の仲だった。マクノートン氏は日本進出を真剣に考え、合弁パートナーを探しに来日、どこからも色よい返事がもらえない。失意のうちに日本を去るにあたり、友人に愚痴でも聞いてもらおう、という軽い気持ちでやって来たのだった。
いきさつを聞いた盛田氏がこう言った。「うちが助けてあげてもいい」。その言葉に半信半疑だったマクノートン氏は帰りがけに役員専用エレベータに乗り込むと、すぐそばの部下にこう訊いた。「アキオは本気で言ったのかな?」
見送りのため、エレベータに同乗していた役員が耳ざとくその言葉をキャッチすると盛田氏に伝えた。それこそ相手の本気度が表われた言葉ではないか。盛田氏は間髪入れず、マクノートン氏に手紙を書いた。ぜひとも一緒にやりたい、と。トップ同士が握れば事は早い。とんとん拍子で交渉が進み、両社が日本で協力して合弁会社をつくることになったのだ。
サンディエゴのホテルで「これ、翻訳してくれ」
安藤氏がこのプロジェクトに関わったのは偶然に近かった。安藤氏は1969年にソニーに入社。念願だった最初のアメリカ赴任でニューヨークに出発したのが1974年4月のことで、途中、全米の大手ディーラーを集めたナショナル・セールス・コンベンションがサンディエゴで開かれるので、たまたま立ち寄った。宿泊したホテルに盛田氏が同宿しており、朝食後に呼ばれた。安藤氏は以前、盛田氏の直属のスタッフとして仕事をしていたことがあったのだ。
盛田氏から英語の書類の翻訳を頼まれる。安藤氏は同僚から辞書を借り、何とか訳し終えた。見慣れない単語の並ぶ保険関係の文書だった。「しかも午後から始まる会議への同席も頼まれたんです。それがソニーとプルデンシャルの間で開かれた最初のミーティングだったのです。当時は保険にまったく関心がありませんでしたが、後で考えると因縁めいたものは感じました」
「余人をもって代えがたい」と盛田さんから口説かれる
が、そこからストレートに安藤氏がプロジェクトに関わったわけではない。プロジェクト自体、出だしはよかったものの、進行は困難を極めた。社内でも限られた人しか存在を知らされない極秘プロジェクトだったが、何より、国籍も業種も違う企業同士が結婚し子どもを産むわけである。さまざまな壁が立ちふさがった。プロジェクトリーダーはソニー本体の役員クラスがつとめたが、遅々として進まず、3人も入れ替わった。最初のミーティングが開かれてから3年半が経過しようとしていた。
実は4人目となったのが安藤氏だった。盛田氏じきじきの指名だった。「当時、私はアメリカにいたので、世話役として会議によく出席していたのです。その時、ソニーの主張のほうがおかしいと思えば、プルデンシャル側に立って話をすることがよくありました。それで、ソニーの中で唯一話がわかるのはあいつしかいない、とプルデンシャルが私を指名し、盛田さんもその意見に納得、『君しかいない。余人をもって代えがたい人材なんだ』という言葉で私を口説いたのです」
内心、「まさか保険なんて」と思ったが、トップからそこまで言われれば受け入れるしかない。当時、安藤氏は36歳、本社に戻れば課長になれるかなれないか、くらいのキャリアだった。安藤氏が話す。「私がやるならば、本来の生命保険の価値をお客様にしっかり伝える、世界に二つとない、ソニーにしかできない生保会社を作りたい、と思いました」
27人 VS 35万人! 量的には圧倒的に不利だが…
安藤氏はプルデンシャル側の代表者、坂口陽史氏と協力してプロジェクトを進めることになった。大蔵省からの内認可を得て会社が設立されたのが1979年8月のこと。営業開始が1981年4月だった。マクノートン氏の最初の来日から実に5年余りが経過していた。安藤氏は代表取締役常務に就任。開業前の半年間、安藤氏はアメリカに渡り、内勤事務から販売の現場、支社など、プルデンシャルの現場を肌で体感している。この体験が後で非常に役立った、と安藤氏は振り返る。
営業開始日の4月1日、同社がメディアに掲載した広告が同社のあり方を象徴しているといえるだろう。右手にカバン、左手に書類を抱えたスーツ姿の男性が中央に立ち、その上に、「きょうから生命保険が変わる。ライフプランナーが変える。」というコピーが躍る。「当時、日本の既存生保は『ザ・セイホ』と呼ばれ、営業を担当する生保レディが35万人もいました。それに対して全員男性のわが社のライフプランナーはたったの27人。ちっぽけな蟻が巨象に戦いを挑むようなものでした」
本邦初!男性が保険を売る ライフプランナー制度
安藤氏は生命保険の何を、どう変えようとしたのか。「生命保険は購入したらすぐに役立つものではありません。むしろすぐに役立たないほうがいいのかもしれませんが、いつかは必ず役立つ。その時の生命保険の価値をどう最大化するか。そのためにはお客様のニーズをよく聞いて、個別に商品を設計する必要があるのです。ところが、それまでの生命保険は、そうしたお客様の個別事情はあまり考慮されず、パッケージ製品を売るようなものでした。いわば、商品の中身に納得し“理”で購入するのではなく、営業員の“情”やおつきあい、横並び意識で購入するイメージです。その構造を変えるために、ライフプランナーというプロフェッショナルを誕生させたのです」
ライフプランナーとなれるのは当時は4大卒の男性のみ。他業界で営業実績のある人材をヘッドハントして採用した。洋の東西を問わず、保険外交員は「回転ドア」と言われる。入る人がいたら出ていく人がいる、人の入れ替わりが激しい業界だった。ソニー生命のライフプランナー制度はこの“常識”にも抗ったものだ。「ライフプランナーは社員ですが、単なるサラリーマンではなく、起業家精神をもった一人のプロフェッショナルとして遇しています。会社の中の部下の多さではなく、お客様への貢献度で報酬と地位を決定する。スポーツ界では監督より高い年棒をもらっている選手がいるのが普通ですが、それと同じ構造になっています」
男性が保険営業に携わる。これは当時の生保業界にとって常識外れだった。「『男性はマネジメントが難しい。何が起こるか分からない』。業界の人は異口同音に言いました。『安藤さん、正気ですか』と。その時に私は成功を確信しました。この人たちは時代の変化をまったくわかっていない、こういう新しい価値を提供するやり方を考えたこともないのだ、と思えたからです」
レッド・オーシャンを尻目に 悠々とブルー・オーシャンへ
安藤氏が仕掛けたイノベーションはみごと実を結んだ。ソニー生命はライバルひしめくレッド・オーシャンではなく、悠々自適の航海が可能なブルー・オーシャンに漕ぎ出すことができた。業績も順調で、今や大手生保の一社に数えられるようになった。27名で出発したライフプランナーは今や4000名を超す大所帯となった。ライフプランナーという言葉も単に生命保険の販売を超えて、長期にわたって個人や企業に対するリスク管理のプロフェッショナルを意味する言葉として定着してきているが、実はソニー生命およびプルデンシャル生命のみが使える登録商標なのだ。
ソニー生命はなぜ成功したのか。「保険に未知なソニーと日本に未知なプルデンシャルが一緒になったからではないでしょうか。未知と未知の掛け合わせが大胆な発想を生み、業界の常識を覆すすばらしい結果を生んだのです」
イノベーションを難しく考える必要はない。それは「常識外れ」の別名なのだ。
総括
安藤氏のソニー生命のイノベーションストーリー、いかがでしたか。
いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で安藤氏の話を振り返ってみたいと思います。まず注目すべき領域は、事業化の領域です。ソニー生命の基盤となったのは、米国のプルデンシャル生命です。その意味では全く新しいものをオーガニックに思いついた訳ではありません。但し、日本にそれまでなかった新しい概念の生命保険を業種を飛び越えて日本に導入する過程はダイナミックです。
そして、事業化を根底で支えたのが、ソニーのイノベーション戦略です。ただそれは、戦略というものではなく、寧ろ自らの存在価値のようなものかもしれません。この2つの領域で俯瞰すると共に、そこから得られるインプリケーションを考えてみたいと思います(図表01参照)。
図表01 本事例の仮説モデルでの該当要素
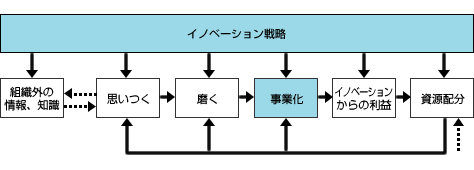
天使の前髪を掴む
準備している人にはチャンスは訪れる
天使に後ろ髪はない。あるのは前髪であり、常に準備している人にチャンスは訪れる。ダ・ビンチの言葉ともアメリカの諺とも言われるこの有名なフレーズを、安藤氏とソニーは体現している。元々プルデンシャル生命保険の会長と旧知の仲だった盛田氏の存在は大きいが、日本進出の際のエレベーター内でのエピソードや、サンディエゴのホテルでの盛田氏の将来ある若手に敢えて自らの夢の実現を託す決断、余人をもって代えがたいと口説かれることも、正になるべくしてこうなった因縁を感じざるを得ない。そのチャンスを最大限活用し、最初は「保険なんて」と思っていた安藤氏も徹底的に考え抜き、実行し、いまやソニーの営業収益の多くを稼ぎ出す存在になっている。経営学にifは禁句だが、「もしソニーグループにソニー生命や他の金融会社が存在していなかったらソニーは今頃どうなっていただろう?」ということを考えてしまう。それほど、経済成果をもたらす革新、即ちイノベーションとしてのソニー生命の存在は大きいといえよう。
銀行をもちたかったという盛田氏の想いがあったからこそとはいうものの、そのチャンスを活かしきった安藤氏は、正に天使の前髪を掴んで離さなかったのだろう。
事業化に際し、出来上がった構造に注目
安藤氏は、生命保険の本質をお客様一人ひとりの役立ち度の最大化と置いている。そのためには、顧客接点でのコミュニケーションの内容を根本的に変える必要があった。そして安藤氏は業界の構造を変える新たな事業化の取り組みを始める。ライフプランナーという制度が正にそれを象徴している。パッケージではなく個別。情ではなく理。女性ではなく男性。契約社員ではなく正社員。部下の多さではなくお客様への貢献度。
35万人もの圧倒的顧客接点をもっていた既存の生命保険会社にとっては、業界の構造自体を覆すことは出来なかった。なぜならそれは自己否定につながるから。そのことは、ライフネット生命会長の出口氏が、日本生命の中でネット生保を創ることが出来なかったことと同根だろう(本連載第6回参照)。
注目すべきは、かつての生命保険のように、構造が出来上がっている(ように見える)業界が日本中いや世界中にあるということだ。総務省の産業分類を参照すると、農業、林業から始める日本の産業は、漁業、鉱業・砕石業・砂利採取業、建設業、製造業、電機・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業などとなっている。
どうだろう? 完全に構造が出来上がっていると思われる業界はないだろうか? 改めてしげしげとこの分類を眺めていると、正にイノベーションの可能性を感じざるを得ない。そして、安藤氏に代表される多くの日本の起業家たちが、異なる業界に進出し数多のイノベーションを興している。その結果今の日本があるといっても過言ではない。チャンスは正にこの瞬間にあるといえるだろう。
ドメインを決めない
ソニーはイノベーションの場
戦略とは、顧客・顧客価値を決め、収益構造や競争優位を確立し、組織を創り、人を動かして推進していくことといえよう。その前提として事業立地を決めなければならない。どの分野で事業をするのかを決めないことには、戦略は推進しようがないことは自明だ。
しかし、イノベーションの苗床としてのソニーは違った。それは社名変更をする際のエピソードに表われている。ソニーが東京通信工業株式会社から社名変更したのは1958年。今から半世紀以上前のことだ。社名は、音『SOUND』や『SONIC』の語源となったラテン語の『SONUS (ソヌス)』と、小さいとか坊やという意味の『SONNY』が由来という。またそれは、簡単な名前で、どこの国でもだいたい同じように読めて発音できることが大事、ということで考案されたそうだ。
終戦直後に設立され、その僅か12年後に世界を見据えて大胆な社名変更をしたソニー。社名変更の理由を尋ねられると盛田氏は、「われわれが世界に伸びるためだ」と答えたという。社名の案として、ソニー電子工業とかなんとか電気というものもあったが、「断固、ソニー株式会社でいくべきだ」と譲らなかったのは盛田氏本人だった。そこには、世界に雄飛する会社のイメージと共に、業種・業界に縛られないソニーの精神が宿っているのだろう。
盛田氏は銀行を持つのが夢だったと前述したが、なんとか電気やソニー電子工業と社名変更をしていたら、電気や電子という言葉に縛られ、金融機関としてのソニー生命の誕生はなかったかもしれない。
安藤氏は言う。「ソニーとは自由な精神であり、独創(オリジナリティ)です」。それは、イノベーションの場としてのソニーの存在を示すものであり、現在と将来の可能性を表わす言葉であり、ソニーにしかできない何かがあるという確固たる自信の表出なのだろう。そして、自らを縛らないことで新たな価値を創出し続けることを意図する、非常に頑強なイノベーション戦略といっても過言ではない。
正にこれからの“make.believe”を具現化をしていくのはソニーやソニー生命なのかもしれない。
【インタビュー・文:井上功 /文(事例):荻野進介】
PROFILE
安藤国威氏
ソニー生命保険株式会社 名誉会長
1942年生まれ。東京大学経済学部卒業。
69年ソニー株式会社入社
79年ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社(現ソニー生命保険株式会社)代表取締役常務、85年同副社長就任。
90年より米国ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長兼COO。
94年 6月ソニー株式会社取締役就任。96年インフォメーションテクノロジーカンパニープレジデント就任以来、パーソナルコンピュータ“VAIO”の開発・事業化に尽力。
2000年 6月ソニー株式会社代表取締役社長兼COOに就任。
2005年ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長。
2011年ソニー生命保険株式会社名誉会長、現在に至る。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










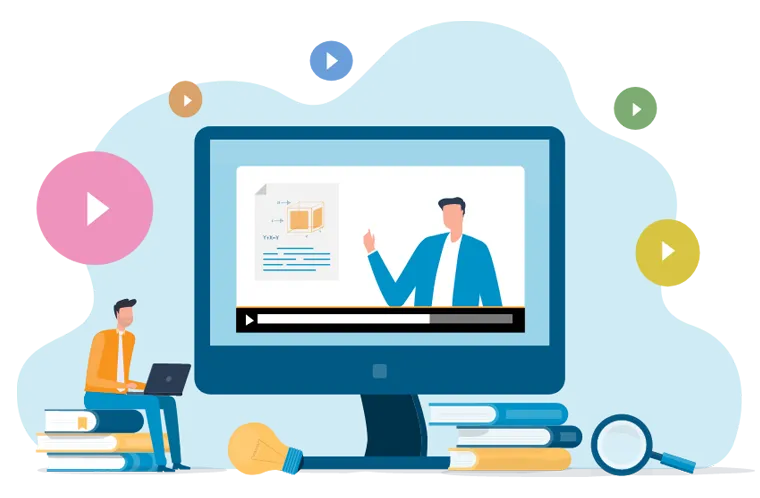 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての