インタビュー
イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
“けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- 公開日:2013/03/17
- 更新日:2024/03/31
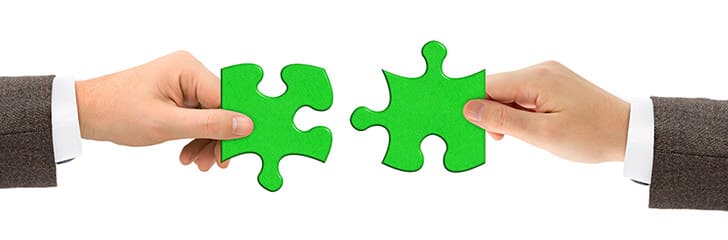
本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。 第3回では、日本経済新聞社の上杉栄美氏にご登場いただきます。上杉氏は、経済情報を核とした言論報道機関としての日本経済新聞社の中で、やや異色に思われる人材・教育事業を強力に推進し、多彩な読者ニーズに最適な形でコンテンツやサービスを提供する「複合メディアカンパニー」への転換を実現しています。それでは、上杉氏の組織の中でのイノベーション創出のストーリーをお楽しみください。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 日経の紙面は報道ニュース集であると共に 環境変化に対応した企業の実例集でもある
- 会社横断プロジェクトで認められ 事業化へ向けて動き出す
- チェンソーを振るう人だけではなく 山の魅力を高め、登りやすくする人も必要
- 総括
日経の紙面は報道ニュース集であると共に 環境変化に対応した企業の実例集でもある
Aという経営資源を投入して、Bという製品サービスを作る。そうしたビジネスモデルが成立している企業において、同じAから、Bとはまったく別のCという製品サービスを作るのに成功したら、それをイノベーションと呼ばずして何と呼ぼう。
成熟産業の1つであり、イノベーションが起きにくいといわれる新聞社で、それを成し遂げた人物がいる。日本経済新聞社、人材・教育事業本部の上杉栄美氏である。
その場合のAとは新聞社の経営資源である記者、Bはもちろん新聞、Cは記者が講師役をつとめる企業向けの研修プログラム、題して、「日経 経済知力研修」(以下、経済知力研修)である。
その研修は、(1)経済の見方やビジネストレンドの解説、(2)同社が主催する「日経TEST」の模擬テストと解説、(3)新聞記者の情報術、(4)それ以外のテーマでの講師紹介、という4つのプログラムで構成されている。いずれも同社の編集委員やベテラン記者が講師をつとめ、教材も日本経済新聞などを活用したオリジナルのものだ。
もちろん、人材・教育事業本部という部署があるくらいだから、同社に研修事業はもともとあった。その内容は、(1)1日単発をメインとする個人向け公開セミナー(=日経ビジネススクール)、(2)eラーニング、(3)個別企業向けオーダーメイド研修の3つに分かれていた。うち、(1)(2)は社外のコンサルタントや学者が独自のコンテンツを提供する形であり、(3)の一部でのみ、編集委員や記者経験者が講師役となっていた。経済知力研修はこの(3)の枠を大きく広げたのだ。

上杉氏は入社以来、広報事業畑、研修事業畑を歩んできた。2000年、出産のため休職したが、2001年3月に復帰。その復帰後3日目に、いきなりeラーニング事業の立ち上げを任される。期限はすでに決まっていた。同僚1人と共に4カ月弱奮闘し、見事7月にカットオーバー。「これが今までで一番の修羅場体験でした」と当時を振り返る。
このeラーニング事業で培われた経験が経済知力研修につながっていく。どういうことだろう。「今ほど普及していなかったeラーニングを紹介するために、徹底的に企業の担当者と頻繁に会うことにしたのです。企業に出向き、研修のニーズを聞いているうちに、『うちの社員はとにかく内向きで困っている。情報感度を上げ、視野を広げるのにいい研修はないか』という相談が複数の企業から舞い込むようになったのです。お客様から問い合わせがあって、『ないです』とは言えませんし、1社では弱いけれど同じ問い合わせが3件あったら、社会的ニーズも高いはずと考えました。しかも経営環境の変化がものすごく速くなっています。日経の記者が、変化に対応するためのノウハウを教える講座。これはビジネスになる。そう確信しました」(上杉氏、以下同)
上杉氏が頭に思い描いていたのは、編集委員が講師をつとめ、新聞の拡販事業として行われていた「日経の読み方セミナー」を“研修コンテンツ”として昇華し、充実させることだった。教材は日々の日経新聞である。「日経の紙面こそ、ビジネス環境の変化に対応した企業事例の宝庫と考えたからです。講師は記者、教材は日経。これこそ、当社だけが実現できるオリジナルコンテンツだと思いました」

コンセプトはすぐに固まったが、肝心の事業化には大きな壁があった。記者の本業は記事の執筆である。しかも優秀な記者ほど多忙だ。そういうなかで、研修事業に協力してもらえるとはとても思えなかったのである。妙案はしばしお蔵入りとなった。
会社横断プロジェクトで認められ 事業化へ向けて動き出す
が、待てば海路の日和あり。上杉氏のアイデアは思いがけないことで陽の目を見ることができた。
きっかけは、全社横断のプロジェクトチームが発足し、そのメンバーに上杉氏が選ばれたことだった。2008年春のことだ。プロジェクトの目的は、新たな投資は行わず、既存の経営資源を使って、新事業の立ち上げ、もしくはコスト削減を行い、全社のキャッシュフローを豊かにすること。各部局から1人ずつ、総勢19名のチームが編成された。「新事業統括室という組織のトップがリーダーでした。各部局に人選びを任せると、社歴や役職を気にして、平凡な人選になりがちだから、一番忙しく働いている人を出してほしい、とトップ自ら各部局に言ってまわったと聞いています」。上杉氏の場合、eラーニング事業の見事な立ち上げや、その後の積極的な営業活動が評価されたのだろう。

プロジェクトが走り出すと、2週間に1度というハイペースで、議論が行われた。各部局のエースだけに、メンバーは全員、多忙を極めている。対面での会議以外に、メーリングリストが用意され、アイデアを出し合ってはすぐさま可否が判断された。「行ける」となったものはすぐに詳細がつめられた。
上杉氏が早速、温めていたアイデアを出したのは言うまでもない。記者という既存の経営資源を使い、新しい商品を生み出すという、まさにプロジェクトの趣旨に沿ったものだったから、案の定、すんなり、GOが出た。目標は翌2009年4月スタート。あとは具体化だが、上からのお墨付きが得られたのだから、話は早い。早速、編集局を含む複数部局との調整を始めた。
そこでは、複数のキーパーソンを相手に、上杉氏は次の2点を強調した。
1つは、新聞発行事業と、研修教育事業の親和性の高さである。執筆と講義というアウトプットの違いはあるにせよ、どちらも、世の中で起こっていることを分析、あるいは解説して、分かりやすく伝えていくという点では共通している、と。
もう1つは、記者が研修講師をつとめることは、自分たちが作っている“製品”の受け手に触れる機会が多くなることだから、本業である記事の執筆にも大いに役立つのではないか、ということだった。
上杉氏の熱意にほだされ、論理に納得し、最終的に編集局も協力してくれる運びとなった。
チェンソーを振るう人だけではなく 山の魅力を高め、登りやすくする人も必要
事業化に向けた準備は着々と進んだ。上司が部内から協力者をアサインしてくれた。なかでも、上杉氏が大いに頼りにしたのが、記者出身で、ビジネススクールの企画・運営にも携わったという異色の経験をもつ雨宮秀雄氏(現・人材・教育事業本部 研修・解説委員)だった。
「コンテンツの中身から事業運営まで、実に有益なアドバイスをもらいました。しかも講師役にも打ってつけの方でした。雨宮さんがいなかったら、この事業は形にならなかったかもしれません。新規事業開発を前人未到の山そのものだとしたら、自分ができるのは、登り始めるポイントを決め、険しい森をチェンソーで切り拓きながら、とりあえずの“けもの道”を作ることに過ぎません」。こう謙遜気味に語る姿から、自分の役割認識と組織の力を信じる姿が浮かび上がる。登ろうとする山それ自体の魅力を高める人、即ち雨宮氏がこの事業には必要不可欠だった。

最後にもう1人、上杉氏が切り拓いた“けもの道”の幅を広げ、舗装したり、案内板をつけたりする人も必要だ。具体的には、利用規約の整備や適切な料金設定、効果的なプロモーションを担当する人のことである。これについても、上司が適任の人を用意してくれた。そういう意味では、上杉氏は上司に非常に恵まれていたといえるだろう。「新聞社の伝統だと思いますが、現場の声を重視し、『やりたい』と手を挙げた人に仕事を任せてくれる風土があるのです。また、私の部署には、編集局、販売局、広告局の出身者がいたので、その人たちの助けを借りて、部門間の調整がスムーズにいったことも大きかった」
上杉氏は社内だけではなく社外も頼りにしている。カリキュラムの概要が固まった時点で、顧客企業の親しい担当者に明かしてみたのだ。「耳で聞くだけの講座内容だと、研修担当者も社内で推薦しにくい、という意見をいただきました。そこで、受講後に修了レポートを最後に書いてもらうようにしたのです。これなら学習成果が形となって現れますし、そのレポートに記者が添削して返す形にすれば、内容のオリジナル度も増すわけです」
講師役を引き受ける編集委員や記者への教育も行った。講演会と研修の違い、本題に入る前のアイスブレークの大切さ、ファシリテーションのやり方、議論の双方向性を高める工夫等々、1人ひとり、丁寧にアドバイスした。
あっという間に時間が過ぎた。当初の計画通り、経済知力研修は2009年4月から販売を開始、現在では企業向け研修事業の売上の中核をなす事業に育ちつつある。
上杉氏は学生時代にはコピーライターになりたかったのだという。発想の元になる情報収集術について尋ねると、「ある事象を見聞きした場合、抽象化して頭の中に入れておくのです。それを繰り返していると、一見、何の関係もないAとBの間に共通項が生まれます。それが新しい発想のエンジンになることが多い」とのこと。
前述した「新聞発行事業と研修教育事業の親和性の高さ」という指摘もこうして生まれたのだろう。この事業発足のきっかけとなった、「日経の紙面はビジネス環境の変化に対応した企業事例の宝庫」という洞察は、物事に意外な点から光をあてるコピーライター的発想といえる。そう、イノベーターは一日にして成らず、なのだ。
総括
イノベーションは新結合
ただし、結合するものを理解していないとつなげられない
上杉氏の人材・教育事業の推進ストーリーはいかがでしたか。ここからは、上杉氏のイノベーション創出のポイントを、イノベーション研究モデルに沿って振り返ります。
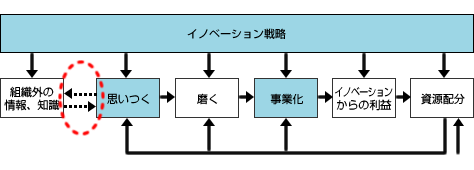
まず、上記モデルの【思いつく】領域でのポイントを挙げます。それは、自社の保有している経営資源の理解や捉え方です。上杉氏は、経済情報を収集・編集・執筆している言論報道機関の要としての記者の存在に注目します。日々の膨大な取材を通じてストックされている新聞社の情報自体に加えて、記者の行動特性や思考の方法、仕事の仕方自体が価値あるものと捉えています。記事として形になって世に提供されるものの価値と同時に、それを生み出す記者自身に焦点をあてたのです。新聞記者は、真実の追究に向けて、取材という行動を通じて見えないものを形にしていく過程をディレクションする人ともいえます。その価値の提供方法が新聞というメディア以外でもあり得るのではないか、と上杉氏は考えたのです。
新聞社の最大の経営資源ともいえる記者の価値の発揮方法を、講師という新たなメディアで実現する。それは、日本経済新聞社が目指す複合メディア戦略推進とも符合します。メディアをコミュニケーションの媒介物として俯瞰的に捉え、自社に適用しなければ成し得られなかったことでしょう。経営資源と、それらがもつ価値や意味性の正確な把握。これこそが、日本経済新聞社における人材・教育事業推進の1つめのポイントだと云えます。
第2のポイントとして挙げられることは、外部との接点です。研究モデルの中では、【組織外の情報、知識】と【思いつく】の間のところです。eラーニング事業の立ち上げ時に、企業の担当者、即ち顧客・市場と密にコミュニケーションするようになった上杉氏は、「同じ問い合わせがお客様からほぼ同時期に3件入ったら、社会的ニーズが高いはずだと考えました」と語っています。顧客の声がそのままイノベーションにつながるとは思えません。ただし、まったくニーズがない中で、唯我独尊で新たなビジネスを成立させることもできないのは自明です。
顧客から何かできないか、という打診があって、「『ないです。できません』とは絶対に答えたくない」と話していた姿も非常に印象的でした。顧客の要請や期待に応えようとする真摯な姿勢こそが、今までにない新しい価値を創出するエネルギーになっているのでしょう。そして、事業を進める段階で上杉氏はお客様自体を巻き込んでいきます。「社外のお客様自体を頼りにしている」という発言には、共創戦略ともいうべきマーケティング活動が宿っています。市場との接点を開きながら、市場の声を真摯に訊き、市場の価値を取り込んでいく。まさに市場との接点を最大限活性化し続けているのです。
多様性の担保はまさしく人材の新結合
それを支えるのは組織・経営側の責
第3は、【事業化】の領域での多様性です。上杉氏は、新規事業開発を山にたとえ、「自分ができるのは“けもの道”を作ることに過ぎない」と語っています。イノベーションは1人では興せません。顧客のニーズやウオンツ、競合企業の状況、ビジネスモデルなどの多様化・複雑化がごく当たり前の現代において、多様性の力を得ずしてイノベーションを生むことは不可能でしょう。新規事業の山自体の魅力を高める人と、“けもの道”を舗装し案内板を取り付ける人。各自の得意技や持ち前を認識し、それらが最大限に発揮されるように全体をディレクションしながら事業開発を進めていきます。
この多様性の担保と推進を、組織が完全にバックアップします。編集局、販売局、広告局……。さまざまある新聞社の組織のノウハウや経験・実績を、新規事業推進に向けて最大活用できるようにしているのです。まさに組織の中からイノベーションを創出するときの最大のメリットを享受しながら、多様性を活かし新たな価値の創出につなげているのです。上杉氏は「恵まれていた」と話していますが、日本経済新聞社においてそれは偶然ではなく必然だったのでしょう。
第4に、【イノベーション戦略】の存在が挙げられます。ただ、それは正面切った「イノベーション戦略」というべきものではありません。失礼ながら、節約型イノベーション戦略ともいうべきものが、1つのプロジェクトの形で推進されました。企業経営を価値/コストのマネジメントで表現するとして、2008年に発足した全社横断プロジェクトは、分子の拡大と分母の縮小の両方にメスが入れられたと聞いています。その内容は、既存の経営資源を活用し新たなコストをかけずにイノベーションを興す、というもの。上杉氏は、今まで実現不可能だった記者という経営資源と人材・教育事業とのリンクを、このプロジェクトを最大活用することで前に進めます。
経営側のプロジェクトメンバーの選定が見事です。新事業統括室のリーダーが、「面白そうな若手を集める」という基準で、いわば独断と偏見で人選しています。社歴や肩書きなど一切お構いなし。各々の部局で一番エッジが立っている人が選出されています。そこでは聖域なく本音が飛び交うエキサイティングな会議が展開されたそうです。どこを切っても同じ絵柄の金太郎飴のような組織からはイノベーションは生まれません。同質の状態であれば、新たに結合する意味や価値がないからです。このプロジェクトでは、まさに異能・異才人材の新結合が行われたといっても過言ではありません。
モノではなくコト
モノづくりではなくコト輿し
最後に発想について言及します。上杉氏は、事象を抽象化して頭に入れておくと言っています。つまり、事象の意味を問い、抽象度を一段上げて、モノではなくコトとしてストックしているのです。これは一体なんだろう? このことは何を意味しているのだろう? そういった自問自答を繰り返しているとも話しています。そうすることで、「日経の紙面こそがビジネス環境の変化に対応した企業事例そのもの」という自事業の本質的理解が生まれ、それが新聞社における新規事業につながっていくのです。
様々なコトが日々上杉氏の頭の中でつながったり離れたりしているのでしょう。それはひとり新結合といっても過言ではない。今この瞬間も、何かと何かが高い抽象度をもって、上杉氏の頭の中でつながっているに違いありません。
そして、プロジェクトで概ね了解を取り付けた上杉氏は、最後は幹部を口説きます。「新聞事業と教育事業、どちらも世の中で起こっていることを編集、分析、解説し、分かりやすく伝えていく点では同じだ」と。新聞事業と教育事業をコトに昇華し新結合させて語りきる上杉氏は、レトリシャンでありコト興しのイノベーターなのでしょう。
【インタビュー・文:井上功 /文(事例):荻野進介】
PROFILE
上杉栄美氏
株式会社日本経済新聞社 人材・教育事業本部

1988年入社 事業局に配属
1990年 事業局経済事業部
1992年 同・企画開発部
2000年 文化・事業局経済事業部
2007年 同・総合事業部
2009年 教育事業本部
2012年 人材・教育事業本部、現在に至る。
2008年よりDiSC認定コンサルタント
2010年より財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










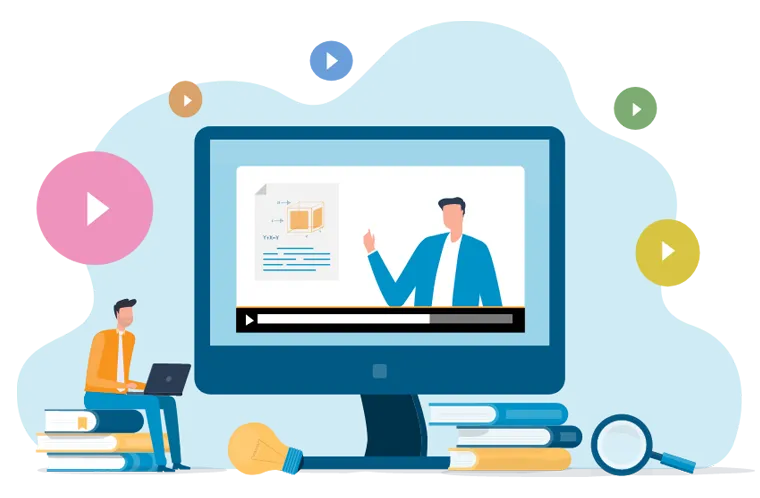 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての