インタビュー
イノベーション研究 第25回
組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- 公開日:2015/01/28
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。今回は、これまでの研究成果についての中間報告の中編です。
前回ご紹介したように、23社に及ぶインタビューと、リクルート等の事例を俯瞰した結果、組織の中からイノベーションを興す8つのポイントが見えてきました。
ポイント(1) 常識の泥沼から這い出せ~慣行の外に出るにはどうすればいいか
ポイント(2) 青臭い意志をもて~大義を決め、考え抜く
ポイント(3) 虫の目をもて、鳥の目ももて~抽象度を上げて、下げる
ポイント(4) とんでもない人間を唆せ~奇人・変人を見つけアサインする
ポイント(5) 人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな~兵站を確保する
ポイント(6) オープン! オープン! オープン!~開かれた実行部隊をつくる
ポイント(7) 矛盾をマネジメントせよ~ひたすら耐えて、根負けさせる
ポイント(8) 称賛という水遣りを忘れるな~誉め言葉を変え、認知と称賛を繰り返す
中編ではこの8つのうち、まず4つのポイントを、事例を交えて見ていきます。前編と併せてご一読いただければ幸いです。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- ポイント(1) 常識の泥沼から這い出せ ~慣行の外に出るにはどうすればいいか
- ポイント(2) 青臭い意思をもて ~大義を決め、考え抜く
- ポイント(3) 虫の目をもて、鳥の目ももて ~抽象度を上げて、下げる
- ポイント(4) とんでもない人間を唆せ ~奇人・変人を見つけアサインする
ポイント(1) 常識の泥沼から這い出せ ~慣行の外に出るにはどうすればいいか
常識の泥沼とは一体何でしょうか?
組織は常識を創り出す装置、ということができます。
組織では、顧客を見据え、顧客価値・収益モデルを設定し、競合に対する優位性を担保して、事業活動が展開されていきます。そして、効率的かつ効果的に事業が推進されるためには、フェアウェイが定まっていることが望ましいでしょう。理念・目的・使命(ミッション)・目指す姿(ビジョン)などに始まり、行動規範や価値観(バリュー)、就業規則・人事制度・業績評価などの言語化された決まりごとや、慣習・組織風土・文化・作法や人との関係などの不文律などが、フェアウェイを決めるものだといえます。
フェアウェイが決まると、組織の構成員は内発的・外発的な動機を基に、凝集性を最大化して、活動を行っていきます。参加した組織の中での活動は、フェアウェイのなかで行われることになるため、人はそのフェアウェイに拘泥されます。フェアウェイが常識となってしまうのです。事業活動が推進されるにつれ、どんどん常識の泥沼にはまっていく。個人の観点では、「フレーミング」といわれる固定的なものの見方や考え方に支配されることであり、組織の観点では、「バリューネットワーク」から脱却できない、「コンピテンシー・トラップ」にはまる、もしくはイノベーションのジレンマに陥ることを意味します。このことは、数多の経済・経営学者が20世紀初頭(100年以上前!)より主張してきたことです。
組織の中からイノベーションを興すには、まず、このような常識の泥沼から這い出る必要があります。自社・自組織の慣行の領域の外に自らを置くことが絶対条件となります。では、どうしたら常識から自らを解き放つことができるのでしょうか?
イノベーション研究モデルでは、この「常識の泥沼から這い出せ」を、イノベーション戦略に位置するものとしました(図表01参照)。
図表01 【常識の泥沼から這い出せ】の研究モデルでの領域
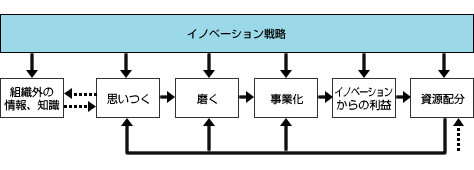
戦略的決定は経営陣の専権事項であり、トップの覚悟が欠かせません。では、早速事例を紐解いてみましょう。
常識の泥沼から這い出すきっかけとして、最も効果的かつ即効性があるもの、それは、存亡の危機です。
慣行にとらわれすぎて、組織が存続することすら危ぶまれる状況に陥った事例が品川女子学院です。漆紫穂子氏が学校経営に着手したときに、学校は東京都の廃校危険指数でワースト5に入っていました。「このままだと、1925年に曽祖母が設立した荏原女子技芸伝習所以来の伝統がついえてしまう」。そう考えた漆氏は、他校、進学塾、生徒、保護者、教員、職員、卒業生などの意見を聞くことに徹します。これらのヒアリングを基に、制服改革、授業改革、シラバスづくり、環境整備、ミッション・ビジョン・バリューの設定などを次々と行い、完全6年間中高一貫の学校を創りあげるのです。存亡の危機が、慣行の外に出ざるを得ない状況を作ったということができます。
この存亡の危機に近い状況が、数十年前に三菱商事でも起きています。1980年代、売上高で常に1位だった同社が、5位に転落した時期があります。社員の衝撃は計り知れないものだったようで、経営層だけでなく現場でも何度も議論がなされました。売上競争を続けるか、やめるか、と。そのときの様子を、現経営陣の占部利充氏が語っています。「『トレーディングから事業投資へ』『インターナショナルからグローバルへ』の2つがキーワードでした。そして、自分たちの機能って何なのか?という自問自答を突き詰める形での事業機会や組織の再点検が全社を挙げて行われました。そして、売上高競争からの決別という転機を捉えて、事業投資会社への道を邁進することになったのです」。これはまさしく、常識の泥沼から這い出した好例です。当時の総合商社は、売上高の20兆円超えは当たり前。そんな激烈な売上競争の慣行の外に自らを置き直すことは、困難を極めたに違いありません。しかし、売上高5位への転落という状況をショック療法として活用し、三菱商事はトレーディング会社から事業投資会社への転換を見事に成し遂げたのです。
存亡の危機から新たな価値を創出し、再生や復活を遂げた企業や組織は、他にも数多く見られます。研究インタビューはしていませんが、IBMや富士フイルムなどはその代表的な例です。メインフレームを主軸とするコンピューターメーカーからサービス企業に生まれ変わったIBMは、その変革の本質を見失わないようにするために、EMO(Emerging Business Opportunity)という新規事業創出を狙う仕組みを設けました。これは世界中から有望な人材を集め、新規事業の「実験」を行わせるもので、4年間で150億ドル(1兆8000億円)以上のビジネスを創出しています。
また、劇的な環境変化で既存事業が消滅する危機にあった富士フイルムの企業変革は、21世紀に入り同時代的に進展したものであり、まさに古森重隆氏を核とした経営陣と全社が一丸となって慣行の外に出た結果、成し得たものでしょう。今や、富士フイルムは化粧品メーカーでもあるのです。
閉園の危機から復活し、日本一の動物園を創りあげた旭山動物園の元園長、小菅正夫氏の慣行の外に出る話も印象的です。ほぼ確定していた閉園の危機を回避し、一から理想の動物園を創りあげていったストーリーをご存じの方も多いでしょう。そのなかでも、園長に就任早々、お客様の目線になって動物園を歩き回ったエピソードが秀逸です。当時、飼育係は檻の奥にいて餌を与え清掃をする業務を行っていました。動物は飼育係を「餌をくれる人」として認識し、檻の奥ばかり見ていた。当然、お客様にはお尻を向けることになります。また、檻も小さくて動物たちはほとんど寝ていたそうです。これでは、見ている方は全然面白くありません。動かないし、どんな顔をしているかも分からない。文句が出るのは当然といえます。そんなことを、小菅氏は顧客目線で歩いてみて初めて知るのです。そこから彼は、今までの動物園の常識をことごとく覆していく。動物園とは関係のないローラーコースター(導入時は人気の施設だったが、流行が廃れ無用の長物になっていた)の廃止に始まり、解説する飼育係や行動展示などがその常識破りの一例です。こうして着実に入園者数が増え、決して交通の便がいいとはいえない旭山動物園を、日本一の動物園にすることに成功しました。常識を徹底して覆すことで、イノベーション(経済成果をもたらす革新)を成し遂げたのです。
常識というのは厄介な存在です。事業が軌道に乗って成長し、顧客価値が磨かれて、勝ちパターンが見えてくればくるほど、あっという間に組織の中にはびこる。挙句の果てに意思決定の基準にまで及んでいきます。そして、構成員はごく自然に常識の泥沼にどっぷり浸かってしまうのです。そんな状況下で、自らが自社の事業の『対抗軸』を作ることはできるのか? 前述したように、経営の危機にあってそれを成し遂げた企業はあります。では、業績が極めて堅調なときに自社の『対抗軸』を作ることができている企業はあるのでしょうか?
三井物産において、初代のイノベーション推進室長に就任した高荷英巳氏は、就任前に社長である飯島彰己氏からこう言われています。「なんとか当社が新しいものに触れられるようにしたいと思っている。やり方は任せる」。当時の三井物産の業績は極めて堅調。だからこそ、今までにない新しいものに触れる機会が重要だと経営者は考えたのでしょう。この『新しいもの』を、『慣行の外』『常識の外』『イノベーション』に結びつけて考え、高荷氏は行動します。イノベーション推進委員会という既存事業とは別のプロセスを設け、イノベーション推進室では世界中の課題に対する専門家を組織し、また年間200億円のイノベーション推進予算も確保します。そして、既存の商社の枠を大きく超えたイノベーションを推進しているのです。
活用できる資源は、当然業績が堅調なときの方が潤沢です。一方、逆境にさらされているときにこそ、大きな変革へのエネルギーが生まれる、ということもできます。どんな状況であれ、自社の『対抗軸』を自社で作る、ということがどの企業にも求められているのです。
リクルートには、New RING(Recruit Innovation Group)という新規事業提案制度が20年来存在します。そのキーワードは、「リクルートをぶっ潰すにはどうしたらいいか?」です。自社の事業をぶっ壊すのが自社の社員なら、こんな健康的なことはない。そして、ぶっ潰されないように既存事業を磐石にするということも、同時に求められることなのです。
ポイント(2) 青臭い意思をもて ~大義を決め、考え抜く
大義とは一体何でしょうか?
大義とは大義名分のことであり、元々儒教に由来する考え方で、臣下として守るべき道義や節度、出処進退などのあり方を指します。今日では転じて、「行動を起こすにあたってその正当性を主張するための道理・根拠」となります。イノベーションは経済成果をもたらす革新であり、それは社会に新しく正当的な価値をもたらし、組織的な行動を伴うものでもあるので、大義といった錦の御旗は必要です。
イノベーション研究モデルでは、このポイント(2)もイノベーション戦略の領域に位置させました(図表02参照)。では、幾つかの事例を紐解いていきましょう。
図表02 【青臭い意思を持て~大義を決め、考え抜く】の研究モデルでの領域
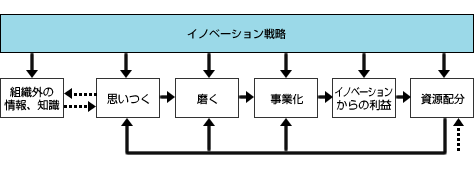
三菱商事では、水ビジネスを立ち上げるにあたって、そのリーダーである水谷氏が、「この事業自体が世界のためになり、日本のためになり……」「日本で最初にできた、日本の水を背負い、支えていく会社」といった大義を決めています。その大義があってこそ、真の和製水メジャーと呼ばれる企業が生まれていったのです。
<第2回 水ing(スイング)株式会社>
JR東日本では、安全・安心・信頼・確実という鉄道事業の根源的な大義を踏まえた上で、「通過する駅から集う駅へ」というコンセプトを立ち上げ、便利・新しい・快適という今までにない価値をお客様に対して提供する、と決めています。鉄道事業本部と並列の事業創造本部というイノベーション創出組織を立ち上げ、ステーションルネッサンスをキーワードに、エキュートやグランスタなどの全く新しい提供価値を創出し続けているのです。
<第1回 エキュート>
AIU損害保険において全く新しい保険商品の開発を成し遂げた大坪浩子氏は、常に「自分たちは最終的に何がしたいのか?」「顧客に代表される関係集団がすべてハッピーになるためには何か必要か?」「なぜ我々がやらなければならないのか?」といった問いをプロジェクトメンバーに発し続けてきました。それはまさに大坪氏の、そして会社としての大義の追求であり、目的の同一化ともいえます。
<第5回 AIU損害保険株式会社>
東京通信工業という終戦直後に設立された小さなメーカーが、その12年後にソニーに社名変更し、さらにその20余年後に金融事業を立ち上げて成功軌道に乗せました。社名変更の際にはソニー電子工業などの案が最有力だったそうですが、盛田昭夫氏は「断固、ソニー株式会社でいくべきだ」と譲らなかった。「ソニーとは自由な精神であり、独創(オリジナリティ)です」と語った元ソニーの代表取締役でありソニー生命の創設者でもある安藤国威氏の言葉が、まさにソニーという会社の大義であり意志だったに違いありません。
<第8回 ソニー生命保険株式会社>
国が管理する28の空港の経営改革を進める国土交通省の河田敦弥氏と高橋哲也氏は、空港の民営化を霞が関で推進するために、8か条からなる仕事の判断基準を設けます。心は自由であるか? 逃げていないか? 当事者・最高責任者の頭と心で考え、行動しているか? などからなるその判断基準の根底には、私心にとらわれずパブリックマインドで仕事をしているか、という大義があります。空港民営化の基盤となる運営権の設定期間は、短いものでも30年、長いものだと50年の長期に及びます。自分たちの子供や孫が誇れるような空港にしないといけない、という大義がなければ、官僚と民間のカオスの組織での空港民営化は成し得なかったでしょう。
<第9回 国土交通省>
東日本大震災を契機に、宮城県石巻市雄勝町で復興支援活動に従事し、廃校となっていた小学校を再生し、「モリウミアス」という自然学校を作ろうとしている油井元太郎氏の言葉からも、大義が感じられます。「子供」「教育」「社会」「日本」「未来」といった単語が、インタビューの最中に彼の口からごく自然に発せられていました。同時に、誰がなんと言おうとやる、やり遂げる、絶対に諦めない、という迫力も伝わってきました。その根底には、「日本一過酷な環境に生きている子供たちに、日本一豊かな教育を提供したい」と話した雄勝中学校長(当時)の佐藤淳一氏と共通の意志や大義があるのかもしれません。
<第14回 公益社団法人 Sweet Treat 311>
自動車メーカーとTier1と呼ばれる部品メーカーを繋ぎ、新しい価値を創造しているAZAPAの社長である近藤康弘氏に、「最終的に実現したいことは何ですか?」と問いました。近藤氏は即座に「世界平和を実現したい」と答えています。「今行っている仕事・事業は、あくまでも日本企業がグローバルで戦っていける下地を作るため。その延長線上に、日本企業とBOP(Base of the Pyramid。1人当たり所得が年間$3000以下で生活する層を示す)の人たちとを繋ぐことを実現したい。世界の貧困層に仕事を供給し、真の世界平和を実現したい。因みに、社名のAZAPAは平和の象徴であるオリーブの希少種の名前です」と堂々と語る近藤氏の眼光はあくまで鋭く、気概とエネルギーに満ち溢れていました。近藤氏の大義が表出した瞬間ともいえるでしょう。
<第18回 AZAPA株式会社>
彼らに共通しているのは、その目的に向かう意志の強さとエネルギーです。われわれはどんな新しい価値を創出するのか? 誰の役に立ちたいのか? そして、それは何のためにやるのか? なぜやるのか?
まさしく、レンガ積みの寓話です。ある旅人が道を歩いていたら3人のレンガを積む人に出会った。1人目に訊いた。「あなたは何をやっているのですか?」「見れば分かるだろう。レンガを積んでいるんだよ」。2人目に訊いた。「あなたは何をやっているのですか?」「僕はレンガを積んで、壁を作っているんだ」。そして最後のレンガ積みにも問うた。「あなたは何をしているのですか?」「私はレンガを積んでいます。レンガを積んで、壁を作ります。壁を四方に巡らせ、屋根を張り、鐘楼を吊り下げて、教会を作ります。そしてみなで祈るのです」。共通するのは、みな3人目のレンガ積みである、ということです。青臭いけれども地に足がついた、共通善ともいうべき大義をもっているのです。
ポイント(3) 虫の目をもて、鳥の目ももて ~抽象度を上げて、下げる
イノベーション研究モデルでは戦略の領域に入る、3つ目のポイントである【虫の目をもて、鳥の目ももて】に関して説明します(図表03参照)。
図表03 【虫の目をもて、鳥の目ももて】の研究モデルでの領域
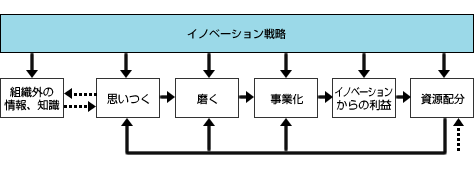
すべての物事は二面性をもっています。木を見て森を見ず、になってはいけない。逆もまた真なり。虫の目で木を見て、幹を見て、枝葉をじっくり観察しながらも、鳥の目で林を、森を、俯瞰して見なければ、イノベーションの基となる概念を磨くことはできないのです。物事の二面性について、抽象度を上げたり下げたりしながら、考え抜くことが必要です。
ここで、例として経営の要諦について考えてみましょう。
短期的視点―長期的視点
凝集性―多様性
論理―感情
外部適応―内部統合
顧客―効率
競争―調和
ラーニング―アンラーニング
戦略―組織
価値―コスト
経営者が置かれる状況を考えたとき、このような対極にある概念が思い浮かびます。両極を考え抜く必要があるのです。
抽象度を上げたり下げたりする観点としては、二面性以外でもさまざまありそうです。逆、裏、対偶、包含、昇華、置換、縮小、拡大、比喩、演繹、帰納、アブダクション、目的、目標、手段などです。これらの思考に基づき、概念の抽象度を上げたり下げたりすることが必要なのです。では、事例を見てみましょう。
駅の存在価値を、従来の輸送に伴う通過点から、集う場所というコンセプトに変えて、ステーションルネッサンス活動は始まりました。それは鳥の目で鉄道事業を見直した結果、見えてきた世界ということもできます。お客様を輸送するという目的を達成するときに、乗客は駅に集まり、電車に乗って移動し、目的地に着いたら駅から離れていく。身体の血管を流れる血液のようなダイナミズムが、鳥瞰的に物事を捉えたときに獲得できたのでしょう。一方、集う駅に必要なものは何かを考えるときには、エキュートの開発者であったJR東日本の鎌田由美子氏は、始発から終電まで大宮駅に3日3晩立ち通して乗客の様子を観察します。そこで、お客様が百貨店と違い立ち止まらないというショッキングな事実にぶち当たる。これはまさに、虫の目で現地・現物・現場を実践したからこそ得られた知見です。事業コンセプトを考えるときには徹底して抽象度を上げ鳥瞰して考え、実際のサービスを考えるときには現場での手触り感を重視して具象度を高める。鳥の目と虫の目があって初めて成し得たイノベーションです。
<第1回 エキュート>
『新しい掃除行動を作る』というブランドステイトメントを打ち立てた、ライオンの竹森征之氏の場合はどうでしょう? 彼が統括していたルックというブランドの商品は、お風呂やトイレ、キッチンのカビなどの汚れを落とす洗剤などで広く知られていました。竹森氏はブランドマネジャーに就任して早々に、『ブランドステイトメント』、即ち『その商品が実現する約束』を変えることを実施しています。本来なら、汚れを根こそぎ取り除く、とか、カビのない爽やかな世界を作る、といった約束になりそうなものですが、竹森氏は違いました。掃除の行動に注目し、今までにない新しい掃除行動を作ることを約束したのです。掃除行動という『コト』に焦点をあて、洗剤自体から汚れを落とす行為や行為者に価値の主体が変わることを促していったのです。ものより『コト』。機能より『意味』。抽象度を上げて考えることを構成員に問う、まさに鳥の目をもたざるを得なくさせるブランドステイトメントです。そして、「ルックお風呂の防カビくん煙剤」という商品を生み出すのです。この商品は、中外製薬から事業譲渡を受けたバルサンの技術を活用しています。くん煙することで、お風呂にカビを生えなくする商品なのです。掃除行動が根本的に変わってくる商品を作り出しました。この商品は掃除をしないことを促進する。カビを生えさせない、つまり掃除をする必要がない世界をつくろうというのです。この商品は、今までのルックの商品が売れなくなることを促進しているのです。それは明確な自社製品の対抗軸であり、抽象度を上げたり下げたりした結果生まれたイノベーションといってもいいでしょう。
<第12回 ライオン株式会社>
トヨタ自動車でモビリティの未来を考えている未来プロジェクト室の大塚友美氏の活動も、抽象度を上げたり下げたりすることの繰り返しです。組織のミッションは「モビリティの未来を考えること」であり、自動車の制約はありません。最終責任者のひとりは、モビリティにもこだわらなくていい、と言ったほどです。それは、自動車メーカーのトヨタ自動車にとっては概念昇華ともいうべきものです。そこにあったのは、既存の延長線上にない全く異質な課題が自動車業界を見舞うのではないか、という危機感でした。そこで、自社の対抗軸ともいうべき組織を作ったのです。そこでは、モビリティの未来をさまざまな角度から、様々な関係者と検討し、実現に向けたプロトタイピングが日々行われています。それは、自己肯定と自己否定の連鎖といってもいい。自動車業界で世界有数の企業が、未来のモビリティを真剣に創出しようとしている。しかも、本社がある豊田市から遠く離れた原宿にわざわざ租界をつくり、実行している。それは、自動車という手段ではなく、モビリティという目的を基に考えられたことだからこそ実現できているのでしょう。
<第20回 トヨタ自動車株式会社>
ポイント(4) とんでもない人間を唆せ ~奇人・変人を見つけアサインする
次に、イノベーションを興す主体者に注目しましょう。イノベーション研究モデルでは、主に思いつく、磨くの領域になります(図表04参照)。
図表04 【とんでもない人間を唆せ】の研究モデルでの領域
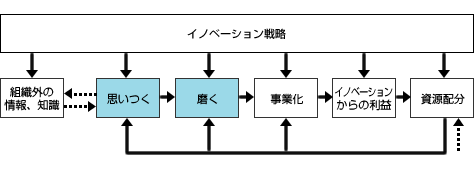
イノベーターの特徴として人口に膾炙しているものに、『ヨソ者、若者、バカ者』があります。慣行の領域の外に出る必要性の観点からすると、ヨソ者はベタベタの組織人よりもイノベーションを興せる可能性が高そうです。フレーミングに染まっていないという意味からは、若者がイノベーターとして活躍する素地があります。常識を完全に覆す発言を繰り返す人は、組織の中では往々にしてバカ者のレッテルを貼られます。
『ヨソ者、若者、バカ者』は、イノベーションを興す人材のキャラクターとしてかなり整合性の高いものといえるでしょう。
アメリカの歴史学者であるトーマス・クーンは、『パラダイムシフト』というイノベーションと近似の概念を普及させるきっかけとなった著書『科学革命の構造』において、「パラダイムシフトへの転換を成し遂げる人間の多くが、年齢が非常に若いか、あるいはその分野に入って日が浅いかのどちらかである」と主張しています。若者であり、分野の専門性を得るまでに至っていない、いわばバカ者が、本質的な発見によって新しいパラダイムを興す、と言っているのです。
では、実際に研究インタビューの対象となったイノベーターを見ていきましょう。
国土交通省において、国が管理する空港の経営改革を推進する組織の責任者が、河田氏です。彼は生粋の官僚であり、年齢も30代後半と若くはありません(失礼)。しかし、空港の民営化を推進することがミッションであるこの組織全体を見据えると、様相が異なってきます。
実質的なリーダーとしてイノベーションを推進している高橋氏は、2012年に組織に参加しています。以前は、ゼネコンや事業再生を手がけるハンズオン型のコンサルティング会社でその専門性を発揮していました。この組織において官僚は河田氏と高橋氏の2名のみで、残りの10名弱のメンバーはすべてヨソ者で構成されています。経営コンサルタント、公認会計士、弁護士、投資銀行・不動産会社・証券会社等の出身者などが空港民営化というイノベーションを興そうとしているのです。昼間から笑い声が絶えないその組織は、霞が関から完全に『浮いて』いると思われます。このような『変な』組織でもなければ、民間企業とは比較にならない頑強な基盤を有する霞が関で、イノベーションを興すということはできないに違いありません。
<第9回 国土交通省>
AIU損害保険で、今までにない概念の保険商品の開発を推進した大坪氏も、とんでもない人ということができます。インタビューを通じて自らを「異端」と語り続けました。6年前に同社に転職して以来、大坪氏はずっと『空気を読んでいません』。また、タテ社会、ムラ社会の日本の会社や組織において、自分の存在意義を、『大きな山を動かすこと』と規定しています。そして、入社以来さまざまな改革(イノベーション)を成し遂げているのです。そのエネルギーは尋常ではありません。とにかく強く激しい。合目的的であり、曖昧なことを許容しません。言葉へのこだわりは常人の域を遥かに越えています(一方女性としての心配りや、ご自身の明確な『幸せ基準』をおもちでした)。こういっては失礼ですが、奇人・変人であることに異論はありません。このような奇人・変人が、同質化したオトコ社会においてイノベーションを興しているのです。
<第5回 AIU損害保険株式会社>
オムロンヘルスケアとNTTドコモの合弁会社であるドコモ・ヘルスケアの社長の竹林一氏も、とんでもないエピソードを有しています。そのなかでも、東海道五十三次の踏破は、シリアルイノベーター(組織内で何度もイノベーションを興す人)としての面目躍如のものでしょう。
オムロンには、マネジャーになって6年目で3カ月間休んでいい、という長期リフレッシュ制度があります。竹林氏はマネジャーになって10年目に、その制度を活用しました。当時は新規事業開発のマネジャーとして激務に追われる日々。制度を活用するかどうか、上司に尋ねます。答えは、「おまえが会社に来ているかどうかは関係ない。会社にいようがいまいが、そんなことはどうでもいい、おまえとの約束は事業を成功させるかどうかである」。
そこで竹林氏がとった行動が、自宅まで歩いて帰るというものでした。それだけではびっくりしませんが、問題は自宅の場所です。当時、竹林氏は東京に単身赴任。自宅は滋賀県大津にありました。元々歩くことが趣味だったので、大津まで東海道を歩いて帰ってみようと思ったそうです。思ったら即実行。都合15泊16日。竹林氏は東海道を歩き続けました。その間に考え続けたこと、それは、「自分は一体何のために仕事をしているのか?」ということだったそうです。
東海道をひたすら歩く。歩きながら考える。自分とは。仕事とは。社会とは。自分の存在意義は。時間的呪縛から解き放たれて、こんなことを徹底的に考えたのでしょう。この東海道行が1つのきっかけとなり、竹林氏はさまざまなイノベーションを興すことになるのです。
<第15回 ドコモ・ヘルスケア株式会社>
自分の名前を冠した『尾崎牛』を作った牛肉商尾崎の尾崎宗春氏。畑違いの異分子であることを活かして、旧来の発想にとらわれていた技術者を解放したYKKの大谷渡氏。官僚でありながら、ハンズオン型、横繋ぎ型のネットワーキングを実現している経済産業省の守本憲弘氏。お客様の行動や動線を肌で掴むべく、3日3晩大宮駅に立ち続けた鎌田氏。彼らはみな、とんでもない人間であり、奇人・変人といっても過言ではないでしょう
ここで、インタビューしたイノベーターの特徴をまとめてみます。
まず印象的だったのが、「エネルギー量」の多さです。
イノベーターの方々は、1つの質問に対して豊富な言葉と多くの時間をかけて答える傾向にあります。語尾は明瞭、論理は明快、ある種のウィットが込められていることも多い。声が比較的通ることも共通項です。そして、そのエネルギーは膨大です。どんどん前に進んでいく感じが、インタビューからひしひしと伝わってきたことを記しておきます。
次に、「志」の強さが挙げられます。これは、ポイント(2)の大義とも繋がるものです。
ある人は日本を背負い、ある人は徹底的にカスタマー利益を追求する。50年後の想定される社会から逆算して事業を創造した人がいれば、パブリックマインドをすべての判断基準に置いて事業を推進している人もいる。すべてのインタビューの場に、青臭い志がありました。一方で、商売っ気もほとんどのイノベーターが有していました。
リクルートワークス研究所が以前、事業創造人材の研究を実施しましたが、そのまとめとして提示した人材像が、『青黒人材』というものです。青臭い志と腹黒い執着心や商売っ気を併せ持つ人として事業創造人材をイメージした言葉で、非常に分かりやすい。その『青黒さ』をイノベーターはもっていたのです。
そして、それぞれが「楽しむ姿勢」をもっていました。
イノベーターの方々はとにかく楽しそう。イノベーションは新しいことであるが故に、成功する保証はどこにもありません。加えて、新たな価値を市場に普及させる際に、資源(人・モノ・カネなど)の動員を必要とします。そのプロセスは、軋轢・誤解・矛盾・ねたみ・軽蔑・誹謗・中傷・落胆・失望の嵐です。にもかかわらず、彼らはとても楽しそうでした。厳しさを楽しんでいるようにすら見えました。自身をハグレ者と称したり、アウトローを自認したり、絶対に出世コースにはいないと豪語したり……。それでも自分が進めてきたイノベーションに関しては、「こんなご機嫌なことはない」とでも言わんばかりでした。
エネルギー量が多く、青臭い志をもち、心から仕事を楽しむ人たち。もし、皆様の組織の中に奇人・変人がいて、彼らがこのような特徴をもっていたら、間違いなく組織の中からイノベーションを興すことでしょう。
次回は、イノベーションを興す8つのポイントの(5)~(8)について、ご紹介していきます。
【総括(文):井上功】
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての