インタビュー
イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- 公開日:2013/06/26
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。 第6回は、ライフネット生命保険株式会社(以下、ライフネット生命)の出口治明氏にご登場いただきます。出口氏がライフネット生命を設立し、マザーズ上場を経て、保有契約件数17万人強の事業規模まで成長させるのに、5年ほどしか経っていません。出口氏はどうしてライフネット生命という企業を立ち上げたのか? ネットで生命保険を売るというビジネスが、なぜ出口氏の前職である日本生命保険時代にできなかったのか? この圧倒的なスピードで事業を推進している秘密は一体どこにあるのか? それは模倣が可能なことなのか?等々、興味は尽きません。組織の中から新たな価値を創出するには、既存のビジネスで培われたフレーミングからの脱却が必要です。しかし、それは簡単ではありません。極めて強固なビジネスモデルを確立した企業ほど、難しい。結果的に組織を離れることになりましたが、出口氏は今までなかったインターネット生命保険というビジネスを確立し、現在進行形で執行しています。それでは、出口氏に語っていただきましょう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
海外進出取り止め、これまでの努力が水の泡に
営業職員はゼロ、徹底した情報開示や商品のわかりやすさを売り物に、インターネットで保険を売る戦後初の独立系生保、ライフネット生命が設立されたのは2008年5月のことである。ネットの進化もここまで来たかと、当時、感慨深かったものだ。
以来、丸5年が経ち、保有契約件数が17万件まで、右肩上がりの成長を続けてきた。その創業者にして、同社会長を務めるのが出口治明氏その人である。
「組織におけるイノベーション創出」をテーマとする本研究においては、どうしても、日本生命のOBたる出口氏に尋ねたい問いがあった。「日本生命で同じようなビジネスを立ち上げることは不可能だったのでしょうか」と。
出口氏は即答した。
「どんな企業であれ、社員はトップが考えていること以上のことはできません。企業が新しいビジネスを始めるかどうか、あるいはその新しいビジネスの中身は、よくも悪くもトップの器によって決まるということです」
出口氏は1995年から同社で国際業務部長を務めていた。自他共に認める、同社の本格的海外進出を推進する旗振り役だった。1996年には「2020年に売上げの20%を海外で稼ぐ」という「トリプル20」プランを作成し、役員会から承認を得ていた。
ところがである。好事魔多し、というべきか、1997年に社長交替があり、しかも折悪しく、北海道拓殖銀行が破綻、国内の金融システムの脆弱さが露わになったときだった。新社長はこう宣言した。「海外進出は取り止める。今後はもっぱら国内強化に努め、販売員の数を増やすことに注力せよ」と。
万事休す、だった。折角上った梯子が外された。細心の準備で進めてきたすべてが否定され、無駄になった。
海外進出でさえこれだから、ネット生保というアイデアは当時の日本生命のトップの頭にかけらもなかったはずだ。もちろん、出口氏の頭にもなかった。「当時、私が日本生命の経営者で、ネット生保というアイデアが頭にあったとしても、取り組まなかったでしょう。事業で重要なのは、ポジショニングと経営資源です。販売員不要のネット生保は、当時の日本生命が取り組むべき事業ではなかったはずです。それよりも何よりも、全経営資源を投入して海外に出て行くことを選択したと思います。日本生命の置かれたポジションと経営資源を考えれば、それがベストの選択肢でした」
といって、出口氏はその社長を恨んでいる風ではない。「最終的には50年経たないと答えが出ないと思いますが、私が考えた日本生命を大きくさせるやり方と、当時の社長が考えたやり方が異なっていたということ。それは運や偶然としかいいようがありません」
出口氏は翌1998年に、公務員を対象に団体保険を販売する公務部長となり、2003年からは子会社のビル管理会社に出向して働いていた。はっきりいって閑職である。ところが、2006年3月、知人の紹介で会った、あすかアセットマネジメント代表の谷家衛氏に誘われ、現在代表取締役社長兼COOを務める岩瀬大輔氏という得がたいパートナーも得て、ライフネット生命というベンチャー企業を作ることになったのである。そろそろ還暦という年齢だった。
マニフェストがあるから仕事が速くなる
ライフネット生命は2012年3月にマザーズ市場に上場した。開業から約4年で上場という猛スピードである。「ネットで保険を売るというのは誰もやっていなかったビジネスなので、トライ・アンド・エラーを繰り返していくことが重要です。そのために必要なのがあらゆる物事のスピードを上げることです。スピードを上げれば、トライ、つまり試行の数を増やせるということですから」
一方で、企業は着実に前進していかねばならない。そのためには、しっかりとした「羅針盤」が必要となる。羅針盤なき航海は、船を誤った方向へ導いてしまうからだ。同社の羅針盤となっているのが「マニフェスト」である。それには「社員が遵守すべき行動指針」と、生命保険という商品をもっとわかりやすくして、低料金で提供でき、手軽かつ便利なものにするための工夫が、箇条書きでわかりやすく書かれている。
注目すべきは、そこで書かれている言葉のレベルである。
例えば、〈私たちの会社は、学歴フリー、年齢フリー、国籍フリーで人材を採用する〉とある。出口氏が言う。「これがもし〈高齢者にも優しい会社にする〉とあれば、人事担当者が迷って私に聞きに来るでしょう。でも聞きに来ないのは、年齢フリーで採用する、と具体的に明記しているから。そうなると上司にいちいちお伺いを立てなくて済むので、仕事のスピードが速くなる。現に当社では、60歳を超えていてもきちんと正社員として採用しています」
保険の素人だから思いついたサービスとは
ここで説かれていることを別の言葉でいえば「ダイバーシティ」となるが、同社の場合、その「フリー」の対象として、学歴、年齢、国籍の他に付け加える事項がある。「前職」だ。そう、同社の社員の前は保険会社とそれ以外というのがおよそ半々になっている。この社員構成が、業界にとらわれない発想を可能にしているようなのだ。
例えば、同社は昨年10月に「4つの新しい商品・サービスへの取り組み」を発表、実行しているが、その1つに、給付金請求時の診断書を不要にしたサービスがある。
これまでは同社も、他の保険会社同様、医療保険の給付金を請求する場合は医師の診断書の提出が必須だった。いわば保険業界の常識である。
これに対して、他の業界出身の社員が疑問を抱いた。というのも、2010年4月以降、医療費の内容が分かる「領収書」と個別の診療報酬の算定額が分かる「明細書」をすべての患者に発行することが病院に義務付けられたからだ。その明細書には、検査、処置、手術、注射、投薬、リハビリなど、個々の診療内容が単価や数量と共に記載されている。その社員はふと考えた。これこそ保険請求時の診断書に代用できるのではないか、と。
出口氏が説明する。「このサービスの実現によって、今まで5000円程度かかった診断書取得費用がゼロになりました。さらに診断書の発行・書類の郵送期間、またこちらで診断書を読み解く手間も省けるため、給付金受け取りまでの日数がこれまでの平均43日から23日※へと劇的に短縮しました(※2012年10月から2013年3月末までの実績値)。多様な社員がいればこそ、多様なアイデアが出てきます。前歴だけではなく、性別や年齢にもまったくとらわれません。当社は業界で初めて女性常勤役員を誕生させましたし、おそらく同じく業界で最も若い年齢の役員がいる会社でもあります」
多様なつながりを大切にし、組織を外に開いておく
出口氏によれば、多様なアイデアを生む組織を作るのにもう1つ、大切なことがある。トップたる自分を含め、社員が常に外部と接触していることだ。「私たちは開業3ヵ月後から、『ふれあいフェア』と名づけたお客様との集いを定期的に開催し、お客様の声を真摯に聴き続けています。週1回、社員が面白い人を順番に連れてきて、その人の話を聞く勉強会を開いています。例えば88歳のタクシー運転手を連れてきて、東京大空襲の話をしてもらったこともあります。また、10名以上でしたら、同業他社の方も含め、会社見学をいつでもOKにしてあります。先日はプルデンシャル生命の方が来られました。私自身も、聴衆が10名以上集まったら、全国どこへでも講演に出かけています。その数は月間20回、年間にすると200回ほどになります」
多様な情報や考えをもった多様な「個」がマニフェストという羅針盤(組織のコアバリューといってもいい)に即して行動し、自由闊達な議論を行っていくと、思わぬ化学反応が起きる。その成果を、失敗を恐れず試してみることで、事業や商品、組織が常に磨かれ、レベルアップしていくという流れだ。
その根底に、上意下達のピラミッド型を否定した、イノベーションが起きやすくするための、組織自体のイノベーションがある。最初の話に戻るが、ライフネット生命がそんな組織になっているのも、まさしく出口氏の「器」によっているのだろう。
総括
出口氏のライフネット生命のイノベーションストーリー、いかがでしたか。
いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で出口氏の話を振り返ってみたいと思います。今回注目すべき領域は、イノベーション戦略です。ライフネット生命設立から現在に至るまでの戦略を俯瞰すると共に、そこから得られるインプリケーションを考えてみたいと思います(図表01参照)。
図表01 本事例における仮説モデルの該当要素
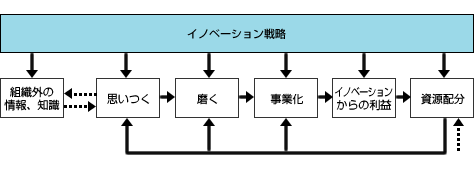
大企業からイノベーションが起きるか?
ベンチャーからしか生まれないか?
日本生命のなかでネット生保がなぜ生まれなかったのか? これが今回のインタビューで導き出したいことでした。人材、資金、技術、実績、ネットワークなどのさまざまな経営資源の保有状況を踏まえると、大企業とベンチャー企業では圧倒的差がありそうです。一方、情熱や理想、カオスや一体感といったものは大企業には負けないベンチャー企業の強みかもしれません。
イノベーションの開祖と言われるシュンペーターにも、イノベーション創出のモデルが2つあります。マークⅠ(図表02参照)とマークⅡ(図表03参照)です。
図表02 シュンペーターモデル マークⅠ
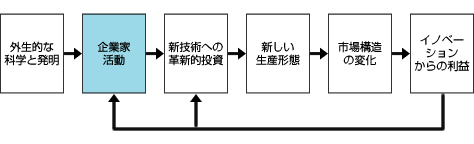
マークⅠは、著書『経済発展の理論』のなかで提示されました。その特徴として、
●企業者と業主(管理者)を明確に峻別
●企業者とは、「新結合の遂行を自らの機能とし、能動的に遂行する経済主体」
●企業者の新結合の遂行とは、慣行の外に出ること
を挙げています。
つまり、イノベーションは企業者からしか生まれず、企業者は新結合しか行わず、業主とは異なる人である、と設定したのです。当初はシュンペーターは、組織の中からイノベーションは生まれない、と想定していたことになります。
それに対してマークⅡではまったく異なることを言っています(図表03参照)。
図表03 シュンペーターモデル マークⅡ
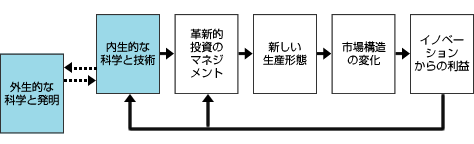
マークⅡは、著書『資本主義、社会主義、民主主義』のなかで提示されています。そこでは、
●独占的な地位を占めている大企業こそがイノベーションを生む
●革新的投資へのマネジメントは大企業でこそ活きる
●多くのイノベーションが大企業によって創出される
と述べています。
つまり、イノベーションは大企業からしか生まれない、と論を変えたのです。
1912年の『経済発展の理論』刊行から、1942年の『資本主義、社会主義、民主主義』発表までのちょうど30年の間にシュンペーターに一体何が起こったのかは、今となっては知る術がありません(大企業の発展は、この間に起きています)。しかし、マークⅡで彼が語っていることの方が、現代の企業や組織を取り巻く環境にフィット感があると考えるのはわれわれだけではないでしょう。
出口氏の論は明快です。「それはトップに依存する。そして時代の影響を受ける」「トップ以上のことは社員にはできない。事業推進で最も重要なのはポジショニングと経営資源」。出口氏は、組織の中からイノベーションを生み出せない、と言ってはいません。トップの方針や寛容、社員の能力や多様性があれば、イノベーションは興せるのでしょう。そして、数多の企業で、組織の中からイノベーションは実際に興せています。
この問題に関しては、軽々に答えを出すことはできません。シュンペーターが新結合の概念を提示して以来、100年余が経過してもなお、イノベーションは不確実であり矛盾だらけの存在だからです。
そして、組織の外で始めたことですが、出口氏がライフネット生命で取り組んでいる経営は、その進化や普及のスピードが非常に速いがゆえに、イノベーション推進のヒントがたくさんあると思います。その幾つかを挙げてみましょう。
意思決定の基準は多様性を担保する基盤
先ず、意思決定の基準の明確化を取り上げます。イノベーションは多様性の許容からしか生まれません。違いの認識をすることなしに、新結合は生まれないからです。一方、ライフネット生命にはマニフェストが存在します。マニフェストの第1章には、社員が遵守すべき行動指針が書かれています(図表04参照)。この行動指針は非常に分かりやすい。それは、意思決定の基準ともいうべきものです。このOSともいうべきマニフェストを基に、多様な社員が判断を繰り返し、トライ・アンド・エラーを繰り返す。それは正にスピード経営であり、経営判断の分散化であり、社員が経営者として機能している証左でしょう。また、行動指針以外にも、事業の方向性を示したものが、第2章以降で書かれています。それは正に羅針盤であり、多様な意見を根底で担保する基盤のようなものなのでしょう
図表04 ライフネット生命 マニフェスト第1章
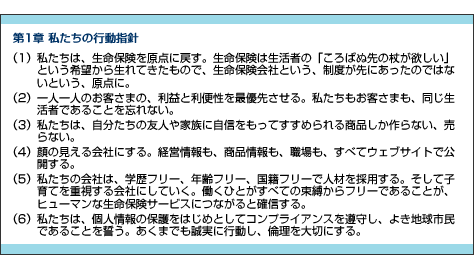
真のダイバーシティ、完全にオープンな組織が、イノベーションを促進
次に、真のダイバーシティの実現があります。ライフネット生命では、それは、女性活躍支援を意味するものでもなければ、単なる多様性の推進を指すものでもありません。何もかもフリーで社員を活かす、というものです。そのフリーのなかに違いがあり、そこにこそダイバーシティの真髄があります。出口氏に以前インタビューをした際に質問しました。どうすればイノベーションを興せますか?と。出口氏の答えは極めて明快でした。「違いの認識とマネタイズ。この2つを徹底すればイノベーションは興せます」。違いの認識がどうすれば興せるのか、それはダイバーシティの推進以外にないでしょう。そこを徹底して実施しているライフネット生命の凄みを感じます。
最後に、オープンであるということを挙げます。競合も含めて会社見学が自由な会社、こんな会社は民間企業ではほぼ聞いたことがありません。社長が月に20回以上講演している会社、これも同様です。しかも、それは一方的な講演ではなく、訊くことを中心とした対話になっているのだといいます。そこで交わされる会話のなかにこそ、事業推進や新たなイノベーションのヒントがある、そう確信している社員の姿が想像できます。共創型のイノベーション推進とでもいうべきコミュニケーションの基盤が、ライフネット生命では出来上がっているのです。
出口氏へのインタビューを通じて、上記のように幾つかのイノベーション推進のヒントが見えてきました。そして、これらを基に推進されているイノベーション経営の評価は、次代に委ねられるのでしょう。勿論、時々刻々と変化する顧客との関係や信頼の総体が決算という形で表出し、その時点での評価となるのは言うまでもありません。ただ、それは短期的なものにすぎない。「最終的には、50年経たないと答えが出ないと思います・・・・・・」。出口氏は日本生命やライフネット生命の成長戦略に関して、非常に飄々と、寧ろ達観しているようにも見える表情で答えていました。しかし、「運や偶然としかいいようがありません」とも話す言葉に、確固たる自信や自負がうかがえました。
【インタビュー・文:井上功 /文:荻野進介】
PROFILE
出口治明氏
ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長兼CEO
1948年三重県生まれ。
京都大学を卒業後、1972年に日本生命保険相互会社に入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当。生命保険協会の初代財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に東奔西走する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、同社を退職。
2006年にネットライフ企画株式会社設立、代表取締役就任。
2008年にライフネット生命保険株式会社に社名を変更、生命保険業免許を取得。
2013年、現職。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての