インタビュー
イノベーション研究 第24回
組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- 公開日:2014/12/17
- 更新日:2024/03/31
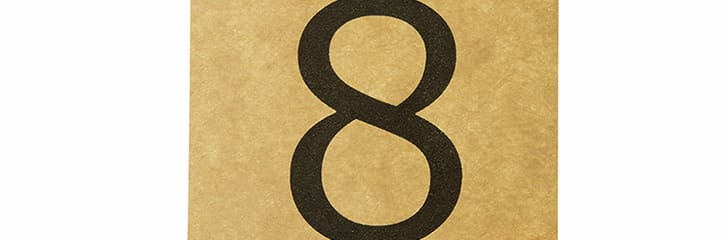
本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。今回から3回に渡り、ここまでの研究成果について、中間報告いたします。
まず、今回は、イノベーション研究開発を始めた動機や研究の背景、研究計画、仮説モデルの詳細についてご紹介しながら、これまでの取り組みについて俯瞰してまいります。そして、次回は、「組織の中からイノベーションを興す8つのポイント」について、具体的なエピソードもふまえて、さらに議論を深めていきたいと思います。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 2年間に渡り、23社のイノベーターにインタビュー 業種・規模・歴史等は多岐に渡る
- イントレプレナーを対象に イノベーションを「経済成果をもたらす革新」と定義
- 研究を通じて明らかにしたいこと リサーチ・クエスチョンの設定
- イノベーション研究モデルの仮説を構築 参照したのは日本(企業)に相応しいシュンペーターのマークⅡ
- 戦略的決定が、組織の中からのイノベーションには不可欠
- 研究インタビューの概要
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント
2年間に渡り、23社のイノベーターにインタビュー 業種・規模・歴史等は多岐に渡る
この研究インタビューを行うことになった根源的動機は、日本(企業)のイノベーション創出力の低下です。語り継がれて久しいですが、日本企業からなぜスティーブ・ジョブスのようなイノベーターが産まれないのか? アイフォンやアイパッドのような革新的なイノベーションがなぜ日本発ではないのか? といった問いに対する答えが欲しかったのです。
その答えは能動的であり行動を呼び覚ますものでなければなりません。自然科学的な完全解を求めるのは、社会科学の世界ではご法度という人がいます。しかし、「こうすれば自社のイノベーション創出力を高めることができるかもしれない」「まずここから始めてみよう」といった実行に向けたわくわく感がなければ意味がないともいえます。そして、この研究インタビューが、イノベーション創出に向けた企業や組織の中での何かしらのきっかけや契機になって欲しい、とも考えました。
もう1つ実感していたことがあります。それは、上記に反するようですが、本当に日本(企業)はイノベーション創出の力が落ちているのか? ということです。総論では低下しているかもしれないが、各論では違うのではないか? 失われた20年の間に、粛々と組織の中からイノベーションを興している企業・組織があるのではないか? 今までにない価値を提供している商品・サービスは沢山ありそうだ。そんな想いにかられていました。
2012年の晩夏、実際に組織の中からイノベーションを興している企業や組織に取材する企画を、小社にて立ち上げました。そして、2013年1月のJR東日本を皮切りに、2014年11月まで合計23社にインタビューを実施してきました。
インタビューした企業・組織の業種は、商社、金融、メーカー、IT・情報、インフラ、流通・サービス、マスコミ、官公庁、教育機関、NPO法人等と非常に多岐に渡ります。
企業規模では、株式時価総額では世界有数のポジションを占める大手企業から、従業員が数名のベンチャー企業まで取材することができました。
歴史を見ても、設立以来百年以上経ている企業から、設立から数年しか経ていない組織まで、さまざまな状況にあることが分かります。
イントレプレナーを対象に イノベーションを「経済成果をもたらす革新」と定義
インタビュー対象として共通しているのは、『組織の中からイノベーションを興している』ということです。ここでは、アントレプレナー(起業家)を扱っていません。インタビューしている方々はすべてイントレプレナー(企業内起業家)です。『組織の中から』ということが、この研究インタビューの拘りの1つです。
そして、『イノベーションを興している』というもう1つの拘りがあります。実際に何かしらのイノベーションを興した人、もしくは現在進行形で興そうとしている人を対象にしています。
ここで意識したことは、イノベーションの定義です。この言葉が厄介です。1958年の経済白書で『技術革新』と訳されてしまったイノベーションは、日本では技術色や発明のイメージが未だに付きまとい、研究所やR&D部門の専権事項のように捉えられています。また、人によってその言葉の意味が大きく異なるのもイノベーションの特徴です。技術革新はもとより、新たな価値の創造、変革、新しい顧客・市場をつくる、新規事業推進、非常識な発想、変化の醸成、市場構造を変える等、さまざまな意味解釈が行われています(因みに中国では『創新』と訳すそうです)。
このように解釈が人によって大きく異なる言葉の領域を研究するのであれば、定義が必要不可欠です。そこで、この研究では、イノベーションを以下に定義しました。
経済成果をもたらす革新
ここでは、イノベーションを単なる革新とは規定していません。「経済成果をもたらす」ということを重要視しています。イノベーションは、顧客・市場がその価値を享受しなければ意味がありません。一人の天才の頭脳の中で完結したところで、それはイノベーションとは呼べないのです。価値を実感するには顧客・市場への普及が必要です。普及させるためには、拡大再生産が不可欠です。拡大再生産のためには、ヒト・モノ・カネ・情報・時間といった資源動員がなされなければなりません。経済成果をもたらすことを重視しているのは、このような考えからです。
研究を通じて明らかにしたいこと リサーチ・クエスチョンの設定
イノベーションを定義した後、冒頭に書いた問いをリサーチ・クエスチョンの形でまとめました。
組織に於いてイノベーションを興すために、誰が、どの領域の、何を、
どのようにすればいいのか
詳しくは、以下の通りです。
組織に於いて(イノベーションを興すために)……世界の労働者の大多数が所属している組織の中で
●組織は、民間企業、政府等、NGO/NPO等含む
●多様性の観点から、外部との連携を重視
誰が……イノベーションを推進する人と組織
●組織内・外の人、組織側(制度等)
●各々の役割や関係性を考慮
どの領域の、何を……発想し、磨き、普及させる中で何をするのか
●この流れのどの領域を扱うか
●人材の志向、特性を踏まえた
●役割に応じた行動や支援の仕組み
●イノベーションの普及場所・時代を考慮
どのようにすればいいのか……どうすれば、思いつき、磨き、普及させることができるのか
●人材と組織の観点から
こうしてリサーチ・クエスチョンを設定し、解決したいことをはっきりとさせました。
イノベーション研究モデルの仮説を構築 参照したのは日本(企業)に相応しいシュンペーターのマークⅡ
研究を進めるにあたって、モデルが必要です。それは、本連載ではお馴染みのイノベーション研究モデルです(図表01参照)。
図表01 イノベーション研究モデル
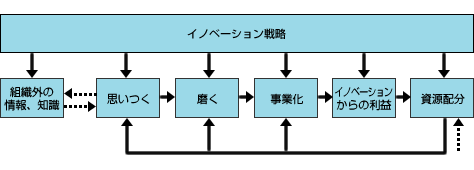
これは、シュンペーターのイノベーションモデルを参照しながら考案しています。
シュンペーター氏は言わずと知れたイノベーションの開祖ですが、彼はマークⅠとマークⅡのモデルを考えました。これら2つのモデルの構成要素と特徴を挙げます(図表02、03参照)。
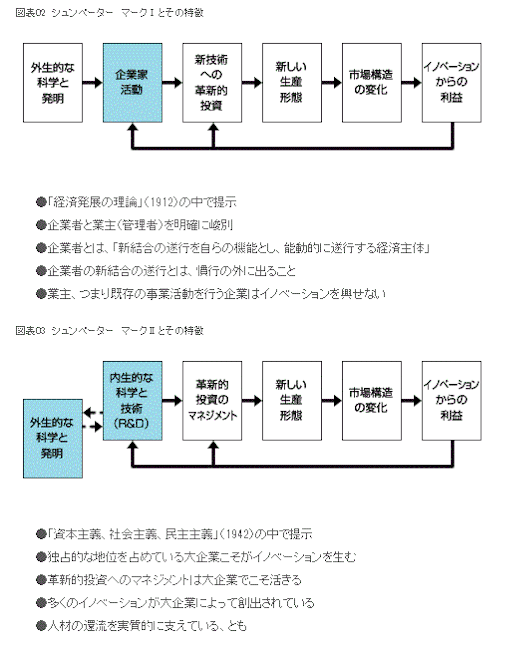
イノベーション研究モデルで参照しているのは、シュンペーターのマークⅡです。
マークⅠはアントレプレナー型のモデルです。シリコンバレーのようなイノベーション創出の生態系をもたない日本では、企業や組織こそがその代替となる場になるとの仮説をおきました。マークⅡがそれにあたります。では、マークⅡを参照した背景についてもう少し細かく見ていきます。
21世紀当初、ビットバレーが話題になりましたが、それがシリコンバレーのようなイノベーション創出の基点になっていることはなく、もはやその言葉自体がほぼ死語と化しています。欧州には数多く存在しているフューチャーセンターに代表されるイノベーション創出の場は、近年日本でも散見されるようにはなりましたが、そこからイノベーションが興きているという話はほとんど聞きません。起業家の人口比と経済成長の関係を研究しているGEM(Global Entrepreneurship Monitor)によると、日本の起業活動率は世界でも際立って低い状況です。調査対象69カ国中で、イタリアに次いでワースト2位であり、アメリカはもとより、欧州各国からも大きく差をつけられている状況です(図表04参照)。
図表04 各国の起業活動率(TEA)
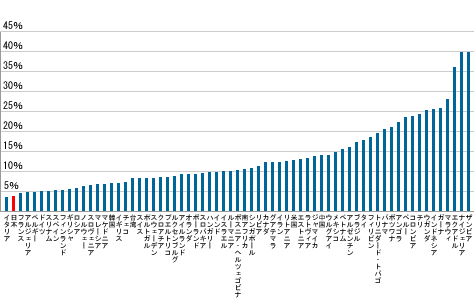
出所:平成25年度起業家精神に関する調査(GEM)
また、起業家のジャパニーズドリームを妬むような社会風土が少なからずこの日本にあることは、近年のさまざまな出来事からも想起できます。
このような状況や事実を踏まえ、日本のイノベーション創出の場としては企業・組織が適切なのではないか、との仮説を設定したのです。
戦略的決定が、組織の中からのイノベーションには不可欠
次に、イノベーション研究モデルの構成要素についてご説明します。
図表01のイノベーション研究モデルと、図表03のシュンペーターのマークⅡを見比べると、その違いがはっきりします。最大の違いは<イノベーション戦略>の有無です。組織としてイノベーション、つまり経済成果をもたらす革新を産みだすためには、戦略的決定が必要です。
イノベーションの研究は数多くの経済、経営学者及び思想家、事業家等が行っていますが、ほぼすべての研究者が言及していることがあります。それは、組織の中からイノベーションを興すためには【慣行の領域の外に出る】ことが必要不可欠だ、ということです。
シュンペーター氏は、新結合の遂行のため、慣行の領域の外に出る必要性を説いています。その際に、固定的思考習慣に陥ることや、普及の際に社会の抵抗を受けるような困難に直面する、とも語っています。
ドラッカー氏は、新事業は既存の事業と分離して組織する必要があると説明し、既存の事業とは異なるシステム、ルール、評価基準が必要だと主張しています。
『イノベーションのジレンマ』のなかでクリステンセン氏は、「バリューネットワーク」という概念を提唱します。「バリューネットワーク」とは、企業が顧客のニーズを認識し、対応し、問題を解決し、資源を調達し、競争相手に対抗し、利潤を追求する枠組みのことです。価値の測定基準がネットワークによって異なることに気付かないことが失敗に繋がるとし、企業は需要に合わせた能力・組織構造・企業文化を形成するが、そのこと自体がジレンマに陥っていると訴えたのです。
この他にも、マーチ氏はコンピテンシー・トラップの弊害を説き、ティース氏も野中氏も同じように言及しています。組織の中からイノベーションを興すには、【慣行の領域の外に出る】ことが絶対に必要なのです。
では、戦略的決定なしに組織が【慣行の領域の外に出る】ことが可能でしょうか?
現実的には非常に難しいと思われます。<イノベーション戦略>がない企業・組織で、現場が勝手にイノベーション創出を企てたとしましょう。スカンクワークスとかアンダー・ザ・テーブル、密造酒づくりといった試みは、例えばプロジェクトXやガイアの夜明け等でも数多く見ることができます。トップに黙って勝手に進める。何回もダメ出しされ、何度となく断られても、くどく試行を続ける。逆境に追い込まれ、辺境に追いやられても諦めずに進める。その結果、最後はトップが折れて、成果を認め、イノベーションが興きる。美談として語り継がれるこのような話は多々あるでしょう。
しかし、すべてのエピソードには、それが組織の中からのイノベーションであるならば、【慣行の領域の外】か【中】か、の判断があった筈です。【慣行の領域の中】のであれば、それは【革新】ではないからです。単なる既存事業の延長に過ぎません。若しそれが【慣行の領域の外】であるなら、波及・普及させるためには資源動員が必要です。資源動員には戦略的決定が必要であり、<イノベーション戦略>は不可欠のものです。シュンペーターが戦略をどう扱っていたかは分かりませんが、企業・組織を前提にする限り、戦略とイノベーションのプロセスを分けて考えることは合理的ではないのです。これが、<イノベーション戦略>をモデルに加えた理由です。
<イノベーション戦略>以外の項目についても言及しましょう。
モデルの一番左にある、<外生的な科学と発明>と<組織外の情報・知識>は、ほぼ同じ意味で使っています。オープンイノベーションは、正にこの領域を扱っている、今世紀に入って研究が進んでいる分野と言えるでしょう。
<内生的な科学と発明>に関しては、研究や事業開発のみならず、企画やアイデアから産まれるイノベーションもあることを考慮して、組織の構成員が何かを<思いつく>、というニュアンスに変えています。
<革新的投資のマネジメント>に関しては、投資はイノベーションのプロセスすべてに影響を及ぼすものと考えてその置かれている位置を変え、更に投資はカネのみならず人・モノ・情報・時間等の資源も必要と考え、<資源配分>に拡大解釈をしています。
<新しい生産形態>は、モノ以外のイノベーションもあることを考慮し、イノベーションを<磨く>というプロセスに置き換えています。
<市場構造の変化>は、構造変化の前には必ず市場への普及が必要と考え、<事業化>としています。
こうして、イノベーション研究モデルが完成しました(図表01)。これを基にしながら、23社のインタビューを進めていったわけです。
研究インタビューの概要
研究インタビューが何を行っているのかをまとめると、以下のようになります。
●アントレプレナーではなく、イントレプレナーが
●業種や規模、歴史等を限定しないさまざまな組織の中から
●経済成果をもたらす革新を
●社会に対して興している
ことに対して、
●シュンペーターの2つのイノベーションモデルのうち
●マークⅡを基にした研究モデルに則って
●企業・組織のイノベーターにインタビューをすることで
その内容や特徴・傾向を抽出していく。
2年間インタビューを実施してきて、23社の内容を俯瞰して考える機会が必要だと感じました。そこで、抽象度を上げたり下げたりしながら、虫の目で見直し鳥の目で考えて、いま一度イノベーターの方々の話を振り返り、その手触り感を思い起こし、組織の中からイノベーションを興すためのポイントを抽出しようと試みました。
尚、インタビューをまとめるにあたって、23社以外にも参考にした企業があります。それはリクルート(現在はリクルートホールディングス及び7つの事業会社、3つの機能会社と、その他の関係会社で構成)です。創業以来50余年、一貫して情報を扱ってきたリクルートは、その経営形態やマネジメントモデル、人事制度やコミュニケーション、新規事業提案制度創出の仕組み等が非常にユニークです。組織の中からイノベーションを興すということを体現してきた、といっても過言ではありません。自分が約30年所属してきたということもあり、手触り感をもって語ることができます。そのため、諸処でリクルートの事例が登場することをご容赦ください。
組織の中からイノベーションを興す8つのポイント
これらのインタビューの結果をさまざまな角度から検討した結果、組織の中からイノベーションを興す8つのポイントが見えてきました。
ポイント(1) 常識の泥沼から這い出せ~慣行の外に出るにはどうすればいいか
ポイント(2) 青臭い意志をもて~大義を決め、考え抜く
ポイント(3) 虫の目をもて、鳥の目ももて~抽象度を上げて、下げる
ポイント(4) とんでもない人間を唆せ~奇人・変人を見つけアサインする
ポイント(5) 人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな~兵站を確保する
ポイント(6) オープン! オープン! オープン!~開かれた実行部隊をつくる
ポイント(7) 矛盾をマネジメントせよ~ひたすら耐えて、根負けさせる
ポイント(8) 称賛という水遣りを忘れるな~誉め言葉を変え、認知と称賛を繰り返す
8つのポイントは、インタビューから抽出することができた数多くのエピソードによって補強されていきます。今回はまず、その見出しをご提示しました。次回、具体的なエピソードをご紹介しながら、組織の中からイノベーションを興すリアルに迫っていきたいと思います。
【総括(文):井上功】
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての