インタビュー
イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- 公開日:2015/06/24
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第30回は、ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社代表取締役の中石真一路氏にご登場いただきます。
中石氏は、難聴の方々が非常にクリアに聞こえるスピーカーシステムを提案し、大きなイノベーションを興し、社会を変えようとしています。それは、従来の補聴器のように難聴者側で問題を解決するのではなく、話者と聞き手の構造全体を捉え、コミュニケーションの様相を変えていこうというものです。それはまさに発想の転換であり、コペルニクス的転回です。それは一体どういう方法なのか? 百聞は一見にしかず。中石氏のイノベーションストーリーをご覧ください。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 音を増幅させるだけでなく、クリアな音を実現し 聞き取りやすい音質に変換する
- 遠くまで音を届けるスピーカーから 難聴者でも聞き取りやすいスピーカー研究へ
- 会社での事業化を断念し NPOを設立し独自で研究を継続
- 振動版は紙ではなくアルミ スピーカーらしからぬ形状
- イノベーションの原動力 目の前の人を笑顔にしたい
- 総括
音を増幅させるだけでなく、クリアな音を実現し 聞き取りやすい音質に変換する
掌に包み込めるくらいの卵型のスピーカーと鉛筆のように細長いマイク。たったこれだけで、軽度から中程度の難聴者の生活が一変する。補聴器なしで、声や音が聞こえるようになるのである。いや、聞こえは補聴器以上という。近眼の人が眼鏡をかけたような画期的なことだ。
COMUOON(コミューン)(R)という商品のことである。

特別、大きな音が発せられるわけではない。開発したユニバーサル・サウンドデザインの社長、中石真一路氏が説明する。「人間の声の子音にあたる1000Hzを境に音の圧力を卵形状のエンクロージャーであげています。言葉の明瞭度がアップし聞き取りやすくなるのです。もう1つの工夫は音の拡散を防いでいること。通常のスピーカーだと音が拡散してしまいますが、音の指向性を高め狭い環境でも壁面での反射がしにくい構造にしています
2013年12月に発表されると、斯界の話題をさらった。現在、同社からの寄贈分も含め、全国260を超える自治体の役所や医療機関、福祉施設、学校などで導入されている。特に聴覚特別支援学校や難聴学級での授業法を一変させつつある。今までは聞き取りが難しい言葉については口形をパネルで見せるなどして視覚情報に置き換えて教育していた。
例えば、英語の授業では、難聴者は「Books」の「s」などがよく聞き取れないので、生徒たちも聞き取りに苦労していたが、このCOMUOONを使えばはっきり聞き取れるのだ。30年以上、聴覚学級の指導を行ってきた教諭も「生徒の苦手意識が薄まり、授業が一変した」と喜んでいる。

子供たちだけではない。高齢社会は難聴社会でもある。昨年は1000台余りが売れ、今年は海外での販売を計画している。
この製品の画期的なところは、難聴者自身が補聴器をつけることによって、音を増幅させたり調整をするこれまでのやり方とは違い、話者側がマイクに向かって普通に話をすることによって、聞こえやすい音声を届けることが可能になる、という点だ。しかも補聴器は日々技術革新が行われているものの、万能ではない。音源から離れれば、おのずと聞こえにくくなる。COMUOONはその点、最大80センチ※までスピーカーと聞く人を離しても大丈夫だという。この独創的製品はいかにして形となったのか。
※ 個人の聴力レベルによります。
遠くまで音を届けるスピーカーから 難聴者でも聞き取りやすいスピーカー研究へ
中石氏が大手レコード会社のEMIミュージック・ジャパン(現ユニバーサルミュージック)に在籍していたときのこと。アーティスト関連のウェブおよびシステム全体を管理するプロデューサー兼ディレクターの職にあったが、もともとは新規事業開発を希望し、同社に中途入社していた。テーマは次世代スピーカー。音を遠くまで飛ばす技術が開発できればライブやコンサートで重宝すると考えていた。
あるとき、社長の付き人として慶應義塾大学環境情報学部の武藤佳恭教授のセミナーに参加したところ、小音量でも遠くまで音を飛ばせる、まさに自分が作りたいと願っていたスピーカーとアンプを見せてくれた。特にスピーカーはスズムシが羽をすり合わせて音を出す原理を応用したもので、「スズムシスピーカー」と教授は呼んでいた。
これだ! 中石氏は、このスピーカーの商品化をやらせてほしいと社長に申し出た。ちょうど会社が設立50周年で、何か新規事業を、という機運が高まっていたこともあって研究開発案件として承認してくれた。2010年のことである。
研究を進めていくうち、思いがけない発見があった。武藤教授いわく、難聴の人に音を聞かせたところ、「聞こえやすい」と言われた、というのである。
中石氏も最初は半信半疑だった。中石氏の父が難聴であったので、試作機を実家に持ち込み検証を行ったところ、テレビの音量が四六時中、大きかった実家がみごとに静かになった。父もこう言った。「これ使うと、よく聞こえるぞ」と。
会社でも実験を行った。軽度と中度の難聴者7名に集まってもらい、音を聞かせると、やはり聞こえやすいとの意見があった。
中石氏は決断した。音を遠くに飛ばすスピーカーではなく、難聴者でも聞こえやすいスピーカーを作ろうと。
実は父だけではなく、中石氏の祖母も難聴者だった。音が聞こえなくなると人間の生活に深甚な影響を及ぼす。その人には話しても無駄、という雰囲気が生じ、自然と疎外されていくのである。中石氏はそのことを深く実感していた。
会社での事業化を断念し NPOを設立し独自で研究を継続
研究の方向性が変わったので、会社に報告して了承を得なければならなかった。本格化する高齢社会を迎え、スピーカーにどのくらいのニーズが発生するかを分析した事業報告書を作った。
が、折角のプレゼンに社内は乗ってこなかった。「レコード会社がなぜ難聴者のためのスピーカーを開発しなければならないのか」
半分は予想されたことだった。「何としても研究は継続したい」という意思を伝え、知人と共に立ち上げたNPOでの研究については認めてもらった。
2011年11月、NPO法人 日本ユニバーサル・サウンドデザイン協会を立ち上げ、難聴者でも聞こえる音の研究および健聴者の難聴への理解促進に邁進する。全国からスピーカーを集め、試作機の開発と検証を繰り返した。
研究を進めていく上で必要なのは理解者だ。音響工学や補聴器を専門に研究している教授を紹介してもらい会いに行った。「難聴者でも聞こえるスピーカーなんてあり得ない」という反応の研究者もいたが、非常に面白いと協力してくれる教授も現れた。
次に大切だったのが難聴の方の協力だ。「これが本当に苦労しました。難聴の方にモニターになってもらえませんかと言っても、なかなかOKとは言ってくれません。『何か企んでるんでしょう?』と言われる始末でした。しかし、『難聴者でも聞こえやすいスピーカーを研究している人がいる』という噂が少しずつ広まり、全難聴の方との接点ができたことで検証に協力してもらえる体制が広がっていきました」
振動版は紙ではなくアルミ スピーカーらしからぬ形状
2013年3月、NHKの朝のニュースで「難聴でも聞こえやすいスピーカー」としてNPOでの研究について取り上げられると、「どこで買えるのか」「商品化はいつか」といった問い合わせが殺到。「まだ最終商品までいたってなかったのですが、『これだけ製品を望んでいる人がいる』ことを確信したことで、これまでの開発が無駄ではなかったと自信になりました。退路を断つため6月末でユニバーサルミュージックを退社しました
研究を重ねていくうち、中石氏はスピーカーの振動板に着目する。通常のスピーカーの場合、振動板はコーン形状(すりばち状)であり、素材は紙などが採用されている。中石氏はもっとよい素材があるのではないかと考え、さまざまな素材で試した。そして2年に及ぶ試行錯誤の結果、アルミハニカムパネルに辿りつく。
早速、試作機を製作し難聴者に使ってもらったが、「音自体はいいが、いかにも大きな音が出そうで、そばに置きたくない」という意外な反応が返ってきた。そこで、スピーカーのデザインを一新。現在のような卵型の可愛らしいものにしたところ、「これは何? 可愛いわね!」と利用者の顔から笑みがこぼれた。検証実験に協力してくれた難聴者の数は100名を超えた。かくして、その年の12月に商品が発売されたのである。研究を始めてから3年余りが経過していた。
イノベーションの原動力 目の前の人を笑顔にしたい
中石氏は幼い頃は発明少年だった。小学校4年のとき、隣の家の柿をとるため、網の上に鋏をつけた虫取り網を作って獲物をせしめた。家の軒先においていたのを父親に見つかる。用途を話して怒られるかと思ったら、「お前は天才だな」と逆に褒めてくれた。
虫取り網にも工夫を加えた。細い木に止まっているセミも逃がさずにつかまえられるよう、網の部分を改良したのだ。「年下の子供たちに、たくさんセミをとってヒーローになっていましたが、子供心にこう思っていました。皆、すげぇすげぇと言うものの、どんな原理でセミが逃げないようになっているかを探ろうとも尋ねようともしない。それを聞いて真似すれば、同じようにたくさんのセミを自分でとれるのに、もったいないなと」
その後、中石氏は、「一流大学、一流企業」というエリート街道とはまったく別の道を進む。「兄弟が多く、家計が大変そう」だったので、大学進学はせず、ゼネコンに就職。ところが現場で怪我をしてしまい半年近くリハビリに通う。学歴の大切さを改めて痛感し、退職後に建築の専門学校に通い、卒業後しばらくは建築業界に戻って働くが、ITの可能性に興味をもちデジタルハリウッドへ。身に付けたウェブ技術をもとに、以後、12年余りの間にIT関連企業を10社ほど転々とする。その間、携帯電話のカメラにQRコード読み取り機能を導入するプロジェクトに参画するなど、さまざまなアイデアを提案し貢献してきた。
スズムシスピーカーという土台となる発明はあったものの、難聴も医学も音響学も体系的に学んだことのない中石氏が、なぜこのイノベーションをほぼ独力で成し遂げることができたのか。「難聴で困っているたくさんの子供たちや、そのお母さん方に出会ってしまったからです。目の前に難聴で苦しんでいる人たちがいる。それが私が見た現実でした。お会いしたら知り合いです。知り合いだからこそ何とかしてあげたいという気持ちがふつふつと湧いてきたんです。机の上でパソコンとにらめっこしながら、市場規模的にこの層をターゲットに、などとビジネスのみの視点で考えている人たちとはそこが違う。唯一の後悔は、難聴で苦しんだ祖母にCOMUOONを使ってもらえなかったことです」
身近な1人は救えなかったかもしれないが、世界に5億人、10年後には9億人に増えるともいわれる難聴者が、今COMUOONを待っている。
総括
中石氏のイノベーション創出ストーリー、いかがでしたか?
では、さっそくイノベーション研究モデルを踏まえながら中石氏のイノベーションを振り返ります。
注目するのは、【組織外の情報・知識】から【思いつく】【磨く】【事業化】まで連なる1本の線です(図表01参照)。
それでは、さっそく、大義ある中石氏の行動を深掘っていきましょう
図表01 イノベーション研究モデル
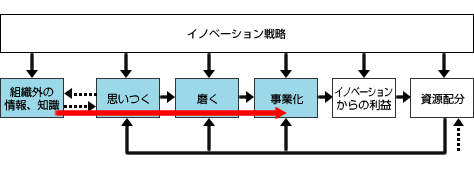
子供のころに育まれた
本質を追求する姿勢
中石氏は子供の頃から本質を追究する姿勢をもっていて、それを実践的に磨いていました。隣の家の柿の実をとるために、網つきの高枝切り鋏を発明して、難なく柿を得ています。虫取り網の改善も、徹底していました。セミは太い幹の木以外にも止まることが多いため、細い幹のカーブにフィットするように、網の形状を変えました。そうするとセミに網を被せたときに、網の脇からセミが逃げてしまうのを防げるのです。
工夫をすることで本質に迫ることができる。中石氏はそう思ったに違いありません。同時に、本質に目を向けない自分の周りの人たちのことを、もったいないと言っています。ちょっとした見方や考え方を変えることで、結果や成果が大きく変わる。真理に近づく。人と同じことをやっていても前に進むことはできない。そんな中石氏の発想と実行が、その後のキャリアでも新しい価値の創造に繋がっていきます。ゼネコン→怪我→建築の専門学校→ゼネコン→IT企業……。働いた会社は10社に及びますが、そのなかでいくつものイノベーションを興しています。ユニバーサル・サウンドデザイン社を立ち上げる前には、なんとQRコードを携帯で読み取るビジネスモデルのコンサルティングに携わることになるのです。それは、物事の本質を追究する姿勢から生まれたといっても過言ではありません。
鳥の目で見る
虫の目で見る
COMUOONはコペルニクス的転回、と書きました。それは、当たり前の否定から始まります。
難聴者は、自ら補聴器をつけて聞こえやすくするもの
補聴器は耳に装着するもの
障害は、障害のある人が自ら乗り越えるもの
声や音が聞こえにくくなることは、加齢の影響からくるもの
レコード会社は、音に携わるが難聴者への理解は必要ないもの
何々はこういうもの、という風に頭のなかで決めつけてしまうことは、日常生活でよくあります。常識です。それは、イノベーションの可能性を否定してしまう。
中石氏は、難聴者は補聴器をつけるもの、という常識を根本的に疑います。コミュニケーションは相対で行うものであるならば、難聴者側ではなく話しかける側が工夫し努力すればいいのではないか? それは、まさにコペルニクス的転回です。
難聴者が聞こえやすくなるためには一体何が必要なのか、という物事の本質を、鳥の目で俯瞰して考え抜いて、コミュニケーションの様相に辿りつく。難聴者が実際何に困っているかについては、虫の目で核心に迫る。鳥の目と虫の目の、行ったり来たりでCOMUOONのコンセプトは磨かれ続けたのです。
事実と真実は異なる
手触り感を得て前に進む
中石氏のCOMUOON開発のストーリーには、難聴で苦しんでいる人たちの真実が常にありました。それは事実ではありません。真実、もっというと『本当の真実』とでも言うべきものです。
イノベーション創出支援のコンサルティングを行っていると、新規事業の提案書を見る機会が多くあります。そこでは、「認知症の患者が現在日本では400万人います。それが2025年には800万人になるのです」とか「BOP層の人口は現在20億人以上います。彼らが一番困っているのは水です」「企業内でのメンタル発症者の割合は過去10年間増加の一途を辿っています」「介護分野における政府の負担は今後20年間でほぼ倍になります」といったことがまことしやかに語られます。そして、その殆どが、グラフや表で示されます。
ネットを検索すると、その殆どがものの数分で手に入ります。これらは間違いのない事実です。しかし、真実ではない。ましてや、『本当の真実』ではあり得ない。手触り感のある真実は、ネット上にはありません。中石氏は難聴で困っているたくさんの子供たちやそのご両親に実際に会っています。一人ひとりと真摯に向き合い、対話し、何に困っているのかを掴んでいます。その過程で、自分は一体何をすべきなのかを常に自問自答していったともいえるでしょう。そして、前に進み続けているのです。
事実と真実。ネットと圧倒的な手触り感。極めて修辞的で感覚的な違いであり、微差かもしれません。しかし、その間には、中石氏の「父親の役に立ちたい」「目の前の人を助けたい」という純粋な気持ちと、真実を掴む行動があったのです。
中石氏のイノベーションに、これからも目が離せません。
【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】
PROFIL
中石 真一路(なかいし しんいちろう)氏

1973年東京都生まれ、熊本県育ち。慶應義塾 大学SFC研究所 所員。 デジタルハリウッド卒業後、12年間にわたりプロジェクトマネージャーとしてwebサービス開発に従事。
2011年11月NPO法人日本ユニバーサル・サウンドデザイン協会設立に参画、約3年にわたる研究の末スピーカーシステムによる聴覚障害者の支援技術の開発に成功、卓上型会話支援機器「COMUOON(R)」を世に送り出す。 2012年4月ユニバーサル・サウンドデザイン株 式会社を設立。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての