インタビュー
イノベーション研究 第1回 エキュート
通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 公開日:2013/01/30
- 更新日:2024/03/31

- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 組織の中でのイノベーション創出
- エキナカが目指したのは駅のノーマライゼーション
- 駅の特性調べ、百貨店と駅ビルの違い まずは現地・現物で課題を確認
- 情と理の双方を駆使し交渉と説得を繰り返す
- 上から下まで一枚岩 だからこそ無理も効いた
- 総括
組織の中でのイノベーション創出
問題意識
まず、「組織の中でのイノベーション創出に関する調査・研究」を行っている背景についてご説明します。2011年現在で6300万余名と推定される日本の生産年齢人口の大半を占める企業内就業者が、従事する組織の中でイノベーションを興すことが、世界で日本の価値を高めることに繋がると考えています。しかし、失われた20年に代表される長期の経済低迷、少子・高齢化の進展、財政懸念、新興国の台頭、IT技術の急速な進展、成功体験の呪縛、政治の混乱といった様々な問題が目の前に立ちはだかり、特にここ数年は、大胆な一歩を踏み出せていないのではないでしょうか。
一方、このような状況下でも、着実・確実にイノベーションを興している人や組織があります。彼らは日本国内のみならず、世界の先進国、新興国、BOP層に対してもイノベーションを推進しています。そのようなイノベーターの方々や当該組織に取材をすることで、イノベーション創出のヒントを得たいと考えました。本レポートでは、その取材から得たエッセンスについてご紹介してまいります。
定義について
「組織の中でのイノベーション創出に関する調査・研究」としましたが、その定義について事前にお伝えしておきます。
まず組織についてです。冒頭で申し上げたように、生産年齢人口の圧倒的多数が、個人事業主ではなく組織の中での就業者です。ここで取り扱う組織は、その多くが株式会社を中心とした企業になると思われます。ただし、近年急速にその存在感を増しつつあるNPO、NGO等の組織や、団体・連合会、中央官庁、地方公共団体等の組織も調査・研究対象として含めます。
次に、イノベーションをどう捉えるかについてです。過去の通商産業白書において、イノベーションが「技術革新」と訳されて紹介されて以来、日本ではイノベーションは技術的要素を前提としたものというイメージが強いと思われます。一方、急速に普及しつつあるiPadに代表されるタブレット端末に活用されている技術は、今まで存在していたものの組み合わせだということは広く知られています。今後も、革新的な所謂「技術革新」は起きるでしょう。同時に、必要なのは技術にこだわることではなく、新たな価値を創ることと考えます。そこで、イノベーションを以下のように定義しました。
<経済成果をもたらす革新>
イノベーションの研究は、100年前のシュンペーターに始まり枚挙にいとまがありません。ここではそのレビューをするのではなく、いかに組織の中から「経済成果をもたらす革新」が興せるのか、に焦点をあてていきます。
なお、統計解析を基にした研究は、当初は行いません。最初の数ヶ月は、イノベーションを興した方(チーム)に取材して、価値創造の苦労やプロセス、そもそもの動機、こだわってきたこと、組織内・外とのコミュニケーションの工夫、組織・制度側の仕組み等の抽出を試みていきます。ただし、イノベーターへの取材を通じて今後そのような研究に発展する可能性はあると考えています。
研究モデル
このように、<経済効果をもたらす革新>を、組織の中からどう生み出してくのか、がリサーチ・クエスチョンとなりますが、仮説として、図表01のようなモデルを設定しています。シュンペーターの「マークⅡモデル」を踏まえ、「内生的な科学と技術」「革新的投資のマネジメント」「新しい生産形態」「イノベーションからの利益」といった概念を、現代的要素を加味して、「思いつく」「磨く」「事業化」「資源配分」に変更しています。また、組織の中での意思決定がイノベーション創出に大きな影響を与えることが想定されるため、「イノベーション戦略」を全ての要素に関わるものとして置いています。線形の流れに見えることが個人的には多少違和感がありますが、初期モデルとして置いて、イノベーターの方々のインタラクションの様相を、このモデルを通して眺めてみようと思います。
図表01 イノベーション研究モデル
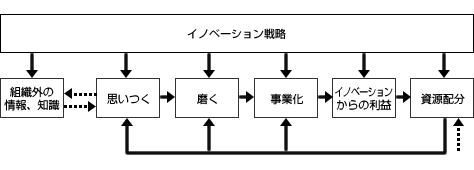
第1回として、エキナカの代名詞であるエキュートを立ち上げたJR東日本の鎌田由美子氏の事例をご紹介します。
エキナカが目指したのは駅のノーマライゼーション
駅がどんどん変わっている。美しく便利になっていく。その先鞭をつけたのは、2005年、JR東日本が大宮駅と品川駅にオープンさせたエキナカ、通称エキュートであるのは間違いない。
JR東日本は、もともと公社である国鉄の分割民営化によって1987年に誕生した。国鉄時代の駅とは、純粋に列車の乗り降りをする場であり、それ以外には、キオスクや立ち食いそば屋といった限られた業態しか存在しなかった。
が、民営化により事情が一変した。収益拡大を期して、1997年、事業創造本部が同社内に設置され、鉄道事業に加え、駅を基盤とした小売、飲食、ホテルなどの生活サービス業の育成が急務となった。当時、「鉄道7割」対「それ以外3割」だった事業比率を「それ以外4割」にするのが経営目標となった。
それを象徴するキーフレーズが「ステーションルネッサンス」であり、それを具現化したのがまさしくエキュートなのである。すなわち、駅の改札内に“異空間”――ひとつのコンセプトで統一された、駅ビルでも百貨店でもない、まったく新しい物販・飲食スペース――を出現させたのだ。現在、エキュートは前記2カ所に加え、立川、日暮里、上野、品川サウス、東京、赤羽の計8カ所にまで増えている。
このエキュート誕生と成功の立役者が同社社員の鎌田由美子氏(現・同社事業創造本部 地域活性化部門 部長)である。
発端は、東京・吉祥寺の駅ビル会社に出向し、テナント開発を行っていた鎌田氏が2001年11月、突然、事業創造本部に呼び出され、上司の新井良亮氏(現・ルミネ社長)から「立川駅・大宮駅開発プロジェクト」のリーダーに命じられたことだ。
その際、与えられたのは、「通過する駅から集う駅へ」という、「ステーションルネッサンス」の中身をより具現化した言葉と、両駅の工事日程から導き出されるわずか3年という期間、それに具体的な場所のみ。最初は部下も2人だけだった。
鎌田氏は「晴天の霹靂だった」と、当時を振り返る。鎌田氏はJR東日本初の四大卒文系女性社員として1989年に入社。最初は上野駅の旅行センターに配属されるが、流通に興味をもち、自ら願い出て百貨店に出向、2年の間に20カ所にも及ぶ売り場・部署を経験。後に、「百貨店の鬼」とまで社内で言われるようになっていた。
駅の特性調べ、百貨店と駅ビルの違い まずは現地・現物で課題を確認
鎌田氏は部下と一緒に、まず大宮駅に向かった。計3日間、午前4時台の始発から零時を回る終電までの終日、駅構内に立って、乗客の様子を観察したのだ。そこで分かったのは「(百貨店と違い)客が立ち止まらない」というショッキングな事実だった。
さらには、新宿の百貨店にも部下を連れて足を運んだ。フロアに立ち、目をつぶって耳を澄ませてみる。次に、駅ビル・ルミネにも行き同じ動作を繰り返す。百貨店では単一の音楽しか聞こえないが、ルミネでは複数の音楽が流れている。これが自主編集型フロアとテナントの違いであり、自分たちがこれからやるのは前者であることを、自分も含めたメンバーたちに身体で覚えさせようとした。
一方で、既存の百貨店とも違う空間を目指さなければならない。本人が話す。「百貨店でもスーパーでも、入り口と出口は決まっています。だからメインの入り口前に生鮮食品を置く百貨店はありません。でも、駅の中はどこでも入り口になるし、出口にもなります。そこにどんな業種を並べようが、すべて自由。私にはそれが楽しかった」
その鎌田氏には「新業態を立ち上げなければ」という気負った思いはなかった。もっていたのは、「無機質な場所を楽しくしたい」という思いだったという。
その思いは、大学で社会福祉を専攻した鎌田氏が好きな言葉につながる。「ノーマライゼーション」である。障害者などが地域で普通の暮らしを営むのが当然だとする福祉の考えを表現した言葉で、「通常化」と訳される。実は就活時にもそれを訴えた。「鉄道や流通に興味があって入社したわけではありません。よく利用していた上野駅が当時はバリアフリーの対極で非常に使いづらい状態だった。社会福祉の視点を生かして、そうした駅がもっと使いやすくなればいいのに、と面接で話しました」(鎌田氏、以下同)
駅が「無機質」なのにはしかるべき理由がある。安全かつ確実な定時運行を確保するためだ。しかし、それは「人が通過する場」として駅をとらえた場合であって、「人が集う場」として考えれば、無機質一辺倒ではなく、ある部分は「有機質」であってもよい。これがエキナカを考案するにあたっての鎌田氏の根底にあった考えだ。それは駅を特別な場所ではなくすること、つまり、ノーマライゼーション(=通常化)の思想とも根底において通じているのは言うまでもない。
情と理の双方を駆使し交渉と説得を繰り返す
さて、駅改札内に自主編集型のテナントスペースを出現させる、という基本方針は固まった。それぞれのコンセプトも決まった(大宮は「マーケットアベニュー」、品川は「プレミアムプライベート」)。問題は2つあった。ひとつはテナント誘致であり、もう一つは社内の説得である。前者から説明しよう。
それは「地獄のMD(マーチャンダイジング)会議」と部下たちから呼ばれた。コンセプトに沿って、社員それぞれが探し出してきた店を吟味し、出店交渉の対象店を決める場である。毎週木曜日の午後4時から始まり、終わりは夜の10時、11時。鎌田氏が駄目出しを繰り返し、場がいつも紛糾した。「売れているから」「高級ブランドだから」「おいしいから」、こうした理由は即、却下。なぜその商品がエキュートに置かれなければならないのか、が拙いものであっても、自分の言葉で語られなければならなかった。
「公開処刑」とまで言われたその関門を潜り抜けた後の出店交渉も難航を極めた。電話で断られるのは序の口、たとえ面会できた場合も、駅構内という場所を明かすと、「うちは無理」とにべもない反応ばかり。年中無休の長時間営業や商品量の確保に対応できない、という理由で断る店も多かった。「大宮の場合、声をかけた8割に断られました。残る2割も、部下たちの懇願に折れ、情にほだされて入ってくださったようなものです」

もう一つの難関は社内の説得と調整である。
鉄道事業は旅客運送を円滑に行うため、山のようなルールによって成立している。しかも駅を構成するさまざまな物品は複数の部署に所属している。照明ひとつとってみても、従来の、無機質な蛍光灯から、落ち着いた間接照明に変えるだけでも、大変な手間を要した。
なかでも、最も手間を要したのがトイレの問題だ。駅のトイレの便座数は利用者の割合で決まる。通常、駅の利用者は男性のほうが多いため、男性用トイレは女性用トイレより面積が多くなっている。
でもエキュートのような施設を立ち上げると、女性客が多い。しかしその仮定には前例がなく交渉は難航した。
「社外は思いや夢といった定性論が通用しても、社内は違います。床の磨耗度やすべりといった安全性、価格、メンテナンスの簡潔さやコストといった、データを元にした定量論を示して説得することを心がけました」
上から下まで一枚岩 だからこそ無理も効いた
次々にたちはだかる困難と、鎌田氏の理想の高さは、最後には内装や設備の施工業者へのしわ寄せとなった。鎌田氏含め全員が連日、深夜まで現場に張り付き、仕事をサポートした。その姿勢を意気に感じた業者も不眠不休で頑張った。
ようやく形になった時、鎌田氏は感極まり、声をあげて立ちつくしたという。「完全なチームワークの結果だと思います。上も下も強烈でした。直属上司の新井さんはもちろん、副社長だった細谷さん(英二氏。後に、りそな会長。故人)も絶対にぶれませんでした。そうした強力な上司がいても、時々は心が折れそうな時があります。そんな時、ふっと後ろを見ると、必死になってついて来る部下がいる。この人たちの前で絶対に弱音は吐けないな、と思い、また頑張れたのです」
鎌田氏はアントニオ・ガウディの建築が好きだという。石や鉄という硬く冷たい素材を使っているのに、なぜこんなに軟らかいフォルムになっているのか、最初に見たとき、感動のあまり涙が止まらなかったというのである。「この軟らかさや和み感が駅で再現できないだろうか、真剣に考えました」

この発想力、この知的好奇心をもってすれば、駅はこれからも進化し続けるだろう。買い物のために「集う駅」から、鑑賞のために「集う駅」へ。今、約100年前の姿に蘇った新生・東京駅は、その姿を一目見ようという観光客でいっぱいだ。この延長線上で、いつの日か我々は、ガウディ品川、ガウディ東京を目にすることができるかもしれない。
総括
イノベーション戦略と戦略推進者
図表02 本事例における仮説モデルの該当要素
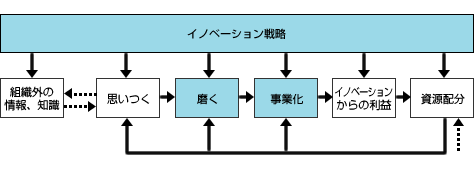
鎌田氏のエキュート開発ストーリーは如何でしたか。ここからは、前述したモデルに則って、エキュートのイノベーションを振り返ります。
JR東日本のエキュートという<経済成果をもたらす革新>の場合、最初に戦略ありきであったと言えるでしょう。今から15年も前に「事業創造本部」が組織内に設置されています。民営化がひとつのきっかけになったのは間違いなさそうですが、当初から「ステーションルネッサンス」というキーフレーズは存在し、「通過する駅から集う駅へ」というコンセプトも明確でした。
ただ、鉄道会社にとって全く異なる概念のサービスを推進するのは、想像を絶する苦労の連続だったに違いありません。その前提としてイノベーション戦略がありました。「ステーションルネッサンス」は、謂わば金科玉条だったのでしょう。鉄道事業の資産を活用しているとはいえ、顧客、顧客価値、収益モデル、競争優位性等が全て異なる事業開発は、そう簡単に出来るとは思えません。当時から今に至るまで、JR東日本には2つの会社が存在しているとみなすことも出来るのではないでしょうか。そして、そのシナジーが最大化されているのが、まさに今現在なのでしょう。多角化と言うと簡単ですが、鉄道事業というインフラを活用したサービス業への展開は、当初から設定されていた「ステーションルネッサンス」という名のイノベーション戦略が存在していたからこそ成し得た技だったのでしょう。
では、戦略があればいいのか、というと話はそう簡単ではありません。推進しやり切る執行者がいないと、戦略は画餅に終わります。JR東日本は鎌田氏を選びました。では、何故、鎌田氏が選ばれたのか。インタビューの中で鎌田氏はご自身のことを「アウトロー」という言葉で話しました。同時にメンバーのことを、「個性的」とか「つわもの」、と表現しています。
自社の考え方や価値観、業界の慣習や常識、顧客や顧客価値そのものに捉えられてしまうことを、「フレーミング」や「バリューネットワークに嵌る」と言います。この所謂フレーミングが邪魔をして非連続のイノベーションが生まれない、ということはよく知られています。鉄道会社において、安全、安心、信頼、確実の価値提供は絶対的ですし、その価値観で長らく事業推進をしてきた方には、若しかしたらエキュートのプロジェクトは出来なかったかもしれません。これはまさに、アウトローを自認している鎌田氏ならではの成功だったのではないでしょうか。
アウトローをアサインした以上、アウトローに暴れさせる。それは、一見ごく普通のことに思えますが、エスタブリッシュメントにとっては相当難しかったのは想像に難くありません。また、最後に責任を取る人がいないと、このようなイノベーション実現は不可能でしょう。鎌田氏は、「上から下まで一枚岩」とはっきり話しています。「直属上司も最終責任者の副社長も絶対にぶれませんでした」とも語っています。
JR東日本のエキュートの場合、ステーションルネッサンスというぶれないイノベーション戦略があり、既存事業とは価値の異なる新規事業を、既存事業とは異なる考え方を持ち行動する人材が、現場感に徹底的にこだわって推進した、と言うことが出来ます(図表02網掛け部分)。得てしてぶれがちなイノベーション戦略(≒新規事業戦略)をきちんと設定し、徹底して推進している方々がいるJR東日本の凄みを感じずにはいられません。
【インタビュー・文:井上功 /文:荻野進介】
PROFILE
鎌田由美子氏
東日本旅客鉄道株式会社/事業創造本部 地域活性化部門 部長
1989年東日本旅客鉄道株式会社入社。
2001年に本社事業創造本部「立川駅・大宮駅開発プロジェクト」においてエキナカビジネスを手がける。2005年、『ecute』を運営するJR東日本ステーションリテイリング代表取締役社長に就任。
2008年11月本社において地域活性化事業を手がけ、2010年6月より現職。
現在、茨城県農政審議会農業改革委員、学校法人日本女子大学評議員も務める。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての