インタビュー
イノベーション研究 第26回
組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- 公開日:2015/02/25
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。今回は、これまでの研究成果についての中間報告の後編です。
23社に及ぶインタビューと、リクルート等の事例を俯瞰した結果、組織の中からイノベーションを興す8つのポイントが見えてきました。
ポイント(1) 常識の泥沼から這い出せ~慣行の外に出るにはどうすればいいか
ポイント(2) 青臭い意志をもて~大義を決め、考え抜く
ポイント(3) 虫の目をもて、鳥の目ももて~抽象度を上げて、下げる
ポイント(4) とんでもない人間を唆せ~奇人・変人を見つけアサインする
ポイント(5) 人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな~兵站を確保する
ポイント(6) オープン! オープン! オープン!~開かれた実行部隊をつくる
ポイント(7) 矛盾をマネジメントせよ~ひたすら耐えて、根負けさせる
ポイント(8) 称賛という水遣りを忘れるな~誉め言葉を変え、認知と称賛を繰り返す
後編ではこの8つのポイントの後半4つを、事例を交えて見ていきます。前編・中編と併せてご一読いただければ幸いです。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- ポイント(5) 人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな ~兵站を確保する
- ポイント(6) オープン! オープン! オープン! ~開かれた実行部隊をつくる
- ポイント(7) 矛盾をマネジメントせよ ~ひたすら耐えて、根負けさせる
- ポイント(8) 称賛という水遣りを忘れるな ~誉め言葉を変え、認知と称賛を繰り返す
ポイント(5) 人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな ~兵站を確保する
後編では、まずイノベーションを興すためにはどうしても必要な兵站(人・モノ・カネ・知恵・機会)に注目しましょう。イノベーション研究モデルでは、資源配分の領域になります(図表01参照)。
図表01 【人・モノ・カネ・知恵・機会を絶やすな】の研究モデルでの領域
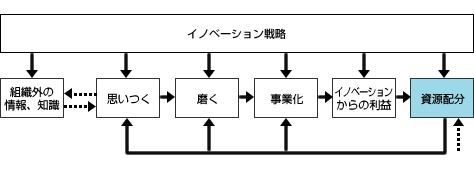
イノベーションを興すには、資源(兵站)が必要です。例えば、皆さんの頭脳のなかで世界を変える素晴らしいアイデアが閃いたとしましょう。それを、一人きりで磨いて磨ききって、果たしてイノベーションといえるでしょうか? 過去のすべてのイノベーションは、一人で成立したものではありません。一人ではアイデアは磨ききることはできず、またイノベーションは社会に普及しないと革新とはいえないからです。普及する際には、必ず資源の力が必要です。発想を磨く人や知恵、形にするための支援となるモノ、社会への波及展開を促すためのカネ(資本)。これらはすべて、必要欠くべからざるものです。そして、イノベーションにはタイミング(機会)が重要です。素晴らしいアイデアも、それを受け入れる時代的背景や社会的土壌、言い換えると機会が必要なのです。
この兵站を確保する、ということを非常に効果的に進めている事例を紹介します。三井物産です。2012年の初頭、飯島彰己社長から高荷英巳氏は、三井物産が新しいものに触れられるようにしてほしい、との依頼を受けます。これを、会社をイノベーティブにしてほしい、というオーダーと捉えた高荷氏は、まずイノベーションに取り組む機会として、プロセスに注目します。既存事業の延長線上にある連続的成長のための資源動員とは異なる、中長期的な成長をもたらす、ただし不確実でもあるイノベーション案件を検討する機会自体が必要と考えたのです。三井物産のような巨大で、長い歴史を重ねている企業体にとって、意思決定のプロセスを変えることが非常に困難であることは想像に難くありません。高荷氏は、イノベーション推進案件に関する新たなプロセスの導入を経営陣に持ちかけ、それを実現するのです。
機会を確保した高荷氏は、人の資源動員も進めます。イノベーション案件を目利きする人です。総合商社は有為な人材の宝庫とはいえ、社内だけで世界中からオファーがくるような最先端のイノベーション案件を見極めるのは不可能です。そこで、世界中のさまざまなメガトレンドに関する専門家をネットワークしていきます。その数100名以上。当該分野における世界での第一人者のネットワークを2年で作り上げていくのです。
次はカネです。イノベーション推進案件を進めるには、絶対的にカネが必要です。飯島社長に請求した額は、年間500億円! さすがに全額は承認されませんでしたが、1年間に投資可能な資金200億円を獲得することに成功します。このようなダイナミズムでイノベーション推進のための兵站を確保できている企業を他に知りません。三井物産全体がイノベーションに向けて懸命に進んでいる印象を受けます。
<第21回 三井物産株式会社>
ポイント(6) オープン! オープン! オープン! ~開かれた実行部隊をつくる
次に、イノベーションを興すプロセスに注目します。イノベーション研究モデルでは、下記のような領域になります(図表02参照)。組織外の情報、知識と、思いつく、磨く、事業化の領域でのコミュニケーションであり、インタラクションともいえます。
図表02 【オープン! オープン! オープン!】の研究モデルでの領域
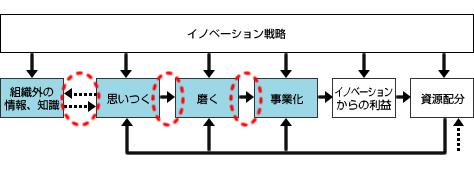
最先端のオープン・イノベーションを推進している企業として、大阪ガスが挙げられます。その施策を推進してきたのが、オープン・イノベーション室室長である松本毅氏です。オープン・イノベーションとは、イノベーションを実現するにあたり、自前にこだわることをやめ、これまで関係がなかった異分野・異業種のなかから最適な知恵のパートナーを見つけ出し、協働して経済的成果を出すことです。
その本質は、『開く』『繋がる』ということにあります。大阪ガス単独では解決できないニーズ(課題)を開示する。それは、いわば弱点の公開です。「ここはわれわれにはできないので、知恵を貸してください」と宣言することです。人間誰しも、自分の弱点を曝け出すことには躊躇します。法人格をもつ企業も同じです。相当な覚悟がないと難しい。では、なぜ松本氏はオープン化に舵を切ったのでしょうか? 松本氏は、製品ライフサイクルの短縮と技術の複雑化が背景にあったと語っています。消費者のニーズやウォンツが多様化した今、それらを十把ひとからげに捉えた商品・サービスでは市場は受け入れてくれません。ITは加速度的に進化し、顧客とのコミュニケーション手法は簡便化してその容易性を増し、一方、必要な技術の領域は飛躍的に広がっています。にもかかわらず、企業一社が単独で保有できる資源は制限され、活用できる技術は急速に限定的になっています。
技術を、【組織が労働力、資本、原材料、情報を、価値の高い製品やサービスに変えるプロセス。製造・マーケティング・投資・マネジメントなども包含する】と捉え直すと、なおさらその傾向が強まっていることに気付かざるを得ません。『開く』ということは、この時代、すべての企業に求められていることなのです。
そして、『開く』ことで、『繋がる』が促進されます。社内の課題(ニーズ)と社外の技術が繋がるのです。組織内外の知が繋がり、組み替えられ、新しい知が創出され、全く新しい価値が創出されるのです。それは、組織内外の脳が繋がるということです。一人の脳を点とイメージしてみます。点は点に過ぎない。けれども二人が繋がると線ができます。脳と脳が繋がり、線が生まれるのです。では、三人だとどうでしょう? 三人の脳、つまり点が繋がると、三角形ができます。三角形の面積は、お互いの距離が離れていればいるほど大きくなります。社内の同じ目的や目標をもち、同じ意思決定の基準値のなかで働いている人同士の繋がりよりは、社外の人との繋がりの方が『離れている』ということができます。離れている者同士が繋がると、その三角形や多角形の面積は飛躍的に大きくなります。四人以上だと立体になるのです。開かれているということは、閉じていることと異なる意味や強さをもっているのです。
このようにして、大阪ガスは、オープン化を推進しています。それは、野中郁次郎教授の提唱するイノベーションを育む『開かれた共同体』を、極めて実践的な方法で推進しているといっても過言ではないでしょう。
オープンとは対極にある閉鎖的な組織として見られがちなものの筆頭に、中央官庁が挙げられます。官僚制はしばしば階層的で閉じているピラミッド構造として捉えられます。政治との繋がりが密接なためか、密室的なイメージすら漂います。そんな霞が関のど真ん中で懸命に組織を開いている人がいます。国土交通省の河田敦弥氏です。
河田氏は、日本の空港の民営化を進めるにあたり、開かれた共同体を国土交通省内に作りました。民営化を促すためには、民間の知恵が必要と考えた河田氏は、関係する領域の専門家を外部から招聘します。不動産、商業施設、用地開発、金融、法律、会計などのプロフェッショナルたちです。そして、各々の専門分野があるが故に全体として強固なダイバーシティ組織を創りあげます。中央官庁では異例のことといっていい。そして、閉ざされた国土交通省のなかで、空港経営改革推進室が出島のように機能し始めるのです。
この組織のレイアウトが一風変わっています。東京・霞が関、国土交通省のフロアの一角。そのほぼ中央に、四方を壁で仕切られた空港経営改革推進室はあります。メンバーすべてが男性という男所帯で、昼間から笑い声が絶えない。そんな様子を揶揄してか、それとも羨んでか、周囲からは「部室」とも呼ばれています。部室は机の配置も一風変わっています。お役所といえば、田の字に机を並べた島型レイアウトが普通ですが、ここはまるで違う。それぞれの机が壁に沿って、そして壁向きに並べられているのです。これはメンバーの一人である高橋哲也氏の発案によるもの。その理由を高橋氏がこう話しています。「島型だと、机の上に書類が山のように積まれてしまうので、前の人の顔が見えなくなり、向かい合っている意味がなくなってしまうのです。逆に、こうして壁向きにすると、一人ひとり仕事に集中できる一方、いざ話し合いが必要な場合、椅子をくるっと回せば全員と対面できる。要は、日頃からきちんと会話ができる環境を作りたかったのです」。レイアウトひとつとっても、開かれていることと繋がっていることのバランスを担保していることが分かると思います。
オープンであることは、顧客・市場と組織の間でも必要なことです。近年、UX(User Experience)の必要性がイノベーションの領域で叫ばれていますが、それは、顧客と組織とがオープンに繋がっていなければできません。イノベーションの答えを顧客がもっているとは限りませんが、少なくとも顧客の「不」を捉えずしてイノベーションを興すことは難しい。提供者側の論理に立った独善的なアイデアは、技術が複雑化し価値観が多様化した現代では受け入れられません。顧客不在のイノベーションが波及・普及し、経済的成果を継続的に得ることは、顧客自体がイノベーションの享受者であるが故に、難しいことなのです。だからこそ、顧客・市場と組織との、行ったり来たりのコミュニケーションが必要です。その基点は「不」であるべきだと考えます。
では、「不」とは何か?「不」とは、不便・不安・不満・不足・不利・不快・不当・不自由・不具合・不潔などの困りごとです。事業を「不」を解決・解消するものと定義するとき、「不」を手触り感をもって捉えることが必要です。そのためには、顧客や市場に入り込まないといけない。じっくりと対話し、仮説をもって観察し、時としてプロトタイプを試してもらい、どんな経験をしたいかを問い続けなければなりません。これは一体誰の「不」か? その「不」の大きさは? 「不」の重さ・深さは? 「不」の発生する頻度は? 「不」の生じる背景は? 「不」の解消方法は? このような「不」を組織の中で共有し、組織の兵站(資源)を活用して解決に向けて動くことが、まさにイントレプレナー型のイノベーション創出といえるでしょう。
そのためには組織は開かれていないといけません。開かれて、繋がって、コミュニケーションが繰り返されて、「不」とその解消方法が磨かれていくのです。
ポイント(7) 矛盾をマネジメントせよ ~ひたすら耐えて、根負けさせる
開かれた共同体で、「不」を軸にイノベーション創出が進展していくと、必ず組織の壁にぶつかります。それは、戦略を司る経営者とイントレプレナーとの覇権争い、あるいは階級闘争ともいえるでしょう。イノベーション研究モデルでは、下記のような領域になります(図表03参照)。
図表03 【矛盾をマネジメントせよ】の研究モデルでの領域
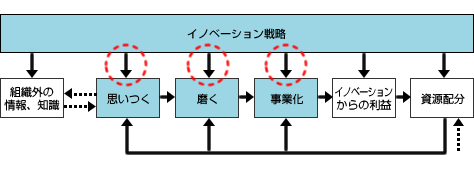
イノベーションは、うまくいくかいかないか分からないことに対して資源を動員して普及させなければならない、という二重の矛盾を抱えています。つまり、その本質が矛盾の塊なのです。マネジメントも矛盾の集合体とよくいわれます。捉えるべき視界がすべて二面性をもっているということです。
長期的-短期的、革新-安定、競争-調和、顧客-効率、多様性-凝集性、外部適応-内部統合、論理-感情、ラーニング-アンラーニング(一旦捨てること)、戦略-組織、価値-コスト。このような矛盾を清濁併せ飲む姿勢で受け入れ、物事を進めていくのがマネジメントともいえます。
イノベーションも同様です。ピーター・ドラッカーは、企業の機能をイノベーションとマーケティングの2つと看破しています。それに、経営者の役割というもう1つの軸を加えて、イメージを深めてみます(図表04参照)。
図表04 イノベーションマトリクス
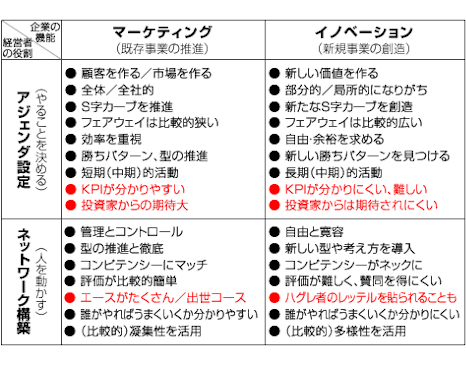
イノベーションとマーケティングの左右の欄を比べてみたら分かると思います。矛盾だらけなのです。何をするにしても矛盾が生じるし、アイデアひとつ承認してもらうにも、組織の壁が立ち塞がります。それは、既存事業が強固で磐石であればあるほど、イントレプレナーの前に厳然とそびえ立ちます。
では、どうすればいいのか? それは、無責任かもしれませんが、「そんなもんだ」と割り切ってしまうことだと思います。「イノベーションはマーケティングとは相容れないものだ」「投資家からあまり期待されないものだ」「ハグレ者でもいいかな」「評価はなかなかされないな」「結構周りにいろいろ言う人が多いな」「シンパはあまりいないな」「どうすればうまくいくか、分からない」「数字で説明せよって言われても、それができたら苦労しないよ」
組織は常識を育む装置です。一旦マーケティングが進むと、どんどん常識で縛ろうとします。それに抗うのがイノベーションともいえます。であるならば、矛盾は当たり前。それを腹に落として、物事を進めた方が建設的です。
そして、最後は根負けさせる。しつこさが、イントレプレナーに必要な最大のコンピテンシーなのかもしれません。経営者から、「もう、お前はしつこいな。分かったから、これだけはやらせてやるから、しばらく顔を見せるな」という言質を引き出せたら、イノベーションは成功したも同然といえるでしょう。
ポイント(8) 称賛という水遣りを忘れるな ~誉め言葉を変え、認知と称賛を繰り返す
最後に、イノベーションを組織に定着させるためのポイントを説明します。イノベーション研究モデルでは、イノベーション戦略と思いつく、磨く、事業化の間で生じるといえます(図表05参照)。
図表05 【称賛という水遣りを忘れるな】のイノベーション研究モデルでの領域
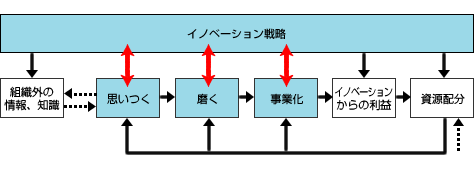
期待されていることが明確であり、さらにその期待に応えると認知と称賛が得られることは、組織の中で仕事をする際に根源的に重要です。何をすると誉められるのかが分かっていることは、原始的かもしれませんが、大切なことです。組織の中からイノベーションを興す、ということに関しても同様です。
「ああ、こういうことが求められているんだ」
「イノベーションというと分かりにくいけど、こんなやり方があったんだ」
「自分でもできそうな感じがする」
イノベーションとしての分かりやすい事例、イントレプレナーとしての共感できるキャリア・モデルとその動機・問題意識・生き様、等々。これらが組織の中で認知・称賛されていくと、イノベーションを興す組織文化が徐々に形成されていきます。
その際に大切なことがあります。それは、認知と称賛に手を抜かない、ということです。
図表04でイメージしていただけると思います。イノベーションは矛盾だらけでよく分からないが故に、意外と誉めることが難しい。そして、継続的に誉めることは、成果が短期的に出にくいために、より一層困難です。イノベーション案件が途中で座礁すると、マーケティング側の意見が跋扈します。
「ほら、俺が言った通りだろう」
「訳が分からなかったから、結局こんなことになるんだな」
「俺たちの稼ぎを無駄遣いしやがって」
……このような声が聞こえてきそうです。
評価基準がはっきりしないことが、認知・称賛を継続的にできないことに拍車をかけます。マーケティング領域は数字で成果を示せるが故に、公正な視点で称賛ができます。イノベーション領域ではそれが示せない。そこに、組織の構成員の解釈の違いからくる誤解・妬み・嫉みなどの付け入る隙が生じます。その結果、イノベーション自体が雲散霧消してしまうことも多いのです。
ここは経営者の出番です。経営者が興したいイノベーションのフェアウェイを示し、それに資する案件であれば継続的に誉め続けることが必要不可欠です。では、どう認知し称賛するか? こんな言葉はどうでしょうか?
「できたらすごいね」
「同業他社がやっていない? ならやろう」
「このアイデアに期待している」
「本当に価値のあることだったら、利益は必ず後からついてくる」
「金を使って失敗しても財産になる。最悪なのは金も使わない、成果も出さないことだ」
「全く違う世界の人と触れ合うことが大切だ」
「過去の成功は捨てよう」
「うまくやろうとするな」
「お前はどうしたい?」
認知と称賛をイノベーション寄りに変える。それを徹底し、継続する。何年先まで、というより、これから先ずっとやる、と決める。これこそが、組織の中からイノベーションを創出することを定着させるために有効なことなのです。
組織の中からイノベーションを興す8つのポイントを、事例を交えて振り返ってきました。そして、1つのことに気付きました。人間の執念であり、情念です。それは、すべての事例にあたかも通奏低音のように流れていました。変革へのエネルギーとも言い換えられます。
アップルやグーグルは世界を変えることを標榜し、社員に行動を求めていることで、広く知られています。そして、2社をはじめとする変革へのエネルギーレベルが高い企業や組織が、実際に世界を変えてきた。本気で変革を志し行動する人と組織であれば、世界を変えることができるのです。それを、この8つのポイントを徹底的に磨くことで実践したい。こう宣言して、中間の総括を締めたいと思います。
次回からは、引き続き、さまざまな組織の中からイノベーションを興してきた事例を紹介していこうと思います。
【総括(文):井上功】
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての