インタビュー
イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- 公開日:2015/08/26
- 更新日:2024/05/28

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第32回は、株式会社リクルートライフスタイルの加藤史子氏にご登場いただきます。加藤氏は、2011年から始まった19歳ならスキー場のリフト券がタダになるサービス、「雪マジ!19」を仕掛けた人です。
加藤氏は、課題の根幹を掴み、顧客や市場の状況を周到に感じ、新たなビジネスモデルを援用することで、市場を創造・活性化しています。そのプロセスは、自身の経験や、状況を踏まえ考え行動していった事実と相まって、非常にダイナミックでした。
なぜタダなの? タダだと儲からないよね? なぜ19歳なの? 「雪マジ!19」の存在を知っている人も、ご存じない人も、ごく普通に疑問に思うはずです。まさに百聞は一見にしかず。さっそく、加藤氏のイノベーションストーリーをご覧ください。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 始めは無料、奥に入ると有料 ネットで隆盛のビジネスモデル
- 19歳はスキー場のリフト無料 昨年は全国181のスキー場で実施
- 産休・育休を経験して思ったこと 社会的価値がある仕事がしたい
- 長野県から持ちかけられた スキー人口V字回復策の提案
- 独自調査で判明した意外な事実 スキーは年齢が上がると参加率が低下する
- スキー場を輸送業ではなく サービス業にしなければ
- スマホゲームとの類推からも リフト無料を思いつく
- 全国4割のスキー場で実施 1割強の19歳が雪マジ会員に
- 総括
始めは無料、奥に入ると有料 ネットで隆盛のビジネスモデル
人間は、無料という言葉に弱い。その心理を逆手に取ってか、最近ではネット上のソーシャルゲームで、フリーミアム(freemium)というビジネスモデルが流行っている。基本的なサービスや製品を無料で提供する代わりに、もっと高度な機能を追求したい人には有料で提供する。入り口は限りなく広くてフリー(無料)だが、ある地点から奥に進むプレミアムの享受にはお金が発生するという仕組みだ。
いや、ネットばかりではない。リアルな世界でも、ひと頃、ソフトバンクが「携帯電話無料キャンペーン」を行い、評判になったことがある。これを発案した孫正義氏は何と小学生のとき、同じようなフリーミアムモデルを考えていたことをご存じだろうか。
孫氏の父親は事業家であり、新しい事業の種をいつも探していた。ひょんなことから、古い民家を借りることになり、喫茶店を開こうと思い立つ。
ところが開業目前となってトラブルが起こった。コーヒー豆の卸屋が来たものの、「ここは交通の便が悪いから、絶対繁盛しない。そんな店に大事な豆は卸せない」と帰ってしまったのである。父は怒り心頭に発し、絶対繁盛させてやると心に誓ったものの、策が思いつかない。思わず、小学3年生だった孫氏に尋ねた。「どうしたらいいと思う?」
孫氏はこう即答した。「タダで飲ませるしかないね。無料券を配ってお客を呼んだらどうだろう?」
父も仰天したアイデアだったが、他に策もなく、それに賭けてみた。
蓋を開けてみたら、大成功だった。店は連日満員で、コーヒーが無料でも、食べ物の注文がひっきりなしに続く。なかには2杯目の有料コーヒーを飲む客も出てくる。たちまち繁盛店として地域でも有名になり、遂には件の豆の卸屋が店にやってきて、「豆を卸したいので、よろしくお願いします」と頭を下げた。
先の携帯電話の無料モニターキャンペーンはこのコーヒー無料券の成功にヒントを得たものだろう。
19歳はスキー場のリフト無料 昨年は全国181のスキー場で実施
前置きが長くなった。このフリーミアムモデルが今、日本のスキー場を席巻している。
「雪マジ!19(読み方:ユキマジナインティーン)」(マジはマジックMagic=魔法の意)といい、19歳に限り、ネット上で会員登録すると、全国指定のスキー場でリフト代が無料になるというサービスだ。無料分を負担するのは各スキー場で、それ以外の経費、つまり用具のレンタル代、ロッカー代、飲食費、駐車場料金などは有料になる。
スタートは2011年11月7日で、初年度の2011-2012シーズンは全国89のスキー場が参加し、約4.9万人の19歳が会員登録を行い、のべ約12.8万人がスキー場を訪れた。
2012-2013シーズンは136のスキー場、登録数約10.8万人、利用者数は約34.6万人。2013-2014シーズンは172のスキー場、登録数約15万人、利用者数は約52.8万人、2014-2015年は181のスキー場(登録数、利用者数は集計中)と、いずれの数字も右肩上がりに伸びている。分かりやすいメッセージが評判を呼び、クチコミで広がったのだ。
これを手掛けたのが、リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター主席研究員の加藤史子氏だ。なぜリクルートがこんなサービスを考え出したのか。なぜ19歳なのか。

産休・育休を経験して思ったこと 社会的価値がある仕事がしたい
リクルートライフスタイルは旅行、グルメ、美容、ファッションなど、日常領域におけるメディアサービスを展開する、リクルートホールディングス傘下の主要事業会社である。加藤氏が所属する、じゃらんリサーチセンター(以下、JRC)は、2005年4月に発足した、国内旅行に関する調査研究を行ったり、観光振興策を考えたりするシンクタンクだ。
加藤氏がJRCに異動してきたのは、2008年4月だった。キャリアウェブという自己申告による異動制度で希望が叶い、出産休暇明けというタイミングでJRCの研究員となった。与えられたミッションは、「国内旅行市場の活性化」という漠たるものだった。それまでは旅行や飲食店に関するネット事業の立ち上げに従事していた加藤氏が、なぜ異質の仕事を選んだのか。加藤氏が話す。
「産休・育休をとると、基本的に、半径500メートル以内で完結する生活を余儀なくされます。ベビーカーで移動する場合、駅ではエレベーターが必須だし、ない場合は誰かに手伝ってもらわなければならない。自分が社会的弱者になったような気がしたんです。それまでの生活では味わえなかった感覚でした。社会的価値に向き合う必要性を強く感じたんです」
当時は、観光庁はまだ存在しなかったが、観光立国推進基本法という法律が成立、施行されていた。異動を決める面接の際、JRCのセンター長の話がとても新鮮だったという。「観光産業の市場規模を10年くらい追ったグラフを見せてくれたんです。約30兆円規模でしたが、右肩上がりどころか、下がっていたんです。私はじゃらんネットnetという旅行サイトの構築立ち上げも手掛けていたのに、そうした数字はもちろん、全体が下がっていることもまったく知りませんでした。じゃらんネットnetを通じ、宿泊予約数を大きく増やし、得意になっていたこともあったのに、それは限られた市場のパイの食い合いに過ぎなかったと。頭をガンと殴られた感じでした。でもそのとき、思ったんです。この仕事は面白そう。自分はリクルートの社員なのだから、リクルートが儲かる仕事をやるのは当然だけれども、それだけではなくて、社会的価値も高い仕事ができるのではないかと」
初めの2008年度、翌2009年度は国土交通省総合政策局と連携を深め、国からの受託事業を請け負った。最初に受託したのは、休暇の平準化推進事業だった。「有識者委員会を作り、人選や交渉、さらに当日の席次表や議事録を作成したりして、あまり民間企業では経験しない国の事業の進め方を知り、非常に勉強になりました。リクルートではサービス対象者のセグメンテーションを精緻にやりますが、行政の仕事は違いました。セグメンテーションはむしろ不要で、万人向けの施策を考えなければならない。リクルートの常識が社会では非常識にもなることを学びました」
長野県から持ちかけられた スキー人口V字回復策の提案
そのうち、第二子を授かり、2010年3月、再び産休に入る。同年8月、早くも復帰すると、ある仕事が待っていた。長野県のスキー活性化事業だ。じゃらんの営業部から持ち込まれた案件だった。加藤氏はすぐに長野県庁に行き、担当者から話を聞いた。こんな内容だった。
その年、つまり2010年は新潟県にスキーが伝来して100周年になる節目の年であり、新潟県はそれを記念して、スキーを伝えたオーストリアの軍人・レルヒ少佐を模したキャラクターを作り、大々的なキャンペーンを実施している。実は、来年はわが長野県にそのスキーが入ってきて100周年なのだ。新潟に負けない記念事業を展開し、落ち続けるスキー人口をV字回復させたい。ついては何か良いアイデアをご提案いただきたい、ということだった。
実際、長野県だけではなく、全国的に見てもスキー人気は尻すぼみになっていた。1993年をピークに、参加人口は毎年減り続け、最盛期の3分の1、スノーボード人口を足しても最盛期の2分の1という減少ぶりだった。
今期は予算措置ができていないので、お金がなくてもできることはないか。県が提案してきたのがスキー場での来場者アンケート調査だった。加藤氏は実施を了解し、持ち帰って調査設計に取り掛かった。
独自調査で判明した意外な事実 スキーは年齢が上がると参加率が低下する
ところが、考えれば考えるほど、調査自体が無意味なことのように思えてきた。「スキー人気が落ちて、スキー場に人が来なくなっている。それを回復させる施策を考えたいのに、現にスキー場に来ている人にアンケートをやっても仕方がないと思えてきたのです」
そこで、リサーチセンターの上司に事情を打ち明け、JRCの予算を使い、インターネットを使っての自主調査に切り替えることにした。過去にスキーやスノーボードをやっていたが今はやっていない人、今でも楽しんでいる人に的を絞った比較調査だ。
その結果、極めてシンプルな事実が判明した。
スキーやスノーボードは年齢が上がるほど、参加率が下がっていく。つまり、40代でゴルフデビューする人はいるが、40代でスキー、スノーボードデビューする人はほとんどいないのだ。
そこから導かれたスキー人気復活の戦略は、次のようなものだった。スキーやスノーボードを始める人が多いエントリー年齢でできるだけたくさんの若者に経験してもらい、かつ、その人たちにその後もなるべく多くスキー場に足を運んでもらうこと。これである。
しかも、エントリー年齢は2つあることが判明した。1つは小学校卒業まで、もう1つが19歳であった。「このうち、19歳が大きな鍵を握っていることに気付きました。この年齢になると、同行者が親から友人に、費用負担が親から自分になります。さらに、スキー場でやるスポーツがスキーからスノーボードに切り替わる。スキーはファミリーか年配向き、スノーボードの方がファッショナブルでかっこいいと思うわけです。別の言い方をすれば、同行者としての友人がいない若者、自分でお金を出せない若者、スノーボードに魅力を感じない若者は19歳でゲレンデに通わなくなってしまう。そこで、同行者、お金、スノーボードの魅力という3つの壁を乗り越えさせ、最大多数の19歳をスキー場に向かわせることができれば、スキー市場は再活性化するはずだ、と思いました」
スキー場を輸送業ではなく サービス業にしなければ
この調査と並行して、ネットでスキー場に関する情報収集をしていると、興味深いインタビュー記事が目に留まった。話し手は星野リゾートの星野佳路社長。同社が福島県にあるアルツ磐梯スキー場を買収した件に関する記事であった。こういう言葉があった。「私たちはスキー場をサービス業と、捉えています」
加藤氏は仰天する。「私はてっきりサービス業だと思っていたのに、そうではなかったんです。実はスキー場の根幹はリフトであり、多くのスキー場はリフト業、つまり、輸送業という位置付けなのです。実際、スキー場の管轄は経済産業省ではなくて、運輸業という観点で、旧・運輸省であり、現在の国土交通省なんです」
もう1つ、星野社長は興味深い話を披露していた。スキー場の来場者にアンケート調査を実施し、全体の満足度がスキー場のどんな項目と関係が深いかを分析したところ、食事のおいしさやスタッフの接客の良さ、はたまた施設の清潔さでもなくて、来場者本人のスキーやスノーボードの上達度だったというのだ。記事には星野社長の次のような言葉が続いていた。「その結果を受けて、われわれは上達保証レッスンを始めました」と。
加藤氏は考えた。自分がゲレンデのオーナーなら同じことをやりたいけれど、できない。上達させるには、何度も通ってもらうしかない。何度も気兼ねなく行ける状態を作るには……そうだ、リフト代を無料にしたらどうだろう。それは先ほどの3つの壁を乗り越えさせることにもつながるはずだ、と。
スマホゲームとの類推からも リフト無料を思いつく
その一方で、加藤氏は別の頭脳も動かしていた。加藤氏の夫はスマートフォンゲーム会社の経営者である。「夫の仕事の話を聞いているうち、こう思っていたんです。初期投資はゼロ、いつでもどこでも手軽に楽しめて、お金もかからないゲームに比べたら、それなりの装備が最初から必要で、寒いなか、ゲレンデにわざわざ足を運んでもらわないとできなくて、ゲレンデリフト代も有料、滑ったり転んだり、時には痛い思いもするスキーは、何て不利な産業なんだろう、と」
加藤氏は、そうしたソーシャルゲームビジネスの利点をスキーやスノーボードにも取り入れられないか、と考えた。
「ゲーム会社がやっているフリーミアムというビジネスモデルの本質は、後払い方式なんです。しかも全員が後払いする必要はなくて、無料にひかれてゲームをした客の何割かがはまってくれ、有料になってでもゲームを続けてくれればよい。ただし、このモデルが可能なのは、たくさんの人が訪れたとしても、相手をするのが機械であるプログラムとサーバーだからです。つまり、コストは変動せず、たくさんの人を一度に対象にできる。同じ構図がスキー場にもあったんです。リフトです。スキー場の経営を効率化するなら、客が少ない日を休日とし、リフトを止めるしかないという話をスキー場の経営者が異口同音に語っていました。そうだとしたら、逆にスキー場を開けている限り、客が100人来ようが1000人来ようが、リフトの電気代や人件費、圧雪費などのコストは同じだと。なおかつ、スキー場は山にあり、キャパが大きいため、無料にして目いっぱい、人を入れてもいいんだ、と考えたのです」
こうして、アンケート調査による数値分析、ネットで収集した情報、ゲーム産業との比較論、この3つがみごとにつながった。そうして形になったのが、19歳のみを対象に、リフト代を無料にする「雪マジ!19」だったのだ。

全国4割のスキー場で実施 1割強の19歳が雪マジ会員に
このアイデアを長野県庁に持参するが、担当者からは「県の事業としては難しい」とすぐに断られてしまう。県庁から県内の有力スキー場に持ちかけたところ、「リフトの無料化なんてとんでもない」という反応だったためだ。
だが、加藤氏はめげなかった。スキー場の多い約20の都道府県を行脚し、プレゼンセミナーを行ったのである。2011年4月のことであった。「聴衆は、スキー場経営者、周辺の旅館業者、地銀関係者、自治体の職員などです。結構人気を呼んで関心は高く、参加人数は総計で1500名にもなりました。ただし、雪マジのアイデアは最後に付け足すくらいで、内容のほとんどは先の調査結果の紹介でした。実施後のアンケートに雪マジの感触を書いてもらい、反応が良かったスキー場経営者には後で電話をかけて、実施を強く勧めていきました」
その結果、冒頭で紹介したとおり、初年度、全国89のスキー場での実施が決まった。そのなかには長野県内のスキー場も含まれていた。
最新の2014-2015シーズンは181だから、ほぼ倍増だ。全国にスキー場は約450あるので、約4割が雪マジを実施していることになる。一方の登録者は2013-2014シーズンで約15万人。日本の19歳人口は2013 年で124万人だから、1割強をカバーしている計算になる。スタートして4年、いずれもかなり高いカバー率といえるだろう。
加藤氏はこう付け加える。「雪マジ!19対象の19歳を調査すると、食事や機材レンタル、周辺での買い物など、彼らがリフト以外でお金を使ってくれている実態が明らかになりました。また、追跡調査では、雪マジ経験者の9割が翌年、20歳になってもゲレンデを訪れていました。このマジ方式が当たり、今では、20歳を対象にした『ゴルマジ!20』(ゴルフ)、大分県との協働事業で22歳向けの『お湯マジ!22 in おんせん県おおいた』(温泉)、19歳、20歳 向けの「Jマジ!20」(サッカーのJリーグ)、19歳~21歳向けの「つりマジ!」(釣り堀と釣り船)、20歳~23歳向けの「ビアマジ!」(ビール)等が生まれています」
実は雪マジによる需要創出効果は、まだ大きく顕在化してはいない。JRCの調査によれば、4年前と比べ、2014-2015シーズンにおける18歳から29歳全体のスキー・スノーボードの直近1年間の経験率は減少傾向にあるからだ。ただ、雪マジ!19実施の影響を受けた年代である19歳から21歳の若年層に限定すると、直近1年間の実施率は伸びている。雪のマジックをより強化し、この層から後の経験率をどうやって上げていくか、加藤氏の挑戦は続く。
総括
加藤氏のイノベーション創出ストーリー、いかがでしたか?
では、さっそくイノベーション研究モデルを踏まえながら加藤氏のイノベーションを振り返ります。
注目するのは、【組織外の情報、知識】と【思いつく】の領域です(図表01参照)。その際に重要なのが、援用力と行動力です。
イノベーターの特徴として、常に何かと何かを繋げようとする思考があります。「このことは、他の何かと繋げられそう。そうすると新しい価値が創出できる」といったことを、極端にいうと365日、24時間考えているのかもしれません。加藤氏もおそらくそうだと思われます。何かの概念を何かと繋げる、援用する力が際立っています。
そして、徹底して行動する。行動することで見えてくる状況自体を取り込むことで、イノベーションが前に進みます。【組織外の情報、知識】と【思いつく】の領域で、加藤氏は思考と実証の高速回転をしているのです。しかも、重くなく、軽やかに、楽しげに行っている。その姿が非常に印象的でした。
それでは、さっそく、加藤氏の行動を深掘っていきましょう。
図表01 イノベーション研究モデル
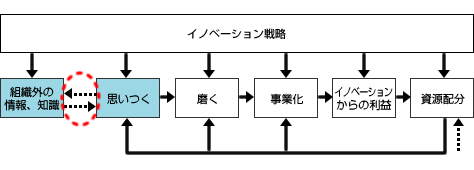
社会的弱者の立場になり
社会的価値と向き合う
加藤氏は、2度の妊娠・出産と休職を経験しています。「そのとき社会的弱者になったような気がした」と話しています。今までの生活では感じなかった不便・不安・不満・不足・不利・不合理・不具合・不信……といった「不」を、さまざまな状況や場面で感じたのでしょう。
弱い立場になってみて初めて見えてくるものがある。それは、社会的強者としてのクライアントやカスタマーと向き合ってきた加藤氏にとって、真の社会的価値に向き合う覚悟をもつきっかけになりました。
観光産業を活性化する仕事に着任した加藤氏は、競争関係のなかで収益を向上させるというビジネスの枠組みと共に、市場全体を視野に入れたゼロサムではない市場創造、ということも重視するようになります。単にリクルートが儲かるということではなく、市場を創ることで活性化を促そう、というわけです。
そこでは、今までの常識が通用しません。リクルートでは、新しい価値の創造を試みる際に、不の深耕を徹底します。顧客をセグメントし、ペルソナを設定。一体誰が、何に、どのくらい困っているのかを、顧客一人ひとりがリアルにイメージできるまで掘り下げます。何度も掘り下げたのち、手触り感が得られて初めて、その人に対するソリューションを考え、ビジネスに繋げていくのです。
一方、行政は異なります。全員一律、万人こそが重要。そこにセグメンテーションは必要ありません。全体を見て、全体感で議論し、誰もが享受できる施策が非常に重要です。それは、パブリック・セクターなので、止むを得ないことでしょう。
リクルートと行政。民と官。競争と公平。リクルートの常識は社会の非常識。どちらがいいということではありません。強いて言うならば、相互の概念や考え方の交流が必要ということでしょう。
この新たなものの見方・考え方を手に入れて、加藤氏は観光産業の活性化という社会的価値の高い課題に取り組んでいくのです。
○○屋さん、○○業からの開放
バリューネットワークの外に出る
自分の会社は一体何屋さんか、何業か、ということは、ビジネスパーソンであればごく普通にイメージできるでしょう。新日鐵住金であれば製鉄業、リコーなら精密機械、三井物産は総合商社、ローソンはコンビニエンスストア……、といった具合です。
一方、何業ということを言葉にして規定した瞬間から、その定義や範囲に囚われてしまうことも事実です。「うちは○○屋だから、そんなことはできない」「○○屋がなんでそんなことをやらなければいけないんだ」「○○屋としての強みは全然活かされていない」
新規事業を創出することを支援するiセッション(R)というワークショップの最終提案時に、経営者からしばしば登場する台詞です。この自己規定が、イノベーションを大いに阻害します。
スキー場はサービス業ではなくて輸送業。リフトは索道事業者が運営していることが多い。そこにあるのは、ある場所からある場所へ人を移送することに価値をおいた、輸送業としての姿です。索道事業者にとって、リフトに乗るお客様はあくまで乗客なのでしょう。乗客は運賃を払うのが当然。そうなると、リフト代がタダ、という概念はまったく受け入れがたいものなのです。
『イノベーションのジレンマ』の著者であるクレイトン・クリステンセンは、固定的なバリューネットワークそのものがイノベーションの阻害要因であると語っています。○○屋さんとか、○○業といった自己規定は、自らをバリューネットワークの内側に入れ込んでしまうことに繋がります。そうなると、顧客や市場の変化の兆しを見逃してしまい、新たなS字カーブの創出が覚束なくなります。イノベーションのジレンマに陥ってしまうのです。
フリーミアムというビジネスモデルを軸に
めげずに徹底して行動する
そこにフリーミアムという概念を持ち込んだのが、加藤氏でした。周到な調査を経て導き出された19歳という必然性のある世代の絞り込みを筆頭に、リフト券をタダにすることで何度も来やすくして上達を促し、スキーやスノーボードの固定ファン層になってもらおうという作戦です。
索道事業者単体にとって、それは一部の乗客の運賃をタダにする単なる値引きかもしれません。しかし、スキー場全体を視野に入れると、話はまったく異なってくるのです。板やウェアのレンタル、食事、レッスン、宿泊……。スキー場自体は閉じた空間であるため、付帯サービスの利用度は高いことが想定されます。そこで儲けることができれば、スキー場としてのメリットはあるのです。まさにフリーミアムのビジネスモデルです。
フリーミアムのポイントは、固定費と変動費の捉え方です。効率を考慮すると、リフトを止めるしかない。動かし続ける限り、リフトに1日10人乗せても1000人乗せても固定費は変わりません。だったら、タダにしてたくさんのお客様にリフトに乗ってもらい、楽しんでもらった方がいい。
この固定費が厳格に存在するビジネスには、他に何があるでしょうか?
輸送業では、空荷や回送の問題があります。空荷を解消するために、サード・パーティ・ロジスティクスが登場しました。運輸会社が連携して、行きと帰りにできるだけ空荷が出ないように効率化を図るというものです。回送電車はいまだによく目にします。車両のやりくりのために必要なのは分かりますが、空気を運んでいるように感じるのは私だけではないはずです。例えばガラガラのこだま号などはどうでしょう? 効率はいいとはいえません。飛行機の空席を埋めるべく登場したのが、マイレージサービスです。
他にも、空席が目立つ映画館。土日の誰も使っていないオフィス……。さまざまな固定費で動いているビジネスが存在します。加藤氏の着目したリフトも、下りはほとんど空です。何かを乗せて、山から下ろすことで、新しい価値を創出することができるかもしれません。
このように、フリーミアムのビジネスの可能性はたくさんあります。加藤氏の凄さは、その着眼点だけではありません。全国行脚を繰り返したその行動力と信念は、克目に値します。否定されても確信をもち、20もの都道府県を訪問し、「雪マジ!19」のシンパを創り続けるのです。そして、需要が創造されていきます。ゼロサムではない市場創造をすることに繋がっているのです。
加藤氏の構想力と具現化力が、次なる日本の社会課題を解決していくことでしょう。
【総括(文):井上功 /インタビュー(文):荻野進介】
PROFILE
加藤 史子(かとう ふみこ)氏

慶應義塾大学環境情報学部卒業。1998年株式会社リクルート入社。高校生向け進学情報誌の制作・編集を経て、「じゃらん.net」の立ち上げ企画開発、「ホットペッパーグルメ」の立ち上げ企画開発など、ネットでの新規事業開発に携わり、2008年より現職。
国内旅行市場動向の調査・トレンドの把握、市場活性化および観光による地域振興に寄与する実証事業を実施・研究。
主な事業・テーマとして「乳児連れ家族旅行促進による需要創出」「携帯ゲームと融合した新・若者旅行」「働く人の“休暇”意識調査」「平日需要創出・旅行需要平準化」「フリーミアムモデルによる雪山活性化、19歳は全国のスキー場でリフト券無料(雪マジ!19)」「GPS・位置情報を活用した次世代観光地分析」「ご当地愛を可視化するソーシャルメディア活用(「かまくらさん」「ふじ氏」)」など、新たな視点で国内旅行市場をより活性化していくことに挑戦。また、「雪マジ!19」に続き、20歳はJリーグ観戦無料の「Jマジ!20」や、21歳はビール無料の「ビアマジ!21」、20歳はゴルフ場、ゴルフ練習場無料の「ゴルマジ!20」、22歳は日帰り温泉無料の「お湯マジ!22 inおんせん県おおいた」など、若者需要創出プロジェクトを手掛ける。
長野県、滋賀県、福井県、山梨県、茨城県、横須賀市で、県や市の観光関連 有識者委員会の委員を務める。観光庁にて各種観光関連委員会の委員を務める。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての