インタビュー
イノベーション研究 第11回 品川女子学院
廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- 公開日:2013/11/27
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第11回は、学校の事例を取り上げます。お話しいただくのは品川女子学院校長の漆紫穂子氏です。そのイノベーションストーリーは今から20年以上前に遡ります。生徒数の減少により、廃校の可能性もあった危機的状態の学校を、まず、外部の知恵や知識・経験を学校内部に取り入れるアウトサイド・インの活動で開いていきます。学校改革が進展していくと、状況に応じて大胆なインサイド・アウトの施策も実行します。野中郁次郎教授の唱えるイノベーションを育むための『開かれた共同体』を、アウトサイド・インとインサイド・アウトのコミュニケーションで実践しているのです。その内容は、大胆で繊細、計画的かつ修正主義、合目的的であり目標合理的、といえるものです。
それでは、ひとつの私立学校を巡る四半世紀に及ぼうとするイノベーションストーリーを、さっそく漆校長に語っていただきましょう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 輝いた28歳を超えさせるための 独自カリキュラム「28プロジェクト」
- 20年前の同校をおそった廃校寸前という危機
- 再生するためにはどうしたらいいか 答えを求めてあちこち尋ね歩く
- 生徒が思わず着たくなるかわいい制服を作ろう
- 改革がひとりよがりになりかけていた 改めて皆で教育目標を策定
- お金よりミッションが大事 高校入試の廃止を決断
- 生徒にとっての品女は 一生付き合う大切な「おうち」
- 総括
輝いた28歳を超えさせるための 独自カリキュラム「28プロジェクト」
日本の学校は次なる進路を過度に意識しがちだ。中学校はよい高校に入るための通過の3年間、高校はよい大学に入るための試練の3年間、大学はよい企業に入るための猶予の4年間というように。こうしたプロセスで追い立てられるように育った子どもは、不幸だ。
品川女子学院。1925年創立の女子中高一貫校。ここにはそうした図式は当てはまらない。
以下が、同校が掲げる教育目標である。
私たちは世界をこころに、能動的に人生を創る日本女性の教養を高め、才能を伸ばし、夢を育てます。
「世界をこころに」「能動的に人生を創る」「日本女性の教養を高める」・・・・・・ちょっと他ではお目にかからないようなフレーズではないか。
いや言葉だけではないのだ。この品川女子学院はその綺麗な目標を言葉だけに終わらせず、きちんと実践に移している。具体的には「28プロジェクト」を始めとする独自のカリキュラムによってである。
女性には男性と違い、出産という重要なライフイベントがある。昨今は学歴含め、男性と同じキャリア意識をもつ女性も増えてきた。プライベートと仕事、そして学びの状況を勘案すると、女性が社会に出て初めて迎える黄金年齢は「28歳」である・・・。同校は、こうした考えのもと、その年齢になった時、一人前に自立し、社会で活躍している女性の育成を目標におく。そのための独自のカリキュラムが28プロジェクトだ。
その中身は実に多彩だ。たとえば、日本文化を学ぶための茶道や華道、着付けの学習、社会を学ぶための企業とのコラボレーションや起業体験プログラム、世界を知るための語学ホームステイを兼ねたニュージーランドへの修学旅行など。特に有名なのが企業とのコラボレーションで、岩塚製菓はじめ、女子学生が開発に携わった商品がいくつも市販されていることだ。

どうだろう。好奇心にあふれた子ほど「行きたい」と思うだろうし、親も思わず通わせたくなるような学校ではないだろうか。
事実、同校の入試実倍率(募集は中学校のみ)は定員に対して約3倍、偏差値も50代半ばの都内屈指の人気校だ。
でも今から20年数年前はそうではなかった。同校は実は廃校の危機に瀕していた。
20年前の同校をおそった廃校寸前という危機
そこにやってきたのが現在6代目の校長をつとめる漆紫穂子氏である。
同校は漆氏の曽祖母が1925年に創立した荏原女子技芸伝習所が前身。漆氏は大学卒業後、都内の別の私立高校に教員として勤務していた。そこを辞めて移ってきたのは1989年。28歳の時だった。
2つの理由があった。一つは母親の病気である。当時、同校の校長は漆氏の父親が務め、副校長の母親が学校経営を一身に担っていた。その母親が末期癌であることが判明したのだ。もう一つの理由はまさに廃校の危機が迫っていたこと。勤務先の教頭が「あなたの実家の学校、大変だよ」と、入学希望者数や財政状態などを記した東京都の内部資料を見せてくれた。そこには廃校危険指数という数字があり、ワースト5に名前が入っていた。漆氏は矢も楯もたまらなくなった。校長である父も学校改革に乗り出そうとしていた。学校を「移る」という決意をするのに時間はかからなかった。
当時、同校は変わらず女子校であったが、品川中学・高校という名称になっていた。一時、校内が荒れたこともあったが、当時は落ち着いていた。正確にいえば落ち着き過ぎていた。漆氏が当時を振り返る。「行事や部活で子供たちの気持ちをまとめ、きびしいしつけを施して、社会に送り出す。そういうやり方で一定の成果を上げていたのですが、男女雇用機会均等法が施行され、女性も男性と同じように働くことが当たり前になってきたのに、自立性が育ちにくいほど生活指導が厳しく、進学体制が整っていない。この2つの理由で不人気校になっていたのです。中等部の応募者が30人、つまり入学試験では全員合格というありさまで、進学塾の偏差値表に載らないほどでした」
漆氏が同校に移った頃には、父である校長主導のもと、いくつかの改革の試みが既に始動していた。漆氏は高等部の進学クラスの副担任という形で同校での勤務をスタート。先輩教員が始めたプロジェクトにも加わる。ここから漆氏の活動が始まる。
再生するためにはどうしたらいいか 答えを求めてあちこち尋ね歩く
このままでは確実に廃校になる・・・。その危機感から、わらにもすがる思いで、漆氏はあちこち訪ね歩いた。
まず同じ私学の他校である。大抵の学校が快く話をしてくれた。学校には定員があるので、いくら人気校でも受け入れられる人数には限りがある。つまり、生徒を集めるノウハウは門外不出で外に出さないというものでもない。私学界には困った時は情報交換して助け合うという精神があるのだ。
進学塾にも足を運んだ。どんな学校だったら、生徒を預けたいと思うか、熱心に聞いて廻った。
校内もヒアリング対象だった。生徒はもちろん、教員、職員、保護者、卒業生・・・・。「外の意見、中の意見、当事者である生徒の意見、全部聞いて回りました。私は若くて力がなかった。だから皆が教えてくれたのでしょう。仮説も何もなく、まったくの徒手空拳です。そうやって得た情報が宝になりました。もちろん、他の教員も回ってくれました。まさに父が言う“座して死を待つよりは・・・”という心境でした」(漆氏、以下同)
漆氏が入る前の段階では、「高等部の進学校化」が改革の中心柱だった。その後、「しつけや生徒指導の見直し」といった非学習面の柱が加わり、さらに、それまでの高校主体に代わって、「中高一貫化」という柱も見えてきた。特に最後の柱は漆氏らが中心となって主張し推進したものだ。
生徒が思わず着たくなるかわいい制服を作ろう
半ば闇雲に動いていくうち、やるべきことが徐々に分かってきた。
まず広報活動を始め、先述の聞き取りの延長線上で塾とのネットワークを整備した。さまざまな媒体に学校の広告を出す仕事も進んでやった。当初一人でやっていたが、徐々に組織化し、広報部を作った。
大きな成果となったのが制服の変更だった。「当時、セーラー服だったのですが、とにかく生徒に人気がありませんでした。これを着ていると男子生徒に声もかけられない、と(笑)。そこで校長を説得し、制服を変えることにしたのです」
漆氏は数名の教員と制服改革プロジェクトを立ち上げた。といっても、潤沢な予算があるわけでもない。自分たちでデザインして生地も確保、メーカーにも直接交渉という異例のやり方を採った。
1990年、キャメルのブレザー、チェックのプリーツスカートという新しい制服ができあがる。スカートはもともと漆氏の私物をパターン化したものだ。この制服着たさに受験する子供が沢山出たほどだ。
1991年には校名を現在の品川女子学院に変更。それ以後も改革は止まず、教員一人ひとりがさまざまな試みを行った。生徒にアンケートを取りその内容をもとに授業のやり方を改善する、シラバスを作り授業内容を生徒と共有する、下駄箱を取り払って生徒が自由に使えるアメニティスペースをつくる等々。「教員のモチベーションの原点は子供なんです。何かをやって子供が喜ぶと、これもやろうとなる。成功より失敗のほうが多かったと思いますが、制服の変更はじめ、2割の成功が大きな流れを確実につくっていきました」

この間、特筆すべきは、教員、職員含め、無理に人を辞めさせることもなく、現有勢力で改革を推進していったことだ。つまり、古い“血”を捨て、新しい“血”を入れたのではなく、既存の組織が自ら新陳代謝を遂げたのである。
改革がひとりよがりになりかけていた 改めて皆で教育目標を策定
ところが1995年に転機が訪れる。既に応募者が急増して偏差値も急上昇、押しかける見学者対応にも困るほどだったが、盤石に思えた改革体制に小さな綻びが出来始めていた。危機感を共有できた時は皆が一枚岩になれるが、危機が去ってしまうと目標を見失い、皆がばらばらの方向を見始めた。生徒と向き合う時間を増やすために会議の時間を節約したり、新しく補充した若い教員と古参の間で不協和音が生じたりといったこともそれに火を注いだ。
その頃、若い教員たちを企業人向けの研修に頻繁に派遣していた。「いいものは外部にあり、どんどん採り入れる」方針だった。しかし、コンサルタントで研修の講師もやっていた知人に、研修の実施を依頼したところ、「あなたの学校に足りないのは研修ではないかもしれない」と助言された。そのコンサルタントが勧めたのは教員にヒアリングすることだった。漆氏は申し出を受け入れた。
ヒアリングの結果は意外だった。「われわれが目指している改革には明確な目標がない」と。「愕然としました。私は、目標があるのに、皆がそれを理解していないと思っていた。でも皆は目標自体がないと思っていたのです。目標というのは上でつくって下に下ろすものではない。それぞれの心の中にある思いと全体の目標が一致した時、初めてその目標が生きたものになることが分かったのです」
そこで、研修を取り止め、代わりに合宿やワークショップを行った。なぜ教員になったのか、教員であることの喜びを感じるのはどんな時か、皆で共有した上で、学校創立の理念を掘り起こして整理した。両者を総合させる形で、品川女子学院のミッション、ビジョン、バリューをつくった。2年がかりだった。そのうちのミッションとなったのが冒頭に掲げた教育目標である。
こうして内部の意識が統一されると、漆氏は再び同校を外に大きく開いていく。2003年には従来行ってきた取り組みを「28プロジェクト」として集約した。翌2004年には企業との商品開発プロジェクトがスタート。企業との共同商品開発は中等部3年生を対象にした総合学習プログラムの中で行われている。
お金よりミッションが大事 高校入試の廃止を決断
同じ2004年、同校は大きな決断を行う。高校入試の廃止である。先の教育目標を達成するためには、3年間では無理で、どうしても6年間が必要だ。それならば、高校から入る道は閉ざさなければならない。「ある意味、苦渋の決断でした。高校入試は優秀な生徒を選抜して入れることができ、校内の活性化につながるものでした。しかも高校入試を止めると大幅な減収になる。その年間収入に占める割合は非常に大きい。でも私たちはミッションを守るために廃止を決め、完全六年中高一貫校にしたのです」
もろもろの成果が実り始めた2006年4月、漆氏は6代目校長に就任した。
生徒にとっての品女は 一生付き合う大切な「おうち」
自分たちの中に答えがないから、とにかく外へ向かった時代。その外には、生徒本人も含まれる。いわゆるアウトサイド・インである。改革の成果が出始めると、今度は改めて自分たちの目標を再確認するため、ぐっと内部に向かった時代。インサイド・アウトである。その2つを経て、品川女子学院の今がある。
その今を象徴するのが濃厚な組織文化だ。生徒が大学を卒業し就職した際、同期や先輩・後輩と話をしていて、「ひょっとしたら品女(しなじょ)?」という言葉が飛び交い、しかも当たることがよくあるという。DNAがよほど強烈なのだろう。「子供たちによく意見されるんです。『特別講座はこれだけ手間をかけているんだから、もう少しアウトプットを考えたほうがいい』とか。大人顔負けですよ(笑)。でもそれだけこの学校が好きで、いろいろ気にかかるんでしょう。彼女たちにとって、品女は一生付き合う大切な『おうち』なんです」。
総括
品川女子学院のイノベーションストーリー、いかがでしたか。
いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で話を振り返ってみたいと思います(図表01参照)。
今回注目する領域は、【組織外の情報・知識】と【思いつく】の間の領域、【思いつく】と【磨く】の間の領域(赤い破線のところ)と、【イノベーション戦略】の3つです。まず、【組織外の情報・知識】と【思いつく】の間の領域について考えてみましょう。
図表01 イノベーション研究モデル
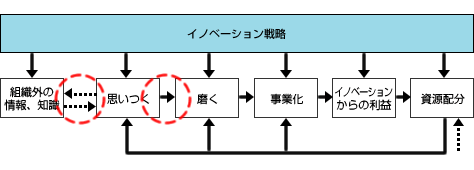
自己開示から相互理解へ
外部の情報や知識を取り込み、「開かれた共同体」を実践
危機的状況に陥ったとき、漆氏が取った行動はとにかく社外の人に意見を聞くということでした。企業人からすると、ライバルも含め関係する人たちにひたすら意見を聞くということはとても意外です。教育界特有の事情があるとはいえ、同じことをビジネスの世界で行うのは少し腰が引けてしまいそうです。しかし、漆氏は躊躇することなく動きます。同じ立場の学校に始まり、学習塾、大学、生徒、両親、卒業生、教員、企業・・・。ありとあらゆる関係集団に対するヒアリングを繰り返します
漆氏は、そのときを述懐して、「仮説などなかった」、「とにかく聞いて回った」、「徒手空拳だった」と語っています。なりふり構ってなどいられない。その真剣さ・熱心さが功を奏し、結果として社外のさまざまな知識・知恵を内部に取り込んでいくことになります。学校改革に必要なことの核心をついていったのです。それが中高一貫教育というコンセプトです。
そこには胸襟を開く、というスタンスがありました。自己開示から相互開示へと繋がり、相互信頼から新結合が生まれたということができます。同質化した組織からはイノベーションは生まれません。違いの認識が新しい価値創造の原点ということができます。それを漆氏は、最初は無自覚的に、次第に意識的に推進していきます。最初につくった組織が広報部というのが象徴的です。広報部は、組織の中と外の接点を司る役割であり、組織外の情報・知識を取り込み、組織内のコトを外部に開示していく機能を有します。それは、『開かれた共同体』の実践であり、開かれているからこその強さを共同体である組織にもたらしていくことになります。正に、アウトサイド・インの変革の実現があったということができます。
まずやってみる
修正主義ともいうべき試行錯誤
次にポイントになるのが、【思いつく】から【磨く】への過程です。この領域でのキーワードは、[実験]であり[修正主義]ともいえる試行錯誤です。
外に開いてヒアリングをした結果を基に、同校は改革の方向性を見定めていきます。制服の変更に始まり、校名変更、アンケートによる授業内容の変更、シラバス開示、下駄箱の撤去に至るまで、次から次へと変えていきます。漆氏は言います。「60%準備できたと思ったらやります。うまくいかなかったらまた変えればいい。その繰り返しです」「入試の説明会では保護者の方々に話しています。とにかくいいと思ったらまずやってみる学校だと。なので、年度途中でも変更がありますし、失敗もやり直しも多い学校です。生徒の一年は二度と戻ってこないからです。チャレンジを楽しむ方、失敗は次年度へフィードバックしてくださる方に向いています。合う合わないがありますので」
ここまではっきりと宣言されると、ある種の潔さを感じずにいられません。イノベーションの世界ではプロトタイピングが重要視されます。まず、つくってみよう。そして試してみよう。聞いてみよう。そこから気づくこと、分かること、得られることを基に、修正を繰返して価値を創出しよう。といった感じでしょうか。
イノベーションには予定された成功はありません。そこで必要なのは、共創とも云うべき顧客の巻き込みです。普及して経済成果をもたらして初めてイノベーションは成立しますが、始めから顧客を巻き込んでしまえば成功確率は上がります。品川女子学院の場合、顧客は生徒であり、教員でもあります。後にプロジェクトと呼ばれるようになる小さな実験の繰り返しは、初めはひとりで、次第に顧客である教員や生徒を巻き込んで、進展していきます。イノベーションは組織的活動であり、関係集団とのコミュニケーションで成り立つことは自明ですが、品川女子学院で行われている実験的試みは、着実に組織の変革を加速していったのです。
改革には目標がない?
そこで、インサイド・アウトでミッションを策定
最後に取り上げるのが、【イノベーション戦略】です。ただ、品川女子学院の場合、変革当初は、イノベーション戦略や、ミッション・ビジョン・バリューといったものはありませんでした。ではどうやって戦略が生まれて浸透していったのか。
改革が進展し、成果が着実に表われると、組織の中に慢心ともいうべき緩みが生まれてきます。教員にヒアリングした結果は、漆氏には驚くべきものでした。品川女子学院の学校改革には目標がない。
学校がなくなるかもしれないという状況は、マズローのいう根底に近い欲求、即ち安全の欲求が脅かされていた状態ともいえます。存続のために何かしら行動せざるを得なかった。改革が成功し、当座の安全の欲求が満たされていくと、人は安心してしまいます。
そんな、目標がないという状況下で、漆氏はアウトサイド・インからインサイド・アウトに行動を変えます。教員に対する徹底したヒアリングを繰り返し、学校創立の理念と合わせて、冒頭の教育目標などを策定します。
それは、内から生まれたイノベーション戦略といっても過言ではありません。ビジネスの世界では、「この会社は戦略がない」とか、「ビジョンがないからダメなんだ」といった言葉がよく現場から聞こえてきます。ないものねだり、のようです。そこからは、前に向く推進力は出てきません。ましてやイノベーションなど決して生まれない。
同校は違いました。現場と議論を積み重ね、想いをひとつに纏め上げ、言葉に拘り、完成したミッション・ビジョン・バリューを基に学校改革を更に進展させていったのです。高校入試の廃止、「28プロジェクト」として企業コラボや起業体験などを推進。これらの改革は、ミッション・ビジョン・バリューを策定して以降、実現したものです。
アウトサイド・インとインサイド・アウト。イノベーションの泰斗である野中郁次郎教授の提唱する『開かれた共同体』を、品川女子学院は、この双方向のインタラクションを通じて実践していきました。そして、同校の次なる目標は、異次元の高みにあるのかもしれません。
【インタビュー・文:井上功 /文(事例):荻野進介】
PROFILE
漆 紫穂子氏
1925年から続く中高一貫校・品川女子学院の6代目校長。
東京都品川区生まれ。都立日比谷高校、中央大学文学部卒業、早稲田大学国語国文学専攻科修了。他校の国語教師を経て品川女子学院へ。2006年より現職。
1989年から取り組んだ総合的学校改革により、わずか7年間で入学希望者が60倍となり、マスコミで大きく報じられる。
学校改革のなかでも「28プロジェクト」は、生徒が28歳になったときに社会で活躍する姿をイメージした教育プログラム。生徒たちは通常の進学指導とともに、企業とのコラボレーションによる新商品開発や起業体験に取り組む。
世界経済フォーラム(通称ダボス会議)の東アジア会議出席、独立行政法人日本学術振興会グローバル人材育成推進事業プログラム委員会委員などを務め、社会と直接つながった「新しい役割の学校づくり」を目指す。
著書に、『女の子が幸せになる子育て』(かんき出版)、『女の子が幸せになる授業』(小学館)、『女の子の未来が輝く子育て』(朝日新聞出版)、『伸びる子の育て方』(ダイヤモンド社)など。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての