インタビュー
イノベーション研究 第12回 ライオン
「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- 公開日:2013/12/18
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第12回は、最前線のブランドマネジャーにご登場頂きます。お話し頂くのはライオン株式会社の竹森征之氏です。竹森氏は、今まで世界に存在していなかった商品を創りだします。それは発売後1年余りで500万個以上売れています。日本の世帯数は約5,000万なので、10軒に1軒がこの短期間で竹森氏が世に送り出した商品を使ったことになります。
21世紀の日本でごく普通の生活をするという前提にたったとき、『不便』、『不満』、『不安』、『不足』、『不利』、『不平』といった『不』は、殆どないと思っていました。しかし、竹森氏の話は違います。ものの見方や概念・意味を変えることで、見事に新しい市場を創っているのです。組織の中から育まれたこの商品は、ブランドステイトメントに支えられ、組織の中と外の知識との交流を深め、内外の資源を動員することで実現していったのです。そして、前提には青臭い志があったことは言うまでもありません。
それでは、全く新しい概念の商品を巡るイノベーションストーリーを、さっそく竹森氏に語って頂きましょう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 煙に乗った銀イオンが天井や換気扇の裏側まで除菌
- ブランドステイトメントに明記 掃除行動を変えるものしか作らない
- きっかけはバルサンの事業承継 すぐに研究員が探査を始めた
- 最初のコンセプトが潰れ プロジェクトは暗礁に乗り上げた
- 社内外を巻き込んで販促効果を最大化する
- ブランドマネジャーはイノベーターでもある
- 総括
煙に乗った銀イオンが天井や換気扇の裏側まで除菌
半世紀前の日本人に「病気はどうすべきか」と尋ねたら、100人が100人、「治すべきもの」と答えるだろう。ところが今、同じ質問を発したら「予防すべきもの」と答える人が案外多いのではないだろうか。
同じことが浴室につきものの黒カビにも当てはまりそうだ。黒カビは生えたら「除去すべきもの」ではなく、生えないように「予防する」ものになりつつある。なぜ? ライオンの製品「ルック おふろの防カビくん煙剤」が売れ行きをどんどん伸ばしているからだ。
従来、浴室のカビは取るものだった。使われたのが塩素系の成分であるため、使用時には手袋や保護用メガネをつける必要もあり、「面倒くさい」というのが一般消費者の反応だった。
ところがこの防カビくん煙剤はカビの除去ではなく、カビが生えるのを防ぐことを目的としたもの。使い方も簡単で、水を入れて浴室中央に置くだけ(もちろん、カビ取り効果はないため、使用前に、目立つカビは取り除いておく必要がある)。しばらくすると煙が出始め、浴室中に充満する。1時間半ほど放置すると、除菌成分である銀イオンが天井や換気扇の裏にまで行き渡り、黒カビの原因となるカビ胞子を除菌する仕組みだ。
2012年9月の発売以来、売れ行きを伸ばし、14カ月で500万個を突破。他社のカビ取り剤は販売がほぼ横ばいのため、カビ防止剤という新しい市場を切り開いた形だ。しかも、この製品の普及により、「カビは予防するもの」が常識になると、カビ取り剤の需要は縮小を余儀なくされる。市場創造と市場破壊、その二つを狙う、まさにイノベーションのジレンマを地でいく、ライバルメーカーにとっては何とも苛立たしい商品に違いない。
ブランドステイトメントに明記 掃除行動を変えるものしか作らない
この製品の開発チームを率いたのがヘルス&ホームケア事業本部リビングケア事業部のブランドマネジャー、竹森征之氏である。竹森氏が今の役職、つまりブランドマネジャーに就任したのは2010年1月のこと。住居用洗剤「ルック」ブランドの全体業務を統括する立場だ。
竹森氏は就任するとすぐにブランドステイトメントを作った。本人が話す。「自分たちがわくわくするような新しい掃除行動を生むもの、ルックの新しい製品はそういうものしか認めませんという内容で、経営側にも認めてもらいました」。既存製品の後追い、ライバルメーカーの物まねはしません、イノベーションだけを志向する、というものだ。かなりハードルの高いルールである。
その結果、まず生まれたのがトイレのふき取り用クリーナー「ルック まめピカ」。トイレまわりの掃除といえば、洗剤や除菌剤を含み、使用後はトイレに流せる専用シートが市販されているが、多くの主婦は「もったいない」という理由でトイレットペーパーを使う。だが、トイレットペーパーは水分を含むとボロボロに崩れてしまうという欠点があった。
そこで、主婦たちの不満を解消し、トイレットペーパーがボロボロにならないクリーナー、「まめピカ」が開発された。発売は2011年3月ですぐにヒット商品となり、今年8月には性能をアップさせた「まめピカ 抗菌プラス」が発売されている。
確かにこれは「トイレットペーパーを存分に使ってトイレ掃除をする」という行動を新しく生み出した製品といえる。
きっかけはバルサンの事業承継 すぐに研究員が探査を始めた
次に取りかかったのが「防カビくん煙剤」だった。
同社の製品には研究開発起点のものとマーケティング起点のものがある。防カビくん煙剤は前者である。きっかけは2004年に中外製薬からゴキブリ退治のくん煙剤「バルサン」を事業承継したことだ。煙を使う原理を応用して別の製品を開発できないか。買収後に早速、研究開発メンバーが頭を巡らせ、試行錯誤を繰り返す。そのうち、あるメンバーが浴室につきものの黒カビがどこから来るかを突き止めた。「天井から浴室の床に落ちたカビの胞子が成長して増殖し、周辺が黒ずんでくることがわかりました。敵は天井にいたんです」(竹森氏、以下同)
それが2008年だった。当時、経営企画部にいた竹森氏の耳にもその情報は入り、「面白い研究だ」と思っていたという。
最初のコンセプトが潰れ プロジェクトは暗礁に乗り上げた
先述したとおり、2010年に竹森氏は事業部に異動になり、ルックのブランドマネジャーに就任していた。これこそ、新しい掃除行動を生む“種”にふさわしいと判断、2010年の後半から「くん煙による風呂カビ防止剤」の開発がスタートした。
銀イオンの煙でカビ胞子を除菌するという技術面の課題は幾度のトライ&エラーを重ねクリアできた。問題は「ゴキブリ相手に使うような煙を、人間が裸で入る浴室に充満させて人体へのリスクはないのか」「防カビといっても、なぜ天井がターゲットなのか」といった消費者の素朴な疑問をどう払拭させるかということだった。
その難しさは製品のコンセプト設計に顕著に現れた。最初のコンセプトは「90日間、黒カビを防ぐ」というものだった。90日間が嘘になっては困るから、モニター調査を綿密に行った。春、秋、冬、いずれも無事成功した。最大の関門は梅雨を含む夏だった。が、メンバーの願いも空しく、あえなく失敗。3カ月も経たないうちに一部のモニター家庭でカビが生え始めたのだ。その年、2011年の梅雨は長く、湿気も多かったのも災いした。でも嘘をコンセプトにするわけにはいかない。「大いに悩みました。一時は発売を諦めたほどです。お客様へのヒアリングを重ね、上司とも相談し、新しいコンセプトを20数個も作りました」
社内外を巻き込んで販促効果を最大化する
苦難の末、新しいコンセプトが決まった。「簡単!まるごと黒カビを防ぐ」。効能が持続する期間はあえて出さず、手順と効果の訴求に絞ったのだ。売り方も工夫した。複数個まとめて売ると、それこそゴキブリ用のくん煙剤を連想させるから、1個売りを基本とした。パッケージには、ゆるキャラ的な煙のマークを入れ、親しみやすさを打ち出した。
ただ、製品はできあがったものの、今までにないカテゴリーのものだけに、販売店や卸はもちろんのこと、営業を始めとした社内の説得も一苦労だった。竹森氏は全国津々浦々の流通を営業と一緒に廻り、商品を置いてくれるよう頼み込んだ。「もっと大変だったのは社内の説得、つまり営業をいかにやる気にさせるか、でした。そこで、東西それぞれで、敏腕の若手営業をそれぞれ20人集め、流通への説明の仕方から始まり、店頭での売り方、POPの内容まで、情報交換会を行いました。若手が出してくれたアイデアを取り入れて実現させると、その彼のモチベーションが上がります。ひたすらそれを繰り返しました」
2013年12月から来年3月にかけては、2個パックで販売し、1カ月後に効果が現れず、カビが生えてしまったら全額返金、という異例のキャンペーンを実施する。これも営業が挙げてきたアイデアの一つだった。

さらに奥の手も用意した。「アリさんマークの引越社」を展開する引越社と連携し、同社を利用する引越し客に同製品を無料で提供した。この製品を使うには、浴室の掃除をすることが不可欠だが、入居直後なら掃除は不要となる。そのきれいな浴室で製品を使ってもらえれば、その後のリピートに結びつくと竹森氏は考えたのだ。
ブランドマネジャーはイノベーターでもある
斬新な商品を開発したからといって、すぐにヒットに結びつくわけではない。竹森氏は商品開発から販売まで、一気通貫で見るブランドの経営者たるブランドマネジャーの役割を十二分に果たしたといえるだろう。
竹森氏は一時、会社から派遣されて大学のビジネススクールに通っていた。そこで、起業家やベンチャーキャピタリストたちに出会ったことが大きな刺激になったという。「みんな面白い仕事しているなあ、とうらやましい気持ちがしました。でも、サラリーマンだって捨てたもんじゃない。会社の中で同じことをやればいい、と思い直しました」
竹森氏は「ブランドマネジャーの心得11か条 竹森流」を自ら定めている。ビジネススクールの恩師にいわれて作ってみたものだ。その内容は門外不出ということだが、今回、特別に見せてもらった。
そこにこんな一条がある。
一、ブランドマネジャーは社内外に対して“この指とまれ”と、とまりたくなるような夢を語れるパフォーマーでなければならない。と同時に、その裏で現実的な算盤を弾く腹黒さの両面を有していなければならない。
夢を語る青臭さと、数字を追いかける腹黒さ。われわれがこの連載で追っているイノベーターにも共通する資質だ。ブランドマネジャーもイノベーターに違いない。
総括
竹森氏の全く新しい概念の商品を創りだしたイノベーションストーリー、いかがでしたか。
いつものようにイノベーション研究モデルに則って、幾つかの観点で話を振り返ってみたいと思います(図表01参照)。
今回注目する領域は、【組織外の情報・知識】と【思いつく】の間の領域、【事業化】と【イノベーション戦略】の3つです。先ず、【イノベーション戦略】について振り返ってみましょう。
図表01 イノベーション研究モデル
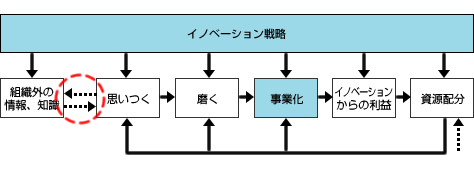
ブランドステイトメントに明示したのは、
新しい掃除行動という概念
竹森氏はブランドマネジャーであり、ルックという商品がカスタマーに対して約束することがブランドステイトメントであるといえます。それは戦略の領域よりも上位に位置づけされ、ミッション、ビジョン、バリューといったものと等価のものです。ブランドマネジャーに着任早々、竹森氏は、『新しい掃除行動』というステイトメントを経営陣に説明し、了承を得ています。
ルックといえば家庭用洗剤としては花王のマジックリンと双璧のブランドです。商品の多くはスーパーやホームセンターの棚に並んでいます。塗る、吹き付ける、混ぜる、こする、磨く、といった行為で汚れを落とすための商品です。失礼ながら、そこから何か新しいことが生まれるとは考えにくいです。しかし竹森氏は違いました。ルックのブランド価値を高めるために、『新しい』という言葉をステイトメントに入れました。敢えていばらの道を選んだともいえます。
また、モノではなくコトにブランド価値を昇華させるために、『掃除行動』という概念を設定したことも注目に値します。ルックという洗剤自体ではなく、掃除をすること、汚れを落とすこと、というコトに焦点をあてました。そうすることで、汚れを落とす洗剤という狭い考え方から思考が解き放たれ、汚れを落とすという行為や行為者に注目していくことになります。洗剤より掃除。モノよりコト。機能より意味。このような論理の高い次元での飛躍が生まれることで、ルックのブランド価値が徐々に高まっていったのです。
外部の資源を最大活用
そこに必要なのは全体を俯瞰してみる目
次に組織外の情報・知識と内部との接点について考えてみます。
この商品の最初のきっかけは中外製薬からの「バルサン」の事業承継でした。煙という素材とくん煙というプロセスは、ライオンとしては今までに全く扱ったことがない新しいものです。研究者は風呂の黒カビに注目しました。この分野では独壇場です。そして、カビ胞子の居場所が風呂の天井にあると突き止めます。そこに薬剤を届ければ、胞子を除菌することができるというわけです。まさに、中外製薬とライオンの新結合が生まれた瞬間。
オープンイノベーションという概念が普及し始めている現在、組織の外部と内部のインタラクションは非常に重要です。M&Aやジョイントベンチャーなどを活用し、外部知識の内部化を図ることは、イノベーション戦略のひとつといっても過言ではありません。そこで必要なのは、組織の内部知識を全体的に俯瞰して見ることです。竹森氏は、中外製薬の事業承継後の研究を、経営企画部という全社組織のメンバーとして捉えていました。そのポジションゆえ、当時の会社の経営状況や課題、戦略や戦術などは見えていたに違いありません。そして後に自身がブランドマネジャーになって、この大ヒット商品としてイノベーションが結実することになります。
社外と社内の知の交流は、お互いの技術、ノウハウ、経験、強み、実績などから、人材やその根底にある想いに至るまで、成されるべきです。そこに必要なのは、お互いが胸襟を開く大胆さと、組織や出自が違うことによる繊細さや高度なバランスといっていい。その絶妙なバランス感覚と大胆さを、竹森氏は持っているといえます。
社内を、顧客を、徹底的に巻き込む
共創型マーケティングの推進
最後に、事業化領域でのポイントについて考えてみます。
今までにないカテゴリーのものをどうやって普及させるのか? この商品は黒カビを落とす、というものではありません。カビが生えないようにする商品です。カビを落とすという掃除行動ではなく、カビを予防するという行為。これをカスタマーや社内に理解・共感させることは容易ではありません。竹森氏は営業に対してその概念の説明を繰り返し、アイデアを引き出し、マーケティングに取り入れます。自分たちが考えたアイデアが即、試される。そして、その結果が実績として表われる。その繰り返しです。先ず社内から、そして顧客をも巻き込んでいくその姿勢は、共創マーケティングそのものです。
引越し会社との提携によるサンプル供与作戦はその白眉ともいえるでしょう。確かに引っ越した先のお風呂は基本的に綺麗です。引越し先はその綺麗さを持続させることを実感してもらうには絶好の場面であり、サンプルを提供する引越し会社にとっても顧客に好印象を残すことになります。その他にも様々な共創型の顧客創造のアイデアを実行していきます。このような竹森氏なら、社内の誰もが彼の“この指”にとまりたくなるに違いありません。
概念を突き詰める
概念を超える
竹森氏のイノベーションストーリーを振り返ってきましたが、ここで気付いたことがありました。それは、概念の追求が概念すら変える、ということです。新しい掃除行動というブランドステイトメント-この項で言い換えるとイノベーション戦略-の進展は、掃除という概念を変え始めているともいえるのです。
この商品は掃除をしないことを促進します。汚れなければ掃除をする必要がないのです。勿論、お風呂にはカビ以外にも汚れは付着するので、全く掃除をしないで済む、ということはないでしょう。しかし、技術や知識が進化すれば、それすらも不可能なことではないのです。
「走れば走るほど空気が綺麗になるクルマをつくる」という概念を推進している自動車会社があります。そうなると、自動車の意味が変わってきます。竹森氏のイノベーションには、このような概念昇華の迫力を感じずにはいられません。ライオンでは、全く新しいコトがこれからも次々と世にでてくるのでしょう。
【インタビュー・文:井上功 /文(事例):荻野進介】
PROFILE
竹森 征之(たけもり まさゆき)氏
ヘルス&ホームケア事業本部リビングケア事業部 ブランドマネジャー
1970年2月24日生
1993年 ライオン株式会社入社(東京・大阪にて量販チェーンストア担当)
1998年 慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール)入学~2000年修了
2000年 市場情報部(リサーチ担当)
2002年 マーケティングプランニング室(ブランドマネジメント推進)
2004年 ビューティケア事業部(ヘアケア・ボディケア担当)
2006年 経営企画部
2010年 現職
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で