インタビュー
イノベーション研究 第7回 ローソン
『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- 公開日:2013/07/24
- 更新日:2024/03/31

本研究では、組織の中でのイノベーション創出のヒントを得るために、イノベーターの方々にインタビューを実施しています。
第7回は、株式会社ローソン(以下、ローソン)のダイバーシティを牽引するお二人、大隅聖子氏及び鈴木一十三(ひとみ)氏にご登場いただきます。
日本では、ダイバーシティを女性活躍支援という意味で捉えている企業が多いですが、そもそもの意味は『多様性、相違点』であり、転じて、『企業で人種・国籍・性別・年齢等を問わずに人材を活用すること。こうすることで、ビジネス環境の変化に迅速、柔軟に対応できると考えられている』といった解釈になります。
ローソンは、ダイバーシティを人材採用の領域で早くから推進してきました。定期入社社員における女性採用目標を定員の5割に設定したのは2005年。2008年の採用人数の3割を外国人留学生とする、というニュースは記憶に新しいと思います。その他にも多種多様のダイバーシティ推進施策を実施しています。
この広義のダイバーシティに新商品・新サービス開発を掛け合わせ、真のイノベーションを実現したのが今回のプロジェクトです。それは新結合の実現です。それでは、大隅氏、鈴木氏に語っていただきましょう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
- 目次
- 本格復帰前の不安を和らげ、かつ強みを発揮してもらう
- 女性の活躍推進が日本再生につながる、という確信
- 単なるダイバーシティではない別の仕掛けを
- COOいわく「風船すべてに責任を持て」
- 「ちょっとひと手間」が付加価値になる
- 「働くお母さん」の生活導線を変えたい
- 総括
本格復帰前の不安を和らげ、かつ強みを発揮してもらう
昨今のメディアには、企業で働く女性の活躍を後押しする施策の紹介が目白押しだ。いわく、育児休業制度、在宅勤務制度、子供の病気休暇、短時間勤務制度等々。こうした制度や施策が整備されるのは、有能な女性が育児というハンディを背負うことなく、男性と伍して働けるという意味でまことに喜ばしいことだが、一方でこうも言える。いずれもマイナスをゼロにする施策であって、真の女性活躍推進のためには別の仕掛けが必要ではないか、と。
言うは易し、そんな仕掛けが現実にあるのか、という方にぜひともお知らせしたい。コンビニエンスストアのローソンがこの4月からスタートさせた「スマートウーマン推進プロジェクト」である。
その概要は、育児休職後に職場復帰した女性社員が、子育てや主婦経験を存分に生かし、半年から1年という期間限定で、商品開発や店舗づくりを担当するというもの。終了後は原則、休職前の職場に復帰する。現在、リーダー含め、8名の女性社員が同プロジェクトに所属している。
休職後、職場復帰を目指す女性は、同僚や先輩に迷惑をかけず、前と同じ仕事が同じペースでできるかしら、という不安を抱きがちだが、同じ立場の女性が集まればそうした不安は解消する。しかも、担当する仕事は、まさに自分自身がそうである「働く主婦」目線の商品開発や店舗づくり。昨今、同社に限らず、コンビニエンスストア業界全体が、新しい顧客層として主婦層の開拓に力を入れており、まさにイノベーションが求められる分野だ。ママさん社員の就労不安を取り除き、彼女たちならではの強みを存分に発揮してもらう。
ただ、プロジェクトといっても、最初からかっちりとした“絵”があったわけではない。現在、プロジェクトリーダーをつとめる鈴木一十三(ひとみ)氏が、さまざまな人たちとの相互作用で作り上げていったものだ。
女性の活躍推進が日本再生につながる、という確信
実際の形になるには、鈴木氏にとって、ある経験が不可欠だった。
鈴木氏は、2011年12月から翌2012年の年末まで、内閣官房に出向していた。出向先は、官民の精鋭を選りすぐった50人ほどで構成され、日本再生のための戦略をまとめる国家戦略室という組織だ。
鈴木氏いわく、そこでの1年強の経験はスマートウーマン推進プロジェクトを立ち上げる上で、二重の意味で背中を押してくれた。どういうことか。「ひとつは、再生戦略の議論の中でも、女性の活躍推進が大きなテーマになっていたこと。でも成功例が少ないのが現実なので、このプロジェクトを始める際、だったら私が頑張ればいい、私のやることが会社の業績に、ひいては日本の再生につながればいい、と思えたのです。もうひとつは、私のような門外漢がいきなり、日本の明日を考えるような組織に入ったものですから、使われている言葉の意味や定義がよくわかりませんでした。でも、そこを曖昧にしては駄目だと思い、わかったふりをせず、知らないことはとことん人に聞き、物事をつきつめて考えることを学びました。この経験が、今までに事例の無い組織を立ち上げる上で、大きな糧となりました」
単なるダイバーシティではない別の仕掛けを
内閣官房から戻ってきた鈴木氏は、新浪氏から「女性がもっと活躍できる仕掛けを作って欲しい」と言われ、ヒューマンリソースステーション(人事部)に配属された。そこで、机を並べたのが理事執行役員で、ダイバーシティ推進担当の大隅聖子氏であった。
ローソンは、美と健康を考えたライフスタイルをサポートする、女性をターゲットにした店舗、主婦や高齢者向けの生鮮強化型店舗など、新しいコンビニの姿を模索してきた。
新しいことをするには、新しい人材が必要だ。その原則に即して、同社は人材の多様化にも力を注いできた。
2005年からは定期入社社員の5割目標で女性を、2008年からは同じく3割目標で外国人留学生を、それぞれ積極的に採用してきた。そうした女性に対する施策も早くから充実させており、育児休職期間を3年まで拡充したのは1992年のことである。日本人・男性以外の社員が確かに増え、ダイバーシティは順調に“推進”されているものの、「もう1ステージ、あげる仕掛けはないものか」と大隅氏は考えていた。
萌芽のようなものはあった。ローソンはヤフー株式会社と組み、この1月、育児や家事、仕事に忙しい主婦向けに食品や日用品の宅配サービスを行うスマートキッチンという事業を立ち上げている。そこでこそ、産休を終え、時短勤務の女性が生かせるのではないか。
COOいわく「風船すべてに責任を持て」
机を並べた2人の間で会話が生まれた。組織のミッション含め、アイデアは鈴木氏が考えた。育休からの復帰女性を一つの組織に束ね、彼女たちならではの仕事を担当してもらったらどうだろう、と。ダイバーシティとイノベーションを両立させる仕組みである。
一方、トップと話をして、箱を作り、形にしていくのが大隅氏の役割だった。「鈴木さんは人と人とをつなぐ力が非常に強い。プロジェクトのメンバーはもちろん、社内外、いろいろな人に会って自分のアイデアを話しては、意見をもらい、自分のアイデアをさらに磨いていく。それを数週間という短期間でやり遂げたのには正直びっくりしました」(大隅氏)
その間、鈴木氏はCOOである玉塚元一氏にも直に相談している。「私が事務局として、プロジェクトという、いくつもの“風船”の糸を下で持っておくべきか、それとも、すべての風船を自分の手で抱え込むべきか、ということでした」(鈴木氏)
玉塚氏はこう言った。
「糸だけ持つのは駄目だ。すべての風船の浮沈にまで責任を持ってくれ」
最も議論になったテーマは所属をどこにすべきか、ということだった。商品部がいいのか、CEOまたはCOO直轄にするか、それともマーケティング組織に置くべきか。それぞれのメリット、デメリットを勘案し、最終的には、顧客の声を拾うマーケティングに落ち着き、鈴木氏の所属も人事からマーケティングに変わった。2013年3月のことであった。そこでまた試行錯誤が行われ、プロジェクトがスタートしたのが4月であった。
「ちょっとひと手間」が付加価値になる
スマートウーマン推進プロジェクトは実際、どんなことに取り組んでいるのだろうか。
活動内容は3つに分かれる。
1つは商品開発への提案である。先述のスマートキッチンの商品やオリジナル商品、プライベートブランド「ローソンセレクト」などに関して、主婦あるいは働く女性の視点から、モニターに参加したり、商品開発への具体的提案を行ったりする。
その際のキーワードが「ちょっとひと手間」だ。「働くお母さんが最も困るのは夕食の準備なんです。そこにローソンをうまく使ってもらえたら、と考えているのですが、現在、われわれが提供している商品は即食性の高いものが多い。一方で、スーパーに行くと出来合いの惣菜が売られている。そう考えると、家庭における手作りと、スーパーにおける出来合い、両者の中間にあたるようなものを提供できないか、と。ちょっとひと手間かけられる。そこが付加価値になるのではないか、と考えています」(鈴木氏)
2つ目は店舗の棚割提案である。ローソン各店舗の棚割は最終的にはオーナーが決定するが、ローソン側でモデル棚割を半年に一度、提案している。たとえば調味料の棚割が代表例だが、主婦ならではの視点で、商品の選択や配置に関する見直しを提案する。
3つ目が社内外の女性の意見の収集である。「それまでは、商品のモニターを集める場合、担当者が知り合いに声をかけて集まってもらうケースが多かったのですが多くは男性でした。これを改め、プロジェクトを通じて社内の女性に声をかけたところ、約250名中、75名も集まりました。これだけの人数がいると、年齢はもちろん、結婚か未婚か、子供がいるかいないか、といったセグメントで分けることができます。商品開発担当者には大変喜ばれています」(鈴木氏)
「働くお母さん」の生活導線を変えたい
数年前、コンビニエンスストア発のスイーツが世を席巻したのを覚えておられるだろうか。その先駆けとなったのが2009年に発売され、爆発的ヒットとなったローソンの「プレミアムロールケーキ」だった。
実は鈴木氏はそのプロジェクトチームの一員だった。「働く女性は、帰宅が夜遅いですから、デパ地下や専門店に行けません。でも自分へのご褒美で、『一日お疲れさま』と、甘いものが食べたくなる時が絶対あるんです。これが大当たりして、今まで縁がなかった女性も確実にローソンに足を運んでくれるようになりました。コンビニエンスストアのスイーツが働く女性の生活導線を確実に変えた。このプロジェクトを通じ、今度は働くお母さんの生活導線を変えたいのです」
働くお母さんが自宅で待つ子供にかける電話といえば、「ちょっとスーパー寄ってから帰るわ」。スーパーは大きいから品揃えは豊富だ。が、一日くたくたに働いた身には広すぎてこたえる。確かに、寄る先がスーパーではなく、コンビニエンスストアに変わる日が近いかもしれない。
総括
大隅氏、鈴木氏のローソンでのイノベーションストーリー、いかがでしたか。
それでは、イノベーション研究モデルを踏まえ、お二人の活動を振り返ってみたいと思います。
今回のイノベーションは2つの方向を持っているといえます。ひとつは、『働くお母さん』と『コンビニエンスストアという概念であり装置』とを繋げ生活導線を変える、という市場創造の方向性です。これは組織の外に向かっています。もう1つは、その実現のために社内リソースを徹底して開拓・活用し、組織づくりからミッション推進までを実現したものです。こちらは組織の内に向かって成しえたイノベーションといえます。このイノベーションを、主に研究モデル上で「磨く」と「事業化」の領域で成しえたものとおき、お二人の話から得られる示唆を、いくつかの観点で考えてみたいと思います(図表01参照)。
図表01 本事例における仮説モデルの該当要素
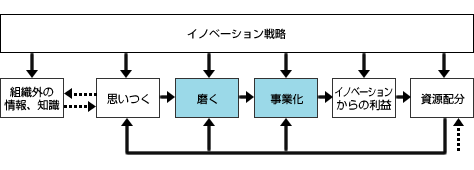
STPの対象は自分自身
自らが顧客であることで、強い仮設をだせる
この一連の研究インタビュー企画では、【組織の中からどのようにイノベーションを興したか】に関して、企業のイノベーターに様々な角度で訊いています。大前提として、イノベーションを【経済成果をもたらす革新】とおいています。イノベーションは普及があって初めて成しえるものです。モデル図では事業化の位置です。事業化とは顧客をつくることであり、マーケティングと置き換えられます。このマーケティング戦略の基本概念にSTP(Segmentation, Targeting, Positioning)があります。顧客をどう分類して、どのような顧客価値を浮き立たせるのか、がセグメンテーションの基本です。
では、セグメンテーションするときに、その対象が自分自身だったらどうなるか? 正にユーザー自身の経験や実感に基づいた、リアルな悩みや不便、不安が自ずと浮き上がってくるはずです。顧客をつくる、即ち市場を創るには、市場を熟知する必要があります。対象が自分だと棲み込むことが自然と出来ます。そして、新商品企画やお店の棚割り等の提案が真に迫り、強い仮説をつくりだすことができるのです。
ローソンでは育児休職後の女性社員の「働く主婦」としてのユーザー視点を活用できるよう、「スマートウーマン推進プロジェクト」として仕組み化しています。半年から1年の期間限定で商品開発への提案や店舗づくりを担当する。育児休職という出来事を想定し、「働く主婦」である対象者がごく自然にコミットできる仕事を用意することで、最適なターゲティングを実現しているのです。それは、イノベーションを生むための組織づくりのイノベーション、でもあります。
2つの攻めのダイバーシティ
21世紀になり、日本でも次第にダイバーシティという言葉が人口に膾炙するようになってきた感がありますが、多くの企業でダイバーシティは女性活躍推進的に捉えられています。
一方、ローソンでは、謂わば2つの攻めのダイバーシティを推進しています。
1つは、多様性の許容・活用を実施していることです。女性活躍支援だけではなく、ヘテロの推進の実現です。それは、言葉で言うほど簡単ではありません。特に他民族、他宗教、多言語との交流が少なかった日本では、例えば欧州や米国などと比べると非常に難しいことだと思われます。そんななか、ローソンでは、積極的な外国人留学生の採用や中途入社人材の活用などを実施し、多様性活用のダイバーシティを推進しています。新しい価値の創出を組織・企業全体で生み出そうとする攻めのダイバーシティということができます。
もう1つは、ダイバーシティと価値創出との接続です。ローソンでは、ダイバーシティのステージを上げることに取り組んでいます。命題は、どうやって経済価値に繋げるのか。生活産業であるコンビニエンスストアという事業立地は、ダイバーシティとの親和性はあるでしょう。しかし、多くの企業で女性チームの商品開発が企画倒れで終わっている現実もあります。そんななか、ローソンでは商品開発、棚割り提案、市場調査の3つの活動で、経済価値の創出を狙っています。2つ目の攻めのダイバーシティは、着々と価値創出に繋がっているといえるでしょう。
コトへの注目の徹底により、価値創出を育む
攻めのダイバーシティのもと、働く主婦を中心にプロジェクトが動き始めます。そこで注目されるのが、生活者視点でのコトへの注目です。働くお母さんが最も困るのは夕食の準備であり、出来合いだけでは物足りない主婦の感性や問題意識に注目し、『ちょっとひと手間』というコトを導きだしています。鈴木氏が以前携わった「プレミアムロールケーキ」も、『一日お疲れさま』という自分へのご褒美、すなわちコトとおいています。そして、それらは生活導線という発想に繋がっていきます。
鈴木氏が、「働くお母さんの生活導線を変えたい」と語る背景には、何を置いたら売れるのかという供給者サイドの発想ではなく、生活者の生活そのものをコトと捉えて価値創出を育む試みがあります。部分ではなく全体。数字ではなく自身のリアリティ。ものづくりではなくコト興し。これらのことが、多様性が担保された組織の中で粛々と推進されているのです。
ダイバーシティとイノベーション
ダイバーシティは多様性のマネジメントです。多様性を許容するには、自己と他者がもともと違うことを認識することが大前提であり、多様な価値観から変化に対する対応力をつけていくことがダイバーシティの要諦でしょう。
一方、イノベーションは新結合です。異なる概念、事象、商品・サービスなどを繋ぎ、新たな価値を創出することです。同種・同様のものを繋いでも新結合は起こせません。つまり、ダイバーシティの実践・許容がイノベーション創出の前提ともいえるのです。
ローソンではこの2つが見事に繋がっています。
日本で、この40年間、コンビニエンスストアは小売業のイノベーションを成し遂げてきました。一見成熟しつつある産業と思われがちですが、今回のローソンの大隅氏、鈴木氏へのインタビューを通じ、更なるイノベーション、新たなS字カーブの創出が出来る可能性を強く感じました。いえ、ローソンに於いては、イノベーションは現在進行形なのでしょう。
【インタビュー・文:井上功 /文:荻野進介】
PROFILE
大隅聖子氏
株式会社ローソン 理事執行役員 ヒューマンリソースステーション ディレクター補佐
1989年リクルート入社。
2006年よりローソン。
おもに店舗開発(新規FCオーナーの開拓)を担当。
2009年には開発本部本部長補佐として、フランチャイズオーナーの複数店舗化、さらには多店舗化経営オーナーを輩出。
その後、法人営業本部を経て、2012年4月から現職。
鈴木一十三(ひとみ)氏
株式会社ローソン CVSカンパニー マーケティングステーション 部長 スマートウーマン推進プロジェクトリーダー
1999年ローソン入社。店舗勤務、人事部(社会保険担当)、ナチュラルローソン(商品部)、中四国支社(商品部)、本社(商品・物流本部商品戦略部)を担当。
2011年、内閣官房 国家戦略室に出向。
2013年より現職。
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
Jammin’チーム
マスター
井上 功
1986年(株)リクルート入社、企業の採用支援、組織活性化業務に従事。
2001年、HCソリューショングループの立ち上げを実施。以来11年間、(株)リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。
2012年より(株)リクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍。2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤≪Jammin’≫を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行なう。
- イノベーション研究 第39回 iCARE(アイケア)
- 「我がこと」化がイノベーションの原点
- イノベーション研究 第40回 トレーフル・プリュス
- 西から吹いてきた医療維新の風
- イノベーション研究 第38回 ファンデリー
- 病院を基盤とした唯一無二のインフラ その上に乗る事業は無限だ
- イノベーション研究 第37回 「カロナビ」
- 管理栄養士やダイエットのプロによるダイエットサービスを提供
- イノベーション研究 第36回 「NewsPicks」
- 既存メディアのリニューアルから新メディアの立ち上げへ
- イノベーション研究 第35回 エンファクトリー
- 「専業禁止」で経営者目線を養い、相利共生のネットワークを築く
- イノベーション研究 第34回 味の素株式会社
- 味の素株式会社が作り上げた「アミノ酸バリューチェーン」
- イノベーション研究 第33回 GEN
- 本物の価値を「繋ぐ」ことで知らしめ人間のキャパシティを広げたい
- イノベーション研究 第32回 「雪マジ!19」
- 衰退市場を救う起爆剤としてのフリーミアムモデル
- イノベーション研究 第31回 リクルート
- アプリ・事業開発に不可欠な“頭と足腰”
- イノベーション研究 第30回 「COMUOON」
- 聞こえにくさを改善する、難聴者にとってのコペルニクス的商品
- イノベーション研究 第29回 「東京マルシェ」
- 日本の高齢化リスクを減らせるか? 八百屋とヨガの意外な組み合わせ
- イノベーション研究 第28回 シルバーウッド
- 日本の超高齢社会を支える静かな「切り札」
- イノベーション研究 第27回 「スパニッシモ」
- 旅で直面したグアテマラの貧困問題 旅で思いつき実行したその解決方法
- イノベーション研究 第26回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(後編)
- イノベーション研究 第25回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(中編)
- イノベーション研究 第24回
- 組織の中からイノベーションを興す8つのポイント(前編)
- イノベーション研究 第23回 大阪ガス
- 大阪ガス流、オープン・イノベーションの衝撃
- イノベーション研究 第22回 オービックシーガルズ
- トップダウンからボトムアップへ 「選手が主役」でつかんだ史上初4連覇
- イノベーション研究 第21回 三井物産
- リソース、プロセス、カルチャーを変えていけばイノベーションは確実に起こせる
- イノベーション研究 第20回 トヨタ自動車
- トヨタの本気、本腰を感じる モビリティの未来を考える組織
- イノベーション研究 第19回 経済産業省
- ハンズオン支援のあり方を模索 今までとは一味違うやり方を推進
- イノベーション研究 第18回 AZAPA
- 技術と技術、企業と企業、人と人 “つなぐ”ことが新しい価値を生む
- イノベーション研究 第17回 YKK
- 仕事の方針とやり方を根本的に変える! 理と情を駆使したチェンジ・マネジメント
- イノベーション研究 第16回 牛肉商尾崎
- 牛肉は日本の自動車と一緒 世界一の輸出品になれる
- イノベーション研究 第14回 Sweet Treat 311
- “思い”の連鎖が形になった どこにもない唯一無比の学び舎
- イノベーション研究 第13回 アイスタイル
- ベンチャーを脱する脱常識のマネジメント
- イノベーション研究 第12回 ライオン
- 「掃除行動の変革」という高い目標が生み出したカビの予防という新市場
- イノベーション研究 第11回 品川女子学院
- 廃校の危機も噂された女子校が都内屈指の人気校に
- イノベーション研究 第10回 リコー
- イノベーションとは「思いの連鎖」“死の谷”を超えたリコーの奇跡
- イノベーション研究 第9回 国土交通省
- 霞が関の一角に存在する、空港改革を担う“部室”とは?
- イノベーション研究 第8回 ソニー生命保険
- すばらしい果実を生んだ未知と未知のかけ合わせ
- イノベーション研究 第7回 ローソン
- 『働くお母さん』をコンビニエンスストアは取り込めるか
- イノベーション研究 第6回 ライフネット生命保険
- イノベーティブかどうかも含め組織のあり方はトップに依存する
- イノベーション研究 第5回 AIU損害保険
- 本質論でチームを結束させ、個別論で難題を突破する
- イノベーション研究 第4回 日東電工
- 知の探索活動を組織化した画期的仕組み
- イノベーション研究 第3回 日経 経済知力研修
- “けもの道”を切り拓く、イノベーターの知力と行動力
- イノベーション研究 第2回 水ing
- 最先端の水道技術を世界へ 目指すは「和製水メジャー」
- イノベーション研究 第1回 エキュート
- 通り過ぎる駅から買い物をする駅へ
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で