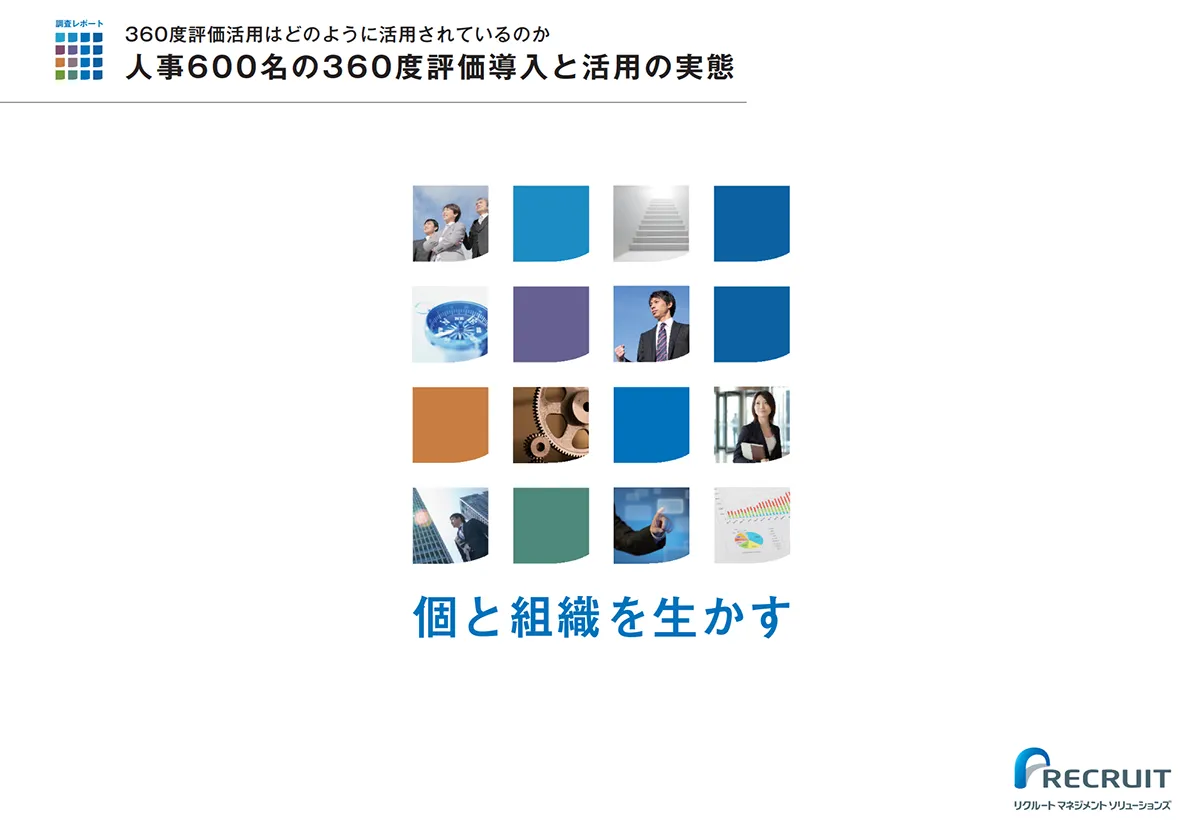- 公開日:2025/07/14
- 更新日:2025/07/14

日本電気株式会社(以下、NEC)はBIツールを活用し、人事データの可視化に取り組んできた。そしてここ数年は、HR以外の部門も人事データを活用できるよう、ボトムアップで施策を進めているという。ピープル&カルチャー部門 HRコンサルティング統括部の菅崎理功氏(写真中央)と、人材組織開発統括部の河村 桂氏(写真左)に詳しく伺った。
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第32回
- 従業員の本音をAIが引き出すことでエンゲージメントを向上
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第31回
- 360度評価に潜むバイアスをアルゴリズムで除去
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第30回
- HRBPとCoEが連携し人事データの活用を「社内文化」にする
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第29回
- LLMでアンケートの自由記述回答分析を大幅に省力化できた
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第28回
- ピープルアナリティクス浸透のカギは文化とリーダーシップ
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第27回
- テクノロジーに精通したヒューマニストでありたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第26回
- 仏教×データ分析で働く人の幸福度を高め企業創りを支援する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第25回
- 生成AIが普及したら人間ならではの仕事を行う姿勢が大事になる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第24回
- データ活用の際に人事に必要な調査リテラシーは何か
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第23回
- 定量・定性の両面から現場にアプローチして人と組織を理解する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第22回
- 適性タイプ分類モデルでバランスよく多様な人財の採用に成功
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第21回
- 社員の「ワクワク感」を高めるEX観点を日本の常識にしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第20回
- 「信頼」を科学してイノベーションを生み出す日本にしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第19回
- 「人事の脱エクセル」が進む可視化中心のピープルアナリティクス
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第18回
- 経営と目線を合わせたピープルアナリティクスが今後の鍵になる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第17回
- マーケットデザインとマッチング理論で適材適所を促進する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第16回
- 負荷を増やさずに人事データを民主化し意思決定を変える
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第15回
- 人的資本投資の開示・マネジメントツールISO30414
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第14回
- データサイエンスとビジネスの橋渡しが最も大事で難しい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第13回
- 他社が始めたから自分たちも、という意思決定でよいのか
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第12回
- スマートビルが横や斜めのつながりを増やして創発を促す
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第11回
- アナリティクスを人事の現場に普及させたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第10回
- 創造性を科学し社会価値創造のエコシステムを作る
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第9回
- NAONAで1on1ミーティングをもっと良いものに
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第8回
- 伝え方次第でデータの効果は0にも100にもなる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第7回
- グローバル市場で技術力で勝つ日本企業を増やしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第6回
- 人事系データの分析課題の多くは「可視化」で解決できる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第5回
- 最後のフロンティア“脳”の計測技術が生活の質を向上させる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第4回
- 人事部門に必要なデータ活用には特有の難しさがある
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第3回
- ピープルアナリティクスで人財ポートフォリオの転換、社員の活躍促進を目指す
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第2回
- これからの人工知能はパーソナル化して“感性”に最適化される
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第1回
- 「統計モデリング」には人事のあり方を変える力がある
BIツールの導入が人事データ活用の大きな転機に
入江:まずは、NECの人事データ活用がどのように進められてきたのかお教えください。
菅崎:以前はマイクロソフト社製のデータベース管理ソフトAccessやExcelで人事データを扱っていましたが、2019年にBIツールTableauを導入したのが大きな転機でした。Tableau導入後には複雑なマクロや計算式・クエリを用いたいわゆる“職人技”が使える限られたメンバーだけでなく、幅広いメンバーが人事データを活用できるようになりました。
河村:2021年には、人事データ活用の専門チームが社内で発足しました。同年には当社の人事データ分析に関する取り組みが、ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会が主催するDigital HR Competitionでグランプリを受賞。人事データを活用しようという機運が社内で高まりました。
入江:Tableauのダッシュボードで見られるのはどんな人事データですか。
河村:いろいろ確認できますよ。退職率や勤務状況、スキルレベルなどを、職種や採用年次、新卒採用かキャリア採用かなどさまざまな切り口で抽出したり、グラフ化したりできます。
人事データの活用法を学ぶ実践的ワークショップを開催
入江:NECでは2023年頃から、人事データ活用のリテラシーを高める取り組みをされていると聞きました。どうして始めたのですか。
菅崎:私を含めたHRBPメンバーのなかに、「人事データは見やすくなったが、うまく使いこなせていない」という危機感が高まったからです。
ダッシュボードを使えるようになったことで、HRBPの仕事はガラリと変わりました。データをさまざまな切り口ですぐ加工できるようになったため、サーベイの分析などに費やす時間を大幅に短縮できたのです。また、誰かにエンゲージメントの状況や人員統計などの人事に関する説明をするときも、ダッシュボードを開けば必要な情報を提示でき、わざわざ資料を作る必要がなくなりました。ただ、そうやって積極的に使いこなしているのは一部のHRBPメンバーだけでした。ツールが整備されても、それを使う文化が社内に定着しなければ価値は生み出せません。そこでHRBPがCoEに協力を仰ぎ、社員の人事データ活用リテラシーを高める活動に取りかかりました。
河村:ダッシュボードを作る側のCoEでも、もっと使ってほしいという思いがあり、HRBPからの声がけは渡りに船でした。
入江:経営層の指示ではなく、現場からの提案で始まったのですね。
菅崎:そうです。NECではボトムアップでこうしたプロジェクトがスタートすることがよくあります。
入江:HRBPとCoEの連携は円滑に進みましたか。
菅崎:HRBPとCoEは、互いの主張が食い違うケースも少なくないと感じます。でも、今回は同じ危機感を共有できていたため、互いにうまく協力し合うことができました。
入江:リテラシー向上を目指す際、課題になったのはどんな点でしたか。
菅崎:ダッシュボード上のデータをどう読み取り、それをどう生かすか分かっていないメンバーが多かったことが課題でした。例えば退職という領域なら、世代別の退職率、人事評価と退職率の相関など、さまざまな切り口のデータがダッシュボードで確認できます。しかし多くのメンバーはデータを眺めるだけで、そこから仮説を立ててビジネスに役立てる方法を知らなかったのです。
そこで、まずはHRBPの有志15人ほどが集まり、全5回のワークショップを半年程度かけて実施しました。社内の事例を引きながら、人事データの読み取り方、仮説の立て方やビジネスリーダーへの説得力のある説明の仕方など多くを学びましたね。
入江:単なるケーススタディに終わらせず、ビジネスリーダーへの提案という行動にまで落とし込んだのがいいですね。ワークショップ参加者の感想はどうでしたか。
菅崎:とても好評で、終了後のアンケートでは「活用につながるヒントをたくさん聞けた」「すぐに実践したい」といったポジティブな回答が多かったです。
河村:ワークショップでは、利用者からの意見をもとに、ダッシュボードの機能強化や操作性の向上につなげている旨を話しました。実際、参加者から寄せられた感想からヒントをつかみ、ダッシュボードを改善したケースもあります。
また、第1回のワークショップの参加者はHRBPメンバーだけでしたが、第2回はデータ活用に関心のあったCoEメンバーも数人参加しましたし、グループ会社から参加した人もいました。評判が良かったため、今後の継続開催を検討しているところです。
入江:参加者が増えれば、社内での波及効果も期待できますね。
今後は生成AIを活用した人事サービスの開発も目指す
入江:ワークショップを開いた結果、どんな効果がありましたか。
菅崎:参加者のうち数名が、エンゲージメントサーベイの結果に基づいて社員との対話を強化する試みを始めました。他にも、ワークショップでの学びを起点にして新たな人事提案にトライしているメンバーもいます。
入江:素晴らしいですね。人事データを活用しようとする文化は、社内に根付きつつありますか。
菅崎:文化というものは定着まで時間がかかるものです。私たちとしては2030年あたりを見据え、長期的スパンで動いていますが、少なくともHRBPにおいては、データ活用をさらに進めようと考える人が多数派になりつつあると感じています。
河村:私も同意です。HRでアンケートをとると、データ活用を進めるべしという意見が多く寄せられます。
入江:では最後に、今後の展望をお聞かせください。
菅崎:BIとAIを組み合わせた施策は大きなテーマですね。すでに一部導入していますが、AIにエンゲージメントサーベイの分析や求職者のESチェック、空きポストと社員のマッチングをさせることなどが考えられます。他にも、先日は私を含めた有志で、目標設定をAIがサポートするアプリを開発し、社内で数万のビューを得ました。具体的には、質問にいくつか答えるとAIが目標を要約・生成し、さらにSMARTにするためのアドバイスをしてくれます。
河村:私たちの部門でも、社員のキャリアを生成AIでコンサルティングするアプリを開発しています。ただ、いろいろなチームが自由に開発するとガバナンスが効かなくなるため、CoEなど特定の組織が全体像を把握するような仕組みも必要です。
入江:なるほど。今後も人事データの活用は進みそうですね。
河村:そうですね。私たちも、社内の誰もが同じ人事データを見られるように、データマネジメントの取り組みを進めていきたいです。
菅崎:実は私や河村は文系出身です。そういう人や新入社員でもダッシュボードを活用できるような、分かりやすい仕組みを作ることも課題です。
入江:そのためには、HRBPとCoEの連携が今後も大事になりそうですね。
河村:そう思います。CoEの立場としては、HRBPとさらに連携し、ツールの改善に役立てたいと考えています。
【text:白谷 輝英 photo:伊藤 誠】
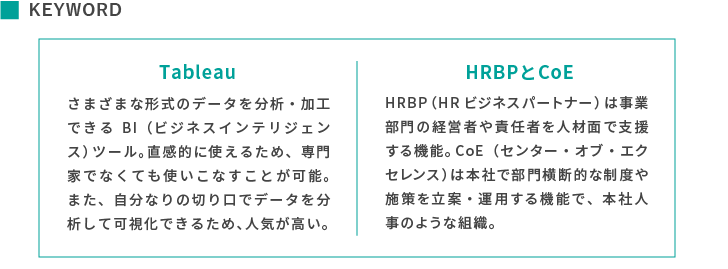

データ活用の推進というと、分析のインフラや技術を整えることに意識が向きがちです。しかし、それらが整ったとしても、「何のために」「どのように」データを扱えばよいかが分からなければ、せっかくの取り組みが無駄になってしまいます。
今回のお2人の取り組みは、データの読み取りや仮説の構築、そして検証した結果をもとにしたアクションの実施という、「データの使い方」の浸透にこだわった点が1つのポイントです。
また、HRBPとCoEという異なる立場にありながら、長い時間をかけてでも人事データ活用の文化を定着させたいという共通の思いをもち、多くの仲間を巻き込んだ取り組みにしている点がもう1つのポイントです。
お2人の気概のある取り組み、皆様もぜひ参考にしてください。
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.78連載「データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 連載第30回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
菅崎理功(かんざきりく)氏
日本電気株式会社 ピープル&カルチャー部門 HRコンサルティング統括部 機能コンサルティンググループ プロフェッショナル
新卒でNECに入社し、労務、官公庁出向などを経て現職。現在はHRBPの立場で人事データの活用施策に取り組む。
河村 桂(かわむらけい)氏
日本電気株式会社 人材組織開発統括部 HRプロジェクトグループ
新卒でNECに入社し、人事・総務を経て、2022年からHRアナリティクスチームに加わり、CoEとしてデータマネジメント関連の仕事を進めている。
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第32回
- 従業員の本音をAIが引き出すことでエンゲージメントを向上
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第31回
- 360度評価に潜むバイアスをアルゴリズムで除去
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第30回
- HRBPとCoEが連携し人事データの活用を「社内文化」にする
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第29回
- LLMでアンケートの自由記述回答分析を大幅に省力化できた
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第28回
- ピープルアナリティクス浸透のカギは文化とリーダーシップ
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第27回
- テクノロジーに精通したヒューマニストでありたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第26回
- 仏教×データ分析で働く人の幸福度を高め企業創りを支援する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第25回
- 生成AIが普及したら人間ならではの仕事を行う姿勢が大事になる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第24回
- データ活用の際に人事に必要な調査リテラシーは何か
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第23回
- 定量・定性の両面から現場にアプローチして人と組織を理解する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第22回
- 適性タイプ分類モデルでバランスよく多様な人財の採用に成功
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第21回
- 社員の「ワクワク感」を高めるEX観点を日本の常識にしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第20回
- 「信頼」を科学してイノベーションを生み出す日本にしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第19回
- 「人事の脱エクセル」が進む可視化中心のピープルアナリティクス
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第18回
- 経営と目線を合わせたピープルアナリティクスが今後の鍵になる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第17回
- マーケットデザインとマッチング理論で適材適所を促進する
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第16回
- 負荷を増やさずに人事データを民主化し意思決定を変える
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第15回
- 人的資本投資の開示・マネジメントツールISO30414
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第14回
- データサイエンスとビジネスの橋渡しが最も大事で難しい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第13回
- 他社が始めたから自分たちも、という意思決定でよいのか
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第12回
- スマートビルが横や斜めのつながりを増やして創発を促す
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第11回
- アナリティクスを人事の現場に普及させたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第10回
- 創造性を科学し社会価値創造のエコシステムを作る
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第9回
- NAONAで1on1ミーティングをもっと良いものに
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第8回
- 伝え方次第でデータの効果は0にも100にもなる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第7回
- グローバル市場で技術力で勝つ日本企業を増やしたい
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第6回
- 人事系データの分析課題の多くは「可視化」で解決できる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第5回
- 最後のフロンティア“脳”の計測技術が生活の質を向上させる
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第4回
- 人事部門に必要なデータ活用には特有の難しさがある
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第3回
- ピープルアナリティクスで人財ポートフォリオの転換、社員の活躍促進を目指す
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第2回
- これからの人工知能はパーソナル化して“感性”に最適化される
- データサイエンスで「個」と「組織」を生かす 第1回
- 「統計モデリング」には人事のあり方を変える力がある
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)