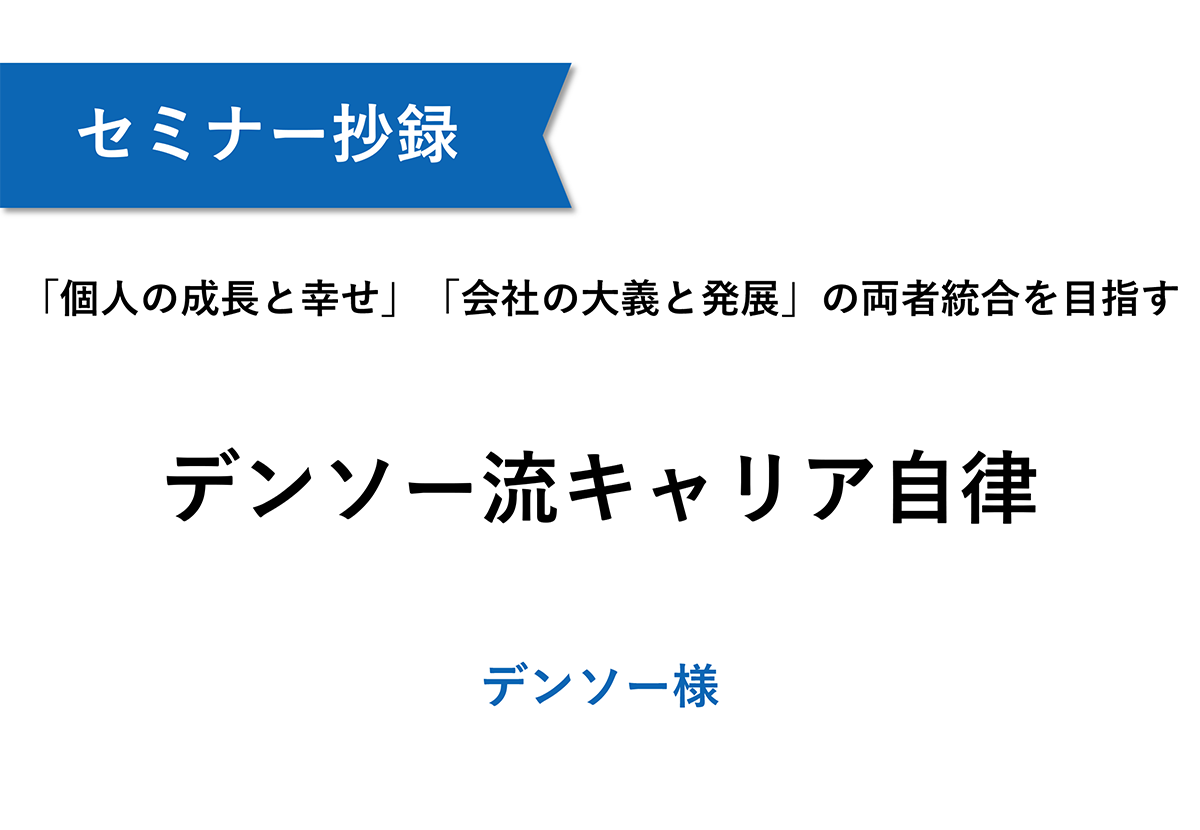連載・コラム
職場に活かす心理学 第13回
いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 公開日:2015/07/22
- 更新日:2024/05/16

残念なことに、日本は先進国のなかでも自殺者が多いのですが、その理由として最もよく挙げられるのが健康の問題です。平成22年度の警察庁の調べによると、自殺の理由は「健康問題」に続いて「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」と続きます。「健康問題」のなかでも、「病気の悩み・影響(うつ病)」が最も多い傾向にあること、家族従事者で最も多い「経済・生活問題」にも仕事に関係あるものが含まれることを考えると、実は仕事や職場の問題が理由になっているものはかなりあるものと考えられます。確かに職場を見てみると、人間関係の問題だったり、先行きの不安だったり、パワハラだったり、業績のプレッシャーだったり、転職後の適応がうまく行かなかったりと、問題は山積しているように見えます。今回は、誰もが多かれ少なかれぶつかる壁を私たちはどのように乗り越えていくのか、うまく乗り越えられるかどうかに関連する要因にはどのようなものがあるのかといったことについて、考えてみたいと思います。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
レジリエンス(精神的回復力)と職場のストレス
レジリエンスは精神的回復力と訳されますが、困難な状況下で発揮されるポジティブな適応プロセスであるとされています。レジリエンスの研究では、愛する人との死別やトラウマ体験といった大きなストレスイベントに対する耐性や回復力が、主に扱われてきました。ところが上記で述べたように、職場や仕事における問題は難しさを増していて、多くの人は日々かなりのストレスにさらされていますし、その状況が早晩変わるとは考えにくいでしょう。
図表01は、愛する人との死別(左の図)と職を失う経験(右の図)の後の、情緒的な幸福感(affective well-being)と、認知的な幸福感(cognitive well-being)の変化を見たものです。情緒的な幸福感とは、快感情(ex.楽しい)があること、あるいは不快な感情(ex.気分が落ち込む)がないことです。認知的な幸福感とは自分の人生や仕事、人間関係などに対するポジティブな評価(ex.人生に満足している)です。
グラフの縦軸は、死別や離職といったイベントの前後での幸福感の比較になるのですが、職を失った直後の感情面での幸福感は、ばらつきは大きいものの、死別の場合と同程度のネガティブな反応を示す場合があることが分かります。ちなみに職を失った場合、情緒的幸福感ではその後のレベルにさほど変化は見られませんが、これは研究数の少なさによる部分もあるものと思われます。一方、認知的な幸福感は徐々に回復する傾向があることが分かりますが、元のレベルに戻るまでには40カ月を要することが予想されています。職を失うといった、自己概念を揺るがすような出来事のインパクトは相当大きいといえるでしょう。
図表01 愛する人との死別と職を失う経験の後の幸福感の変化

出所: M Luhmann, W Hofmann, M Eid, & RE Lucas(2012).
一方で、実は私たちにはネガティブな出来事への耐性がかなり備わっているのではないかと指摘する研究者がいます。図表02は、Bonannoらが2008年の論文で示したものです。「回復」とは異なり、「レジリエンス」が高い場合は、トラウマ的な出来事の直後から、比較的安定して通常の生活を営んでいることが分かります。さらに、実はこの図表のようなレジリエンスを示す人は意外と多く、愛する人との死別を経験した人のおよそ半数に上るのではないかともいわれています。もちろん愛する人を失った悲しみや、気分の落ち込みはあるのでしょうが、Bonannoらの2002年の研究では、レジリエンスを示す人はそうでない人と比べて、悲嘆にくれる状態は一時的であり、日常生活を営む機能は阻害されず、ポジティブな感情を感じることもできていたと報告しています。
図表02 喪失経験やトラウマになるような経験後に通常の生活が阻害される程度の典型例

出所:GA Bonannoら(2008).
レジリエンスを促進する要因1(自己効力感)
それではレジリエンスを示す人とはどのような人なのでしょうか。例えば、「人生において意義のある目的を見つけようとする」「自分は周囲の環境や出来事に影響力があると信じている」「良くも悪くも経験から学び、成長できると思っている」といった特徴をハーディネス(頑健さ:高ストレス下で健康を保つ人がもつ個人特性)と呼ぶのですが、このような特徴をもつ人は、レジリエンスが高いことが分かっています。ハーディネスの高い人は、仕事で大きな失敗をしたり、降格されたりしたときに、どのように自分の置かれた状況を考えるのでしょうか。今はつらいけれども、こうなった理由を明らかにしてそれを克服することで、次の機会が回ってきたときに自分はきっとまた活躍できるだろう、と考えるのではないでしょうか。ハーディネスは後天的に身につけることが可能だと考えられており、近年ハーディネスを獲得するための研修についての研究も行われているようです。
BauerとBonanno(2001)の研究では、このような「自分はこの先○○できるだろう」といった今後に向けた自分のポテンシャルの評価(自己効力感)と、「自分はよくやった」「自分には優れた能力がある」といった自己評価を区別して、それぞれが愛する人との死別後の悲しみの程度にどのような影響を及ぼすかを検討しました(図表03)。その結果、自分のポテンシャル評価(自己効力感)がある場合のみ、安定して悲しみをより多く軽減する効果が確認されています。
図表03 自己効力感が悲しみの程度に及ぼす影響

出所:JJ Bauer & GA Bonanno (2001).
これまでの研究からは、状況にどう「意味づけ」をするかにも、レジリエンスを高めるポイントがあることがわかっています。例えば、仕事での大失敗を自分が成長するチャンスだと捉えるか、自分のキャリアはこれで終わりだと思うかでは、その後の本人の心理や行動には大きな違いが生じるでしょう。ハーディネスのような個人特徴は、今はつらくても先行きに対する明るい見通しをもつことで、レジリエンスを促進しているといえそうです。
レジリエンスを促進する要因2(感情の制御)
そうはいっても、ショックなことや難しい場面では、不安になったり、怒りや悲しみを感じたりすることは、ごく普通の反応でもあります。レジリエンスを示す人は、ネガティブな感情を感じていないわけではなく、うまくコントロールできているということなのかもしれません。
ネガティブな感情は、その感情にラベリングをすることでコントロールしやすくなるといわれてきました。例えば腹が立っているときに、「自分はとても腹を立てている」と思うといったことです。なぜ感情のラベリングにこのような効果があるかは、これまではよく分かっていなかったのですが、近年の脳の神経画像を用いた研究では、ネガティブな刺激(怒りや恐怖の感情を表す表情の画像)を与えられた後に、感情にラベリングをすると、脳の感情反応が抑制されることを示しています。この実験では、実験参加者は図表04に示す6つの課題を行いますが、その際に脳の感情に関する情報処理を行っている部位の活動の状況を測定します。その結果、図表05にあるように、感情のラベリングを行うことで、脳の特定部位の活動が抑えられたことが分かりました。
図表04 6つの課題で用いられる画像イメージ

出所:MD Lieberman, NI Eisenberger, MJ Crockett, SM Tom, JH Pfeifer & BM Way(2013)を参考に筆者が作成
図表05 課題別の感情に関する情報処理部位の活動の推定値(形のマッチング課題を基準として)
.gif)
出所:MD Lieberman, NI Eisenberger, MJ Crockett, SM Tom, JH Pfeifer & BM Way(2013)
困難な状況に置かれたときに、自分の状況を少し客観視することで、感情に飲み込まれることなく、落ち着いてその状況の意味づけを行ったり、対処方法を考えられるようになることが期待できます。
レジリエンスを促進する要因3(社会的資源の活用)
近年のストレスコーピング(対処方法)の研究のなかでは、私たちがどのようにストレスに対処するかにはさまざまなパターンがあることが分かっています。そしてその際に使用可能なものをまとめて「コーピング資源」と呼びます。資源のなかには上記に述べた「自分はやれる!」といった効力感や、物事をポジティブに捉える傾向である楽観性のような「心理的資源」だけでなく、当人が置かれた環境や社会的なサポートなども資源に含まれ、「社会的資源」と呼ばれます。
家庭環境は社会的資源の1つと考えられますが、Finkelsteinら(2007)は、親の学歴が低いと青年期の子供のストレスが増加する傾向があることを示しています。ただしこの研究では、本人の楽観性がストレスの軽減に有効であることも示しています。つまりコーピング資源は互いに補い合う可能性があるということです。
ただし、異なるコーピング資源がどのようにコーピングのプロセスに影響しているかについては、十分に分かっているわけではありません。そもそも、ストレスコーピングに関する心理学的なモデルでは、状況の認知的評価が重要なポイントになります。同じように難しい状況に置かれても、その状況が自分にとってどの程度難しいと感じるか、そして自分がうまく対処できそうかの評価には個人差があります。このような認知的評価と社会的資源の関係はどうなっているのでしょうか。また、資源間の補完性も必ずしも完全ではないかもしれません。社会的資源があれば、心理的資源が全くなくても大丈夫とはいえないでしょう。以降では、社会的資源と心理的資源の関係性について考えてみたいと思います。
社会的資源のなかで、親の学歴のような家庭環境は、変化しにくいものです。そうではなく、増やすことの可能な社会的資源もあります。例えば周囲の人から支援を得ることや、自分が所属する集団に同一視すること、すなわちその集団の一員である自分を強く意識することなどもストレスの影響を軽減することが研究で示されています。例えば、Brissetteら(2002)が行った研究では、楽観性が高いことは、状況をポジティブに解釈することに加えて、周囲からのサポートを増やすことにもつながり、抑うつ傾向を軽減させる効果があったことが報告されています。
下に示すグラフは、Greenawayら(2015)が行った研究の結果です(図表06)。この研究では実験的に自国への同一視の程度を操作した結果、同一視が高まった人ほど周囲のことに対するコントロール感を高くもつ傾向があったことが分かりました。さらに同研究では、コントロール感が高まった結果、人生満足度が有意に上昇したり、抑うつ感が有意に低下したりすることも示されました。
図表06 操作された自集団への同一視がコントロール感に及ぼす影響
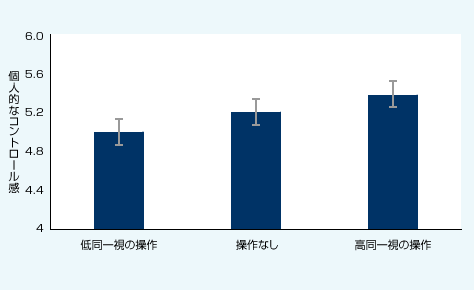
出所:KH Greenaway, SA Haslam, T Cruwys, NR Branscombe, & R Ysseldyk (2015)
以上の結果からは、他者からの支援や、自分の所属する組織との良好な関係性といった社会的資源と、楽観性やコントロール感といった心理的資源の間には、互いに高め合う効果があることが分かります。Hobfoll(2002)は、心理的あるいは社会的資源に関する研究や理論をレビューした結果、私たちはいざというときのために、いずれの資源も増やすような行動を常に行っているのではないかと述べています。
直面するかもしれない困難な状況に対処するためには、ハーディネスのような特徴をもって日々の生活を送ること、いざというときに「自分はなんとかなる」と思えるような小さな成功体験を積み重ねておくこと、周囲の人や所属する組織と良好な関係性を築いておくことなどが有効だといえるでしょう。また不幸にして、難しい場面に立たされてしまったら、自分自身の反応を客観視しつつ、感情に埋没しないようにすることが重要です。ここではあまり触れませんでしたが、自分の状況を他者に説明することも、自己を客観視するには有効だと思われます。素直に自分の気持ちを打ち明けられ、話に耳を傾けてくれる友人や家族の存在は貴重だといえるでしょう。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)