用語集
レジリエンスとは? 意味やビジネスで重要である理由、高める方法を解説
- 公開日:2022/08/23
- 更新日:2025/07/01
レジリエンスは組織運営や業務の遂行においても重要な能力であることから、ビジネスシーンでも注目を集めています。特に、社会人としての経験がまだ浅い新入社員は業務の負荷に対するレジリエンスが低く、早期退職につながりやすいため、企業には早い段階から従業員のレジリエンス向上に取り組むことが求められています。
レジリエンスとは
レジリエンスとは、「回復力」「弾性(しなやかさ)」といった意味の英単語であり、心理学用語としては困難な状況やストレスに対する耐性の強さを指します。レジリエンスが高い状態は「レジリエント(である)」と表現され、レジリエントな人物は逆境に直面しても諦めることなく、克服できる可能性が高いと考えることができます。
レジリエンスがビジネスで重要である理由
ビジネスにおいてレジリエンスが重要視されている背景には、以下のような要因があります。
ストレスに感じていたことも成長の糧になるため
レジリエンスを高めることで、苦手な仕事や、新しい課題、多様な人との協働など、初めはストレスに感じやすいことも、ビジネスパーソンとしての成長につなげていくことができます。
例えば、レジリエンスが高い場合、困難な業務を乗り越えたという経験は、新たな気づきや自信を生み、さらなるレジリエンスの向上につながる可能性があります。また、他者と意見がぶつかった際には、お互いの主張を理解し合い、和解することでより強固な信頼関係が生まれるでしょう。
ビジネス環境の将来予測がしづらくなっているため
社会の状況がめまぐるしく変化し、曖昧で不安定な事柄が増えている現代は「VUCA時代」と呼ばれ、ビジネスにおいても先を見通すことが困難な時代とされています。
そのような現代において、予想外の事態にも柔軟に対応できるレジリエンスには、企業や事業の将来を左右する能力として大きな期待が寄せられています。VUCA時代の定義や求められる能力に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
レジリエンスにおける2つの因子
レジリエンスを知るうえでは、まずは仕組みを理解することが大切です。レジリエンスは、「危険因子」と「保護因子」という2つの因子によって発揮されると考えられています。
危険因子
危険因子とは、レジリエンスを発揮する対象となる、課題やストレスを生んでいる原因のことです。主な例としては、病気や貧困、災害、戦争などが挙げられます。
市場の縮小や従業員同士の対立といったビジネス上の困難も、背景にはこうした危険因子の影響があります。そのため、レジリエンスが高い状態とは、それぞれの危険因子に対して適切に対応できる状態と言い換えることができます。
保護因子
逆境の要因が危険因子であるのに対して、逆境を「乗り越えられる」要因は保護因子と呼びます。具体的には、困難に直面した際に手を貸してくれる周囲の人々との関係性や、事態解決につながる自らの経験・能力などが保護因子にあたります。
効果的な保護因子を増やすことは、レジリエンスの向上に直結します。逆に、現状のレジリエンスが低いと感じる場合には、これらの保護因子が足りていない可能性が高いでしょう。
レジリエントな人・レジリエントではない人
ここではレジリエントな人、またレジリエントではない人の特徴を検証していきます。
レジリエントな人
レジリエントな人は、逆境に遭遇してもうまく乗り越えることができます。以下はレジリエントな人が持っている代表的な特徴です。
- 考え方が多様
- 気持ちの切り替えがうまい
- 自分にも人にも優しい
- 周りの人と協力関係を築ける
- チャレンジを続ける
- 自分の良い面を認識している
レジリエントではない人
レジリエントではない人は、仕事の上で度々訪れる逆境に対して弱いため、通常のパフォーマンスを発揮できるレベルに回復するまで時間がかかってしまいます。レジリエントではない人には、以下のような特徴があります。
- 気持ちの切り替えが苦手
- 考え方の柔軟性が乏しい
- 自分にも人にも厳しい
- 一人で抱え込む
- 対人緊張が強い
- チャレンジしない
- 自分のネガティブな面にばかり注目している
レジリエンス(回復力)の妨げとなる考え方
ここからは回復力を減退させ、レジリエンスをなくしてしまう考え方についてお話します。
ABC理論
ABC理論とは出来事(Adversity)から認知・思考・解釈(Belief)が生じ、結果としての感情・行動・生理的反応(Consequence)が引き起こされると考える理論です。最終的に生じる感情・行動・結果は、認知・思考・解釈が異なれば違いが生じます。つまり、同じ出来事でも解釈によって、受け取り方が変わるという考え方です。
「上司に意見を却下された」という出来事を想定してみましょう。「自分は否定された」と解釈すれば、最終的に怒りが湧いきてしばらくはその感情にとらわれてしまうかもしれません。しかし、「上司は冷静に判断し、当たり前の決断をしただけ」と捉えることができれば、フラットな気持ちのままでいることができます。
一方、出来事に対してその都度ネガティブな受け取り方をしてしまうと、回復が遅くなってしまうことになります。
A-C理論
A-C理論は出来事と感情の間に解釈が存在せず、直結していると考える理論です。ABC理論では受け取り方を変えることによって感情をコントロールすることができますが、A-C理論では解釈の概念が存在しないため、意識することによって感情をコントロールできません。自分で変えられる要素がないため、状況によって受け身となってしまいます。
レジリエンスを高める方法

ここからは、レジリエンスを高めるうえで効果的な方法を紹介していきます。
STEP1.認知を柔軟にする
レジリエンスを発揮するうえで特に重要となるのが、ABC理論のB(Belief)にあたる「認知」です。逆境に直面した際に取れる行動は、その状況を自らがどう捉えているかによって大きく異なります。
特定の視点や一方的な偏見にとらわれていては、解決方法は狭まり、アプローチの正確性も失われてしまいます。物事に向き合う際は想像力を働かせ、さまざまな角度から対象を捉えることを意識しましょう。
STEP2.自分の強み・能力を自覚する
自らが持っている保護因子の存在を正しく認識することも、レジリエンスを高めるうえで効果的な取り組みです。自分の強みや能力を自覚しておけば、困難に直面した際に即座に力を発揮できるようになり、心理的にも余裕が生まれます。
さらに、自らに備わっている力を自覚することは、「自分なら状況をコントロールできる」という自信(自己効力感)を得ることにもつながります。こうした自信は、能力はあっても発揮するのが不安な場面で一歩を踏み出す大きな支えとなります。
STEP3.行動目標設定/数カ月後のイメージを描く
状況や自己を的確に認識できるようになったら、次は目標や計画を立てることを習慣づけましょう。目指すゴールやそこに向けて取るべき行動が決まっていれば、安心して効率的に事態に対処することが可能となります。
具体的なビジョンがまとまらない場合には、数カ月後に自分がどのような状態になっていてほしいかをイメージすることでヒントが見つかるでしょう。また、目標に到達した後は、振り返りを行うことで次につながる発見が得られるはずです。
おわりに
先ほどご紹介した弊社の講座では、今回ご紹介した以外にもさまざまなレジリエンスの鍛え方をご紹介しています。高いレジリエンスを維持することができれば、パフォーマンスが向上するだけでなく、ワークライフバランスの改善も期待できます。従業員のメンタルヘスルケアやワークライフバランスの改善等に関心がある方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。
レジリエンスを促進させる要因についてこちらのコラムでもご案内しています。ぜひこちらもご覧ください。
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

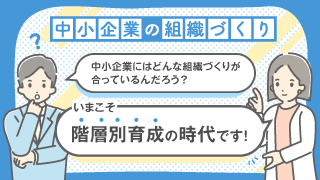














 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての