連載・コラム
職場に活かす心理学 第3回
人はどのくらい自分らしくありたいか
- 公開日:2012/12/19
- 更新日:2024/05/16

「ナンバーワンになれなくてもいいから、オンリーワンになろう」といった趣旨の歌詞が共感を呼びました。また、受験戦争が批判されて以降の日本の教育では、このような考え方が重視される傾向にありました。職場に目を転じてみると、「自分らしい仕事は何か」「仕事で自分らしさを活かしたい」といった考え方を持つ若者が増えているように思われます。自分らしさを殺してでも組織に合わせることを是としてきた年配の上司のなかには、このような考え方を苦々しく思う人もいるかもしれません。
「自分らしくありたい」と思うのは、最近の若者のトレンドなのでしょうか。心理学では「自分らしくありたい欲求」は決して特別なものではなく、私たちが持つ一般的な心理特徴として、「ユニークネスへの欲求」や「他者との差別化への欲求」といった概念を用いて研究が行われてきました。しかし、人は誰しも自分らしく、ユニークな存在でありたいと思うものだ、との主張には、手放しで同意できない人も多いのではないでしょうか。日本人は欧米の人と比べて、さほど自己主張をよしとしないからでしょうか。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
文化によって異なる自分らしさ追求の形
■日本文化においても重要な差別化の欲求
上記のような疑問について検討を行った研究があります。Beckerら(2012)40名の心理学者は、19ヶ国、22の文化圏からデータを集めて、他者との差別化を望む動機には文化差があるかを検討しました。この研究では、「他者との差別化への動機は汎文化的なものであり、この動機が満たされることは快感情を高める機能がある。ただし、差別化をどう実現するかには文化による違いがある」との仮説の検証を行いました。
下図(図表01)は、3つの差別化の形のうち、今回のテーマに関連する2つを表わしたものです。上記の研究にも参加したVignoles(2002)が提案したものです。このうち、「違い(Difference)による差別化」(左)は欧米で、「社会的位置(Social Position)による差別化」(右)は東アジアで多く見られる差別化の形であるとVignolesは考えました。「違いによる差別化」とは、能力、価値観、意見、性格特性などにおける他者との違いがある状態を指します。「社会的位置による差別化」とは、社会的ステータスや役割、友人関係といった社会的関係性における自分の位置づけによって、他者との違いを確認することです。研究の結果は、彼らの仮説を支持するものでした。さらに面白いことに、文化的に自分のユニークさが主張しにくい場合のほうが、差別化への欲求が強くなる傾向が見られたのです(図表02)。つまり、意外にも日本のほうが米国と比べて、差別化への動機を強く持つ傾向があると考えられるのです。
図表01 異なる差別化のパターン
Vignoles(2002)より一部抜粋

※違いによる差別化(Difference)では、中央の四角は形も色も周囲の丸とは異なる。
社会的位置による差別化(Social Position)では、真ん中の丸は、周囲の丸と形も色も同じだが、中心に位置をとっていることで差別化されている。
図表02 差別化への欲求の文化による違い
Vignoles(2002)より一部抜粋

※日本では、開放性の価値は比較的低く、文脈主義的信念は比較的高い。
■日本企業における差別化動機の達成方法
この研究の結果を、今の日本の働く環境に当てはめて考えてみると、いくつかの示唆が得られます。企業で働く日本人は、これまでは組織内で自分の地位を確立することによって、他者との差別化を行ってきました。これは社会的位置による差別化です。つまり、第一営業部の課長である自分は、そのポジションにあることで、周囲の人とは異なっています。
しかし、現在の日本企業ではポストの数が減少する傾向があるため、役職のほかに自分の組織内のポジションを確立させるものが必要です。ところが日本企業ではいまだに異動を伴うジェネラリストの育成を念頭に置いた人材活用が行われていて、専門性によって自分の地位を確立できる人は多くありません。社外のコミュニティなど、会社外の人間関係において自分のユニークなポジションを確認できる場があればそれでも良いでしょう。ただ、このような場も一部の人しかもっていないのが現状ではないでしょうか。
今の日本企業で働く人にとって、他の人と異なる自分の特徴や価値を確認したいといった動機を満たすことは、難しくなっているのかもしれません。日本の労働者を対象とする調査を行うと、他国と比べると専門職志向が高い傾向があるようです。管理職への昇進以外の方法で、組織内の地位を確立したいとの期待の表れと考えることができるかもしれません。
どちらも重要な所属の欲求と差別化の欲求
■所属の欲求
私たちには差別化の欲求以外に、所属や愛着といった、人と同じでいたい欲求もあります。どちらかと言えば、差別化よりも、このような人に接近する動機についての研究のほうが多く行われています。たとえば、「自己カテゴリー化理論」と呼ばれる理論では、絵の好みのようなごく些細なものでも、自分と同じ選択をした人に、より好意的な行動をとることが示されています。自分自身の評価である「自尊心」のベースも、実は成績が良いとか能力があるとかといったことではなく、自分が社会に受け入れられていることを示す指標であるとの考え方が提案され、これを支持する結果が報告されています。人の生存にとって集団への帰属が重要であることを考えれば、他者から受け入れられることを求めることは当然だと言えるでしょう。
■所属の欲求と差別化の欲求のバランスの最適化
差別化された状況であっても、周囲の人と同じところが全くないのは不安でしょうし、疎外感を感じるでしょう。結局私たちは、所属と差別化という一見相反する動機のバランスが取れた状態を目指すと考えられます。このバランスの取り方のひとつとして、Brewer(1991)は、「人は自分の所属の欲求と差別化の欲求の両方を満たせる社会的な集団への帰属を志向する」と論じています。Pickett, Silver, & Brewer(2002)が行った実験では、自分が過去に人と違っていることを実感したときのこと(差別化条件)、あるいは逆に人と同じであることを実感したときのこと(所属条件)を思い出してもらった後、自分が所属する様々な集団について、重要性や同一視する程度の評価をしてもらいました。その結果、人と同じであることを実感した経験を想起してもらった群では、差別化への動機が高まることで、年齢や国籍といった大勢の人を含む集団(社会的分類)ではなく、スポーツクラブや大学の同期生といった比較的少数の対象者しか含まず、差別化が相対的に容易な集団(課題遂行集団)を重視する傾向が高まったことが示されました(図表03)。つまり、他集団との差別化がしやすい集団に属することで、その集団への所属の欲求が満たされると同時に、その集団の一員として他の集団との差別化が図られたと解釈できます。
図表03 集団のタイプと欲求の状態が集団を重要視する程度に及ぼす影響

※コントロール群とは、何も操作しなかった群のことである。
■日本の職場における所属と差別化
この観点で見ると、日本の組織で働く人の所属と差別化の欲求はバランスよく満たされているでしょうか。差別化の欲求については、自分の勤めている会社がたとえば業界で一番である、あるいは他の会社ではできないユニークな事業を行っている、などの明確な特徴があれば問題はないと思われますが、実際のところこのような感覚は持ちにくくなっているのではないでしょうか。また差別化の欲求の実現を所属する組織に代替してもらうとすれば、Pickettらの研究にもあるように、組織規模は小さいほうが望ましいと言えます。大きな組織で働く人にとっては、自分の日々行っている仕事と、会社全体が行っている事業とのつながりを意識することは容易ではありません。ひょっとするとNPOやNGOで働くことを希望する人が増えている背景には、社会的意義の明確な集団の一員になりたいとの動機があるのかもしれません。また所属の欲求については、少なくともこれまでの日本企業では問題はなかったと思われるのですが、組織に対する信頼感やコミットメントが低下しているならば、こちらの欲求の充足も怪しくなってくるかもしれません。
ちなみにこの所属と差別化の欲求が、実は人が様々な集団や文化を形成するメカニズムの根底にあることを示唆する研究者もいます。Masら(2010)は、所属の欲求がありながら、人の集団が最終的に一つに収束しない理由として、コンピュータ・シミュレーションを使って差別化の欲求が影響を及ぼしている可能性を示しています。この結果から、ITの発達により、世界中の人々が物理的な制約を超えて自由に交流できる世の中が今以上に進んだとしても、人には差別化の欲求があるために、結局は大きな一つの集団に収束することはなく、小集団に分かれることを彼らは予測しています。所属の欲求と、差別化の欲求は人と集団の関係性を規定するものとして、かなり広範な影響をわれわれの社会に与えているのかもしれません。
日本企業の課題解決に向けた知見の適用
人が集団との関係性において見せる行動の裏には、所属と差別化の欲求という相反する欲求が存在しており、その充足バランスを一定に保つことを私たちが志向するとしたら、この知見を用いて、職場で生じている問題に対してどのような解決のヒントが見出せるでしょうか。
■自分らしい仕事を求める若手
冒頭で「自分らしい働き方」にこだわる若者が増えていることについて言及しました。仮にこのような若者が、欧米型の社会的な位置ではなく他者との違いによる差別化を意識するのであれば、欧米型のキャリアの積み方が適しているのかもしれません。欧米型の、自分の意見や価値観に合わせて組織を選択し、必要に応じて転職することは、2つの欲求を充足させる方法の一つです。自分がその組織を選択する過程で、その組織と他の組織がどのように異なるかについて明確に意識できることによって差別化の欲求が満たされます。また自分で選択した組織であるため、所属の意識も高まると考えられます。
しかし、彼らのような差別化の追求の仕方は日本文化にはなじまない可能性もあります。果たして日本企業はそれを許容することができるでしょうか。これは若者の問題に限らず、グローバル化する組織におけるマネジメントにおいても、同様の問題が考えられるでしょう。仮に違いによる差別化を組織が許容できる場合でも、今度は彼らの所属の欲求を満たすために、個人と組織が共通の価値観によって強く結びついていることを伝える工夫や、組織に受容されている感覚を高めるメッセージを伝えることが必要になります。
一方で、「自分らしい働き方」を志向する若者には、上記のような他者との違いによる自分らしさではなく、社会的な位置づけとしての自分らしさを指しているに過ぎない人もいるでしょう。それゆえ、どちらであるかを見極めた上で、対応を行うことが求められます。
■創造的な人材の活用
つぎに、創造的な人材をいかに活躍させるかについてはどうでしょうか。近年、創造的で新しいことに挑戦できる人材を求める企業が増えているようです。もし企業がそうした人材を本気で求めるのであれば、それは既存の組織の中での位置づけではなく、自分なりの価値観や意見にこだわった人材を活用することに他なりません。この場合も日本企業は、欧米型の差別化を積極的に許容していく必要があると思われます。
橋本(2011)が日本人を対象に行った研究では、協調性を重視すると言われている日本人でも、実は「自分自身の理想は、協調的であることよりも独立心が強くあることだ」と思っていることが示されています。ところがこの研究の参加者は、同時に「自分は独立心を強く持っていたいが、周囲の人はそれを望まないだろう」とも考えていました。橋本は、協調的な振る舞いを評価することが共有された信念になっている場合、われわれはその信念に従って行動するのだと論じています。そうだとすれば、創造的な人材を活用するには、組織側はそのような共有の信念を否定する方法を見つける必要があるでしょう。
■中高年の動機付け
最後に、中高年の動機付けについて考えてみます。現在、日本企業がおかれているビジネス環境の変化は、組織で働く人に様々な影響を及ぼしています。このような変化が課題として大きくのしかかっているのが、組織で働く中高年従業員であると言えます。彼らの「社会的位置による差別化」の欲求が管理職への登用という形でかなわないだけでなく、それを与えられない組織への所属意識の低下という最悪の事態を招きかねません。組織は中高年従業員にキャリアの見直しの機会を提供しようとしますが、これは他者と異なる自分、自分らしい価値や特徴を意識させるという点で、欧米型の差別化に目を向けさせる試みであると考えられます。仮にこの試みが成功した場合、創造型人材の活用の場合と同様、組織は「違いによる差別化」を供する環境を整えなければなりません。しかし、これまで「社会的位置づけによる差別化」しか考えてこなかった中高年従業員にとって、突然新しい差別化をやれと言っても、難しいこともあるでしょう。その場合は、「社会的位置による差別化」の欲求を管理職というポストの付与以外で満たす方法、たとえば、組織内でその人の存在に意味を与えるような仕事のアサインや肩書きの付与を行い、その人の役割やポジションを周囲が認めるほうが効果的かもしれません。
今回は、所属と差別化という相反する欲求のバランスについてご紹介しました。人と組織との関係性の変化によって生じる問題や、その解決策を考える際の参考になれば幸いです。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



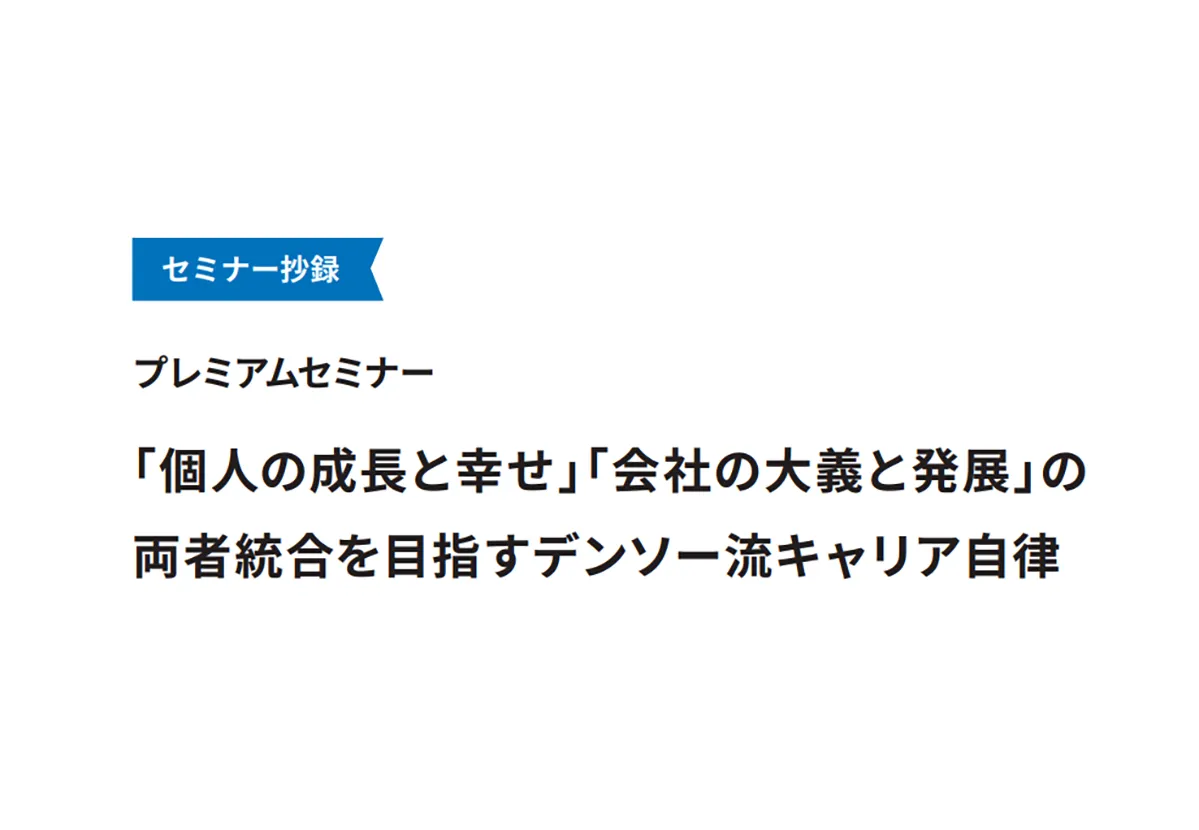









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての