連載・コラム
職場に活かす心理学 第19回
人を助け、助けられること
- 公開日:2019/03/18
- 更新日:2024/04/02

あなたは誰かに現在助けてもらっていると思っているでしょうか。それとも、誰かを助けていると思っているでしょうか。ひょっとすると意外と多くの人が前者にNoと言い、後者にYesと言うのではないでしょうか。それはなぜでしょう。またその現象は、人に助けたり助けられたりする関係性に、どのように影響するのでしょうか。
人が人に対して行う援助に関して、「ソーシャルサポート」や「対人援助」という言葉で、心理学では研究が行われてきました。ここでは研究から、どうすれば人をうまく助けたり、助けられたりできるのかについて考えてみたいと思います。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
助ける側と助けられる側のすれ違い
職場を見回してみると、対人援助がかならずしもうまくいっていないことも多いようです。例えば、隣の職場の同僚が、パワハラを受けているとのうわさを耳にします。あまり親しくないので、そんな話をするのは相手にとって失礼な気がします。仮にそうだとしても、自分にいったい何ができるでしょう。口出しをすれば、おせっかいなやつだと思われてしまいそうです。なんとなくやり過ごしているうちに、同僚は退職してしまいました。なぜ同僚を助けることができなかったのでしょうか。そのうち、なぜ同僚は、自分でなくても周囲の人に早く助けを求めなかったか、それを責めたい気持ちになってくるのです。
このような場面でのすれ違いの原因について、ボーンズとフリン(Bohns & Flynn, 2015)は感情の視点取得がうまくいかないからだとしています。援助行動ではありませんが、フリンとアダムス(Flynn & Adams,2009)は、感情の視点取得がうまくいかなかったことを示す実験を行っています。贈り物の贈り手と貰い手の感情のすれ違いに関するもので、贈り手は値段の高い贈り物の方が、貰い手に喜ばれるだろうと思っているのですが、貰い手が喜ぶ程度は贈り物の値段とは無関係であったという実験です。実験参加者は、ランダムに贈り手と貰い手に分けられ、さらに贈り物が高額の場合(iPod)と低額の場合(CD)に振り分けられます。その上で貰い手は自分が贈り物をありがたいと思う程度を、贈り手は相手が贈り物をありがたいと思う程度を予想して回答しました。結果は図表1のとおりです。さらにこの研究では、贈り手は、値段の高い贈り物は相手に対する配慮であると思うことで、受け取った相手の反応を高く見積もったことを示しました。
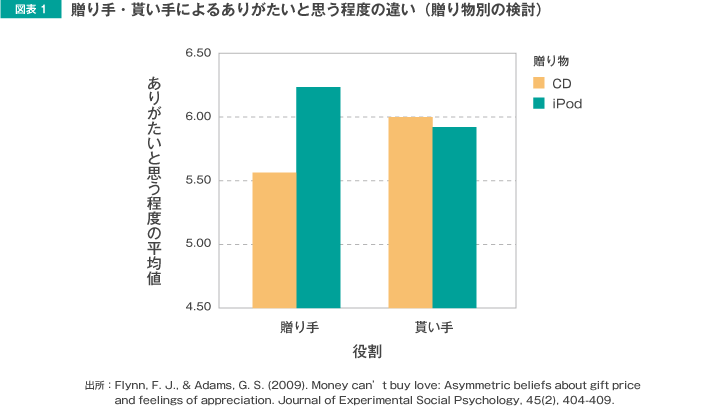
視点取得とは相手の立場に立って物事を見ることです。通常、視点取得は相手の立場を経験しているとやりやすくなります。例えば会社内で、開発担当者が営業の人と話をするときに、過去に営業経験があれば、相手がどんなことを考えているか、何を重視するかが理解できます。一方、“感情”の視点取得の場合、相手の感情を想像したり、共感することが必要になります。理解や認知とは異なり、感情はその時々の反応であるため、多くの人が助ける側と助けられる側の両方を経験しているにもかかわらず、難しいことがあるようです。
以降では、助ける側と助けられる側の感情や心理について見ていきます。
助ける側にとっての人助けの効用
最初に、自分は人を助けていると思う人の方が多いのではないかと書きましたが(機会があれば、調査してみたいと思います)、人を助けることは、一般に快の感情を伴うことが分かっています。人助けをすることは、本人にとってのある種の報酬となります。
なぜ、人助けをするとよい気分になるのでしょうか。自分には他者を助ける力があると思って、自尊心が向上するからでしょうか。それとも、人を助けることは社会的に価値のある行動であり、自分は社会的によい行いをしたのだと思うからでしょうか。
グラントとジーノ(Grant & Gino,2010)は、この問いに答えるために大学の寄付金を集める担当者を対象に実験を行いました。寄付金管理部署の代表者が来て担当者に礼を述べる群(お礼あり群)と、そうでない群(お礼なし群)を設けて、この前後で自主的に寄付金集めの電話をかけた回数をカウントしました。その結果は図表2のとおりで、お礼あり群の方が自主的に多く電話をかけたことが分かりました。ちなみに担当者の給与は固定で、電話をかけた回数とは関係がなく、自主的な電話かけは組織への支援活動と考えられます(向社会的行動)。さらにお礼あり群の電話かけの増加は、自尊心ではなく、自分の価値を認めてもらっていると思う程度によって説明されたのです。
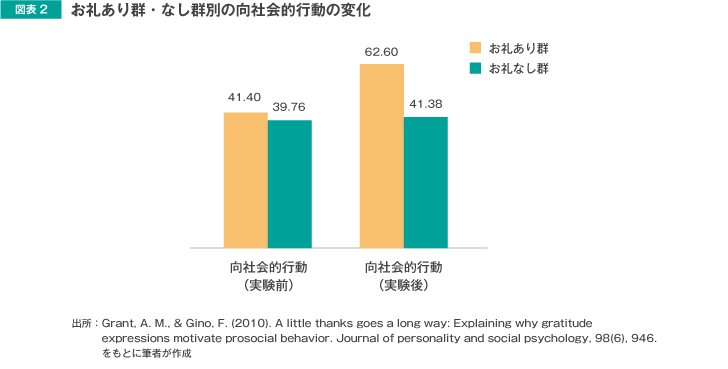
そもそも私たちは、直感的に人に協力をする傾向があるようです。これまでの多くの経験から、見返りを求めず協力をする行動を自然にとるようになっていることが示されています(Rand, D. G., & Nowak, M. A. (2013). Human cooperation. Trends in cognitive sciences, 17(8), 413-425)。もちろん支援に大きなコストがかかる場合は別でしょうが、一般に私たちは、喜んで人助けを行うのです。
職場での助け合いの難しさ
では、なぜ職場での助け合いはうまくいかないのでしょうか。
近年の自然災害をきっかけに多くの人がボランティアに参加したり、自分にできることを探して貢献しようとしています。自然災害などのボランティアでは、相手が困っていることは明らかですし、支援の申し出を断られることは少ないでしょう。被災していない人は、誰もが支援をすべき立場にあります。自分に支援をする能力があるかや、そもそも何を支援すべきか分からないということはあるかもしれませんが、それでも誰も支援しない方がよかったとは思わないでしょう。
職場の支援との大きな違いは、職場では誰が何に困っているかが見えづらく、そもそも支援が必要かどうか分からない、支援を拒否される可能性がある、あるいは必要な支援が特定されていてそれは自分には提供できない、などがあり、そういった違いが支援を難しくしていると考えられます。
助けが必要ないと思う理由には、2つのことが考えられます。1つは、仲間はずれなどの社会的に望ましくない状況に置かれたときに、それに直面する人の心理的苦痛を私たちは軽く見積もる傾向があることです。もう1つは、困っていれば助けを求めてくるはずだと考えてしまうことです。
前者に関しては、ノードグレンら(Nordgren, Banas, & MacDonald,2011)が、オンラインのゲームで仲間はずれにあう実験を用いて、それを観察していた第三者は、仲間はずれにあった当人が感じた心理的痛みのレベルを、本人よりも低く見積もったことを示しました。後者では、ボーンズとフリン(Bohns & Flynn,2010)が、学生の学業やそれ以外の悩みについて学生アドバイザーが支援を行うプログラムを題材とした実験を行いました。学生の利用が少ないプログラムについて、助けを求める側である“学生”の立場で考えると、利用するのに遠慮があるからだとして、プログラムにリソースを使うことを勧めたのに対して、助ける側である“学生アドバイザー”の立場で考えると、必要ないから、リソースを投入しない方がよいという意見になったのです。
助けてほしい場合には、相手が察してくれることはあまり期待できないため、そう主張した方がよいし、助ける側はいってこないからといって助けを必要としていないわけではないことを、認識することが必要でしょう。
なぜ助けてほしいと言えないのか
助けを求めない理由には、相手に迷惑をかけたくない、断られたくない、自分のプライドが傷つく、などが考えられます。相手に迷惑かどうかは、相手との関係性にもよりますし、頼む内容にもよるので一概にはいえません。しかし、助けを必要としている人は断られる可能性を必要以上に大きく見積もる傾向があるようです。
フリンとレイク(Flynn & Lake,2008)は、大学のキャンパスを使って、通りすがりの学生にさまざまな依頼をする実験をしました。依頼をするのも学生ですが、彼らは事前に、依頼を聞いてもらうまでに何名くらいに頼む必要があると思うかを予測します。依頼内容は、アンケートへの回答、携帯を使わせてもらう、場所を尋ねる、といったものでした。内容にかかわらず、当初予測したよりも少ない数で、実際は依頼に応じてくれたことが分かりました(図表3)。人は頼まれると断りにくいのですが、その程度を低く見積もっていたことが理由だと考えられています。
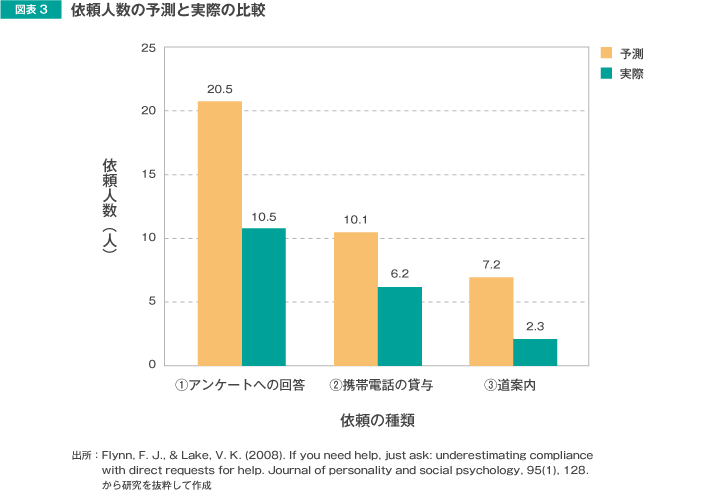
それでは無邪気に頼めばよいかというと、そうでもなさそうです。一度依頼を断られると、次の頼みごとをするのが極端に難しくなることも研究で示されています。思ったよりも他者は依頼を受け入れてくれるのかもしれませんが、それでも断られたくないのが、本音でしょう。
助けを求めない理由には、プライドが傷つくからや、面子が損なわれるからといったこともあります。職場での支援を求める場合には、この点が問題になることも多いように思います。ところが、人はやってしまったことではなくてやらなかったことを強く後悔する傾向が、特に長期的な視点で見ると、あるようです。「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」ということわざがあるように、断られるリスクを恐れず、相談をするところから始めることがよいのかもしれません。
インビジブル・サポート(Invisible support)の効用
サポート研究のなかで、最近注目されているのがインビジブル・サポートです。困ったときにサポートが得られると思うことは、概ねよい結果につながるのですが、実際にサポートを受け、さらにその事実を認識することは、必ずしもよい結果にならないことが分かっています。これは上記のプライドが傷つくことの懸念を考えれば、納得がいくのではないでしょうか。
ハウランドとシンプソン(Howland & Simpson,2010)は、カップル同士の支援行動を用いて、インビジブル・サポートが自己効力感(自分にさまざまなことをうまく行う力があるとの認知)に及ぼす影響を見ています。最も自己効力感が高まったのは、本人は多くのサポートを得たと思っていない(サポート受領の認識が低い)けれども、観察者の評定でインビジブル・サポートを多く受けた人であったことが分かりました。同程度に多くのインビジブル・サポートを受けていたとの観察がなされた場合も、本人が多くのサポートを受けたとの認識がある(サポート受領の認識が高い)場合には、自己効力感の高まりはさほどありませんでした。一方で、そもそもインビジブル・サポートが少なかった場合には、本人がサポートを受けたとの認識があっても、あまり自己効力感は高まりませんでした(図表4)。
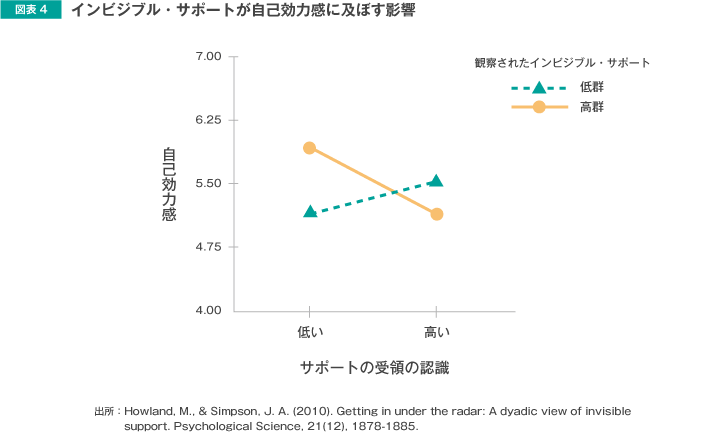
上記の実験は自己効力感が用いられていますが、そもそも自尊心(自己の評価)が低い人は、他者からの支援を受け入れにくいことが分かっています。うまくインビジブル・サポートを提供することが必要です。
ちなみに、インビジブル・サポートは、助けてもらう側にとっては望ましいのですが、助ける側への見返りが少なくなってしまいます。人助けをすることは、助ける側にもよいことがあると述べましたが、やはり相手からの感謝があることはモチベーションとして大きいと思われます。
日本企業の管理職は、既に部下に対してインビジブル・サポートを行っている人もいると思います。そのときは部下がサポートに気づかないとしても、そのうち少しは感謝してもらえることを、期待できるでしょうか。感情の視点取得は難しいのですが、部下が将来管理職になれば、過去の上司からのサポートに気づくかもしれません。しかし今後は、管理職にならない人も多いと思われます。
上司・部下間にかかわらず、職場の助け合いをうまく機能させるためには、インビジブル・サポートを提供しながらも、助ける側のモチベーションの維持が重要です。例えば、助けられた本人が気づかないとしても、周囲で見ていた人がそのサポートを認知して、助けた人を評価したり、その人へのポジティブなフィードバックを提供することは効果的かもしれません。職場は多様化し、皆が同じ立場を経験することがますます少なくなることが予想されるため、今後、意識しておく価値のある課題であると思います。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



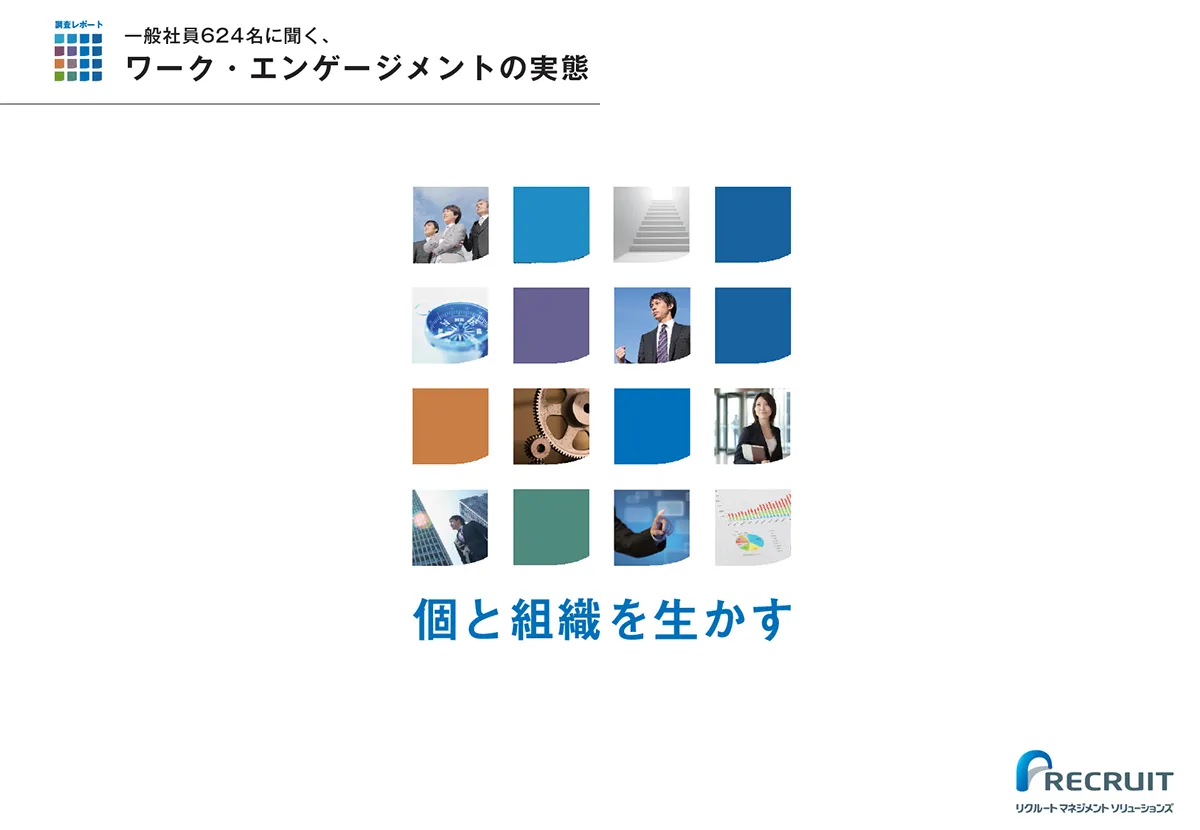
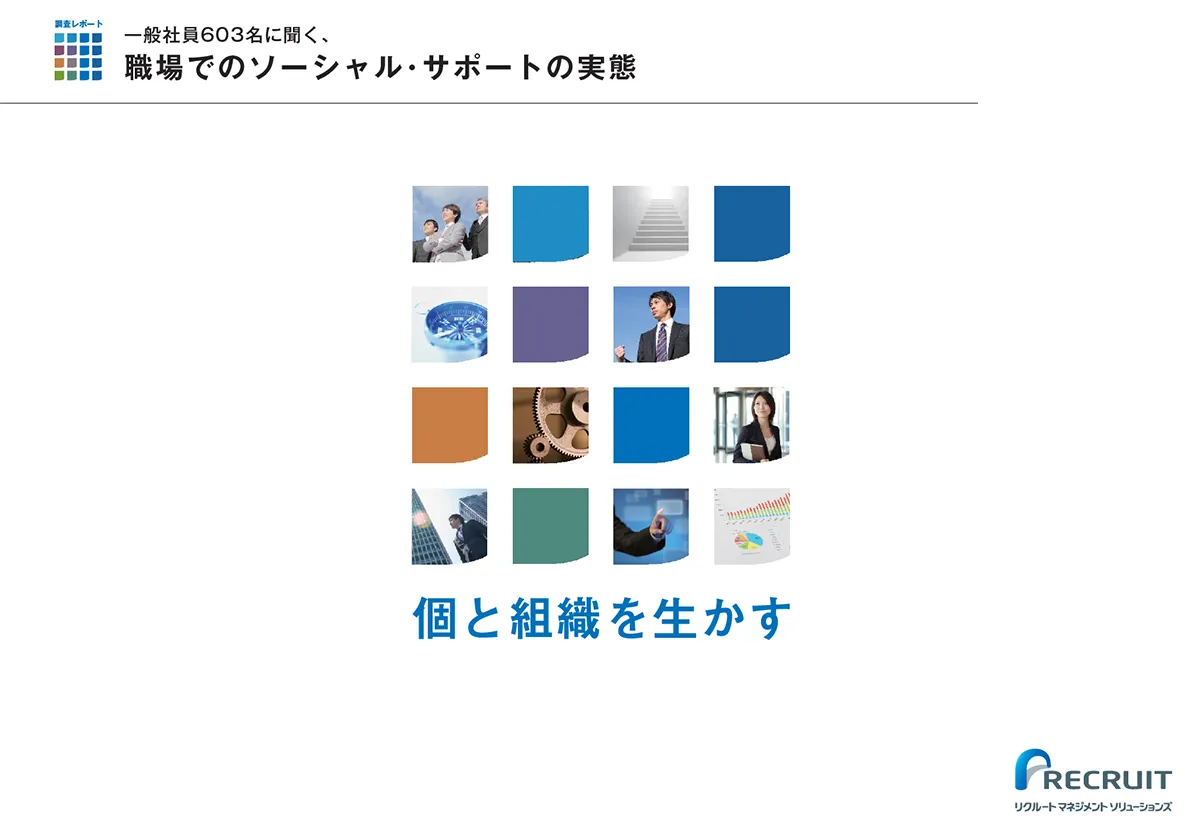









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての