連載・コラム
職場に活かす心理学 第2回
なぜ人は変われないのか?
- 公開日:2012/08/29
- 更新日:2024/05/28

私たちは、自分を変えたいと思う瞬間を経験することがあります。例えば健康のためにもう少し体重を減らしたいとか、もっと人に積極的に話しかけられるようになりたい、といったことです。ところが、実際に変えることをそもそも試さなかったり、試みが失敗に終わった経験をもつ人も多いのではないでしょうか。今回は、なぜ人は変われないのか?といったテーマについて考えてみたいと思います。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
はじめに
行動の変化について、例えば図表01の5段階からなるモデルが提案されています(Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992)。これに沿って、変化のためのどのようなチャレンジが存在するかについて、以下に述べていきます。私たちが変わりたいと思って変われないことを不思議に思うのは、私たちの中には自分の意思で行動をしているはずだとの前提があるからです。「あなたは自分の意思で日々の行動を行っていますか」と尋ねられれば、多くの大人は「そうです」と答えるでしょう。たとえ指示された仕事であっても、自分で「やろう」と思うからこそ、その指示に従うのですから。
一方で心理学の研究の中では、実際に行動を起こす際には、日々の行動の非常に多くの部分を無意識に行っていることが知られています(Bargh & Morsella, 2008)。例えば朝起きてからオフィスに着くまでの行動の多くは習慣化されているため、意識されず行われることが多いのです。変えたい行動が意識的なものである場合と、習慣化されたものである場合では、特に重要となるポイントが異なる可能性があります。そこでまず習慣化された行動、次に意識的な行動について考えてみたいと思います。
図表01 行動変容モデル
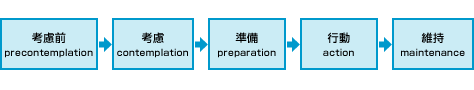
出所:Prochaska, DiClemente, & Norcross (1992)をもとに作成
JO Prochaska, CC DiClemente, & JC Norcross (1992). In search of how people change; Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102-1114.
習慣化された行動の変化
習慣化された行動を変えることの難しさに関しては、主に医療分野や健康管理の分野で研究が行われてきました。生活習慣を変える、アルコール依存症の治療を行う、体重を減らす、といった本人の健康のために行動を変える試みです。このような場合、本人にも行動を変えたいという強い希望があることが多いのですが、残念ながらいつも成功するとは限りません。つまり、「考慮」までは終了しているのに、「準備」あるいは「行動」のステップへと進めないのです。
これについて、Loewenstein(1996)は行動の変化によって生じる感情の影響に着目しました。特に行動を変化させた際に生じるネガティブな感情の影響は大きく、その感情から逃れることを妨げるような、いかなる行動も選択されなくなります。例えば悲しみや、憤りを紛らわせるためにアルコールを摂取することがあります。たとえそれが明日の重要な会議に差し支えるとわかっていても、あるいは、肝臓が悪いからと医者に飲酒を控えるように言われていても、そのときの感情が強いと、お酒を飲むことを選択するかもしれません。強い感情によって、合理的な判断が阻害されることは恐怖症の例によく見られます。高所恐怖症の人にとって、高いところにあがることは合理的に危険ではないことはわかるのですが、恐怖の感情が喚起されるため行うことができません。ここまで特徴的な例でなくても、過去の何らかの経験によって強い感情と結びついた行動をとることは難しくなります。例えば最初についた上司からしばしば激しく叱責された経験をもつ人は、上司に何かを相談することに抵抗を感じるようになるかもしれません。
習慣化した行動を変えることが難しいもう一つの理由は、行動が意識せずに行われるという点にあります。習慣化は、特定の行動をある条件下で繰り返し行った結果、その条件に直面すると意図せずに行われるようになることを指します。例えば、寝る前に歯を磨く習慣は、「寝る前の時間」が条件になります。もう少し細かい癖のようなもの、部下から声をかけられるといつでも「なんだ?」と無愛想な返答をしてしまう、なども含まれます。習慣化された行動は無意識に行われるため変えることが難しいのですが、それを引き起こす条件が生じないように、新しい環境に移ってしまえば変えることが可能です。下図は、Wood, Tam, & Guerrero Witt(2005)が行った研究の結果です。大学を変わった際に、運動をする、新聞を読むなどの習慣が、どのような場合に変化したかを検討した結果です。特に行動が強く習慣化されていた場合は、環境が変われば、自分がその行動をとる意図がないと、その行動をやめてしまうことが示されました。
図表02 環境変化と本人の意図が運動・新聞を読むことの頻度に及ぼす影響
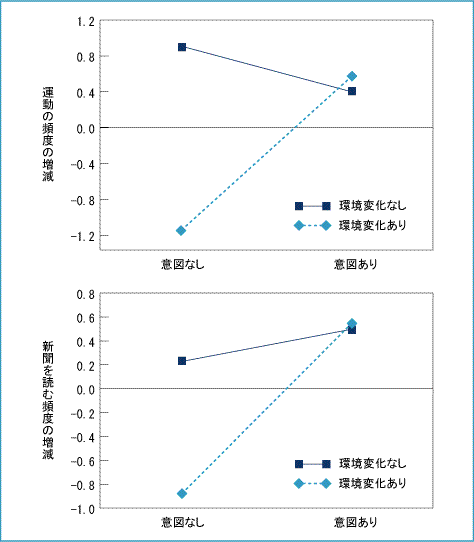
出所:DT Neal, W Wood, & JM Quinn (2006)をもとに作成
A repeat performance. Current Directions in Psychological Science, 15, 198-202.
一般に習慣化した行動を変えるためには、環境を変えることが最も効果的だということになります。ただし、環境を変えることが難しいことも現実にはあるでしょう。その場合は、行動のきっかけになっている条件が何かを特定して、それと行動の結びつきを意識的に絶つ必要があります。前述した上司の例であれば、声をかけられたら「○○さんか」と相手の名前を必ず呼ぶようにする、といったことになります。「無愛想に返事をしない」ではなく、なるべく具体的な行動を決めることが重要です。
それでも無意識にやってしまっていることなので、なかなか継続して行うのは大変です。また、その行動を変えようとすると強い不安やストレスを生じるような場合や、行動を起こすための条件が複雑な場合は、さらに継続は困難になります。
意図的な行動の変化
社会心理学の分野では、伝統的に意図して行う行動についての研究のほうが盛んに行われてきました。こちらでも、意図したことと実際の行動の関連の低さが問題点として指摘されてきました。これまで意図と行動の乖離を説明するモデルがいくつか提案されてきましたが、その中でよく用いられるのが、Ajzenによって提案された「Theory of Planned Behavior(計画的行動理論)」と呼ばれるものです(図表03)。
図表03 Theory of Planned Behavior(計画的行動理論)
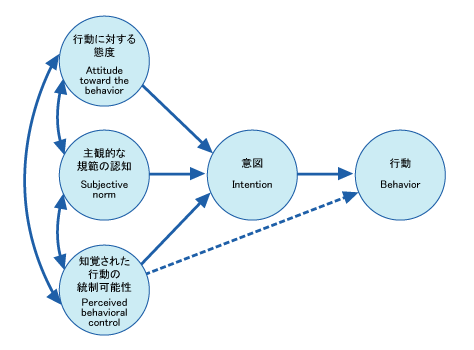
出所:I Ajzen (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
習慣化された行動とは異なり、こちらは「考慮」のステップが重要になります。図表03のモデルの「行動に対する態度」「主観的な規範の認知」「知覚された行動の統制可能性」から「意図」にいたる部分に該当します。つまり、行動するかどうかは、単にその行動が良いと思うか(態度)だけではなく、その行動が社会的な常識に反していないか(規範)、自分はその行動を実行できる力があるか(統制可能性)といったことを考慮した上で、決定されます。例えば、電車の中で携帯電話をかけることについて、仕事の連絡で急を要するので仕方がない(態度)と思いつつも、周囲の人はそれを許さないだろうと感じ(規範)、自分は周囲の目を気にせず電話をするだけの度胸はないと思い(統制可能性)、結局電話をかけなかった、といった例が考えられます。
結局、新規の行動であったり、行動を起こす状況が不確実であったり、行動の結果いくつかの利益が葛藤を起こす可能性があったりするため、行動を起こす意思決定が必要になるのです。行動の変化の場合、自分の行動を変えるのは良いことだと思っていても、周囲がそれをどう思うかが不安だったり、行動を変える自信がなければ、変化しようという意思はもてません。行動経済学の知見からは、人は現在生じる結果を、将来生じるであろう結果と比べて不当に大きく見積もる傾向があることがわかっています。将来的にはメリットがあるが、今行動を変えることで“今”周囲の人はどう思うかということや、失敗した“直後の”ダメージを考えると、なかなか変えることに踏み切れないことになります。いわゆる「先延ばし行動」が生じるのです。
もう一つAjzenのモデルが特徴的なのは、「知覚された行動の統制可能性」は、行動の意思決定後も行動を行うかに影響すると考えられていることです(図中の点線部分)。これはいざ意思決定をしたものの、その場になるとやはり自信がなくてやめてしまう場合などがあげられます。Webb & Sheeran(2006)は行動を変えようという意図が実際にどの程度行動の変化をもたらすかを実験した47の研究をまとめて分析を行った結果、実験の操作によって、変わろうとする意思はかなり強くもつようになったものの、実際に行動が変化したのはそのうちの一部に限られていたことを報告しています。特に、Ajzenのモデルが予測するように、行動の統制可能性を低く見ている場合に実際の行動を起こさない傾向が強まることを示しました。行動の変化を起こすことを目的とした介入(例えば研修など)では、本人が「自分はやれる」と信じるようにすることが、成果をあげるひとつのキーポイントであると考えられます。
変化後の行動の維持
変化を起こすことと同様、あるいはそれ以上に変化を維持することは難しいものです。変化を起こすことと変化を維持することは、図表01でも異なるステップに置かれているのですが、変化の維持に関してはあまり研究が進んでいません。健康心理学の研究者であるRothman(2000)はこの点を指摘し、いくつかのアイデアを提供しています。彼は、行動を起こすかどうかは、結果がもたらす利益への期待によるが、行動を継続するかどうかは、行動の結果が満足のいくものであるかどうかによると論じています。例えば、ダイエットのプログラムの参加者で、当初の期待が高すぎる(例えば、30kgの減量)人ほど失敗してしまうとの研究結果を紹介しています。
Ajzenのモデルが行動の維持にもあてはまると考えると、新しい行動を起こすことで良い結果が得られた場合、すなわち結果に満足した場合、その行動に対する態度はよりよくなるかもしれませんし、行動の結果周囲から恐れていたような反応は起きなかったことを見て、規範の判断が変化するかもしれません。何よりも行動することで満足する結果が得られたことで、行動の統制可能性の認知は高まることが予想されます。
行動の維持に関してはこれからの研究が期待されますが、行動の直後にあまり高い期待をしないようにする一方で、自分の行動が、小さくとも効果があったことを実感させるような取り組みを用いることで、維持のサイクルを促進させることが期待できるのではないでしょうか。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



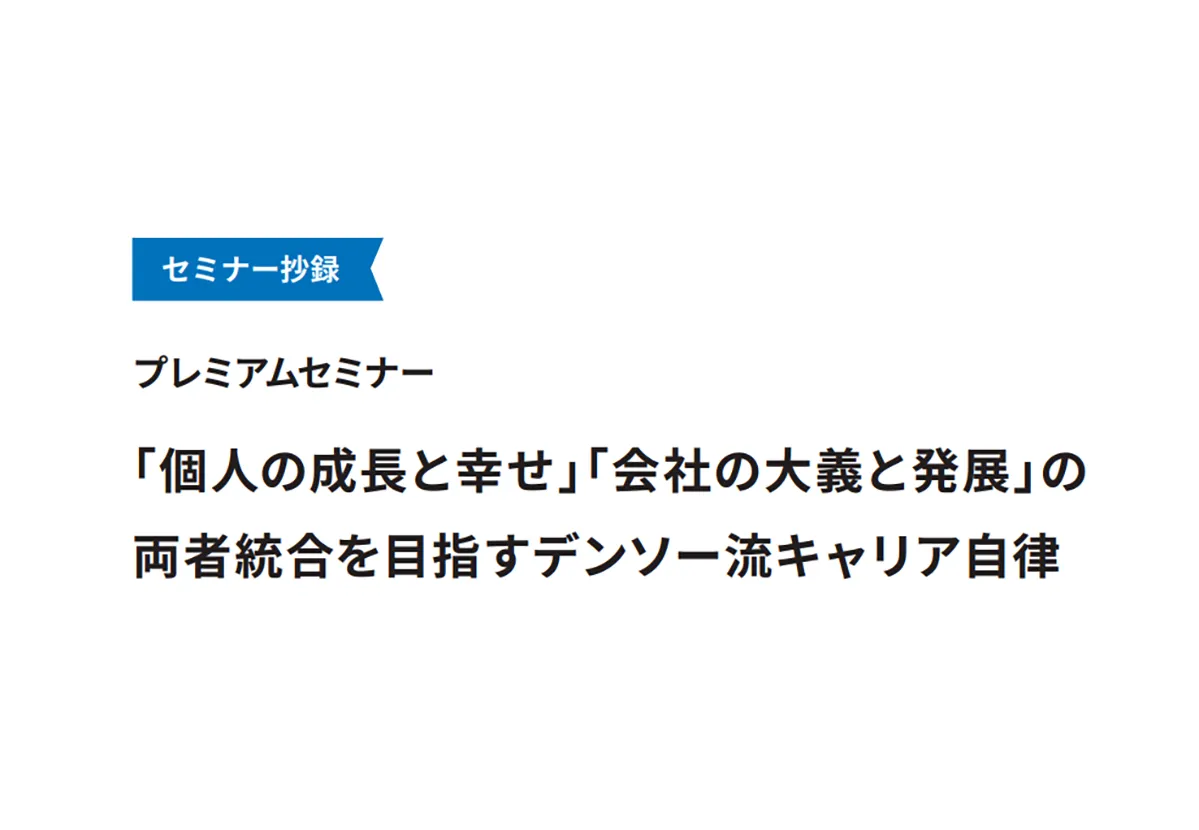









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての