- 公開日:2012/04/25
- 更新日:2024/05/16

2023年1月20日更新
このコーナーでは、人事や職場の課題解決のヒントとなる心理学の知見やモデルをお伝えすることを目的としています。今回は、仕事と幸福感の関係性について考えてみます。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
はじめに
先日、ブータン国王夫妻の来日に伴って、国民総生産(GNP)に替わる国民総幸福量 (GNH) という概念が紹介され、大きな注目を浴びました。日本国内でも、国の幸福度を表す指標を策定する試みが行われています。幸福でありたいと思うことは、誰にとっても至極当然のことです。幸福の問題は経済学や、哲学、政治学など、様々な学問領域で取りあげられていて、もちろん心理学もその一つです。
ここでは、幸福感という言葉を用いて話を進めます。幸福感という言葉は私たちが一般に使う言葉です。様々なニュアンスを含みますが、大きく分けると、心地よいとか満ち足りているという「穏やかな感覚」と、より望ましいことや良いことを行っているという「達成感」に当たる感覚に分かれるとされています。これ以降、紹介する研究では、主として「あなたはどの程度幸福ですか?」といった直接的な質問で幸福感の評定を行った結果を用いています。したがって上記の2つの幸福感が混在したものであることに配慮する必要があります。
幸福であり続けるために何が必要か
■幸福感の50%程度は遺伝によって決まる
これまでの研究では、「どのような特徴を持った人がより幸福であると感じているか」を明らかにする研究が主として行われてきました。たとえば、「裕福な人のほうが幸福か?」「楽観的な人のほうが幸福か?」といった質問です。一方で、「どうすればより幸福になれるのか」についての研究は、意外なことですがあまり行われていません。仮に裕福な人がそうでない人よりも幸福であるならば、今までよりも給料の高い仕事につけば、あるいは昇給すれば、幸福感は上がるでしょう。しかしこの幸福感がどの程度持続するか、この後さらに幸福感を高めるためには何が必要かといった疑問については、検討が十分に行われてきませんでした。
欧米のこれまでの研究では、以下のことがわかっています。
●幸福であると感じる程度は、50%程度は遺伝によって決まる
●時によって、幸福を感じる程度は上下するものの、早晩自分がもともと持っている平均的なレベルの幸福感に収まる
つまり、もともと幸福感を感じやすい人とそうではない人がいて、幸福だと感じやすい人は、時に不幸だと感じることはあっても幸福感を取り戻しやすく、幸福だと感じにくい人は、一時幸福感を感じてもまたそう思わなくなるということです。そう考えると、幸福になりたいと考えるのは、無駄な努力なのでしょうか。そうではありません。幸福感の変動がなぜ起こるのかは十分に明らかになっているわけではありませんが、幸福感は確かに変動するからです
■「環境」と「意図した活動」の変化が幸福感を変動させる
そこでLyubomirsky, Sheldon, & Schkade(2005)は、より幸福になるためには、また幸福であり続けるためには何が必要なのかという疑問をもって研究を始めました。彼らは、幸福感が変動するきっかけとして「環境」の変化と、「意図した活動」の変化を挙げています。彼らの考える幸福の規定因とその説明力は図表01の通りです。
「遺伝」と「環境」の要因が影響する割合は、先行研究から明らかになったものです。「遺伝」が半分の説明力を持ち、その人の幸福感の平均値を決めています。「環境」の要因については、世界価値観調査をはじめとする大規模な調査において、健康状態、収入、宗教などと幸福感の関連が検討されてきましたが、実は関連はさほど強いものではなく、10%ほどの説明力しか持ちません。そこで彼らが着目したのが、残り40%を説明する可能性がある要因であり、それを「意図した活動」であると考えたのです。なぜ「意図した活動」を取り上げたかについては、これまでの幸福感に関わる研究において、特に心理学では人がなんらかの活動を起こしたことでより幸福感を感じることが示されていたからです。
図表01 Sustainable Happiness Model (持続的な幸福モデル)
.gif)
出所:Sheldon, Boehm, & Lyubomirsky (2009)
「環境」の変化は、たとえば宝くじに当たったとか、昇給したといったことですが、「意図した活動」は実際に行った行動の他に、思考や選択などの幅広い活動を含みます。例えば、留学のための勉強を始めること、健康のために食べるものに気を付けること、今日一日を振り返って自分が恵まれていることに感謝することなどです。
Lyubomirskyらは、この2つの効果の最大の違いとして、「環境」の変化による幸福感の上昇にはすぐ慣れてしまい効果が持続しないのに対して、「意図した活動」の変化に伴う効果は長続きすることであると考えました。宝くじに当たっても幸福感を感じるのは最初だけで、すぐにお金がたくさんある状態に慣れてしまいます。これに対して「意図した活動」の変化では、自らの意志によって特定の活動を継続することで、あるいは様々な活動に取り組むことでその状態に慣れることなく、幸福感を上げる効果が持続すると考えたのです。例えば次のような研究を行い、この主張を支持する結果を得ています。
図表02 変化のきっかけと幸福感の上昇効果の持続との関係

研究では、大学生の同じ対象者に1セメスター(学期)に3回繰り返して調査を実施しました。毎回、その時の幸福感を評定するほかに、1回目の調査から2回目の調査までの間に起こった「環境」の変化と「活動」の変化の程度を尋ねました。図表03はこの追跡調査の分析結果です。特にポジティブな「活動」の変化があった人は、3回目の調査時にも幸福感が高かったのに対して、特にポジティブな「環境」の変化があった人は、2回目の調査時には幸福感が高まったものの3回目の調査時にはその効果は消えていました。
図表03 活動と環境の変化による幸福感の推移の違い

出所:Sheldon & Lyubomirsky (2006)
■自らが意図した活動による幸福感はなぜ持続するのか
それではなぜ、自らが起こした活動による幸福感は持続するのでしょうか。Lyubomirskyらは、それが意図することで可能になるため、活動の選択肢が広がったり、意識して持続することで、その状態への慣れを抑える効果があるからと説明しています。例えば環境の変化がきっかけであったとしても、新たな環境について日々恵まれているとの思いを持つといった活動を行うことで、幸福感は持続すると考えられます。
上記の説明はもちろん誤りではないのでしょうが、それに加えて「意図した活動」が自分の存在の意味や価値を確かめることに役立つことの影響も大きいようです。経済学者であるLoewenstein(1999)は、登山家は大変な思いをしつつ山に登り続けますが、そうすることで自己が存在することの感覚を高めるとしています。そしてその活動の根底には、人々が自分の活動に意味を見出そうとする動機があると述べています。登山家は、山に登ることに自分自身の存在価値や生きる意味を見出しています。そしてひとつの山を征服した後は、別の山を目指します。そして彼らはそのような人生に幸福感を感じるのです。
ここで重要なことは、その活動には自分自身が行う意味がある、自分の存在には価値があると思えることではないでしょうか。日本を含むアジアの国々では、西洋に比べると自分の意思で活動することに高い価値が置かれているわけではありません。しかし、上記のように考えれば、誰かのために行動することも、それを自分が行うことに意味があると思えば、幸福感を高める効果が期待できるのです。
自分の存在価値の重要性は、実は幸福感を上げるだけでなく、不幸な状況に対する耐性を論じる際にもあてはまります。精神科医であり、ナチスの収容所に収監されたフランクルはその時の経験をつづった『夜と霧』という本の中で、限りなくストレスの高い苛酷な状況の中で、「自分が生きていることには意味があるのだ」と思えることが先への希望をもたらし、それによって生き延びることが可能であったと述べています。自分の存在意義や価値を置く活動に従事することによって、単に多様な活動を行うことで幸福を感じるよりも安定的に幸福感を高めることが可能であるように思われます。
ここまでの話は一般的な幸福感のことですが、仕事での幸福感はどうでしょう。仕事のみが人々の幸福の源泉である必要はありませんが、私たちが人生の約3分の1を仕事に費やすことを考えれば、仕事が幸福感を高めることは望ましいことでしょう。次に、ハッピーに仕事をし続けるためには何が必要かについて、考えてみたいと思います。
仕事と幸福感
■自ら意図して仕事に取り組む
個人の側から見れば、仕事で幸福であることは人生の幸福感を高めます。一方で、組織の側にとっても実は従業員が幸福であることは重要です。成功を収めている人が幸福感が高いのはもちろんですが、これまでの研究から、幸福感が高い人ほどパフォーマンスが上がったり仕事で成功することも示されているからです。
一般的な幸福感の議論の延長線上で仕事の幸福感を考えるならば、仕事で自ら意図して活動することが継続して行われること、さらにその活動に意味があると思えるときに、仕事での幸福感を高めることができます。昇給や昇格は、それ自体のありがたみは長続きしません。しかしその結果、自分が行う仕事がより意義あるものになると思い、さらに自分がより主体的に活動するチャンスを与えられるならば、幸福感は持続するでしょう。自分が選択した行動を行うことは、より自分の存在を際立たせるからです。逆に昇給がなくとも、上記の条件が満たされれば、幸福感高く仕事に取り組めると考えられます。
Semmerら(2010)の研究でも、仕事はその人を定義する一側面であるために、自分の行うべき仕事の範囲を逸脱した仕事や、行う必要がないと思われる仕事を行わせることは、怒りや組織における反社会的な行動を引き起こすことが示されています。これも、意味のある仕事を行っていないと感じることから生じる望ましくない結末であると言えます。
上記のことが正しいとすれば、マネジメントが重視すべき命題は、
「どうすれば、メンバーが担当する仕事の意義を受け入れ、自らの意思でその仕事に取り組むようになるか」
になります。メンバーが自分の意思で行う仕事の内容を選択、決定できればそれに越したことはありません。自分で選択することで自分の仕事であるとの意識が高まりますし、自分で選んだものは自分にとってなんらかの意味や価値があるからです。ただし「君にやってもらえる仕事はA、B、Cのいずれかだがどれが良いか」ではあまり効果が期待できません。選択肢が限定されたと思った段階で、それは自分の選択にはならないからです。あくまで、本人が自分の選択であり、意思であると感じることが必要になります。
■仕事に意義を見出すことが幸福感につながる
しかし実際のところ、たとえ本人が自分の仕事であると思えない仕事でもやらなくてはならないことも珍しいことではありません。この場合、仕事を行うことの意味は仕事そのものには見出しにくくなります。ただし、仕事を行った結果としてその先にあるものに意味を見出すことは可能です。先にあるものが組織への貢献だとすると、少なくとも本人に組織へ貢献したいという主体的な意図がなくてはなりません。また組織はその貢献に感謝していることを何らかの形でしばしば示す必要があります。先にあるものが、任された仕事を成功裡に終了した先にある、他の仕事へのアサインや昇進である場合、当該の仕事に長期間従事させることは難しくなります。
つまり自分の意思によって活動していると思えるような仕事の任せ方やコミュニケーションのあり方が重要であり、特に仕事そのものに意義を見出しにくい場合は、加えて意義を伝えるための努力が必要ということになります。
以上の議論は、あくまでも一般の幸福感に関する研究結果に基づく類推にすぎません。このような状況を実現する具体的な方法として、上司と部下のコミュニケーション、仕事の任せ方、評価制度などが考えられますが、その結果、本当に従業員の幸福感が高まるかどうかは今後の検証が必要です。しかし、組織と従業員の両方にとって望ましい状態が実現できるのであれば、挑戦する価値のある課題だと言えるでしょう。
関連するコースのご紹介
「幸福」とはなにか――その定義や価値観は人それぞれですが、科学的アプローチによって「幸せの因子」を特定した学問があります。それが「幸福学」です。 本コースでは仕事の創造性・生産性に大きな影響を与えるといわれている幸福感を高めるポイントについて、幸福学の研究成果を元にお伝えします。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



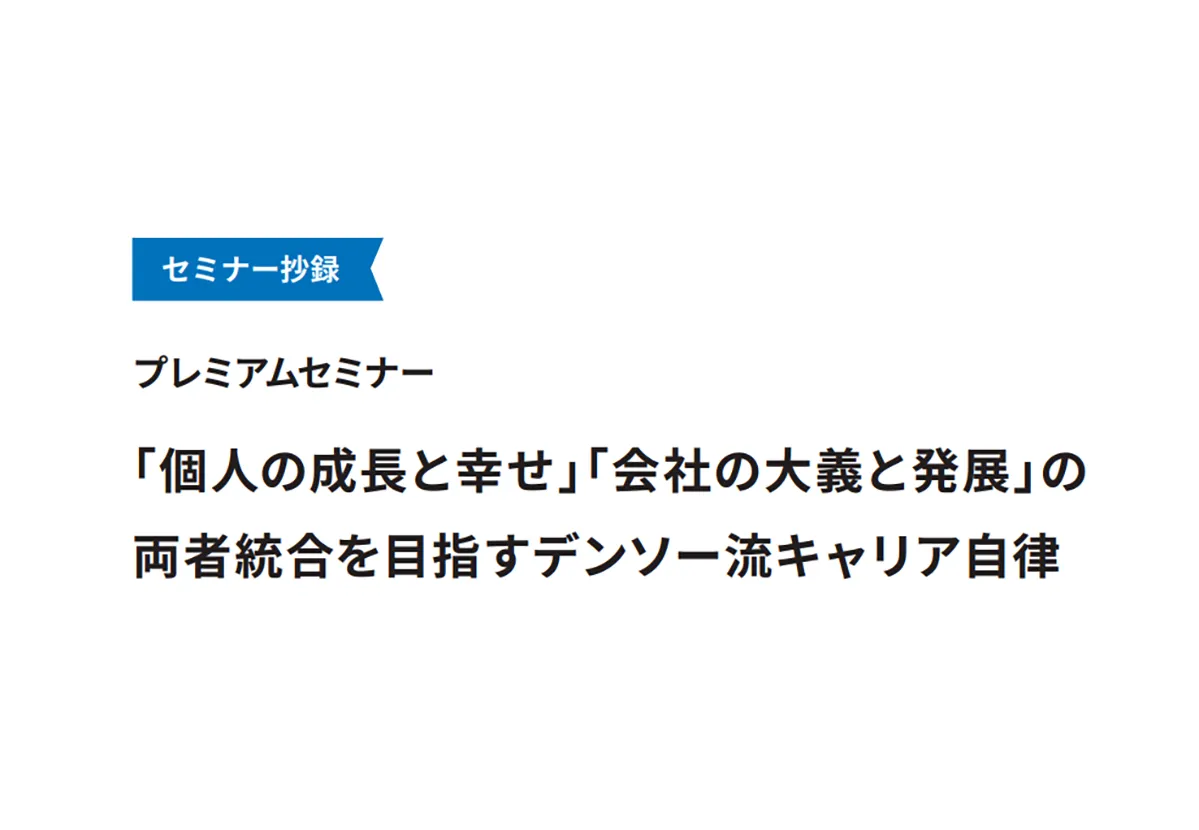









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての