用語集
人的資本の情報開示とは? 義務化の背景や項目、企業別の対応方法を解説
- 公開日:2023/11/02
- 更新日:2026/01/23
人的資本とは、知識やスキル、経験などをもって生産力や経済活動に価値をもたらす「人」を、「資本」とみなす考え方です。従来の「モノ」や「カネ」など、有形資産が企業価値を構成するという認識とは異なり、近年は人材など無形資産こそが企業価値を高めると考えられています。
人的資本の情報開示とは、企業の人的資本の情報を社内外に公表することで、日本では2023年3月期決算より、有価証券報告書を発行している大手企業約4000社を対象に義務化されました。
有価証券報告書における人的資本情報開示状況を見る
【特集】自社らしさを生かした人的資本経営を再考する

- 目次
- 人的資本開示とは?
- 人的資本の情報開示が求められている背景
- 人的資本の情報開示の義務化はいつから?
- 人的資本開示の知っておきたいトピック
- 人的資本の情報開示が義務化される対象企業
- 情報開示が望ましいとされる7分野19項目
- 人的資本の情報開示への対応方法
- 人的資本開示に取り組む企業事例
- まとめ
人的資本開示とは?
人的資本とは、知識やスキル、経験などをもって生産力や経済活動に価値をもたらす「人」を、「資本」とみなす考え方です。
人的資本開示とは、企業が有する人的資本の情報を社内外に公表することを指します。人的資本の情報をオープンにすることで、自社の透明性や信頼性を高められることが情報開示のメリットです。
人的資源との違い
これまでの人事領域で主流とされていた人的資源という考え方との違いは、人材育成に関するコストを企業に対する「投資」とみなす点です。
人的資源の考え方では、人とは企業にとっての「資源」であり、人材の確保や育成にかかる費用などは抑えるべきコスト(消費)とみなされていました。一方、昨今主流になりつつある人的資本では、人材を利益や価値を生み出す資本と捉えます。「人が育てば企業も育つ」という観点から、人材育成を積極的に行う企業も増えているといえるでしょう。
人的資本の情報開示が求められている背景

人的資本の情報開示が求められている背景には、いったい何があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
人的資本の価値への関心の高まり
今や社会のさまざまな分野で、ICT(情報通信技術)の利活用が促進されています。IoTやAI技術、ロボットなどが生活の一部になりつつありますが、これらICTを活用するにも人の能力が求められます。さらなる技術革新を目指すのであれば、人材の育成は欠かせません。
また、ICT化が進む一方で、人にしかできない業務の価値が見直されています。例えば、意思決定や判断力が問われるマネジメント系や、接客業やサービス業などホスピタリティ系、新しいものを生み出すクリエイティブ系の業務です。
そのため人的資本への投資は重要で、人の能力や技術に注力することで企業の成長を目指す考え方が広まっています。無形資産である人的資本は企業価値を左右する大きな要素であり、財務資本に代わる重要な資産といえるでしょう。
欧米での人的資本の情報開示の流れ
先にも述べたように、人的資本の情報開示は世界的な潮流です。例えば、欧州連合(EU)は2014年、非財務情報開示指令において従業員500人以上の企業を対象に、「社会と従業員」を含む情報開示を義務付けました。2021年には改正案が発表され、対象企業の拡大や開示情報のさらなる具体化が示されています。
米国でも同様の動きがあり、米国証券取引委員会(SEC)は2020年、上場企業に対して人的資本の情報開示を義務化しました。欧米では、環境問題やサステナビリティへの関心が高く、ESG投資が注目されたことから人的資本の情報開示も進められています。サステナビリティとは、「Sustain(持続する、維持する)」と「Ability(能力)」を組み合わせた、日本語で「持続可能性」を意味する言葉です。
ESG投資への関心の高まり
ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字を取った造語です。企業が持続的な成長を続けるためには、この3要素に配慮した経営を行うことが必要とされています。
ESG投資とはESGの3要素を考慮した投資手法で、企業の財務面だけでなく、環境問題や社会問題に対する企業の取り組み、つまり社会的なリターンにも着目します。ESG投資への関心が高まるにつれて、判断材料の1つとして企業の非財務情報が重視されるようになりました。人的資本の情報開示が求められると同時に、「ESG」の考え方に則って人的資本の価値を向上させようという動きも高まっています。
有価証券報告書への記載が義務化された
日本では、2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正されました。この改正により、人的資本の情報開示の対象となる企業は、有価証券報告書の2カ所において、人的資本情報を記載することが義務化されました。
まず、第一部【企業情報】の第1【企業の概況】にある5【従業員の状況】には、多様性に関する3指標についての記載が求められます。3指標の内容は、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女の賃金の差異」です。
第一部【企業情報】の第2【事業の状況】には、2【サステナビリティに関する考え方及び取組】が新設されました。このうち「ガバナンス」「リスク管理」の記載は必須とされ、「戦略」と「指標及び目標」についても人的資本や多様性に関する以下の記載が必須となっています。
- 戦略:人材の多様性の確保を含む「人材育成方針」や「社内環境整備方針」
- 指標及び目標:上記にかかわる「当該方針に関する指標の内容、当該指標を用いた目標及び実績」
参考:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について:金融庁
有価証券報告書における人的資本情報開示状況を見る
【特集】自社らしさを生かした人的資本経営を再考する
人的資本の情報開示の義務化はいつから?
改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等は、2023年3月31日以降に終了する事業年度にかかわる有価証券報告書から適用されています。これにより、対象となる企業は事業年度終了後の3カ月以内に、人的資本と多様性に関する情報を記載した有価証券報告書を提出しなければなりません。
人的資本開示の知っておきたいトピック
日本では2023年3月期の決算から人的資本開示が義務化され、国際・国内情勢の変化に合わせて制度化に向けた動きが進められてきました。人的資本開示に関する国内外のトピックを、時系列でご紹介します。
ISO 30414(2018年12月発行)
ISO30414とは、2018年12月に国際標準化機構(ISO)が発行した、人的資本開示に関するガイドラインです。企業において人材という無形資産の位置づけが高まるなかで、自社が有する人的資本を、投資家などのステークホルダーに報告するための国際指針として発表されました。
ISO30414の発行を機に欧米諸国で人的資本開示を義務付ける動きが進んだことから、日本国内においても人的資本への注目度が高まるきっかけとなったガイドラインといえるでしょう。2025年には改訂も予定されています。
人材版伊藤レポート(2020年公表)
人材版伊藤レポートとは2020年に経済産業省が発表した、人的資本経営を実現するためのアイディアや施策をまとめた報告書です。企業にとって人的資本は投資すべき経営資源であることや、持続的な企業価値の向上には経営戦略と連動した人材戦略が欠かせないこと、具体的な取り組み方の指針などがまとめられています。
国内の人的資本経営への関心をより高めることになった資料であり、2022年5月には人材版伊藤レポート2.0も公表されました。
非財務情報の開示指針研究会(2021年6月設立)
非財務情報の開示指針研究会は、経済産業省が2021年6月より定期的に開催している研究会です。リスクマネジメントやサステナビリティの取り組みなど、定量化しにくい非財務情報の開示指針を議論する場として設けられ、2023年7月までに計12回実施されました。
非財務情報可視化研究会(2022年2月設立)
非財務情報可視化研究会は、2022年2月に内閣官房が設置した研究会です。「人への投資は今後の資本主義における成長戦略であり、株主にも人的資本への投資の意義を理解してもらう必要がある。そのために、非財務的な情報の可視化(見える化)が不可欠である」という考えに基づいて、非財務情報の評価方法の指針をまとめるために開催されています。
人的資本可視化指針(2022年8月公表)
人的資本可視化指針は、前述の非財務情報可視化研究会が2022年8月に発表したガイドラインです。人的資本の可視化が必要とされる背景や、人的資本を可視化するステップを紹介しており、「株主や投資家に向けて自社の人的資本をアピールしたいが、具体的にどのような方法を取ればいいか分からない」という企業の手引きとして活用されています。
また、企業が開示した方が良い人的資本情報を、7分野19項目に分類したうえで公表しています。すべての情報を網羅的に開示する必要はありませんが、他社と比べて自社はどこが優れているのか、企業価値を高めるためにどのような取り組みをしているのかを社外にアピールできるよう、適切な項目を組み合わせて活用することが推奨されています。
人的資本の情報開示が義務化される対象企業
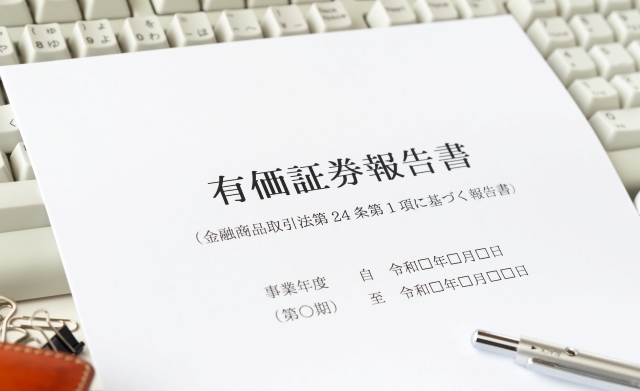
人的資本の情報開示は、金融商品取引法第24条による有価証券を発行している上場企業など約4000社が対象です。有価証券とは株式や社債を指し、原則として以下に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出義務があります。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集または売り出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券および株券にかかる権利を表示している預託証券を含む)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)、および所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く)
参考:企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要:財務省関東財務局
情報開示が望ましいとされる7分野19項目

内閣官房で開催されている非財務情報可視化研究会の「人的資本可視化指針」(※1)において、情報開示が推奨される7分野19項目が発表されています。企業はこれらのなかから自社の戦略に沿った項目を選び、情報を開示することが望ましいとされます。7分野19項目の詳細を見ていきましょう。
1. 人材育成
人材育成の分野では、「リーダーシップ」「育成」「スキル/経験」の3項目が、情報開示項目として推奨されています。
- リーダーシップ…リーダーシップの能力開発とその評価体制
- 育成…研修やキャリア開発プログラムについて
- スキル/経験…業務に必要なスキルや実務経験の向上の取り組み
開示事項の具体例として、社員研修にかけた時間や、人材開発および研修にかかるすべてのコスト、研修と人材開発の効果、スキル向上プログラムの種類や対象などがあります。
人材育成の分野は、投資家からの評価を高めるためにも非常に重要です。興味がある方は、以下の記事もご一読ください。
2. 多様性
多様性の分野では、「ダイバーシティ」「非差別」「育児休業」の3項目が、情報開示項目として推奨されています。
- ダイバーシティ…多様な人材が活躍できる職場づくりをしているか
- 非差別…職場における待遇に公平性があるか
- 育児休業…育児に関する支援制度があるかどうか
具体例としては、従業員の多様性(年齢、性別、障害など)、男女間の給料の差や正社員と非正規社員の福利厚生の差、育児休業の取得率や休業後の復帰率および定着率などです。多様性は企業価値の向上だけでなく、リスクマネジメントの観点からも重要視される分野です。
3. 健康・安全
健康・安全の分野では、「精神的健康」「身体的健康」「安全」の3項目が、情報開示項目として推奨されています。
- 精神的健康…メンタルヘルスケアに関する取り組みをしているか
- 身体的健康…健康診断など、健康を維持する制度があるか
- 安全…労働災害や安全衛生に関する制度があるか
具体例としては、労働災害の発生件数や割合、安全衛生マネジメントシステムの導入の有無、医療やヘルスケアサービスの利用をどのように促進するかの説明などです。企業による健康および安全面への配慮についての表明です。
4. 労働慣行
労働慣行の分野では、「労働慣行」のほか「児童労働/強制労働」「賃金の公正性」「福利厚生」「組合との関係」の5項目が、情報開示項目として推奨されています。
- 労働慣行…公正で健全な労働環境が整っているか
- 児童労働/強制労働…不正な労働をさせていないか
- 賃金の公正性…最低賃金などの公的ルールを守っているか
- 福利厚生…どのような福利厚生制度があるか
- 組合との関係…労働組合との信頼関係が築けているか
具体例として、平均時給や最低賃金のほか、児童労働/強制労働に関する説明、団体交渉の権利などに関する説明などが挙げられます。
5. エンゲージメント
エンゲージメントの分野では、「従業員満足度」の1項目が、情報開示項目として推奨されています。
- 従業員満足度…社員が仕事や企業に対して満足しているか
エンゲージメントとは、企業に対する従業員の愛着心や思い入れを指し、生産性向上に結びつくとされているものです。
開示事項の具体例には、従業員の満足度のほか、ストレスや不満の度合いがあり、従業員へのアンケート調査などで自社の労働環境や待遇、働きがいに関する満足度を可視化します。
6. 流動性
流動性の分野では、「採用」「維持」「後継者育成(サクセッション)」の3項目が、情報開示項目として推奨されています。
- 採用…採用に関する取り組みや実態
- 維持…人材の定着化に向けた施策について
- 後継者育成(サクセッション)…後継者の確保・維持に向けた取り組み
具体的に求められるのは、定着率や離職率のほか、採用にかけたコストなど人材の確保および定着への取り組みに対する説明、後継者の有効率やカバー率といったサクセッションに関する開示です。
7. コンプライアンス
コンプライアンスの分野では、「法令遵守」の1項目が、情報開示項目として推奨されています。
- 法令遵守…法律や社会規範、倫理観に即した経営活動ができているかどうか
コンプライアンスの分野は、リスクマネジメントの観点からも非常に重要といえるでしょう。
開示事項の具体例は、労働力に関する深刻な人権問題や事件の数、差別事例の件数や対応措置、コンプライアンスや人権、ハラスメントに関連する説明などです。そのほかにも、業務停止の数や法令違反の数、罰金の金額などもあります。
人的資本の情報開示への対応方法

ここでは、人的資本の情報開示への対応方法を解説します。
これから情報開示を行う企業の場合
これから情報開示を行う企業においては、初めから完成度の高いものを目指すよりも、できるところから始める姿勢が重要です。
まずは、社内の人的資本を可視化できる体制を整えましょう。開示に必要なデータを計測できる環境がなければ、自社の人的資本を正確に把握できません。従業員の情報を一元管理できるタレントマネジメントシステムなど、効果的なツールの導入も検討するとよいでしょう。
収集した人的資本の情報を参考に、情報開示における自社の目標を設定します。自社が目指すべき方向性を明確にし、それに見合ったKPI(重要業績評価指標)も設定するのがポイントです。開示した情報は企業経営に多大な影響を与えるため、自社の経営戦略を踏まえた具体的な目標設定を心がけます。
次に、理想とする目標と現状とのギャップを把握します。数値など客観的なデータをもとにギャップを調べ、それを埋める施策を実施するとよいでしょう。
すでに情報開示を行っている企業の場合
すでに情報開示を行っている企業の場合は、情報開示の要点を見直しつつ、人的資本への投資を実践します。
人的資本の情報開示は、株主や投資家などステークホルダーの要望を知る良い機会にもなるため、フィードバックを積極的に取り入れ、人材戦略を見直すとよいです。
フィードバックを反映した施策を実施し、検証および改善策を講じたうえで再度フィードバックを受けるなど、PDCAサイクルを回していくことがポイントです。
なお、人的資本の情報開示のメリットとして、ステークホルダーに対する広報活動(IR)や採用活動における差異化が挙げられます。自社の魅力をアピールするため、攻めの開示項目を増やすことも視野に入れるとよいでしょう。
人的資本の情報開示を主導するのは経営陣ですが、人事部門や事業部門などとも連携し、組織全体で情報開示を進めていくことが重要です。
人的資本開示に取り組む企業事例
最後に、実際に人的資本開示に取り組んでいる企業の事例をご紹介します。
株式会社丸井グループ様
株式会社丸井グループは企業価値の向上に向けて、人的資本経営に積極的に取り組んでいる企業の1つです。「人の成長=企業の成長」という理念に基づき、社員一人ひとりが活躍できる環境づくりに尽力しています。
金融庁が2023年1月31日に発表した「記述情報の開示の好事例集2022」によると、人的資本の定量情報の開示においても「失敗を恐れずに開示できるものは開示していく」という前向きな社内風土が情報開示の後押しになったとのこと。最終的に何を開示するかの選択を現場に委ねることで、スムーズな情報収集と開示につながったとのことでした。
京王電鉄株式会社様
京王電鉄株式会社は中期経営計画において、人財戦略を特に重視している企業です。なかでも従業員のエンゲージメント向上に力を入れており、「失敗を許容する風土」づくりを目指しています。
エンゲージメントを経営上の重要項目と捉えている同社は、2023年3月期の人的資本の開示においても、必須項目に加えて「トータルエンゲージメントスコア」と「職場の心理的安全性スコア」を独自に公開しました。
大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業は「事業を通じて人を育てる」社是のもと、社員の夢や学びを大切にしている企業です。「人財育成ポリシー」と「人財育成のエコシステム」を確立し、人材に投資する意義をステークホルダーに証明するため、施策の設計、運用を進めています。
まとめ
日本では2023年3月期決算より、有価証券報告書を発行する大手企業約4000社を対象に、人的資本の情報開示が義務化されました。
人的資本とは人材を資本と捉え、企業価値向上のために積極的に投資を行っていくという考え方です。人的資本の情報開示により企業の方向性が明確化され、ステークホルダーや求職者に対して自社の魅力をPRできます。無形資産やESG投資への注目度が高まるなか、人的資本の情報開示は今後ますます重要視されるでしょう。
人的資本の情報開示にあたっては、正確にデータ計測ができる環境や明確な目標、現状とのギャップを埋める施策などが求められます。人的資本の情報開示はステークホルダーの要望を汲み取る良い機会にもなるため、フィードバックを積極的に取り入れ施策に生かすのがお薦めです。これらの取り組みが、企業価値の向上と持続的な成長につながります。
---お薦めDL資料のご案内---
【DLレポート】「人的資本開示義務化に関する実態調査」の分析結果
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)
















