連載・コラム
「働く」ことについてのこれまでとこれから 第9回
統計資料から見た現代の労働観【後編】
- 公開日:2019/07/22
- 更新日:2026/01/07

ここまでの連載では、近代までの労働について考察してきました。狩猟採集民社会における労働、江戸時代の労働、近代の労働の実態を探ることによって、これからの働き方を考えてきました。
今回は、現代の労働観を扱います。私たちの労働観は、この数十年の間に、どのように推移してきたのでしょうか。そのような推移を見ることによって、これからの働き方を考えていこうと思います。
◆前編はこちら
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第12回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第11回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【中編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第10回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第9回
- 統計資料から見た現代の労働観【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第8回
- 統計資料から見た現代の労働観【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第7回
- 労働中心の時代(近代以後の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第6回
- 労働中心の時代(近代以後の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第5回
- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第4回
- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第3回
- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第2回
- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第1回
- 「働く」という概念が変わっていく
- 目次
- 仕事の満足度
仕事の満足度
1980年代以降、仕事の中心性は低下し、仕事よりも余暇や家族の方が大事であると考える人が増えてきています。また、生活全体として楽しく過ごしたいし、仕事も楽しく取り組みたいと思う人が増加しています。このような状況下で仕事の満足度は、どのように推移しているのでしょうか。
図表1は、1970年代中盤から90年代初頭の仕事満足度の推移です。満足度は全体として高まっています。同時期を通じて「満足している」と「まあ満足している」を足すと7~8割程度で推移しています。それ以降は、別の調査になりますが、1990年代後半から2000年代初頭は満足度が下がっていますが、その後は上がっています(図表2)。
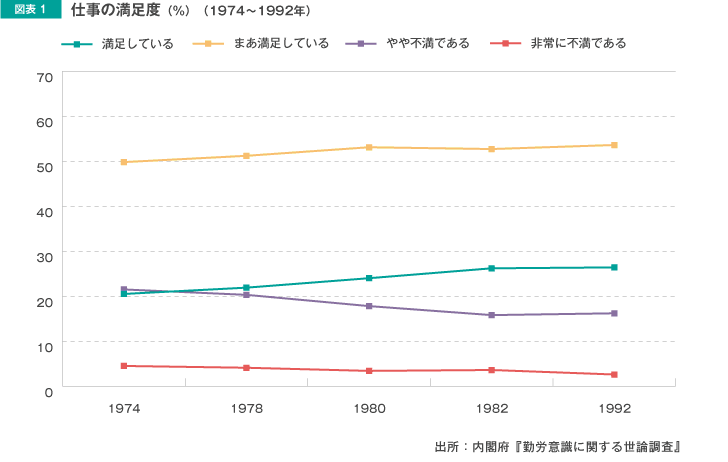
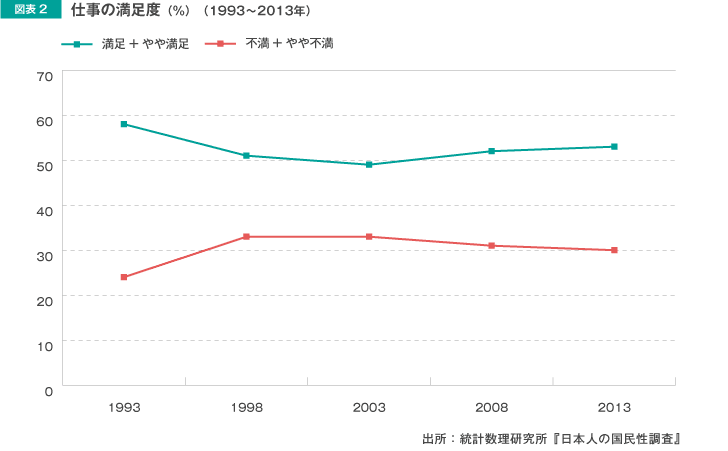
そのことは、労働政策研究・研修機構の調査(図表3)でも支持されています※1。いずれにしろ、仕事の満足度は、ここ40年で微増していると見ることができます。
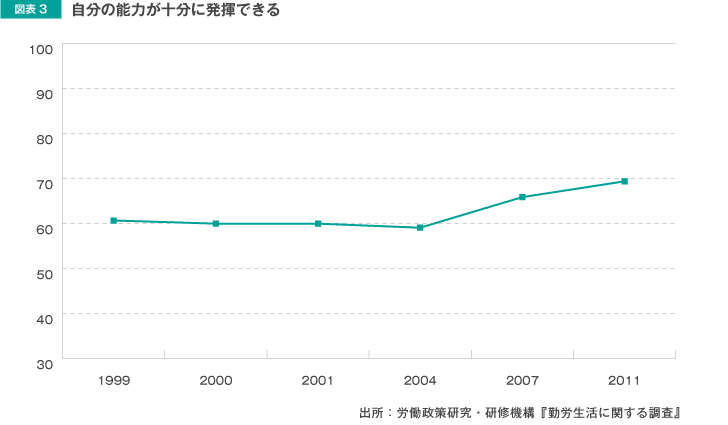
現代の労働観について、まとめましょう。
働く目的はお金のためが主ですが、理想は仲間と楽しく仕事をして、楽しい毎日を送ることにシフトしてきています。社会に対して貢献できることの重要性は増しており、単に稼ぐだけでなく、「自分の仕事が社会の役に立っているか」「社会とつながっているか」ということが重視されるようになってきました。経済的にも豊かになっており、より心の豊かさを求める傾向が強まっています。生活における仕事の比重は低下傾向にあり、最も大事なものは家族になっています。
大昔から私たち人間は、食べるために働き、働くために食べる生活を送ってきました。それゆえに、働く目的が金銭的な報酬というのも理解できる話です。しかしながら、十分に暮らしていけるだけのお金があっても働くという人が日本人の半数以上います※2。働く理由は、金銭的な報酬だけではないということです。
仕事がもたらすものは、金銭だけではありません。仕事によって、人は社会とつながり、社会のなかでの役割を持つことができます。また、居場所を確保することができ、仲間から承認され、自分を表現することができ、仲間と共に何かを作り出すことができます。お客様から感謝され、知らなかったことを知ることができ、できなかったことができるようになり、豊かな経験を得ることができます。
単に食べるためだけであれば、ケインズが指摘したように、それほど長時間働かなくてもいいかもしれません※3。実際、狩猟採集民はそこまで長い時間働いているわけではありませんでした。
それでは、何のために働くのでしょうか。
次回は、未来の労働をお届けします。
第1回~第12回のコラムをまとめたものはPDFでダウンロードいただけます。
こちらのフォームよりお申込みください(無料)
「働くこと」についてのこれまでとこれから
※1 この調査は、「自分の能力が十分に発揮できる」かどうかを聞いています。仕事に満足しているかどうかを聞いているわけではありませんが、能力の発揮度の認知は、仕事満足度と同様の傾向を示すことが多く、代替に値する項目であるとみなして、ここでは使用しています。
※2 統計数理研究所の『日本人の国民性調査』では、「もし、一生楽に生活できるだけのお金がたまったとしたら、あなたはずっと働きますか、それとも働くのをやめますか?」という設問があります。2013年の結果を見ると、62%の日本人が十分なお金があったとしても働き続けると答えています。
※3 経済学者のジョン・メイナード・ケインズは、1930年に「孫の世代の経済的可能性」というエッセイを発表しました。同エッセイは、1928年ケンブリッジ大学の学生に向けて行った講演をまとめたもので、そこでケインズは100年後の経済予測を行っています。「100年以内に、経済的な問題は解決する」と。
ここでの経済的な問題が解決されるとは、衣食住で悩まされ、健全な暮らしができないことから解放されることです。つまり、全世界の人が生きていく上での最低限の富が満たされるということです。その際には、多くても1日3時間、週15時間働けば、経済的な問題はなくなるという主旨の予測も行いました。
バックナンバー
第1回 「働く」という概念が変わっていく
第2回 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【前編】
第3回 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】
第4回 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【前編】
第5回 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【後編】
第6回 労働中心の時代(近代以後の労働)【前編】
第7回 労働中心の時代(近代以後の労働)【後編】
第8回 統計資料から見た現代の労働観【前編】
執筆者
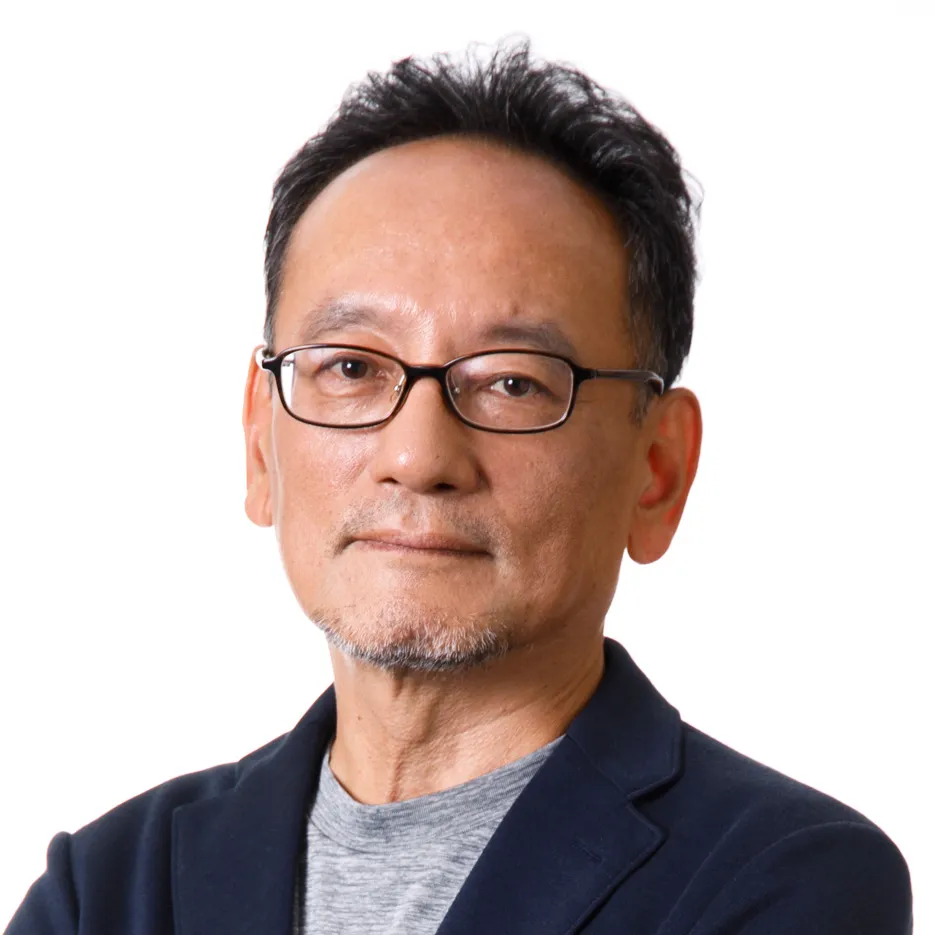
技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
古野 庸一
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社
南カリフォルニア大学でMBA取得
キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事
2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第12回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第11回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【中編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第10回
- 不安だらけに見える未来だからこそ、面白い(未来の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第9回
- 統計資料から見た現代の労働観【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第8回
- 統計資料から見た現代の労働観【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第7回
- 労働中心の時代(近代以後の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第6回
- 労働中心の時代(近代以後の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第5回
- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第4回
- 利己的な勤勉性(江戸時代の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第3回
- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【後編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第2回
- 食うために働き、働くために食って寝る(狩猟採集民社会の労働)【前編】
- 「働く」ことについてのこれまでとこれから 第1回
- 「働く」という概念が変わっていく
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で