連載・コラム
さあ、扉をひらこう。Jammin’2021 session report vol.2
テクノロジーが分からなければ滅びる 〈テクノロジーセッション〉
- 公開日:2022/01/17
- 更新日:2024/05/17
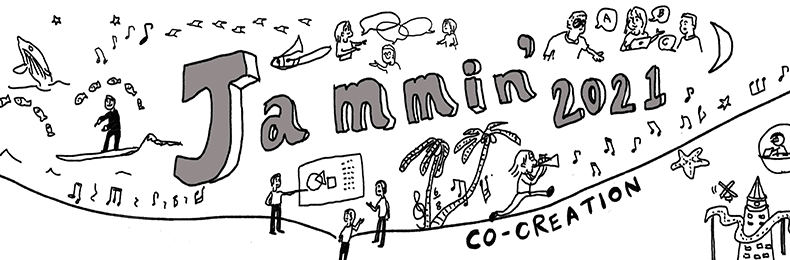
共創型リーダーシップ開発プログラム「Jammin’」は、3年目のJammin’2021を開催している。昨年(2020年)から大幅に増えた「41社・225名」の次世代リーダーたちが、チームを組んで新規事業立案に取り組み、共創型リーダーシップに挑戦している真っ最中だ。そんななか11月12日に、プログラムの1つ「テクノロジーセッション」が行われた。先端テクノロジーを使った新価値創造の最前線の熱量を感じ取る場だ。その模様を紹介する。
- 目次
- 先端テクノロジーを使った新価値創造の最前線の熱量を感じ取る「テクノロジーセッション」
- 【シリコンバレー】優れたアイデアのほとんどはアメリカのベンチャーがすでに試している
- 【AI】精度の高いAIを作るには時間がかかる
- 【ドローン】新事業創出の鍵は、対話・現場訪問・情報探索を重ねて「当たりを発見する」こと
- 【XR】研修トレーニング、遠隔支援など多様な可能性を秘めている
先端テクノロジーを使った新価値創造の最前線の熱量を感じ取る「テクノロジーセッション」
今やビジネスはテクノロジーを抜きにしては成り立たない。Jammin’で新規事業を創出する際、全12コースでAI・ドローン・XRといったテクノロジーを活用する可能性が十分にある。そこでJammin’2021では、2020に続いて、全コースの受講者を対象とした「テクノロジーセッション」をオンライン開催した。4名の専門家が4時間にわたって次々に登場し、テクノロジーの基本知識をレクチャーしてくれる場だ。4名のテクノロジー専門家を紹介する。
● シリコンバレーのスタートアップの最新動向
渡辺千賀氏(Blueshift Global Partners 社長)
● AI
永金明日見氏(株式会社ABEJA AIソリューション事業部 アカウントエグゼクティブ チームリーダー)
● ドローン
徳重徹氏(テラドローン株式会社 代表取締役社長)
● XR
伊藤翔氏(株式会社Synamon Business Development Manager)
それでは、専門家の皆さんに語っていただいた内容をごく簡単に紹介したい。
(なお、各レクチャー後には活発な質疑応答が行われたが、その内容はここでは省略する)
【シリコンバレー】優れたアイデアのほとんどはアメリカのベンチャーがすでに試している

Blueshift Global Partners
社長
渡辺千賀氏
渡辺:日本が30年を失っている間に、世界は進歩しました。シリコンバレーの現状を知ると、世界がどう進化しているかが分かります。私は20年以上シリコンバレーで働いてきた経験をもとに、シリコンバレーのスタートアップの最前線をお伝えします。
はじめに紹介したいのは、デジタル成長企業と死闘する伝統企業の事例です。例えば今、ウォルマートがアマゾンを追い上げています。もはやウォルマートに勝機はないと思われていましたが、Amazonプライムに対抗して始めた有料会員サービス「Walmart 」が会員数を一気に伸ばしており、オンライン生鮮食品販売シェアではアマゾンを上回るまでになりました。この10年弱で無数のテック企業を買収して、エンジニアをどんどん増やし、6000名体制の「ウォルマートラボ」を作り上げた成果が出ています。また、ゴールドマン・サックスは、フィンテックベンチャーに対抗するため、新たに採用する人材の多くをエンジニアに切り替え、すでに従業員の約25%はエンジニアです。そうしてコンシューマ市場に打って出て、デジタル銀行部門「マーカス」に注力したり、アップルと協業して「Apple Card」を発行したりしています。世界的な名門投資銀行ですら、なりふりかまわずデジタル企業へ変貌を遂げているのです。
アメリカでは、優秀なエンジニアの獲得競争が激化しています。ウォルマートが最たる例ですが、企業買収の動機が、所属するエンジニアの獲得にあるケースが珍しくありません。その際、優秀なエンジニアに18~24カ月の在職ボーナスを提示して、企業買収後も一定期間、買収先企業に残ってもらおうとするケースが一般的です。優れたエンジニアは2年在職すればペイするといわれているからです。
2021年、アメリカではベンチャー投資がさらに加速しており、毎日1000億円以上がベンチャー企業に流れ込んでいる状況です。資金の行き先はここ10年に創業したベンチャーがほとんどです。アメリカのベンチャーは「未来のプレビュー」といわれており、彼らは日々、ありとあらゆるトライ&エラーを繰り返しています。優れたアイデアのほとんどは、アメリカのベンチャーがすでに試しているといってよいほどです。最近注目されている企業をいくつか紹介します(図表1)。
<図表1>資金調達中のベンチャー企業の代表例
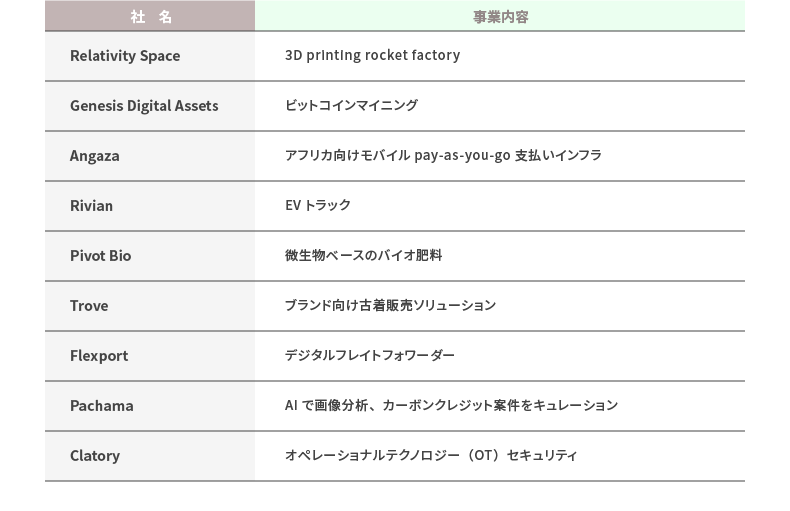
特に最近伸びているのが、企業によるベンチャー投資「CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)」です。グローバルCVC投資はこの4年で約2倍に増えました。CVCの代表格がグーグルで、3つのファンドを持ち、ソフトウェア領域・ヘルスケア領域を中心にいくつものベンチャーに投資しています。不老不死を研究するCalicoなどがグーグルの投資先として知られています。さらに、グーグルはメガファーマとの協業なども積極的に進めています。また、アマゾンはEVメーカーRivianに巨額投資を行い、10万台の電動デリバリーバンを発注したことで一躍有名になりました。このように製品を買うことでベンチャーを支援するあり方は、CVCの理想形の1つと言われています。
以上の説明で明らかだと思いますが、今後はテクノロジーが分からなければ滅びます。その証拠に、アメリカではDXという言葉をあまり使いません。DXをしない選択肢がないからです。ウォルマートやゴールドマン・サックスですら、DXをしなければ崩壊を避けられなかったでしょう。日本の皆さんも、そのつもりで真剣勝負に挑んでください。皆さんの活躍を楽しみにしています。
【AI】精度の高いAIを作るには時間がかかる

株式会社ABEJA AIソリューション事業部
アカウントエグゼクティブ チームリーダー
永金明日見氏
永金:AIは、今やビッグデータをもとに判断・予測するDXの必須ツールとなりました。AIが今これほど注目されている背景には、いくつかの要因があります。1つ目に、安価なデバイスの登場や通信技術の進化によって、現実世界からデータを取りやすくなったことが挙げられます。2つ目に、データ蓄積技術の進化とクラウドサービスの浸透によって、AIに欠かせない大量のデータを安価に保存できるようになりました。3つ目に、ロボティクス技術の進化によって、AIの判断を現実に反映させやすくなったことも大きいでしょう。4つ目に、AIを受け入れやすい文化的土壌が整ったことも、AIの浸透に一役買っています。そして5つ目に、AIアルゴリズムの著しい進化があります。
AIは「ルールベース→統計→機械学習→ディープラーニング」の順で、今も驚くべき速さで進化を遂げています(図表2)。ディープラーニングは2015年頃に人間の画像認識精度を超え、2019年頃に人間の自然言語処理精度を超えました。もはや囲碁・チェスなどでは、人間はディープラーニングAIに勝てません。AIは自動で無限回の対局を行って進化するからです。
<図表2>AIの分類
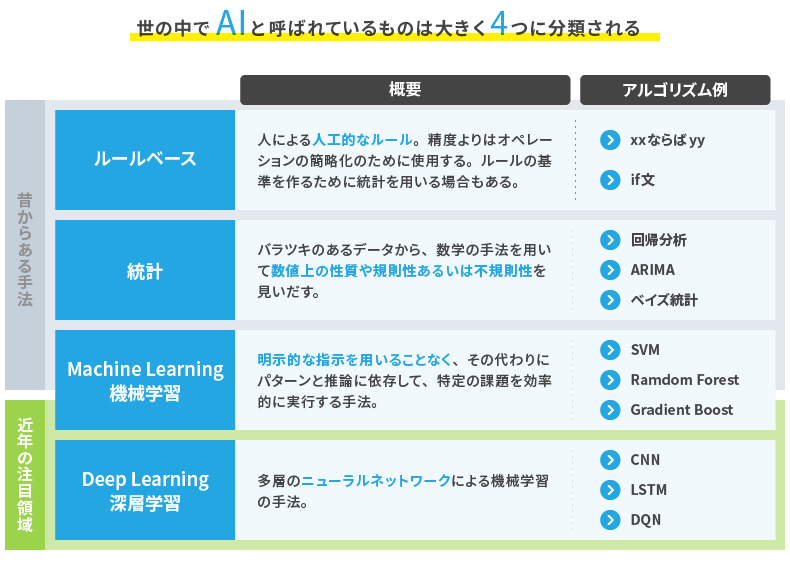
こうして発達したAIは、実はすでに世の中のさまざまな「不」を解決しています。クレジット利用の不正検知AI、エアコン修理部品を予測するAIなど、事例はいくらでも挙げられます。「Deep L 翻訳」という翻訳ツールは、関西弁なども的確な英語に変換できる翻訳精度を備えています。また、大日本印刷はMantra と共同で、「マンガのためのAI 翻訳エンジン」を開発しています。海外に目を向けると、グーグルの親会社であるアルファベットが、AIを活用して創薬に挑むIsomorphic Labsというベンチャーを設立するなど、AIが盛んに活用されています。
AIで解決できる「不」は次の5つです。新規事業に活用する際は、この分類を踏まえるとよいでしょう。
(1)影響要因の可視化(故障要因・遅延理由の発見など)
(2)分類・認識(傷の検知、部品の仕分けなど)
(3)予測(気温・株価・需要の予測など)
(4)最適化(ポートフォリオ・生産計画の最適化など)
(5)生成(存在しない顔の生成など)
AIの精度を高めるには、フィードバック・再学習を行う「DO(デジタルオペレーション)」が欠かせません。なぜなら、最初から賢いAIを作れるケースは少なく、DOしないと十分な性能を発揮できないからです。AIは精度保証ができず、精度の高いAIを作るには時間がかかるのです。また、学習するデータや解くべき問題によっても精度が左右されます。だからこそ、AIの不確実性を補う形で、HI(Human Intelligence)を用いて、AIの実用化に向けて段階的なステップを踏んでいくことが重要です(図表3)。実際、AIをあくまでも人間のサポート役と位置づけ、着実にデータを蓄積しながら性能を向上させる事例が増えています。精度がそこまで高くない状態でいったん現場に導入して、DOを繰り返しながら、より精度を高めていくことがAI開発の成功の秘訣です。
<図表3>HIからAIへの段階的なステップ
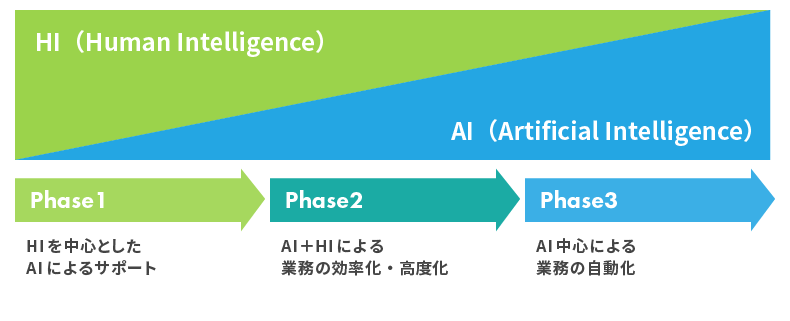
【ドローン】新事業創出の鍵は、対話・現場訪問・情報探索を重ねて「当たりを発見する」こと

テラドローン株式会社
代表取締役社長
徳重 徹氏
徳重:私たちテラドローンは、空撮、測量、点検、データ分析、運行管理などの産業向けドローンサービスを国内外で提供しています。例えば、土地測量はデータ処理・取得をドローンで行うと、これまで2人で2週間ほどかかっていたものが、たった1日で終わります。ほかに、ガスタンクやオイルタンクの肉厚測定、携帯基地局の保守点検、河川の巡視などにもドローンが極めて有効です。これらのビジネスを展開してきた結果、現在私たちは、売上世界トップを争うドローンサービス会社となりました。現在は、Terra DX Solutionsというグループ会社を設立し、建築DX事業にも乗り出しています。
▼ テラドローンのビジョン
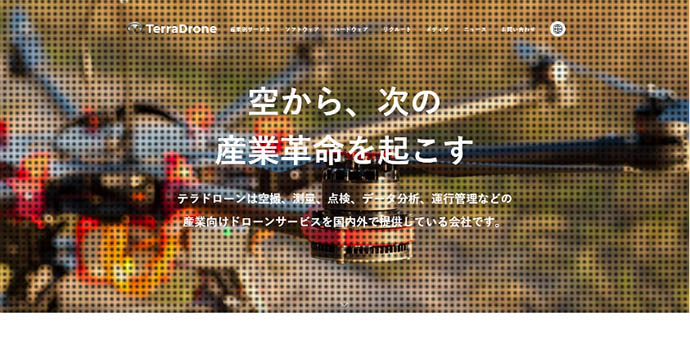
私はかれこれ20年以上、スタートアップで新事業創出を続けており、テラドローンの前はテラモーターズでEVを開発しました。新事業創出で最も大事なのは「当たりの発見」です。新規事業は100のうちの3つが当たればよい方です。失敗が普通であり、多産多死のなかから当たりを探していきます。
では、どうすれば当たりを見つけられるのか。私たちが大事にしていることの1つが、「顧客のペインの大きさ」です。私たちはEVもドローンも建築も素人ですが、顧客のペインが大きければ、素人でもビッグビジネスにできる可能性が十分にあるのです。しかし、ペインが大きければ必ず当たるというわけではありません。当たりを見つけるには、日々情報をとことん調べ、世界中のさまざまな人と対話し、現場をよく観察することが基本です。そうやって行動しながら仮説を修正しつづけ、数多くの失敗を見切るなかで、ようやくドローンサービスのような当たりが見つかります。私たちにとって最も貴重な資源は時間です。リソースがなくなる前に、最も多く学習したものが勝つ世界なのです。
日本の大企業は、新規事業を始める際に事業計画を立てるようですが、私に言わせれば、事業計画などほとんど意味がありません。対話と現場訪問と情報探索によって仮説を絶えず修正し、市場の可能性を見極めるほかに、新事業創出の近道はないからです。膨大な行動と意思決定の果てに、初めて当たりが見えてくるのです。
ドローンサービスに関していえば、第1に顧客価値=顧客のペインが大きかったこと、第2にスケーラビリティが高かったこと、第3に黎明期だったことが「当たり」の決め手でした。創業約半年でUniflyを買収し、ドローンの運行管理システム(UTM)構築に乗り出したこともターニングポイントでした。Unifly買収は周囲から大反対されましたが、私は航空管制がドローンサービスの鍵を握っていることが分かっていたので、まったく迷いはありませんでした。
こうやって「当たり」を見つけられる人材が、日本には本当に少ないのが実情です。皆さんの新価値創造、新事業創出に期待しています。
【XR】研修トレーニング、遠隔支援など多様な可能性を秘めている

株式会社Synamon
Business Development Manager
伊藤 翔氏
伊藤:XRとは、VR(仮想現実)・MR(複合現実)・AR(拡張現実)の総称です。最近、メタバースが大きな話題となり、XRにさらなる注目が集まっています。私たちSynamonは、XR技術の社会実装と市場創造に挑戦している会社です。
さまざまな業界でXRの活用が広まってきています。例えば、私たちは三井住友海上火災保険様とともに「VR自然災害損害調査研修」(画像1)を開発しました。VR技術を使って、損害家屋の査定研修を行う場をバーチャル空間に作ったのです。今後予想される大規模な地震災害に備えた損害調査体制の強化が必要な中、「被災建物モデルの確保と維持が困難である」「研修受講人数に限りがある」という二つの課題から、損害家屋の実地研修はほとんど行えていない状況でした。バーチャル空間上に研修の場を設けることで、それらの課題を解決することができたのです。実際に2021年からリモート下で実地さながらの新人研修を行っており、学習効果も高く好評です。
▼ 画像1 VR自然災害損害調査研修

この事例が典型的ですが、XRは「体験のテクノロジー」です。特にこうした研修トレーニングの体験に有効なことが分かっており、ほかにもトヨタ自動車様が自動車整備の効率化とトレーニングのためにMRを活用したり、ハタコンサルタント様が建築現場の安全管理・品質管理の研修をするVR安全パトロール研修を導入したりしています。
また、XRは単に体験するだけでなく、「遠隔支援のテクノロジー」としても活用可能です。私たちは以前、防衛医科大学校様、KDDI様とともに、第5世代移動通信システム「5G」とVRシステムを活用した災害医療対応支援の実証実験を行いました。バーチャル空間を通じて、医師や消防のプロが遠隔で被災地に指示を出し、治療の優先順位を判断したり、応急処置の方法を教えたり、適した病院を選定したりするのです。実証実験により、5GVRを使った遠隔指揮・遠隔支援が有効であることが分かりました。今後、広まる可能性が十分にあります。
その他、内閣官房の国際博覧会推進本部事務局が運営する「大阪・関西万博関係府省庁連絡会議」に弊社VRサービス「NEUTRANS」を提供したり(画像2)、VRオフィスを作ったり、ARで新たな美術鑑賞体験を実現したりもしています。XRには、本当にさまざまな活用の仕方があるのです。
▼ 画像2 大阪・関西万博関係府省庁連絡会議でのVRを用いた会議の様子

最近はXRハードウェアの進化が目覚ましく、もう少ししたら、現実世界と同じくらいリアルな体感のXRが実現します。テクノロジーの発達と共に、近くXRの流行がやってくるはずです。その流れに乗って、XRを上手に活用していただけたら嬉しいです。
以上、テクノロジーセッションの内容の一端を見ていただいた。Jammin’参加者は、このテクノロジーセッションを受けて、テクノロジーと新価値創造への想いを高めながら、引き続き事業案を構想している。次回の記事では、オーナー(参加企業人事)が集まるオーナーセッションの模様を紹介したい。
【text:米川青馬、illustration:長縄美紀】
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
関連記事
■さあ、扉をひらこう。Jammin’2021 professional interview
「インバウンドは自社ビジネスとつながっている」と気づくとみんなの目が変わる
■さあ、扉をひらこう。Jammin’2021 session report
vol.1 Jammin’2021始動! 41社225名が早くもホンネの交わし合いを始めた〈リーダーセッション1〉
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020インタビュー
vol.1 社会課題の生々しさに触れる経験が参加者を変えていく
vol.2 「現場」で自分たちのアイディアが机上の空論 だと思い知った日が転機
vol.3 「デジタルおがつ町」を3.11に実現したチームの話~アワード出場よりも大切にしたこと~
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’研究レポート
1 越境の経験と学びを可視化する―2020年度Jammin’参加者プレ/ポストアンケートより
2 「経験からの学び」を豊かにする視点-2020年度Jammin’参加者プレ/ポストアンケートより
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’インタビュー
vol.1 もし自分を変えたくないのなら、Jammin’に参加しない方がよいと思う
vol.2 Jammin’に参加して、「経営リーダー」の道を一歩踏み出してみようと決めた
vol.3 1つの企業に勤め続ける方も、Jammin’を通して「外」とつながれる社会にしたい
vol.4 Jammin’参加社員の多くが自らの業務を社会課題とつなげて考えるようになった
vol.5 テーマの枠を超えていく新規事業案がさらに増えたら嬉しい
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020オーナーセッションレポート
vol.1 23社・46名の人事が「人材戦略の進化」について語り合う
vol.2 越境の学びの現場から 「研修が終わってもぜひ関わり続けて」
vol.3 「当たり前」や価値観を揺さぶり、成長と共創の実現を目指す「越境」の取り組み
vol.4 ピープルアナリティクスの専門家が読み解く「共創型リーダーシップ」
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’2020新価値創造セッションレポート
vol.1 多様な力を結集してリーダーシップ開発と社会課題解決を目指すJammin’2020、スタート
vol.2 仲間たちや専門家と共に不を掘り下げる1日〈新価値創造セッション2回目〉
vol.3 DX時代の「不」はテクノロジー抜きでは解決できない〈テクノロジーセッション〉
vol.4 専門家が事業仮説の甘さを鋭く指摘する1日〈新価値創造セッション3回目〉
vol.5 新たな視点で「本当に成し遂げたいこと」を考える1日〈新価値創造セッション4回目〉
vol.6 社会的意義もニーズもポテンシャルも大きな事業案がグランプリに輝いた〈Jammin’ Award〉
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’オーナーセッションレポート
vol.1 イノベーションとリーダーシップを考える
vol.2 イノベーションと人事の役割を考える
vol.3 続・イノベーションと人事の役割を考える
vol.4 イノベーションにおける人事の役割を共創する
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’セミナーレポート
vol.5 VUCA時代に求められるリーダーとは
■共創型リーダーシップ開発プログラムJammin’ Awardレポート
vol.6 37の切磋琢磨の頂点に輝く新規事業案とは
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

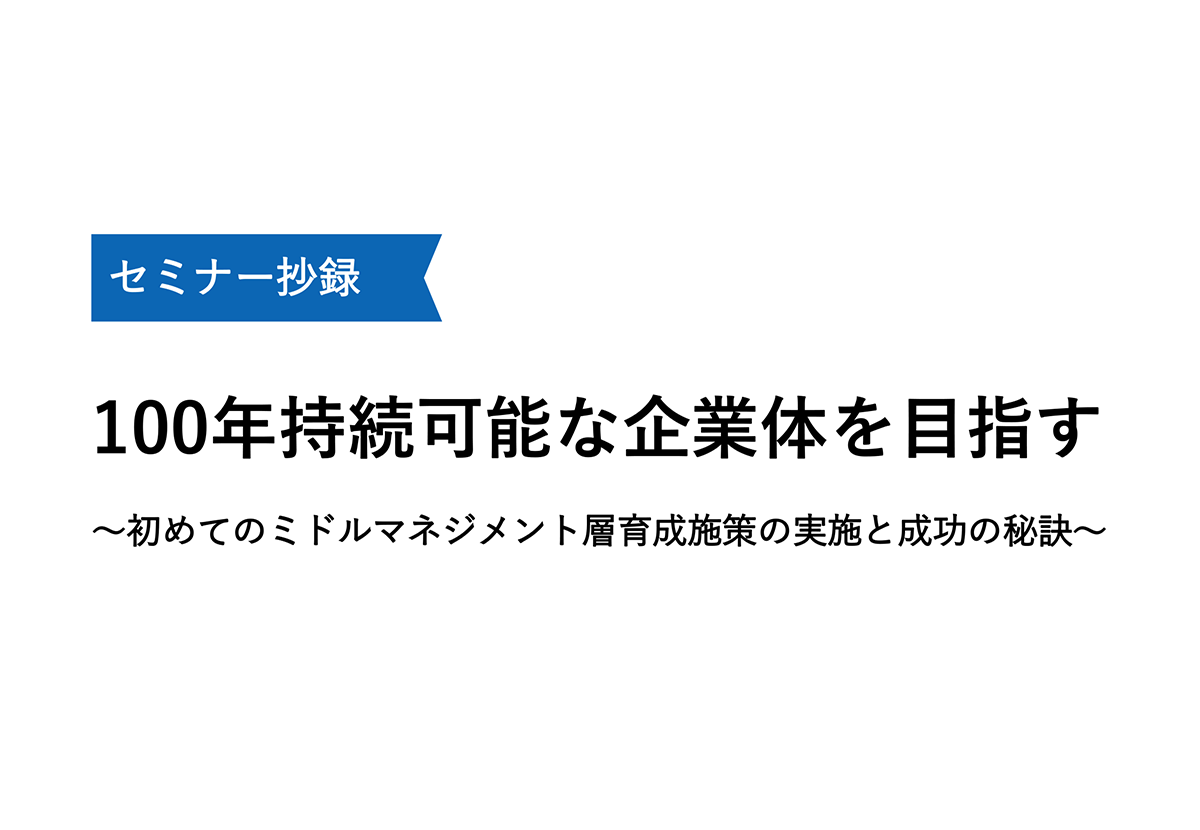









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての