連載・コラム
マネジメント人材育成ブック【6】経営者への道(卓越した経営者の学びのプロセス研究)
卓越した経営者は 日々の鍛錬からも学んでいる
- 公開日:2018/10/22
- 更新日:2024/05/28

近年、私たちが行ったマネジメント(に関する)研究を6つのテーマでまとめ直した『マネジメント人材育成ブック』より、第6章は、「経営者への道」として、「卓越した経営者の学びのプロセス」研究の成果を中心にお知らせします。
はじめに、架空の会社・X食品の新任営業マネジャー(加藤洋介)と、社内の誰かが対話する「ストーリー」がついています。
それぞれの章の研究成果を受けた内容となっておりますので、本文の導入として気軽にお読みください。
また、メルマガ会員の方は『マネジメント人材育成ブック』全体のPDFをダウンロードいただけます。ご興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。
- マネジメント人材育成ブック【6】経営者への道(卓越した経営者の学びのプロセス研究)
- 卓越した経営者は 日々の鍛錬からも学んでいる
- マネジメント人材育成ブック【5】経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
- 優れた経営幹部は 十分に信頼を獲得してから改革する
- マネジメント人材育成ブック【4】女性マネジャーの特徴(マネジメントの男女差研究)
- 女性マネジャーは より「部下」をよく見ている
- マネジメント人材育成ブック【3】成果をあげるミドル・マネジャーとは(ミドル・マネジャー研究・これからのミドル・マネジャー研究)
- 成果をあげるミドル・マネジャーは「持論」をもっている
- マネジメント人材育成ブック【2】経験から学ぶ(経験学習論・経験デザイン研究)
- 修羅場を経験してから しっかり内省すれば一皮むける
- マネジメント人材育成ブック【1】マネジャーになる(マネジャーへのトランジション研究)
- 新任マネジャーのほとんどが トランジションに苦労している
第6話 新任マネジャー、経営者の話を聞く

加藤「せっかく隣の席になったので伺いたいのですが、社長は、いつ経営者になろうと思われたのですか?」
小寺「どうしてそんなことを知りたいのかな。もしかして、君は経営者になりたいのか。」
加藤「いえ、まだそこまで真剣に考えているわけでは…。」
小寺「僕が君の年の頃は、つまり30代の頃は経営者になろうなんて、思いもしなかった。社長を目指そうと本格的に思ったのは取締役になってからだ。」
加藤「もう1つ伺ってもいいですか? 社長になるために、どのようなことを心がけてこられたのでしょうか。」
小寺「そんなに知りたいかい?」
加藤「はい」
小寺「わかった。じゃあ、話そう」
加藤「やった! ありがとうございます!」
小寺はペットボトルの水をゆっくりと飲み干してから、話し始めた。
小寺「まずはプレイヤー、マネジャーとして高いレベルの結果を出すことだ。社長になろうとは思わなかったが、同期の誰にも負けない成果をあげようとは思っていた。営業のときは、常にトップ営業になるよう努力した。これはまあ、当たり前のことだな。それから、とにかく“対人スキル”を磨いてきた。人に会って話をするのが好きなのもあるが、上司・同僚・部下・社外などなど、さまざまな相手とさまざまな場で対話して、いつ何をどうやって言えばいいかを考え続けてきた。
しかも、ただ考えるだけじゃなく、毎週のように自分の行為を振り返って、“自分なりの方程式”を組み立ててきた。営業トークの方程式、プロジェクト立ち上げの方程式…。いろいろな方程式をもっているんだよ。もちろん、営業トークの方程式も一種類じゃない。相手と状況によって違う対応が必要だからな。いくつかのシナリオを作って、それを相手と状況によって臨機応変に使い分け、少しずつ手を加えながら、方程式を磨き続けてきた。いや、今も磨き続けていると言った方がいいだろう。」
加藤「早速明日からやってみます!」
小寺「それがいい。僕の方程式を教えてもいいのだけれど、たぶん自分で作ったほうが役に立つ。それに、方程式を作るスキルを磨くのも大切だからな。それから、若いうちはたくさん失敗をした。たくさん修羅場をくぐってきた。新規プロジェクトがうまくいかないこともあったし、大切な部下の心が離れかけてしまったこともあった。でも、諦めずに粘り強く挑み続けたのがよかったのだろうな。」
加藤「小寺さんでも失敗があったんですね。すごくホッとしました。」
小寺「当たり前だろう。そういえば、社長になって以来、僕は未来の社長を育てようとしてきたけれど、若手で大きく伸びているのは、失敗してもめげずに正面から立ち向かっていく人だな。失敗したとき、修羅場を迎えたときこそ、課題を克服する機会だと考えることが大事なんだ。ピンチは、学びという意味ではチャンスなんだよ。」
加藤「肝に銘じます。」
小寺「あとは、良い上司・同僚・部下をたくさん見つけることだ。僕には、社内の出会いこそが宝ものだ。君は田中くんの部下だよな。」
加藤「そうです。」
小寺「彼なんか、実にいい言葉をかけてくれるんじゃないか。」
加藤「はい。本当に勉強になります。」
小寺「そういう関係を大切にしなさい。あとは、日々勉強だ。お、ちょっと悪い。電話がきたので、ちょっと席を外すよ。」
加藤「ありがとうございました。今日のことは一生忘れません!」
小寺「おおげさだな。」

本当に非日常の「修羅場」だけが 優れた経営者を形成するのか
「次世代リーダー育成」は、長い間、人材マネジメントのトップ課題の1つとなってきました。その理由は、簡単に言えば、次世代リーダー育成が難しいからです。
難しい理由は大きく2つあって、1つは、当然のことですが、経営者になる前に経営者の仕事を経験できないからです。これまで、課長へのトランジション〈第1章〉、部長へのトランジション〈第5章〉の大変さに触れてきましたが、経営者の仕事は、課長、部長、事業リーダーへのトランジションを終えた後にあり、なかなか経験学習〈第2章〉ができません。
仕事を通じた育成が難しいため、次世代リーダー育成は研修をするほかにありません。実際、多くの企業が「次世代リーダー研修」を行っています。こうした研修は改良が重ねられ、内容は充実してきていますが、まだ解決できていない弱点があります。若いうちにいくら経営者の仕事を学んでも、結局、実践の機会がなかなか来ないということです。実践の機会がなければ、学んだスキルは陳腐化してしまいます。このジレンマが、育成が難しい第2の理由です。
では、経営者はどのように育っていくのでしょうか。「一皮むけた経験」研究〈第2章〉をはじめ、これまでの研究では、経営者は「修羅場経験」を通じて成長するとされてきました。しかし、本当にそれだけでしょうか。例えば、「熟慮された鍛錬」〈第2章〉は、経営者の育成にまったく関係ないのでしょうか。また、同じく〈第2章〉では「コルブの経験学習サイクル」を紹介しましたが、経営者は日頃、どの程度の「内省」や「概念化」を行っているのでしょうか。こうした疑問をベースに、私たちは「卓越した経営者の学びのプロセス」研究(図表1)を行いました。
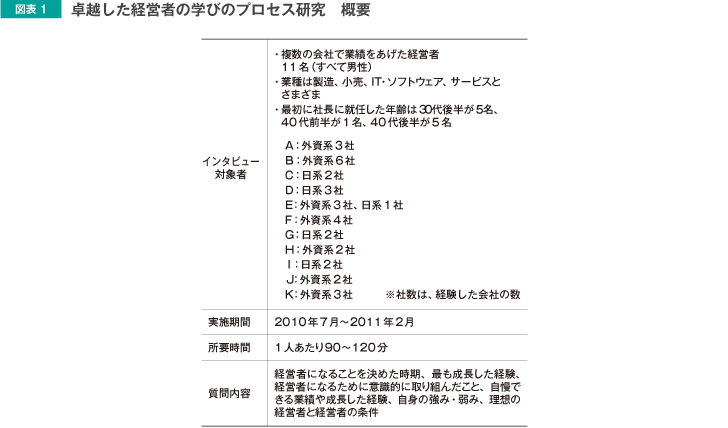
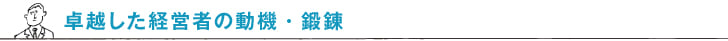
若い時から経営者を目指して 日々対人スキルなどを鍛錬している
この研究で、私たちは、複数の会社で業績をあげた11名の経営者に話を伺いました。最初に質問したのは、どの段階で経営者になる覚悟をしたのかということです。図表2が、経営者の方々の主な回答です。11名中10名に「経営者になる覚悟」があり、うち5名は新卒入社の時点で経営者になることを意識していました。また、残りの方のなかには、コンサルティング会社や銀行など、頻繁に経営者と会い、経営者の目線で考えるうちに、自ら経営者になることを決めた方が何人かいました。それだけでなく、数多くの社長と接するなどして、「自分も経営者をやれそうという自信」(図表3)を持ったという発言をした方が11名中6名いました。
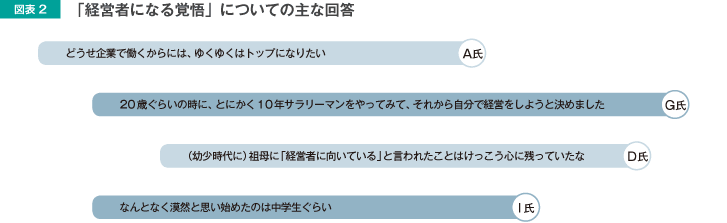
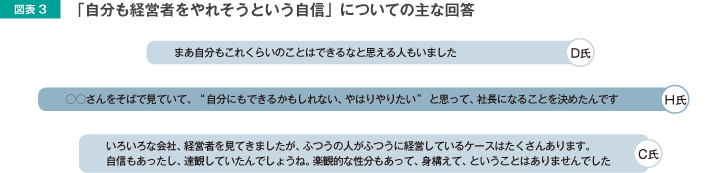
つまり、卓越した経営者の多くは、早い段階で経営者になろうと考え、経営者を目指して学び続けていたのです。それに加えて、「学び続ける信念」(図表4)を強くもつ方も多くいました。こうした方々が、日々の経験・鍛錬から学んでいないわけがありません。実際、11名全員が、「仕事の中で意図的な鍛錬」を行っていました。また、仕事以外では、計画を立てて、定期的に読書(8名)、人脈づくり(4名)などを行っていました(図表5)。やはり、経営者は非日常な修羅場経験だけでなく、日常的な鍛錬によっても形成されていたのです。
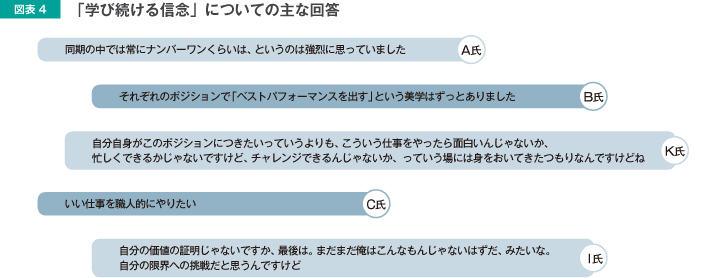
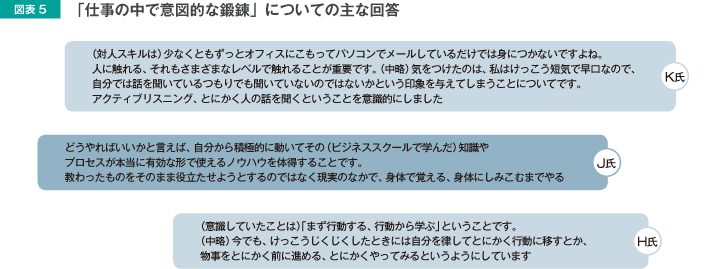
日々の鍛錬で最も鍛える必要があるのは、「対人スキル」(図表6)です。なぜかといえば、対人スキルは一朝一夕では身につけられないからです。対人関係で、まったく同じ状況になることはなかなかありません。部下に良かれと思ってしたことが、部下にとってはむしろ迷惑だったとか、コミュニケーションを円滑に進めるために表面的にはメンバー全員が賛成しているが、実は誰も納得していなかったといったことは、よく起こることです。それは、世の中には本当にさまざまな人がいて、さまざまな場面があるからにほかなりません。そのパターンを数多く知り、対応策を練るには、長い時間をかけて、意図的に鍛錬する必要があるのです。驚いたことに、多くの経営者が、意識的に対人スキルを磨いていました。優れた経営者には、粘り強く対人スキルを磨くことが必須だと知っているのです。
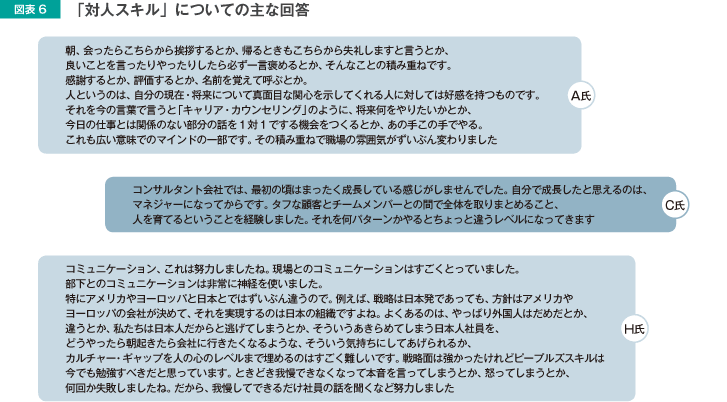
また、面白かったのは、運動をする、食事に気をつけるといった身体訓練、体調管理を行っている方が多かったことです。近年のリーダーシップ論では、レジリエンスやマインドフルネスを扱うことも増えており、経営者の「心身の健康」が注目されています。身体を鍛えることで、ストレス耐性が高まり、仕事の満足感が高まり、業績が上がるという研究報告もあります。多くの場合、経営者になるのは早くても30代後半です。経営者になりたいと思うなら、そのときに健康でいるために、若いうちから心身に気を使う必要があるのです。
一方、やはり11名全員が修羅場経験を経て「一皮むけた経験」をしており、10名が上司の薫陶や研修を役立てていました。これらは従来の研究に沿っており、予想どおりの結果だったと言えるでしょう。
バックナンバー
第1回 マネジャーになる(マネジャーへのトランジション研究)
第2回 経験から学ぶ(経験学習論・経験デザイン研究)
第3回 成果をあげるミドル・マネジャーとは(ミドル・マネジャー研究・これからのミドル・マネジャー研究)
第4回 女性マネジャーの特徴(マネジメントの男女差研究)
第5回 経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
♦PDF版のご案内
この他、第6章では「卓越した経営者の内省と学び」「大企業の経営者はどうなのか」「次世代リーダーをどのように育てるか」などをご紹介しています。ぜひ第6章の全体をこちらからお読みください。
(すでにメルマガをご購読の方はメルマガ内にパスワードの記載があります)
▼▽第6章の全体を読みたい方はメルマガご登録の上、PDF版をダウンロードしてください▼▽
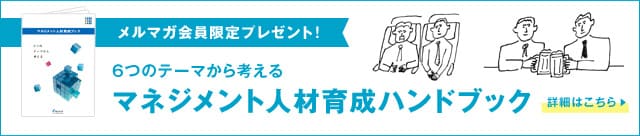
- マネジメント人材育成ブック【6】経営者への道(卓越した経営者の学びのプロセス研究)
- 卓越した経営者は 日々の鍛錬からも学んでいる
- マネジメント人材育成ブック【5】経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
- 優れた経営幹部は 十分に信頼を獲得してから改革する
- マネジメント人材育成ブック【4】女性マネジャーの特徴(マネジメントの男女差研究)
- 女性マネジャーは より「部下」をよく見ている
- マネジメント人材育成ブック【3】成果をあげるミドル・マネジャーとは(ミドル・マネジャー研究・これからのミドル・マネジャー研究)
- 成果をあげるミドル・マネジャーは「持論」をもっている
- マネジメント人材育成ブック【2】経験から学ぶ(経験学習論・経験デザイン研究)
- 修羅場を経験してから しっかり内省すれば一皮むける
- マネジメント人材育成ブック【1】マネジャーになる(マネジャーへのトランジション研究)
- 新任マネジャーのほとんどが トランジションに苦労している
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)














 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で