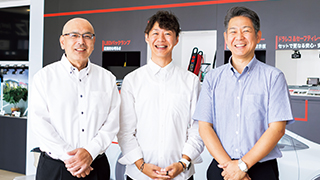用語集
マネジメントとは
- 公開日:2014/04/18
- 更新日:2026/01/20
マネジメントとは資源や資産・リスクなどを管理し、経営上の効果を最適化しようとする手法を指し、経営学の分野の1つで、経営者の経営そのものを指す場合が多いです。一般に「管理」と訳されることが多いですが、評価・分析・選択・改善・回避・統合・計画・調整・指揮・統制・組織化などさまざまな要素を含んでおり、これらを総合した概念をマネジメントだと考えた方が理解しやすいです。
企業における「マネジメント」を一言で表すと「経営・組織を管理する」業務になります。そして管理職は組織の管理責任者です。ここでは、マネジメント力が特に求められる管理職についてご紹介します。
【ダウンロード無料】
6つのテーマから考えるマネジメント人材育成ブック
リクルートマネジメントソリューションズでは、リーダーあるいはマネジャーになるような人材の育成に関する研究を行ってきました。
「マネジメント人材育成ブック」では、私たちが行った研究を6つのテーマでまとめ直し、次世代リーダーの育成やマネジャーの育成に従事している人にとって、おさえておきたいトピックを収録しています。
マネジメント人材育成の新しい施策の検討に、是非ご活用ください。
マネジメントとは?
マネジメントの定義や必要性について以下で詳しく解説します。
ドラッカーのマネジメントの定義
ピーター・ドラッカーが提唱した「マネジメント」とは、組織に成果をもたらすための道具や機能、機関を指す概念です。
この定義は1973年に出版された著書 『マネジメント』 で示されました。
マネジメントは単なる管理手法ではなく、組織が社会や個人のニーズを満たし、その存在意義を果たすための重要な仕組みであるとされています。
ドラッカーの理論において、「組織」とは企業に限らず、社会のあらゆる機関を含む広い概念です。そして「成果」とは、組織が顧客やコミュニティのニーズを満たすことにほかなりません。この視点から、マネジメントは組織の方向性を決定し、目標達成を支えるための役割を担うと考えられています。
また、マネージャーは組織の成果に責任を持つ存在であり、その役割を果たすためには的確な意思決定やリーダーシップが必要です。ドラッカーのマネジメント理論は、企業経営だけでなく、教育や公共機関など、幅広い分野で参考にされています。この理論を適用することで、組織の目標達成や価値創造が期待できるでしょう。
マネジメントの必要性
マネジメントの必要性は、組織が目標を達成し、持続的に発展するための基盤を築くことにあります。ドラッカーの理論でも指摘されているように、マネジメントは単なる管理ではなく、組織が果たすべき役割を全うし、社会的責任を果たすための手段とされています。
これにより、組織は単なる業績向上にとどまらず、社会全体への貢献が期待されるでしょう。
具体的には、マネジメントを通じて組織の目標を明確化し、その目標に向けて人材を適切に配置することが重要です。また、従業員の能力を引き出し、育成することで、成果の向上が見込まれるでしょう。
さらに、マネージャーの存在は、業務を効率的に進めるだけでなく、組織運営や後輩の指導など、幅広い役割を担う点でも不可欠です。
これらの要素を踏まえると、効果的なマネジメントは組織にとって重要な機能であり、長期的な成功と社会への貢献を支える鍵になると考えられます。
マネジメントとリーダーシップの関係
マネジメントとリーダーシップは、組織運営において異なる役割を持ちながらも、相補的な関係にあります。リーダーシップは、組織やチームにビジョンや方向性を示し、メンバーを鼓舞して変革を促進する役割として発揮されます。一方、マネジメントは、設定された目標に基づいてリソースやプロセスを効率的に管理し、組織運営を支える役割を果たします。
例えば、新たなサービスの方針や理念を提示するのがリーダーシップであり、そのサービスを具体化するためにリソースを管理し、計画を実行するのがマネジメントです。リーダーシップとマネジメントがバランスよく発揮されることで、組織はビジョンを実現しながら持続的な成果を生み出すことができます。
現代の企業では、両者のスキルをバランスよく発揮することが重要だとされています。これにより、変化に柔軟に対応しつつ、組織の目標達成を目指すことが期待されるでしょう。
管理職がぶつかる4つの壁
【1】部下に対して
仕事を任せきれない、厳しく要望できない、うまく育成できないなど。
【2】担当組織の課題設定について
自分なりのビジョンや方針を打ち出せない、自分のビジョンや方針を部下に納得させられないなど。
【3】関係者に対して
直属の上司との関係がうまくいかない、他部署との調整がうまくできないなど。
【4】自分自身について
プレイング業務に時間を割かれてマネージャーとして機能しない(実務が多く、マネジメント業務とのバランスがとれない)、上位者と部下に挟まれて判断に困る、など。
上記のなかでも特に多いのは「対部下」に関する問題で、着任して半年以内の新任管理職の8割が課題に感じています。しかし調査によると、部下に関する問題は時間の経過にともない減少。多くの管理職は、経験と学習で部下に関する問題を乗り越えています。
一方、「自分自身」に関する問題は、時間が解決してくれるものではありません。この問題を解決するためには、セルフマネジメント力を高める必要があります。このセルフマネジメント力は、部長職などさらに高い次元で仕事をする際に必要となるスキルです。
◆無料限定資料配布中
「マネジメント育成ブック」「VUCA×Z世代新人育成」などを配布中!
人事お役だち資料無料ダウンロード
◆無料動画セミナー
これからのマネジメントに求められる3つのポイントを解説。
「メンバーの自律を促すこれからのマネジメント」
管理職(マネジャー)の役割・仕事内容

管理職(マネジャー)には、組織の各メンバーが本領を発揮できる環境を生み出し、より効果的な経営につなげていく役割があります。例えば原価や予算などのコスト面の管理はもちろん、特に重要なのは人材活用です。一人ひとりの意欲や生産力につながる仕組みを整え、経営戦略に応じた業務遂行ができるように組織を支えるのが、マネジメントの大きな要素でもあります。仕事内容で特に重視しておきたいのは、以下の4つです。
【1】部下の動機づけをする
部下に仕事を任せて育成するためには、仕事に対する部下の意欲を引き出せる環境づくりが大切です。管理職は部下がチーム内で同調性・有能性を示し、前向きに仕事に取り組めるよう動機づけを行います。
【2】目標を設定する
部下へ仕事を割り当てる前に、部下をどの方向に伸ばすのか、育成目標を設定しなければなりません。適した仕事を与えられ、どの方向に努力すべきか理解できた部下は、実力を発揮します。
【3】適切な指導を行う
部下の仕事内容を把握し、部下から発せられるシグナルを敏感に察知することも管理職の仕事です。そして、常に自分の行動を内省して、自ら成長するように部下を指導し、精神的にもサポートします。部下は、業務における自らの問題点を意識し、改良の努力をしなければ成長できません。
【4】定期的に評価・フィードバックを行う
部下と共に定期的に仕事内容や業績を振り返り、フィードバックをして改善ポイントを認識してもらいましょう。管理職が部下と意思疎通して課題を共有すれば、成長につながります。
上記を行うことで、部下と連携した業務の遂行が可能になり、さまざまな環境で成果を上げられます。【1】~【3】のスキルやスタンスについては弊社の管理職研修で学べますので、ぜひご活用ください。
マネジメントに必要なスキル
効果的なマネジメントを行うには、どのようなスキルが必要なのでしょうか?
以下で詳しく解説します。
部下育成スキル
部下育成スキルは、マネジメントにおいて欠かせない要素の1つです。
このスキルは、部下の成長を促し、組織全体の成果向上を支える役割を果たします。単に業務の指示や目標設定を行うだけではなく、部下の状況を把握し、必要に応じて助言や支援を行うことが求められるでしょう。
例えば、適切なタイミングでフィードバックを提供したり、自ら模範となる行動を示すことで、部下は自分の課題を認識し、成長するきっかけを得るとされています。
また、部下が自立して成果を上げられるよう、業務の進め方だけでなく、考え方やスキル習得に向けたサポートが必要です。
このような育成を通じて、部下が自己成長を実感できれば、組織としても安定した成果を期待できるでしょう。部下育成スキルを磨くことは、マネージャー自身の成長にもつながると考えられます。
コミュニケーションスキル
コミュニケーションスキルは、マネジメントを成功させるために重要な能力の1つです。
組織の目標を達成するには、マネージャーが自分の考えを部下に適切に伝え、相互理解を深めることが必要です。一方的に指示を出すだけでは、部下の納得感を得ることは難しいため、双方向のコミュニケーションが求められるでしょう。
良好なコミュニケーションを築くためには、部下の意見に耳を傾け、彼らの考えを尊重する姿勢が欠かせません。また、普段から話しやすい雰囲気をつくることも効果的とされています。部下が相談や報告をしやすい環境を整えることで、進捗状況を把握しやすくなり、問題が発生した際にも迅速な対応が期待できます。
さらに、積極的に部下に話しかけ、意見を引き出すことで、信頼関係を築くきっかけとなります。こうした関係性が、組織全体のパフォーマンス向上につながるとされています。コミュニケーションスキルを磨くことは、マネージャー自身の成長にも寄与するでしょう。
戦略立案力
戦略立案力も、マネジメントにおいて重要なスキルの1つです。
このスキルは、組織やチームの目標達成を目指し、リソースを適切に配分しながら計画を立てる能力を指します。戦略立案では、ヒト・モノ・カネ・情報・時間という限られたリソースを可能な限り活用するための判断が求められます。
戦略を策定する際には、組織の現状を適切に分析し、目標達成のための優先順位を明確にすることが重要です。例えば、限られた人員や予算のなかでどの業務を優先すべきか、どのような情報を活用して計画を進めるべきかといった具体的な判断が求められるでしょう。
また、計画を実行する段階では、状況に応じて戦略を柔軟に見直す力も必要です。特にプロジェクト管理においては、計画どおりに進まない場合に備え、リスクを見越した調整が期待されます。こうしたプロセスを通じて、組織全体の効率的な運営が可能になると考えられます。
交渉力
交渉力は、マネジメントにおいて不可欠なスキルであり、利害関係者との合意形成を通じてプロジェクトや組織の目標達成を支える役割を果たします。このスキルは、単に自らの要求を主張するだけではなく、相手の立場や利害関係を理解し、双方が納得できる結果を導くことを目指す点に特徴があります。Win-Winの関係を築くことが理想です。
交渉において重要なのは、相手の優先順位や背景を考慮しながら、具体的かつ現実的な提案を行うことです。これにより、相手の協力を引き出しやすくなるとされています。また、交渉プロセスでは、冷静な問題分析力や柔軟な発想が求められます。なかでも不測の事態が発生した際には、迅速かつ適切な対応が交渉を成功に導く鍵となるでしょう。
さらに、交渉力を高めるためには、事前の準備が重要です。過去の交渉事例やデータを活用し、状況に応じた解決策を準備しておくことで、より効果的な交渉が期待されます。このスキルを磨くことで、組織全体のパフォーマンス向上に寄与するでしょう。
課題設定スキル
課題設定スキルは、マネジメントにおいて重要な役割を果たすスキルの1つです。
このスキルは、組織やチームが抱える問題を的確に特定し、解決に向けた具体的な目標を設定する力を指します。適切な課題設定が行われることで、組織全体の方向性が明確になり、メンバーが自身の役割を理解しやすくなるでしょう。
課題を設定する際には、まず組織やチームの現状を適切に把握することが必要です。これには、データや状況分析を通じて問題の本質を明らかにすることが含まれます。
次に、達成可能でありながらも挑戦的な目標を設定することで、メンバーの意欲や達成感を引き出すことが期待されます。また、目標は一人ひとりのスキルや意欲に合わせて調整されるべきです。
課題設定のプロセスでは、目標を適切にメンバーに伝えるコミュニケーション能力も重要です。このプロセスを通じて、メンバー間で目標に対する共通理解が深まり、組織全体の効率的な動きが促されるでしょう。
課題設定スキルを磨くことで、組織の問題解決能力が向上し、持続的な成長が期待されます。
評価力
評価力(アセスメントスキル)は、マネジメントにおいて不可欠なスキルであり、チームやメンバーのパフォーマンスを適切に把握し、成長を促すための基盤となります。このスキルを活用することで、部下の能力や性格、長所を適切に評価し、効果的な育成や支援策を立案できるとされています。
評価を行う際には、定量的なデータだけでなく、部下の意欲や態度といった定性的な側面も考慮することが重要です。
例えば、KPI(重要業績評価指標)を用いた目標達成度の測定や、日々の行動観察から得られるフィードバックを組み合わせることで、より多角的な評価が可能になるでしょう。これにより、部下の課題を特定し、具体的な改善策やトレーニング計画を提示できるようになります。
また、公正な評価を行うことで、部下のモチベーション向上や信頼関係の構築にも寄与するとされています。評価力を磨くことで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
管理職がマネジメントを遂行する方法

組織を管理する管理職は、リーダーとして「人を動かす立場」ゆえに多くのことが求められます。最初にご紹介したとおり、管理職ならではの壁にぶつかることもあるでしょう。中でも自分自身に関する問題は時間が解消してくれるものではなく、管理職自身が意識して向き合うべき問題といえます。
それでは自分自身に関する問題のなかで、最も重要なテーマは何でしょうか? それは「自分の判断軸を明確にすること」です。人は何かを判断するとき、自身の価値観や理念に左右されます。組織の管理者の判断がぶれると部下との信頼関係が築けず、戦略や方針が組織内に浸透できません。
経営上の判断がぶれる=方針が定まらない主な原因は、管理職自身が組織の課題を適切に把握できていないためです。解決策としてはまず、部下にヒアリングして現在の組織の課題を明らかにし、方針に必要な構成要素を全社で共通言語化すると良いでしょう。
また、管理職自身が自己ビジョンを持つことも必要です。なぜなら、そのビジョンが事業の成長を導くエンジンとなり、ビジョンのレベルによって組織のポテンシャルをどこまで引き出せるかが左右されるためです。マネージャーに就いたら、常に部下と交流して組織の課題を把握し、自身の判断軸をはっきりと打ち出しましょう。
おわりに
今回は、マネジメントがもたらす組織への影響と、管理職(マネージャー)の役割および仕事内容についてご紹介しました。経営・組織を管理する管理職には、レベルの高い自己ビジョンを持って判断し、部下を指導する「リーダー力」が求められます。ただし、自己ビジョンのレベルを自ら引き上げることは、たやすくありません。そのようなときはぜひ、リクルートマネジメントスクールの人材育成研修をご活用ください。
人事ご担当者におすすめのコンテンツ
◆無料お役立ち資料
「中間管理職(マネジャー)に関する意識調査【前編】~オーバーワークについての傾向と考察~」
◆管理職のマネジメント特集
「リクルートマネジメントソリューションズの管理職研修・マネジメント研修」
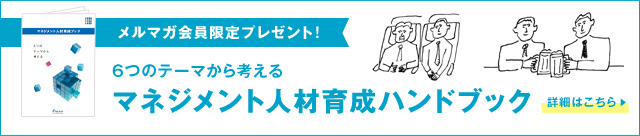
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)