連載・コラム
職場に活かす心理学 第8回
大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 公開日:2014/03/26
- 更新日:2024/05/16

ソチオリンピックが先月行われましたが、メダルへの大きな期待をかけてテレビの前で観戦しながら、本番で力を発揮することの難しさを痛感した方も多かったのではないでしょうか。私たちが直面する結果へのプレッシャーは、オリンピック選手の感じるそれとは比べものにならないかもしれません。それでも、「緊張した」「硬くなった」「プレッシャーに押しつぶされそうになった」経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
今回は、なぜ人は本番で良い結果を出すことが難しいのか、その裏にある心理的なプロセスに着目してみたいと思います。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
自分自身への注目の高まり
大切なとき、本番や成功のプレッシャーがかかるときには、多くの場合、私たちは自分を強く意識すると考えられています。つまり、ある種の自意識過剰の状態になっているといえます。このような状態での心理的特徴を扱った理論にWicklundとDuval (1972)の「客体的自覚理論(Objective Self-Awareness Theory)」があります。この理論では、人が自分を対象として意識することでどのような心理的影響が生じるかについて述べています。具体的には、人は自分を客観的に知覚すると、自分の望む姿とのギャップに気付かされることがあり、その結果、怒りや、失望、悲しみなどのネガティブな感情が喚起されるとしています。そして、その状態を回避しようとしたり、ギャップを埋めようとすると考えられています。この理論をベースとして、ネガティブな自己知覚からの逃避手段としてのアルコール依存や、ネガティブな感情が喚起された結果としての抑うつや不安感などとの関連が研究されてきました。もちろん現実と理想にギャップがなく、ポジティブな感情(ex. 満足、プライド)を感じることもあるでしょうが、多くの研究はネガティブな側面を扱ってきました。
どのようなときに、私たちは自分自身を強く意識するのでしょうか。例えば大きな鏡に自分の姿が映っているのを見たり、大勢の人から自分が注目されているのを感じるときなどに、自分自身への注目が高まるといわれています。
図表01は、Phillip & Silvia(2005)が行った研究結果の一部です。実験参加者は、大きな鏡がある状況(高自覚群)とそうでない状況(低自覚群)に分けられ、自分の理想やあるべき姿と、現在の自分についての評定を行った後、そのとき感じた感情についての評定を行いました。その結果、高自覚群では現在の自分と理想やあるべき自分とのギャップが大きいほど、ネガティブな感情を感じる傾向があったのに対して、低自覚群ではそのような結果は見られませんでした。理想の自分と現実の自分とのギャップは、自分を客観視することで初めてインパクトをもつのだといえるでしょう。
図表01 自分に関する理想と現実のギャップとネガティブな感情の関係性

プレッシャーが自動化された動作や行動に与える影響
重要な場面や成功のプレッシャーがかかる場面では、自分のことを応援してくれるチームメートやサポーターがいるかもしれません。たとえ自分に好意的なサポーターであっても、その存在がプレッシャーを高めることがあることも研究では指摘されています。特に運動や競技の場合、自己を意識すると、理想やあるべき姿に対して自分が十分でないことが気になるのですが、その結果、うまくやろう、失敗しないようにしようとして、十分に訓練されていて普段は意識せずに自然に行えるはずの手作業や身体的な活動を意識してしまい、かえってパフォーマンスが低下してしまうと考えられています。
冒頭でオリンピックのことについて述べましたが、十分なトレーニングを積んだ運動選手のパフォーマンスへの影響はこの典型です。例えばゴルフの達人はパットを打つ際、いちいち自分の動作手順を意識するわけではありません。数多くの練習のなかで、言語化するのが難しいような微妙な力の加減やコントロールを身につけています。ところが緊張したり、ここぞという段になると、自分自身に注目が向いてしまい、自分の動作の一つ一つを意識するようになり、かえってうまく打てなくなってしまうのです。
Beilock, Carr, MacMahon, & Stakes (2002) は、サッカーの経験者と、素人を対象にして、上記のようなメカニズムが生じることを示しました。一定区間のドリブルを行う時間を計測したところ、もちろん全体的に経験者の方が速かったのですが、2つの実験条件の下で、経験者と素人では異なる反応が見られました。1つは自分のドリブルのスキルに注目する条件で、ドリブル中にトーンが聞こえたら、その際に足の外側と内側のどちらでボールに触っているかを言うように求められます。もう1つはドリブルを行いながら、それとはまったく関係のない別の課題を行う条件で、ドリブル中に不定期にさまざまな単語が聞こえますが、そのなかで特定の単語を聞いたときには、その単語を声に出して言う課題を行います。サッカー経験者の場合、ドリブルは通常意識せず行える課題であるため、ドリブルのスキルに注目する条件下で成績が悪くなっていることが分かります。ところが、ドリブルとは関係のない課題を同時に行う場合には、ドリブルのパフォーマンスの低下は起こりませんでした。サッカーが初めての人の場合には、ドリブルを意識して行う必要があるため、いずれの条件でもパフォーマンスに違いは見られませんでした。
図表02 2つの条件下でのドリブル時間の違い

プレッシャーが知的課題の遂行に及ぼす影響
上記のような現象は、動作が自動化されていることによるものですが、そうでない場合はどうでしょう。例えば、数学のテストに臨む場合を考えてみてください。ひょっとするとビジネスの場面ではこちらのようなケースの方が当てはまるかもしれません。問題を解くためには、解き方を考え、それを意識して実行することが大切になってきます。しかも、うまくいかない場合には、解き方を見直して新しい方法を考えなくてはなりません。先ほどのゴルフのパットの例と異なるのは明らかで、自分自身が行っていることに十分注目を向けることが必要になります。
このような状況でプレッシャーがかかると、「テスト不安」が生じるといわれています。うまくできなかったらどうしようという不安ですが、このような不安は、テストの解答に向けるべき注意をそいでしまうことが研究の結果から分かっています。そしてそのような注意の散漫は、思考を十分に働かせることが必要な課題の遂行レベルを低下させてしまうのです。
Beilock, Kulp, Holt, & Carr(2004)は、数学の問題を用いて、十分に練習された問題を解く場合(繰り返し練習した問題)と、同じ解き方を適用できるものの新たな問題を解く場合(初めての問題)の正答率の違いを検討しました。その結果が図表03に示されています。繰り返し練習した問題の場合は、プレッシャーの影響は出ていませんが、初めての問題の場合、プレッシャーのかかる状況下では、正答率が低くなっています。問題の難しさはどちらも同程度なのですが、繰り返し練習した問題の場合は解答がほぼ自動化されているためあまり考える必要がなく、プレッシャーの影響は出ないと考えられます。一方、初めての問題の場合はその場で解法を考えて試してみるという認知的な負荷のかかる活動を行うため、プレッシャーの影響が出たと考えられます。
図表03 繰り返し練習した問題と初めての問題における正答率の比較

以上のように、プレッシャーの下で十分に力が発揮できない現象には、主として2つの心理的なメカニズムが存在すると考えられています。前者は行っている課題に注意が向きすぎて、後者は行っているもの以外に注意が向いてしまって、課題の遂行が阻害されています。
例としては運動と勉強を挙げましたが、もちろん、運動であっても実施中に戦略を見直すなど、思考を必要とする競技もあるでしょう。またテスト問題を解くときでも、計算や漢字の書き取りなど、かなり自動化されたプロセスもあるかもしれません。Beilockらが数学の問題を用いて行った研究でも、繰り返し練習した問題でプレッシャーの影響が出なかったのは、計算が自動化されていたためであると論じています。どのようにプレッシャーの影響が生じるかは、課題そのものというよりも、その遂行が自動化されているか、あるいは遂行に十分な注意を向ける必要があるかによって、決定されると考えられます。
仕事で大切なプレゼンテーションがあったとして、時間どおりにシナリオをしっかり組んで、練習まで行って臨もうとしています。そして、本番の直前に、上司から癖のあるフレーズを使わないように指摘されたとします。この場合、指摘されたフレーズを使っていないかが気になり、せっかく練習した言い回しや間合いのとり方などがうまくいかなくなるかもしれません。これは、自分の行動に過剰に意識が向いてパフォーマンスが低下している場合です。一方で、自分はプレゼンテーションが苦手だという認識があり、十分に練習したにもかかわらず不安感が高まった結果、何をしゃべるかを忘れてしまった場合は、プレゼンテーション以外のことに注意が向いた結果、パフォーマンスが阻害された場合です。
自分への注目の効用
ちなみに、冒頭で客体的自覚理論の話をしましたが、自覚には主体的自覚もあるといわれています。主体的自覚とは、認識の対象として自分自身に注意を向けるのではなく、主体として自分が経験していることに注意を向けることだとされています。自分の経験を楽しんだり、その経験からくる感情や思考を十分に“味わっている”ときは、主体的自覚の状態にあります。フロー状態にあるとき、何かに熱中していて他のことに気が付かないようなときには、かなり強い主体的自覚状態にあると考えられます。十分な注意を必要とする課題を遂行する場合には、主体的自覚が強まった状態の方が望ましいといえます。
最近「マインドフルネス」という言葉で、ポジティブな意味での主体的自覚が研究されています。「マインドフルネス」とは、自分が現在経験していることに、強く注目し、認識している状態であるとされており、これも強い主体的自覚状態の1つといえます。ある研究では、この「マインドフルネス」の程度の個人差と、その日の「マインドフルネス」の状態を測定し、これらと自分が自立的であると感じる程度やネガティブな感情を感じる程度との関連を検討しました。その結果、個人特性としても、またその日の状態としても「マインドフルネス」が高い方が、自立性を感じる程度は強く、ネガティブな感情を感じる程度は弱くなりました。つまり、今の経験に十分にコミットして取り組んでいる人の方が、自分の自立性を感じられるし、ネガティブな感情を経験しないということでしょう。本連載の第1回で、幸福感を持続させるためのコツは、自分で自立的に何かに取り組み続けることであることを示唆する研究を紹介しましたが、それとも符合する結果といえるでしょう。
客体的な自覚についても、プレッシャーの下では自動化された行動を阻害する可能性があることを述べましたが、状況によっては課題の遂行に重要な役割を担います。例えば、客体的な自覚がなくては他者の視点を取得したり、自分の行動を制御したり、プライドを感じることができないといわれています。自分を客観的に振り返ることは、自分を成長させるための第一歩になるでしょう。
Duval & Silvia(2002)の行った実験では、客体的自覚状態にある場合で、失敗をしたとしても改善の見込みがあると思うときには、失敗の原因が自分にあると考えますが、客体的自覚状態にない場合には、改善の可能性の高低にかかわらず失敗の原因を自分に帰する傾向は見られませんでした。失敗は自尊心を低めるため、決して快いものではないのですが、それに向き合い、自分ごととして改善する気になるかどうかは、客観的に自分を見つめられるかにかかっているとも解釈できるでしょう。
図表04 自己認識レベル別 自分への失敗原因帰属と改善可能性の高低との関係

良い結果を残したいという意欲が高い状態にありながら、なぜプレッシャーがかかるとうまくいかなくなるのか、といった素朴な疑問から、それに関連すると思われる心理学の研究をいくつか紹介しました。運動だったり勉強だったりと、研究での題材は仕事の場面とは一見関連性の低いものが多くなりましたが、そこから得られる知見には仕事の場面で活用できるものもあるでしょう。プレッシャーがかかると、私たちはある種、自意識過剰な状況に陥る傾向があります。その結果として、誤った、あるいは普段と異なった注意の配分を行ってしまうのです。会社で重要な意思決定を行っているとき、決定の妥当性よりも自分がどう評価されるかが気になったりしてはいないでしょうか。このまま作業をやり続ければ納期どおりに終了するはずが、失敗できないとの不安から無駄にやり方を見直したりしていないでしょうか。
後半で述べたように、客体的自覚と主体的自覚はそのいずれもが場面に応じて必要になります。ところがそれをうまく制御する方法は、確立されているわけではありませんし、制御が難しい場面も多々あると予想されます。私たちができることは、自らの行動を振り返り、自分がどんなプレッシャーの下で、どのような行動や思考をする傾向があるかを把握すること、さらにそれを他者と共有することで、客体的自覚の精度を高めることなのかもしれません。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

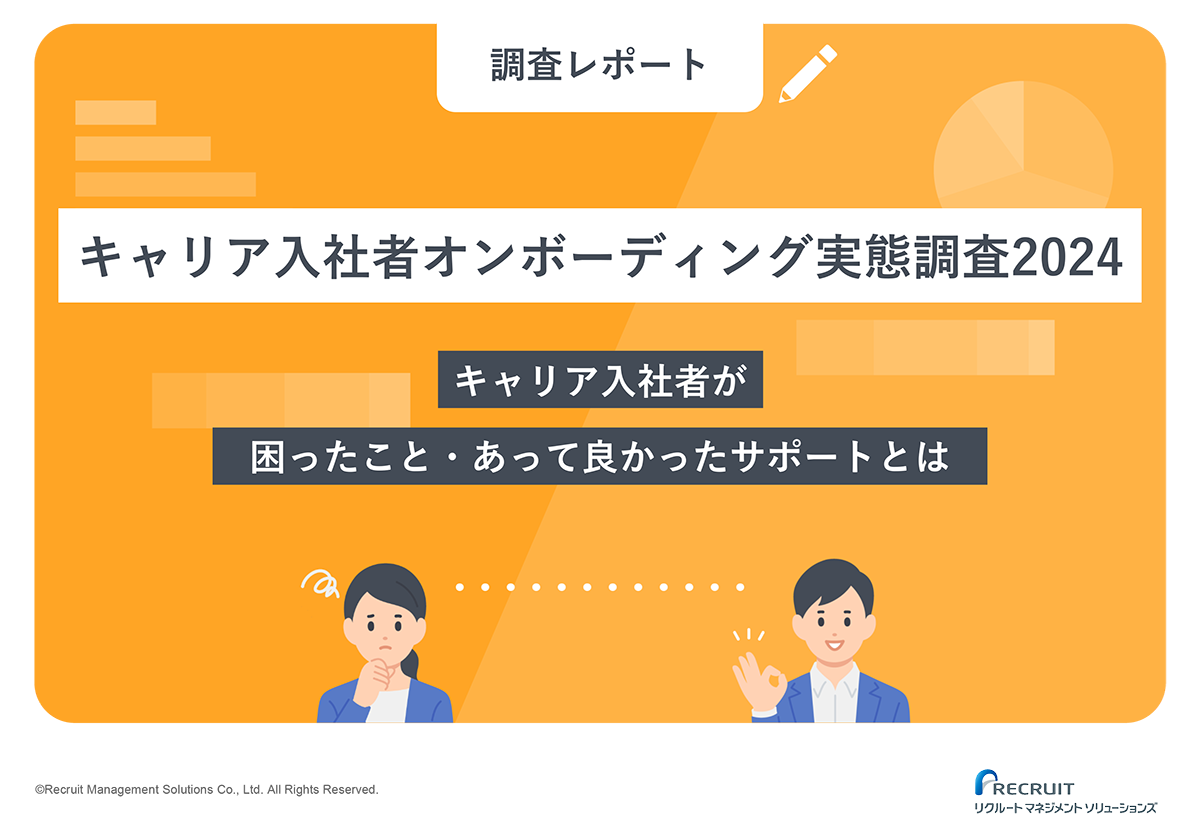
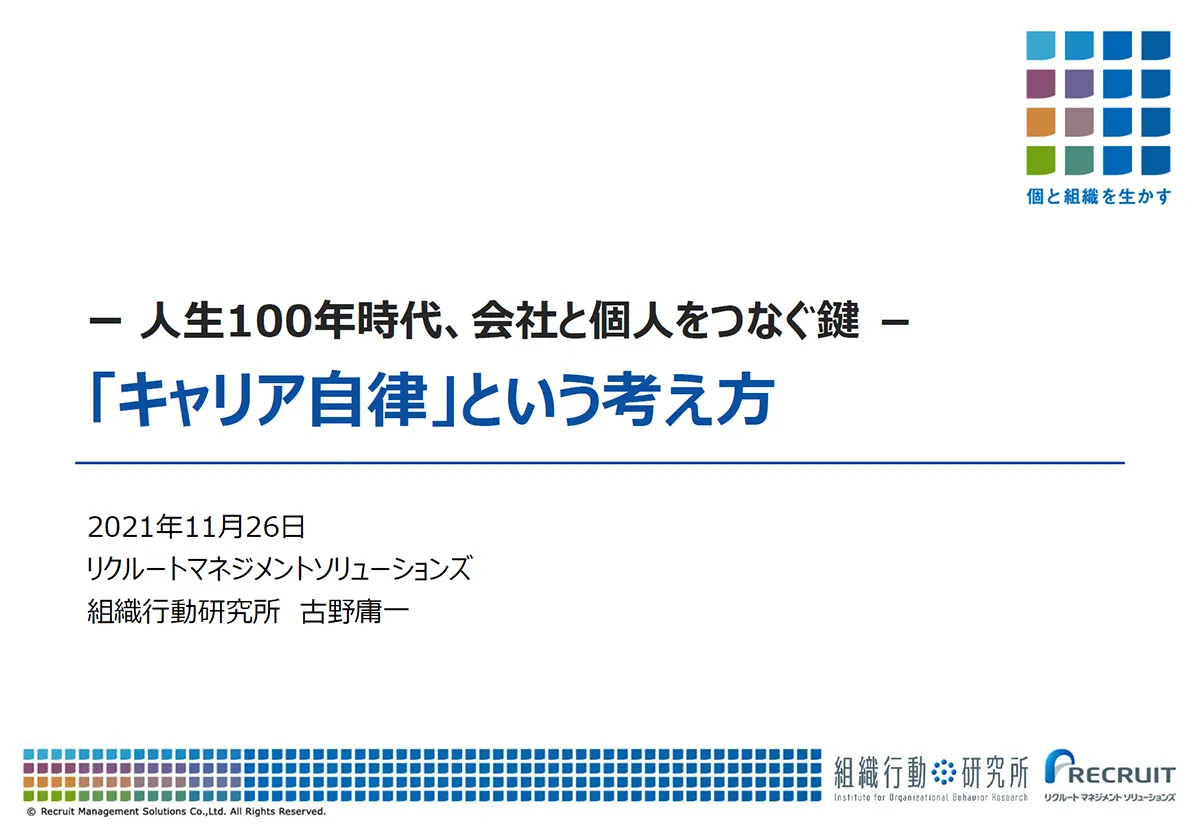
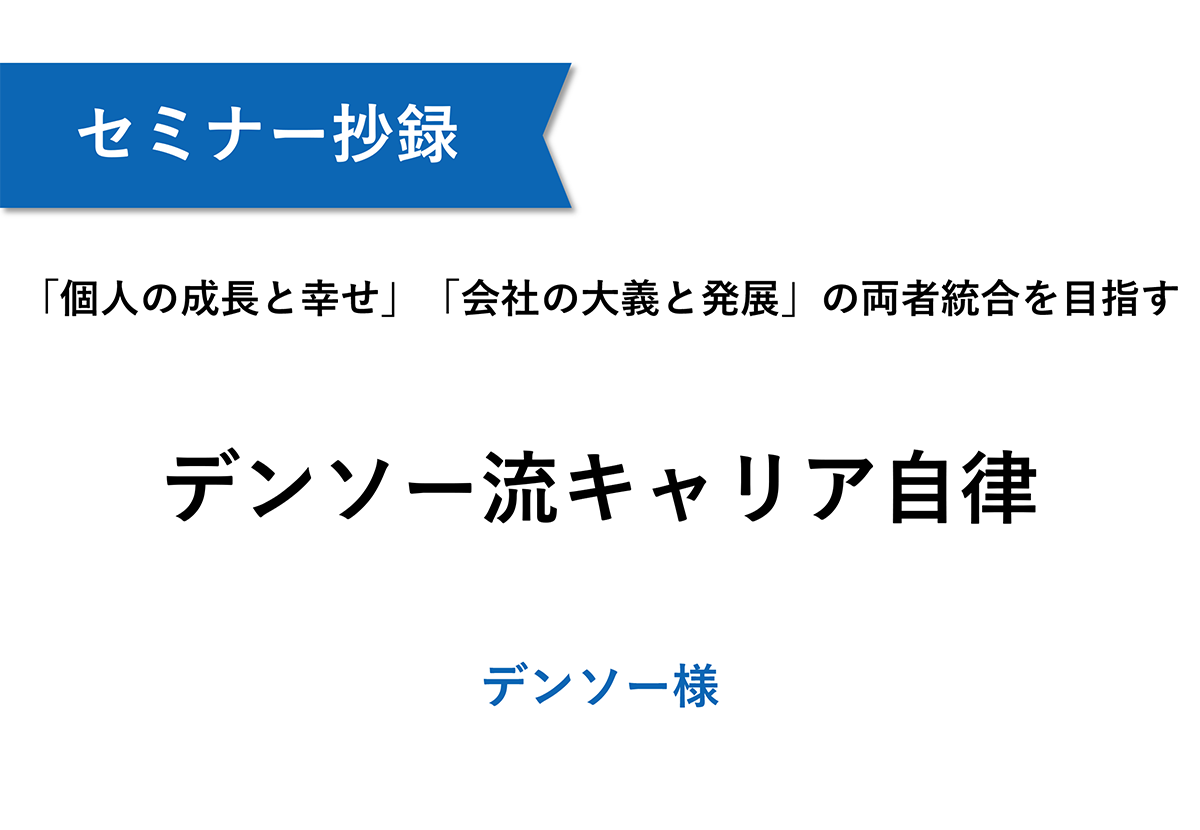









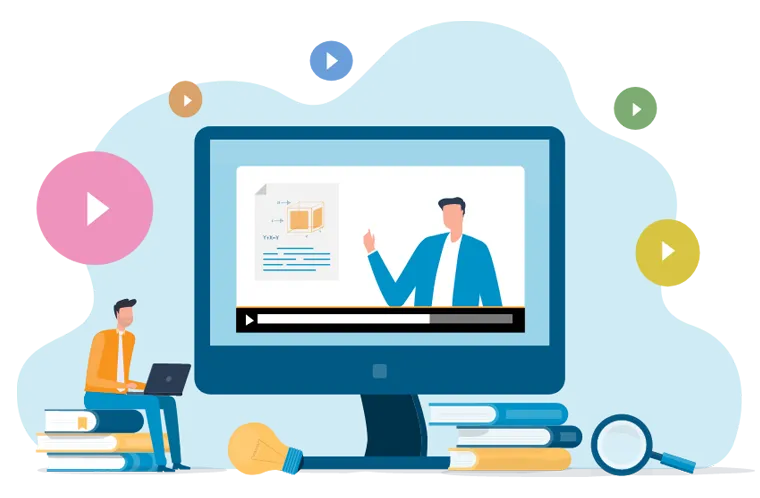 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての