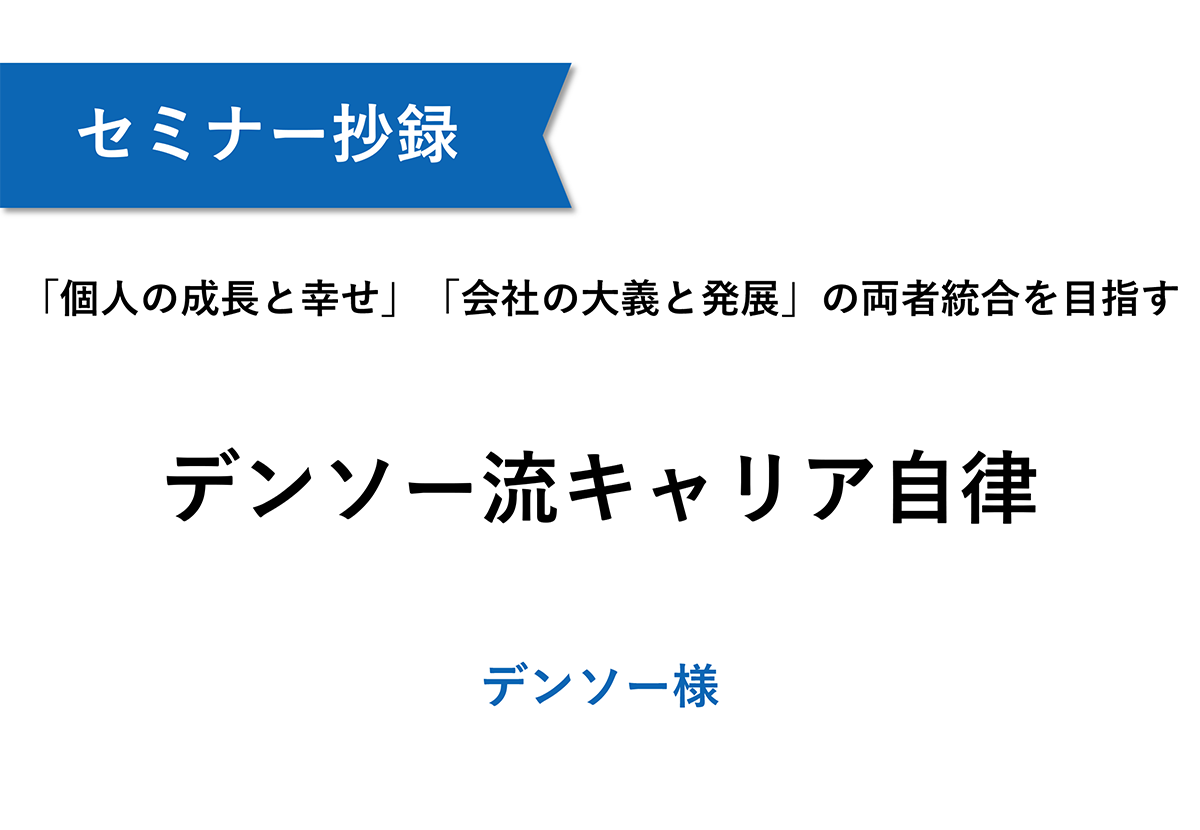- 公開日:2014/01/22
- 更新日:2025/06/25

最近、多くの企業が、自律的に動ける人材を求めるようになっています。ビジネスにおいて仕事の専門性が増したり、環境変化のスピードが速くなったり、より細やかな対応が求められるようになると、現場の一人ひとりが自分で考えて、自律的に動ける組織の方が望ましいことは容易に想像できます。これまでの日本企業が強みとしてきた、統制のとれた、計画をしっかりと実現できる組織で求められてきた従業員のイメージとは、ずいぶん異なるといえるでしょう。
人事の方から「新人や若手が自律的に動けるような育成を考えたい」「部下の自律を活かすマネジメントを管理職に学ばせたい」とご相談をいただくことや、自律を促進させるために1on1などの施策を導入する事例も増えてきています。
そこで、「自律的に動く」とはどういう現象であるのか、またどのようにすれば人は自律的に動くようになるのか、などについて、関連する心理学の知見を参考に考えてみます。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
自律的に動くとは?目標意図と実行意図
ここでの自律は、自分の考えや意思を持って、選択や意思決定を行ったり、行動したりすることを指します。人が「自律的に動く」という現象は、大きく2つの要素に分解して考えることが可能です。Gollwitzerは、ある目標や目的に向けて人が行動を起こすときには「目標意図(goal intention)」と「実行意図(implementation intention)」の2つの意図が作用するとしています。
目標意図とは、自分が成し遂げたいことを特定するものです(私は○○を実現したい!)。実行意図とは、ある目標を達成するための行動をいつ、どこで、どのようにとるかをあらかじめ決めているものです(もしAという状況になったら、私はBの行動をとろう!)。これら2つの意図は独立しており、目標意図があっても実行意図が存在しない場合があります。「やろうと思えばできるのだが…」「やりたいことはあるがやり方が分からない…」という発言が聞かれるのは、そういった場合です。
逆に、「自分に与えられた仕事をやろう」というときには、目標意図はあまり強くなく、自律的な目標設定とはいえません。そして最も効果が高いのは、しっかりとした目標意図と、その実現に向けた実行意図が共にあるときだということが、実証的に示されています。
図表01 実行意図と目標意図の強さと行動の関係

出所:Paschal Sheeran, Thomas L. Webb, & Peter M. Gollwitzer(2005
ちなみに、私たちはかなえきれないほどたくさんの願いをもつといわれています。大金持ちになりたい、世界一周旅行をしたい、高校時代に戻って人生をやり直したい、モデルのような体型になりたい、社長になりたい、など。その中で私たちは実現に向けた目標を目標意図として選択しているのです。それでは、私たちはどのようにして、自らの目標を選択・設定するのでしょうか。
私たちが自分であるものや状態を目標とする場合、それは自分にとって何らかの望ましい価値をもつ必要があります。加えて、その目標を達成できる可能性を少なくとも自分自身は信じられる必要があるのです。これをバンデューラは自己効力感と呼んでいて、多くの実証研究において、自己効力感は人が行動を起こす際の重要なキーになることが分かっています。この点で目標は、実行可能性をあまり問題にしない願いとは異なります。
数多くの願いのなかから特定の目標を選択するときには、自分は無理だと思うことには手を出さない、という至極常識的な結論が導かれるのです。しかし実際のところ、選択肢が多かったり、価値判断が難しかったり、実行可能性が不透明だったりするため、特にキャリアの選択など大きなものになると、かなり悩んでしまうことになります。
【無料動画セミナー】
自律的に考え、行動できる組織づくりに向けてマネジャーに求められることとは?
メンバーの自律を促すこれからのマネジメント
仕事における自律的な目標設定
これまでは、一般的な「自律して動く」ことについて考えてきましたが、仕事における目標意図とは何でしょうか。組織に属して働く人の場合、仕事で何を実現するかの目標は、多くの場合、組織から与えられます。与えられた目標を、自分のものとして目標意図をもつことはもちろん可能ですが、現在の組織が社員に求める「自律的な動き」を考えると、目標を与えられなくても、自分で目標を設定することが必要になります。
上で述べたように、自ら目標を設定するためには、価値を感じる目標を選ぶこと、それを実現できると思うことが必要となります。
営業のAさんの例
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aさんはこれまでソフトウェアの営業を行ってきました。初期の頃は商品に関する知識をつけ、お客様のニーズをきちんと捉えて、妥当な商品を勧めることで、営業の目標達成を目指してきました。最近は、あまり苦労しなくてもそれなりの成績があげられるようになりました。そろそろ管理職に上がるタイミングを迎えており、上司からもそれに向けた指導を受けるようになっています。
一方でAさんは、1つのソフトウェアだけでは簡単に解決できない問題について、お客様から相談を受けることが多くなり、自分の力不足を感じています。そこでAさんは営業としてもっと力をつけたいと思うようになり(目標の価値)、より難しい問題を解決できるようになることを決心します(目標意図)。
Aさんは、自分にはプログラムを開発する知識も経験もないものの、営業として現場のことはよく分かっている自信があるため、複数のプログラムの組み合わせによる対応や、プログラムのマイナーな変更を開発部門に相談することで、何とか問題が解決できそうに思っています(実現可能性)。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
一般に意識的に目標をもつのは、選択を迫られたり、変化を志向したり、難しい状況におかれたときが多いと考えられます。このケースの場合、Aさんは組織や上司からの「良い管理職になってほしい」という期待に応えるためではなく、「営業としての自分の力を伸ばしたい」という欲求から、目標意図をもちます。
もちろん「管理職として活躍すること」を目標意図にすることも可能ですが、その場合、自分はどのような活躍をしたいのかということを、Aさんは考えなくてはなりません。重要な点は、Aさんが自分で「こうすると決めた」ということが自律的な目標設定だということです。自律的な目標設定は、多くの良い点をもっています。
自律的な目標設定の効用
自分で目標を決めると、その目標へのコミットメントが高まることが分かっています。Howard J. Kleinら(1996)が80を超える研究をまとめた結果、目標へのコミットメントの最も重要な先行要因は、自分で決める、あるいは自分がかかわって決めるというものでした。さらに彼らは、目標へのコミットメントが高い方が、難しい目標であってもパフォーマンスをあげることができると論じています。
図表02 目標へのコミットメントの高さとパフォーマンスの関係
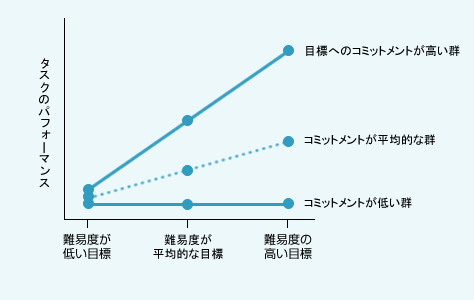
出所:Howard J. Kleinら(1996)
日本の中高年ホワイトカラーを対象に、中年以降の仕事でのつまずきをどう乗り越えるかを研究した結果でも、同様のことが示唆されています(今城・藤村 2013「中年期ホワイトカラーのキャリア停滞からの復活プロセス」)。自分で選んで始めた以上、多少のことではあきらめないため、より高い成果がもたらされると考えられます。
また、自分で決めた目標であることに加えて、自分自身との関連性が強い目標の場合は、ネガティブなフィードバックを受けた後、一層やる気が高まることも実験で示されました。 JC. Brunstein & PM. Gollwitzer(1996)が医学部の学生に行った実験で、医者として必要な能力の測定であるといわれて受けたテスト(関連あり群)では、1度目の失敗のフィードバックの後、2度目の成績が上昇しました。一方、医者としての能力とは関係のないテストとして問題を解いた場合(関連なし群)、1度目の失敗のフィードバック後は、2度目の成績が低下しました。
図表03 フィードバック内容によるテスト成績への影響

出所:JC. BrunsteinとPM. Gollwitzer(1996)をもとに作成
仕事の負荷が高く、裁量が小さいといった、一般にストレスを高めるような条件下でも、自分で決めた目標を追っており、それを達成できるとの信念をもつことで、仕事への満足感は11%上昇し、気分の落ち込みは12%軽減するとの研究報告もあります(Pomaki, Maes, & Doest, 2004)。
つまり、自分で設定した目標を追求することは、やる気を高め、うまく進まないときの耐性を高める効果が期待できるのです。
【おすすめの研修】
中堅社員研修
さまざまな目標の性質
同じ状況に置かれていても、設定される目標の内容や難しさは人によってまちまちです。価値を感じる対象や、自分の成功の見込みは、その人の過去の経験に左右されます。過去に、ある目標を達成した結果、高い満足感を得たり、自分にとって価値が高いと感じられたりした場合は、未来の目標設定の際も、同様の目標を立てようとすると考えられます。一方で、組織で働いている以上、自分の目標と組織の目標がうまく合っている場合の方が、望ましい結果が得られると考えられます。
仕事と組織の目標のすり合わせ
Hyvonenら(2009)は、フィンランドで、25~35歳の若手の管理職を対象に個人的な仕事の目標に関する研究を行いました。結果は、自分の能力向上が最も多く(30.5%)、続いて昇進(23.7%)、幸福(15.2%)、転職(13.7%)、安定した仕事(7.4%)、組織の目標(5.6%)、自分の収入(3.9%)となりました。さらに、組織の目標を自分の仕事の目標にしている人は、仕事へのエンゲージメントが最も高く、仕事による疲労感が少ないことが、一方、安定した仕事や転職を自分の仕事の目標にしている人は、仕事へのエンゲージメントが低く、仕事による疲労感が高いことが示されました。
組織が個人に自律的な目標設定を求める場合には、その目標が社員個人の価値観や過去の経験からもたらされることを念頭に、組織の目標と社員の自律的な目標をうまくすり合わせることが重要だといえます。
目標のレベルの個人差
目標は内容が異なるだけでなく、そのレベルにも個人による違いがあります。どの程度難しい目標を個人が採用するかは、結果の望ましさと、成功確率の高さによって決定されると考えられます。高い目標を達成することに価値があると感じ、頑張ればその目標が達成できると思えば、チャレンジングな目標を設定します。どちらか一方がなければ、高い目標は設定されません。
自己効力感の概念を提唱したバンデューラは、過去難しい目標に挑戦して成功した経験が、本人の効力感を高め、より高い目標に向かわせると論じています。社員に高い目標を持ってもらうためには、仕事での成功経験が必要だと言えます。
自律的な目標の決定は、自律的な行動への第一歩です。組織からの要請に従うだけでは、個人が自律的に目標を設定できる程度に限界があります。一方で、個人の側から見たときには、組織のなかで働いている以上、組織の目標とすりあっていた方が、自律的な目標の達成可能性は高まります。つまり、自律的に仕事の目標設定を行わせても、個人の目標設定における価値観が組織のそれと大きくずれておらず、かつ本人に十分な仕事の経験と知識が備わっているなら、組織が心配するほど組織の目標に反する目標にならないのかもしれません。
実行意図の重要性
目標意図だけでなく、どのようにしてその目標を達成するかといった実行意図がしっかり考えられている場合の方が、よい結果が得られることが分かっています。前に述べたように、実行意図とは、「Pだったら、Qを行おう」といった言葉で表現され、どのようなときにどのような行動をとるかをあらかじめ決めておくことです。Gollwitzer & Sheeran(2006)は、実行意図を形成することで、行動を起こすべきタイミングを逃すのを防いだり、新しい行動の獲得を阻害したりするような習慣化した対応や考え方をブロックする効果があるとしています。
図表04 前の試合時のパフォーマンスと比較した今回のパフォーマンス(意図条件による違い)
.gif)
出所:Anja Achtziger, Peter M. Gollwitzer, & Paschal Sheeran(2008)
Anja Achtziger, Peter M. Gollwitzer, & Paschal Sheeran(2008)は、テニスの選手を対象に、フィールド実験を行いました。目標意図の条件では、「一球一球に集中し、全力でプレイし、試合に勝つ」といった目標をもつよう操作が行われ、実行意図と目標意図の条件では、目標意図の操作に加えて、試合中に感じるネガティブな感情や思考について例えば「もし、怒りを感じたときには、自分自身を落ち着けて、自分は勝てる、と唱える」などの実行意図を獲得する操作を行いました。結果的に、実行意図をもった選手は、前の試合と比べてパフォーマンスが上昇したことが示されました。
目標意図だけで、実行意図が伴わない典型的なパターンに、「○○すべきだと思うが、やり方が分からない」といったことがあるでしょう。通常、目標意図は実行可能性を感じることで初めて意図となるため、実際には目標意図も固まっていない可能性があります。ただしここでは、目標意図はあるのに、実行意図が伴わない場合のことを考えてみます。
キャリアのステップアップを考えるBさんの例
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bさんはキャリアのステップアップのために、英語を勉強して2年後の異動で海外駐在のポジションに就きたいと考えています(目標意図)。そのためには、英語の勉強をする必要があるのですが、仕事が忙しく、思うように進みません。
Bさんの場合は、上手に実行意図を形成することで、目標に向けた活動が前進する可能性があります。例えば、通勤中やちょっとした時間ができたら、毎日10個ずつ単語とそれを含む例文を覚えること、1カ月後に単語集が終了したら、覚えた単語を使った文章を1つずつ、毎日10単語分作成すること、など、細かくスケジュールを決めます。あるいは、どうしても仕事が忙しく、ノルマが達成できなかった場合は、週末に遅れを取り戻すというルールを自分に課すことなどが考えられます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
目標意図は、自律的に決めたほうが、効果が高いことを述べましたが、実は多くの実行意図の研究からは、与えられた実行意図を用いる場合が多いことが分かっています。ただし、一方的に知識を教えてもらうのではなく、自分がつまずきそうなポイントを予想した上で、対処法を教えてもらうことが必要だと思われます。Bさんのケースでは、時間がないといった阻害要因に対して、効果の期待できる実行意図を挙げましたが、これが実行を阻害する理由でない場合には、あまり効果的ではないでしょう。
効果的な実行意図をもつためには、なぜ、どういったときに実行が阻害されるかを自分自身がある程度認識することが必要です。その結果、新しい阻害要因が出てきたり、実行意図が効果的でなかったりしたときに、自分で軌道修正することが可能になるでしょう。
さいごに 企業が「自律的な人材」に求めること
最後に、これまでは触れませんでしたが、企業が「自律的な人材」に求めているのは、単に自律的に動くことだけではなく、企業も気づかないような質の高い目標をもって、それを実行することです。そのためには、ここまで述べてきた自律的に動くという範疇を超えて、従業員の専門性やスキル、問題意識の質を高める必要があります。
一方で、現場に出て仕事をしている人がもっている視点には、有効なものが多く含まれているはずです。ひょっとすると、スーパースターではなく、組織で働く一人ひとりの従業員の自律性が、思いのほか、組織の力を強める可能性もあるのではないでしょうか。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)