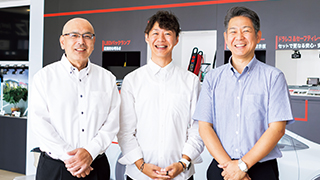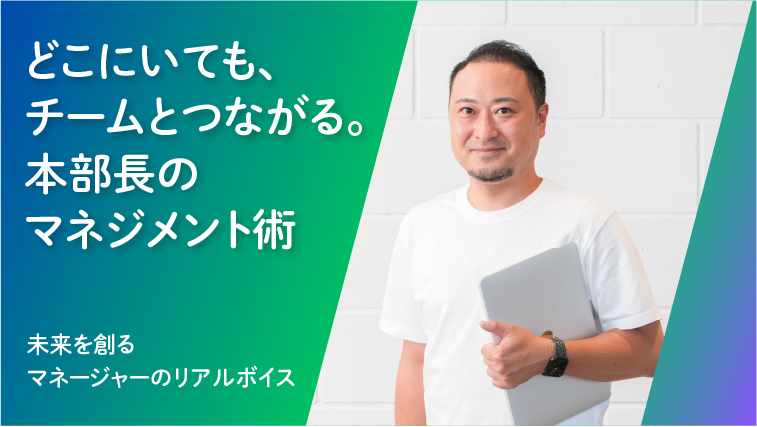用語集
ロジハラ(ロジカルハラスメント)とは? 意味・具体例・対処法を解説
- 公開日:2025/11/04
- 更新日:2026/01/20
業務上の正論が、時として相手を精神的に追い詰める場合があります。
論理的には正しい指摘であっても、人を傷つけるコミュニケーションは「ロジハラ(ロジカルハラスメント)」と呼ばれ、職場での新たなハラスメントとして注目されています。
職場で健全な関係を築くためには、こうしたリスクを理解し、適切に対処することが求められます。
本記事では、ロジハラの定義や具体例、発生しやすい場面、予防・対処のポイントについて解説します。
ロジハラとは

「ロジハラ(ロジカルハラスメント)」とは、正論を使って相手を精神的に追い詰めてしまう言動のことを指します。
内容自体は間違っていなくても、相手の気持ちや状況を無視して一方的に押し付けることで、強いストレスや不快感を与えてしまうのが特徴です。
また、過度に論理的な説明を求めることで、相手を追い詰めてしまうケースもロジハラに含まれます。
特に職場では、立場が上の人が部下や同僚に対して行うことが多く、パワハラの一種として扱われるケースもあります。
「正しいことだから問題ない」と思い込むと、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうことがあるため、注意が必要です。
ロジハラは、相手の萎縮や自信喪失のきっかけにもなり得ます。
周囲との関係がぎくしゃくするだけでなく、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。
正論を伝える際には、言い方やタイミング、相手への配慮が一層重要です。
ロジハラが発生しやすい業務場面と具体例
職場では、ふとしたコミュニケーションが「ロジハラ」につながることがあります。
特に注意したい場面は以下のとおりです。
- 部下への業務指導やフィードバック時
- 会議・ミーティングでの意見交換や議論中
- 業務ミスやトラブルが発生した際の対応
- 社内での情報共有や報告・連絡のタイミング
- 取引先とのやり取りや交渉が発生した際
部下への業務指導やフィードバック時
立場の優位性を背景に、正論で部下を精神的に追い詰めてしまう場面は、ロジハラが起こりやすい状況の1つです。
指導や注意が本来の目的を逸れて、部下のプライドを傷つけたり、過剰に責める内容になったりすることがあります。
具体例:
- 「その提案の費用対効果を数値で示してください。感覚的な判断では承認できません」
- 「その判断に至った論理的なプロセスを教えてください。直感では業務は進められません」
こうした発言は、本人にとっては「正当な指導」のつもりでも、受け手にとっては追い詰められたように感じてしまうことがあります。
会議・ミーティングでの意見交換や議論中
会議中のやり取りにおいても、過度に論理性や根拠を求めることで、相手を追い詰めてしまう言動は、ロジハラと受け取られる可能性があります。
その結果、議論が活性化するどころか、場の空気が硬直し、発言しづらい雰囲気をつくり出してしまいます。
具体例:
- 「その意見はあなたの感想にすぎません。根拠を示してください」
- 「その企画はロジックの前提が欠けています」
冷静な指摘であっても、言い方や伝え方次第で相手を萎縮させることがあります。
業務ミスやトラブルが発生した際の対応
トラブル対応の場面では、原因の究明や再発防止が求められます。しかし、ミスをした相手を責め立てるような論調は、ロジハラにつながる恐れがあります。
特に、感情を交えた断定的な発言は、職場での信頼関係を損なうきっかけとなり得ます。
具体例:
- 「これまで何度か同様のミスがありますが、改善のために具体的な取り組みは行っていますか?」
- 「AIなどを活用すれば防げる方法はいくらでもあるのではないでしょうか?」
ロジカルで正しいことを追求するのではなく、相手がそう考えた背景を探ったり、指摘ではなく一緒に考える姿勢を見せるなどの工夫をして、相手に受け入れられやすい発言にすることが重要です。
社内での情報共有や報告・連絡のタイミング
チャットやメールなどの社内コミュニケーションでは、口調や意図が伝わりにくいため、正確性を求めるあまり細かい指摘や詰問が続くと、報告する側に強いプレッシャーを与えてしまうことがあります。
結果として情報の共有が滞ると、組織にとって大きなリスクとなります。
具体例:
- 「結論をYESかNOで伝えてください」
- 「1週間ほど経過していますが、いつ完了しますか?」
取引先とのやり取りや交渉が発生した際
取引先との関係においても、ロジハラ的な言動が起こる場合があります。
発注側の立場を利用して、必要以上に厳しい言葉を投げかけたり、責任を一方的に押し付けたりする行為は、単なる交渉の範囲を超えたハラスメントと受け取られることがあります。
ビジネス上の交渉では、冷静で丁寧な言葉遣いと相互理解が不可欠です。
職場でのやり取りは、内容が正しくても伝え方次第で相手を傷つける可能性があります。
ロジハラは、気づかないうちに誰もが加害者にも被害者にもなり得る問題です。
そのため、相手の立場や感情に配慮した伝わりやすいコミュニケーションを意識することが重要です。
ビジネスコミュニケーション研修
ハラスメント対策の基本 ~管理職として押えておくべき知識~(240)
ロジハラをしてしまう人にみられる傾向と特徴

ロジハラをしがちな人には、いくつかの共通した傾向があります。
- 他者より優位に立ちたがる
- せっかちで早く物事を動かしたい
- 共感力や想像力が不足している
本人に悪意がなかったとしても、言動の背景にある心理や行動パターンが原因となって、相手を傷つけ、職場の空気を悪くしてしまうことがあります。
他者より優位に立ちたがる
ロジハラを行う人は、議論や意見交換において勝ち負けにこだわる傾向がみられることがあります。論理的な正しさを重視するあまり、相手を言い負かしたり論破したりしないと自分の意見が通らないと思い込んでしまうのです。
このような思考パターンは、「きちんと筋道を立てて説明すれば相手は必ず理解するはず」という真面目な姿勢の表れでもありますが、結果的に相手を追い詰める形になってしまいます。
また、論理的であることに強いこだわりを持つため、感情的な反応や直感的な判断を受け入れにくく、相手が納得するまで説明を続けようとする場合もあります。
この傾向が強い場合、指摘や説明がいつの間にか一方的で執拗なものになってしまい、相手の萎縮や反発を引き起こすことがあります。
せっかちで早く物事を動かしたい
ロジハラを行う人は、効率性を重視し、物事を早く進めたいという気持ちが強い傾向があります。「論理的に考えれば答えは明確なはず」「なぜすぐに理解できないのか」といった思いから、相手に対して性急な理解や判断を求めてしまうのです。
このタイプの人は、仕事に対して真面目で責任感が強く、成果を出すことに熱心である一方で、相手のペースや理解度に合わせることは苦手な場合があります。
結果的に、「早く結論を出してください」「もっと効率的に考えてください」といった発言で、相手にプレッシャーを与えてしまいます。
本人は「業務を円滑に進めるため」と考えていても、相手の思考プロセスや状況を十分に考慮せずに論理的な回答を急かすことで、それは相手を追い詰める"効率性の押し付け"となり得ます。職場では、論理的であることと同時に、相手のペースや状況に配慮したコミュニケーションを取ることが重要です。
共感力や想像力が不足している
ロジハラ傾向のある人には、他者の立場や感情を想像する力、いわゆる共感力が不足しているケースがあります。
相手の状況や気持ちを考慮せず、自分の論理を優先することで、無意識のうちに相手を追い詰めてしまうのです。
「事実を伝えただけ」「悪気はなかった」といった言い分も、受け手には伝わりません。
言葉は内容だけでなく、伝え方の工夫や配慮があってこそ、相手に届き、人を動かす力を持つことを理解する必要があります。
ロジハラを防ぐために押さえておきたい3つのポイント
「ロジハラ(ロジカルハラスメント)」は、誰もが加害者になり得る可能性のある行為です。
論理的であること自体は問題ではありませんが、相手の感情や立場を無視した言葉遣いや態度は、相手を追い詰める要因となり得ます。
そのため、日常のコミュニケーションでは、意識的に「ロジハラを避ける姿勢」を持つことが重要です。
ここでは、職場でロジハラを防ぐために意識したい3つのポイントをご紹介します。
ポイント①:主張と配慮を両立するアサーティブな対話を意識する
アサーティブ・コミュニケーションとは、自分の意見や気持ちを適切に伝えながら、相手の立場や感情も尊重する対話方法です。
一方的な主張や押し付けではなく、「私はこう思いますが、あなたはどう感じますか?」のように相手に問いかける姿勢を取ることで、お互いの理解が深まりやすくなります。
こうした対話は、心理的安全性の高い職場環境づくりにもつながります。
ポイント②:誤解や圧迫感を与えない言葉選びを心がける
内容が正しくても、言葉がきつすぎたり、表現が過度にストレートだったりすると、相手にプレッシャーを与え、ロジハラと受け取られる可能性があります。
特に、他人の前で断定的に指摘する場合は、相手の尊厳を傷つけるリスクがあります。
言葉のトーンや場の雰囲気に配慮することが、円滑で建設的なコミュニケーションの鍵となります。
ポイント③:相手の意見や感情を否定せず、受け止める姿勢を持つ
ロジハラを防ぐためには、まず相手の話にしっかり耳を傾けることが大切です。
発言の正誤よりも、「そのように感じた」という相手の感情を受け止める姿勢が重要です。
意見が異なる場合でも、否定から入らず「そのような考え方もあるのですね」と共感を示すことで、対話の空気が和らぎ、建設的な議論につながります。
※関連研修:アサーティブ・コミュニケーション研修|誠実で率直な伝え方を習得するコミュニケーション研修
ロジハラを受けた際の対処法
ロジハラ(ロジカルハラスメント)は、受け手に大きな精神的負担を与えることがあり、放置すると心身への深刻な影響につながる可能性があります。
ここでは、ロジハラに直面した際に取るべき、実践的かつ現実的な対応策を紹介します。
関係を深めすぎず、適切な距離感を保つ
まず意識すべきは、ロジハラを行う相手との適切な距離感です。
業務に支障のない範囲で、必要最低限のやり取りにとどめることで、不要なストレスを避けられます。
相手との接点を過度に持たず、感情的な影響を受けにくい関係を維持することが、自己防衛の第一歩となります。
信頼できる上司や人事に相談する
1人で抱え込まず、信頼できる上司や人事部門に相談することも大切です。
相談する際は、具体的な発言内容や対応状況、感じた負担などを整理し、事実に基づいて説明することを心がけましょう。
組織としても、メンバーの心理的安全性を守る責任があり、適切な対応を促すことが可能です。
ロジハラの自覚を促す発言をする
加害者自身が、自らの言動をロジハラと認識していないケースも少なくありません。
そのような場合には、自分が感じた負担を冷静に言葉にすることも有効です。
あくまで感情的にならず冷静なやり取りを心がけることで、相手との関係改善につながる場合があります。
まとめ
ロジハラ(ロジカルハラスメント)は、正論であっても伝え方や状況次第で、相手を精神的に追い詰めてしまう行為です。
悪意がなくても、受け手には大きな負担となり、職場の信頼関係や生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
ロジハラを防ぐためには、相手への配慮を忘れない対話姿勢と、丁寧な言葉選びが欠かせません。
被害を感じた場合は、1人で抱え込まず、冷静に距離を取り、信頼できる人に相談することが効果的です。
誰もが加害者にも被害者にもなり得ることを意識し、日々のコミュニケーションにおける配慮や工夫を重ねることが、健全な職場づくりにつながります。
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)