連載・コラム
職場に活かす心理学 第18回
心理学を問題解決にもっと活用するには
- 公開日:2018/09/03
- 更新日:2025/03/27
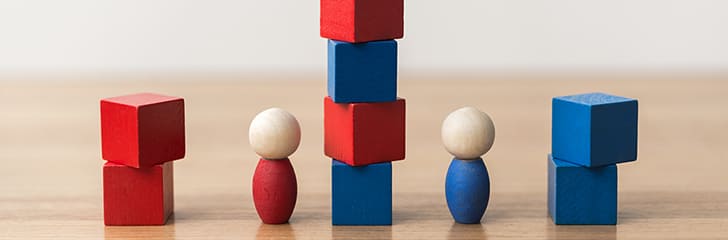
『職場に活かす心理学』の連載がスタートして、18回目になります。今回は、個人や社会の問題解決に、心理学がどのように役に立てるのかについて、あらためて考えてみたいと思います。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
“素朴心理学”と学問としての心理学
心理学は人の行動や心理に関する学問ですが、他の学問領域に比べて興味をもたれる方が多いのではないでしょうか。なぜならば、自分や人がどのように感じ、考え、行動しているかは、私たちが日々の生活を送る上で重要だからです。
社会心理学で著名な研究者であるハイダー(Heider)は、普通の人々でも、自分を取り巻く社会やそこでの出来事、人間の行動などをどのように理解するかに関する“素朴心理学(naive psychology)”を有していると述べています。私たちは、日々の生活のなかで、自分なりの心理学を用いて、予測や、解釈や、意思決定を行います。日々の生活を問題なく送れているということは、私たちの素朴心理学はそんなにまずくないのかもしれません。
それでは心理学を研究したり、学んだりする意味はどこにあるのでしょうか。学問としての心理学は、科学性を重視します。素朴心理学と大きく違うのは、誰にとっても真実である心に関する理論を見つけることを目指している点にあります。素朴心理学は、一人ひとりの経験に基づき構築されるため、人によって少しずつ異なっていたり、ある種のゆがみをもつことがあるのです。また私たちが意識していない心理的なプロセスも存在します。私たちの頭や心を悩ませる問題の解決のためには、素朴心理学では見えない、あるいはゆがんで見えている現実を、人の心の正しい理解を通じて捉えなおすことが助けになります。
しかし、心理学の知識を使えば職場の問題はすべて解決するかといえば、もちろんそんなことはありません。この連載を読んで、自分の周囲にある問題や現象について、新たな視点を得たり、ご自身が思ったことが整理されたりして役に立ったという方がいらっしゃれば、それはとてもうれしいことです。一方で、得られた知識を使って、うまく問題が解決したという方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。心理学の研究目的の多くは、人の心理に関する科学的な真実を追求することであって、問題解決ではありません。そのため研究知見を課題解決に使うのは、心理学者であったとしても結構難しいのです。
ところが最近、心理学や行動科学の知見を政策決定や教育、健康管理といった場面で積極的に活用する動きがあります。そして、いくつかの試みでは、高い成果をあげたことが報告されています。そこで、教育と政策決定における心理学の活用例を紹介しながら、個人や社会の問題解決に役立つ可能性について、考えてみたいと思います。
ちなみに、心理学はかなり細分化されていて、例えば産業組織心理学は、まさに組織や働く人を研究する応用的な心理学分野で、具体的な問題解決策もいくつか提案されています。欧米や中国、インドなどの企業では、すでに産業組織心理学の知見の活用は進んでいます。しかし、これらの知見によって、職場で起こるすべての問題を解決できるわけではありません。例えば、最近話題に上がっている「心理的安全性」ですが、研究が示しているのは、心理的安全性が高い職場では、あるいは職場の個人が心理的安全性が高いと感じていれば、良い効果が認められるということです。どうすれば心理的安全性が向上するのかについては、よく分かっていません。そこで、前回の記事(「心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?」)では、その方法の1つとして自己肯定を行うことの意味について、触れました。今回取り上げるものも、問題解決につながることを直接的に示した研究です。
教育における心理的介入
イェーガーとウォルトン(Yeager & Walton, 2011)は、教育における社会心理学的な介入の効果についてレビューを行いました。彼らが取り上げた研究のなかには、前回紹介した自己肯定感を高める操作の効果を見たものもあります。それと異なるものとして、例えば潜在的な能力観に働きかけるものが紹介されていました。ブラックウェルら(Blackwell, Trzesniewski, and Dweck, 2007)は、都市部の7年生で、家計の収入が低い黒人とヒスパニックの学生たちを対象に、学習スキルに加えて脳の機能や、それが鍛えれば強くなることを学ぶセッションを実施しました(実験群)。その結果、学習スキルのみのセッションを受けた統制群の学生と比較して、数学の能力が上昇したことが報告されています。実験群は、セッションを受けることで、増加的な能力観(能力は鍛えれば高まる)を身につける一方、統制群の能力観は固定的(能力は〈努力しても〉変わらない)であったことによるものだとしています。
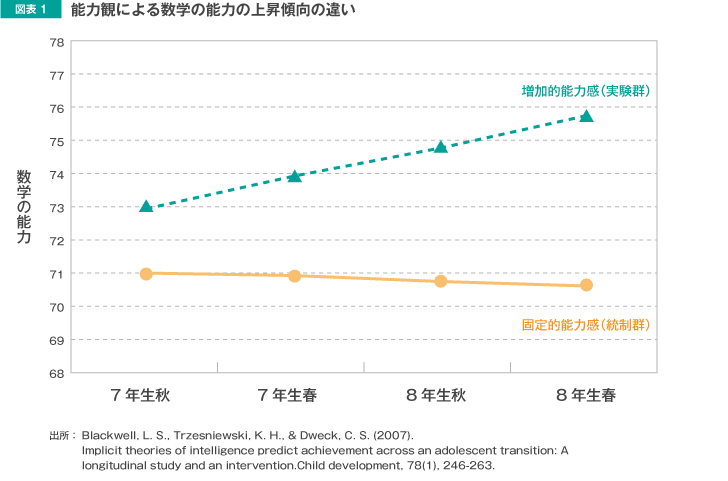
またウォルトンとコーエン(Walton & Cohen, 2007)による別の研究では、ネガティブなステレオタイプにさらされている学生が、周囲に受け入れられ、価値を認められていると思うことで望ましい効果が得られることを示しました。この研究の実験1では、コンピュータサイエンスに適した特徴をもつ友人の名前を「2人挙げる群」「8人挙げる群」「そのようなリストアップをまったくしない群(比較のため黒人の学生のみ)」に、白人の学生と黒人の学生がランダムに割り振られました。実は、2人の場合と比べると8人の友人の名前を挙げることは、白人学生にとっても黒人学生にとっても難しいことでした。しかし、白人学生では、2人の条件と8人の条件で自分がコンピュータサイエンスで成功すると思う程度には差がなかったのに対して、黒人学生では8人の条件の場合に、その程度が低下することが分かりました。これは、8人の友人の名前を挙げるという課題を行ったことで、黒人の学生のみが自分の人種グループはその分野に向いていないと感じてしまったためだと解釈されています。さらに実験2では、実際にこれからコンピュータサイエンスを履修する学生を対象に、自分に向いていないと感じたり、失敗したりすることはごく普通のことだと思わせるための課題を行います。その効果は黒人の学生に対してのみ有意で、その後の成績が向上したことを示しました。
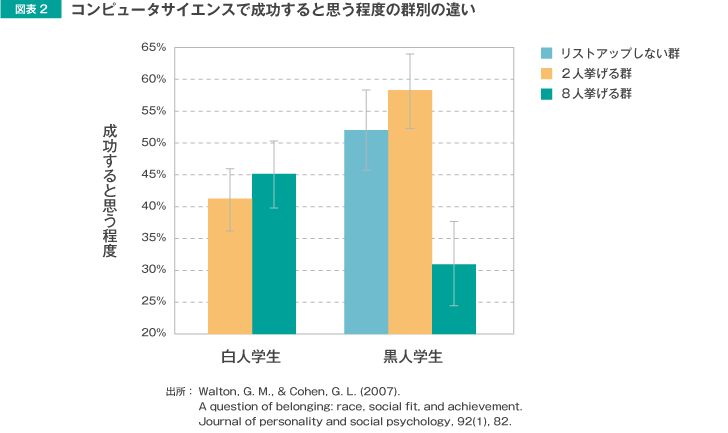
以上のように、いくつかの研究では心理的な介入の効果が示されているのですが、イェーガーとウォルトンは、こういった介入は決して万能ではないことを強調しています。実際のところ、同じことをやっても成功するかどうかは環境によって左右されるのです。アナロジーとして、飛行機が飛ぶという奇跡的なことは、エンジンや機体の形状やパイロットの操作など、さまざまな要因の組み合わせで実現していることを挙げています。気流によって機体が上昇したり、翼の形や位置で前に進むスピードが影響を受けることは実験室でも確認できるのですが、いざ本当の飛行機を飛ばすとなると、さらに試行錯誤やチューニングが必要となります。同様に心理的介入でも、ウォルトンとコーエンが行ったように、実験室での理論の確認の後、フィールド実験を行う際には、介入方法をその場の目的や環境に合わせてうまくデザインすることが必要になるのです。
ここで紹介されている介入方法は、皆さんの直感に反して、短時間に行われており、決して記憶に残るような印象の強いものではなく、本人に介入意図を知らせることなく行われています。このような方法は、心理学による説得の研究に基礎があります。また介入の効果は意外なほど長期にわたって持続しているのですが、ここでは成功した経験が自動的に再現され、さらに前進するメカニズムが働いていると考えられます。そのためには、自分の成功を実感できることや、自分が前進できることを信じることを、どのように起こせるかがポイントになるとのことです。説得の方法も、経験の再現も、それを示唆するような研究がすでに心理学にはあります。ただし問題解決の文脈ではないため、そういった知見をもつ心理学者が、状況を考慮しながら適切に適用する必要があるのです。
政策決定における効果
昨年、英国で孤独省なるものが発足したニュースを聞いた方がいるかもしれません。経済的に発展した国において、対人関係の希薄化や孤独は、じわじわと深刻な社会問題を引き起こしつつあります。またこのような、明らかに心理的な社会問題だけでなく、ここ数年、心理学や行動科学を政策決定や社会問題解決に積極的に活用しようとする動きが欧米を中心に起こっています。
2010年に英国で行動洞察チーム(Behavioral Insights Team)が創設され、政策決定に行動経済学や心理学の知見を取り入れる取り組みがなされています。その後、チームの活動は米国やオーストラリア、シンガポール、ニュージーランドなどに広がっています。このチームの成果としては、例えば税金を正しく納めていない人からの5%以上の支払い増加や、臓器提供登録の10万人以上の増加などが挙げられます。このような成果が出たチームの活動の成功の背景には、やはり個別の環境を考慮したことがありそうです。教育への心理学の知見適用と同様に、具体的な方法については、まず社会実験が行われ、その結果を生かすことで、成功を収めています。
心理学や行動科学の政策決定への関与についてレビューを行ったサンスティン(Sunstein, 2016)によれば、このような取り組みの効果は、人々に新しい行動の利益をどう感じてもらうかや、どのように物事を選択するかの構造を変えることによって生じるとしています。例えば、住宅ローンの組みかえによって利益が出るような政策を実行しても人々にその利点が伝わらなければ意味はありません。あるいは、食品を手に届きにくいところに置くだけで、摂取量を減らすことができることを利用すれば、健康に良くない食品の摂取を減らすことができるかもしれません。
上記のような変化を起こすための効果的な方法もいくつか分かっています。例えば、デフォルトルール(予防接種は全員受けるものだが、個人が選択すれば受けないこともできる)、行動の意図やコミットメントを表明すること(「今度の選挙には必ず行きます」)、社会的規範の使用(ほとんどの人がボランティアに参加する)、損失を嫌がる傾向の利用(この省エネのテクニックを利用しないと1万円損をする)、フレーミング(「10%脂肪が含まれる」との表示と「90%の脂肪カット」)などが、挙げられます。
上記のBehavioral Insights Teamでは2011年に、ホールスワース(Hallsworth)と同僚がまだ税金の支払いがない10万人の市民に手紙を送りました。その手紙には、次の4つのバージョンがありました。
(1)10人中9人の人が期限内に納税しています
(2)イギリスでは、10人中9人の人が期限内に納税しています
(3)イギリスでは、10人中9人の人が期限内に納税しています。あなたは未納税である少数者のうちの一人です
(4)納税をすることで、私たちはみんな保険・道路・学校などの重要な公共サービスを受けることができます
最後のメッセージを除いて、これらは社会規範を利用したメッセージになっています。これらの手紙は非常に有効で、どれかを受け取った人たちは、手紙を受け取らなかった人たちの4倍も納税を行いました。最も有効な手紙は(3)で、郵送後1カ月もしないうちに、318万ドルもの税が納められたのです。
ただし、政策決定に心理学を使用する場合、プラスの面ばかりではなく、例えば気づかないうちに政府の意図通りに行動させられるのではないかという不安が生じるとの指摘もあります。特に効果が出れば出るほど、どういった場合に心理学的知見を用いることが許容されるかは、難しい問題になっていきます。教育への活用や健康増進といった本人にとってのポジティブな価値が明らかなものと異なり、組織や国といった集団全体へのプラスと個人の選択や意思決定の自由のバランスをどう考えるかは、ある種のガイドラインが求められるように思われます。
上記の課題はありつつも、多くの社会問題、少なくとも個人と社会の双方にとって問題であるものには、もっと積極的に心理学を活用することは決して悪いことではないと思います。そのためにも、もっと適用先の状況や環境に合わせた実験や研究が求められるでしょう。
次回連載:『職場に活かす心理学 第19回 人を助け、助けられること』
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
- 職場に活かす心理学 第20回
- コミュニケーションと人間関係
- 職場に活かす心理学 第19回
- 人を助け、助けられること
- 職場に活かす心理学 第18回
- 心理学を問題解決にもっと活用するには
- 職場に活かす心理学 第17回
- 心理的安全性;職場は心安らぐ場所か?
- 職場に活かす心理学 第15回
- 「人はどのようにして道徳的な判断を行うのか」
- 職場に活かす心理学 第14回
- 情けは人のためならず
- 職場に活かす心理学 第13回
- いざというとき踏ん張るための「レジリエンス」
- 職場に活かす心理学 第12回
- 自己評価はなぜ甘くなるのか
- 職場に活かす心理学 第11回
- 直感的な判断はどれくらい正しいのか
- 職場に活かす心理学 第10回
- コントロール感の効用と幻想
- 職場に活かす心理学 第9回
- 職場・仕事で築かれるべき「信頼関係」とは
- 職場に活かす心理学 第8回
- 大事なときに最大限の結果を出すことはなぜ難しいか
- 職場に活かす心理学 第7回
- 自律的行動とその意味とは?どうしたら人は自律的に動けるのか
- 職場に活かす心理学 第6回
- 仕事で大切なのは責任か夢か
- 職場に活かす心理学 第5回
- 自律学習とメタ認知
- 職場に活かす心理学 第4回
- 集団で活動すると人は力を発揮するか?
- 職場に活かす心理学 第3回
- 人はどのくらい自分らしくありたいか
- 職場に活かす心理学 第2回
- なぜ人は変われないのか?
- 職場に活かす心理学 第1回
- 「幸福感」を高めるために必要なこと
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










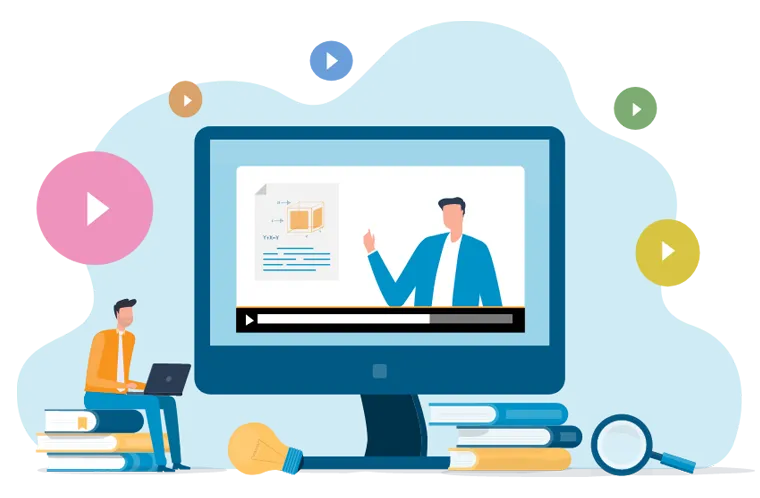 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で