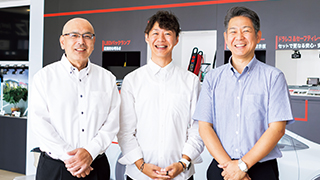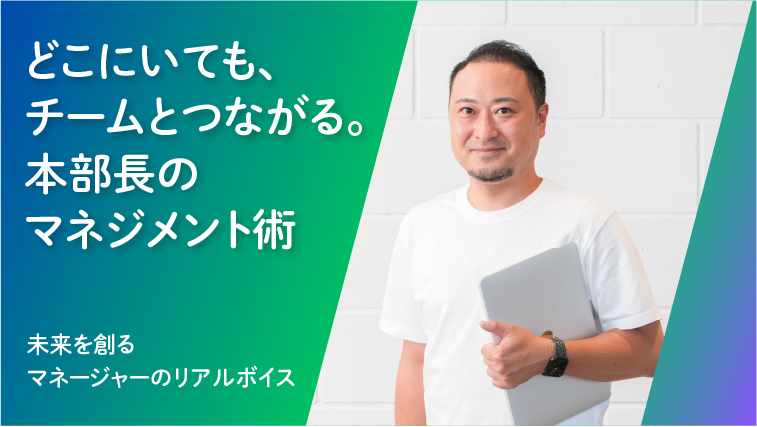用語集
企業コンプライアンスとは? 違反事例・原因・対応策を解説
- 公開日:2025/11/04
- 更新日:2026/01/20
コンプライアンスとは、法令や規則、社会的規範や企業倫理(モラル)を含む「基本的ルール」を遵守することを指します。企業においては、信用失墜のリスクを避けるため、コンプライアンス教育を実施することが一般的となっています。
この記事では、企業におけるコンプライアンスの基本から、違反事例・発生要因、具体的な対応策までを整理し、実務に役立つ視点を解説します。
- 目次
- 企業コンプライアンスとは
- 企業にとってコンプライアンスが重要な理由
- 企業コンプライアンス違反の事例
- 企業でコンプライアンス違反が起きる主な原因
- 企業がコンプライアンス対応で取り組むべきこと
- まとめ
企業コンプライアンスとは

企業が持続的に信用を得るためには、法令を遵守するだけでなく、社会的責任を果たす姿勢そのものも求められるようになりました。
ここでは、コンプライアンスの基本的な定義に加え、混同されがちな関連用語との違いについて整理します。
コンプライアンスの定義
コンプライアンス(compliance)とは、法令や規則、社会的規範や倫理などを遵守することを意味します。一般的にいわれるコンプライアンスとは「企業コンプライアンス」のことであり、企業が法律や内規等の基本的ルールを守って活動することを指します。また、法令に限らず社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも含む場合が多いです。
内部統制との違い
コンプライアンスと混同しやすい用語の1つに「内部統制」があります。
内部統制とは、企業が事業活動を効率的かつ健全に行うための仕組みのことです。
具体的には、「①業務の有効性および効率性」「②報告の信頼性」「③事業活動に関わる法令等の遵守」「④資産の保全」を目的としています。
コンプライアンスが、「法律や条例といった社会的なルールを守る」ことを意味するのに対して、内部統制は「そうした行動が実行されるよう社内体制で監視・管理する仕組み」であるという点に違いがあります。
コーポレートガバナンスとの違い
コーポレートガバナンスとは、日本語で「企業統治」と訳され、経営の透明性や健全性を確保するための仕組みです。
取締役会や社外取締役の設置などがその一例です。
一方、コンプライアンスは、法令や社会的ルールを守ることを指し、不正の防止や信用の維持が目的となります。
両者は企業の持続的成長を支える重要な基盤であり、どちらか一方だけでは機能せず、相互に補完し合う関係にあります。
CSRとの違い
CSRとは、日本語では「企業の社会的責任」と訳され、企業が社会の一員として果たすべき責任全般を指します。
製品やサービスの提供、雇用の創出、納税、メセナ活動に加え、環境への配慮や社会貢献なども含まれます。
コンプライアンスは、CSRの一要素と位置づけられることもあります。
法令やルールの遵守は、CSRを実現するための前提条件であると捉えると分かりやすいでしょう。
企業にとってコンプライアンスが重要な理由
ここでは、法的リスクの抑制と社会的信用の維持という2つの視点から、企業にとってのコンプライアンス遵守の重要性を整理します。
法的リスクを抑制するため
コンプライアンスの基本は、「法律をはじめとする社会的なルールを守ること」です。
ルールに反する行為があれば、行政処分や刑事罰などの法的制裁を受ける可能性があります。
日常的にコンプライアンスの遵守を徹底することで、こうした法的リスクを抑制することにつながります。
社会的責任を果たし、信用を維持するため
企業活動において、社会からの信用は事業継続に直結する重要な資産です。
コンプライアンス違反が起きれば、社会的信用の低下や取引の停止に加え、企業に長期的な損失をもたらすおそれがあります。
実践コンプライアンス研修シリーズ
コンプライアンス対策の基本
新入社員のためのコンプライアンス研修
企業コンプライアンス違反の事例
コンプライアンス違反は、企業に深刻な影響を与えるリスク要因です。
ここでは、代表的な事例として「ハラスメント問題」「法令違反」「不正会計」「情報漏えい」について解説します。
ハラスメント問題
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどは、労働施策総合推進法をはじめとする法令にも抵触し得る重大なコンプライアンス違反です。
これらの問題は従業員の健康や職場環境に深刻な影響を及ぼし、悪質な場合は刑事事件化や行政指導の対象となることもあります。
再発防止や管理職の対応力向上には、体制整備と継続的な教育が欠かせません。
法令違反
企業活動においては、労働基準法や独占禁止法、下請法など多くの法令を遵守する必要があります。
こうしたルールに違反した場合、行政処分や損害賠償といった法的な影響だけでなく、社会的な信用低下を招く可能性があります。
軽微な違反でも見逃さず、早期に対応することが重要です。
不正会計
不正会計には、粉飾決算、売上の水増し、経費の不正処理、助成金の不正受給などが含まれます。
会社法や金融商品取引法などに抵触する場合もあり、刑事罰や民事訴訟に発展するリスクをはらんでいます。
特に経営層が関与し、組織的に行われていた場合には社会的批判も強く、株主・取引先の損害も大きくなります。
定期的な監査や内部通報制度の活用が不正の抑止につながります。
情報漏えい
個人情報保護法や不正競争防止法に違反するおそれのある情報漏えいは、故意・過失を問わず企業に大きな損害をもたらす可能性があります。
例えば、社用端末の紛失、誤送信、SNSでの不用意な投稿など、日常的な行為が引き金となるおそれがあります。
こうしたリスクを防ぐには、情報管理ルールの整備に加え、社員一人ひとりの意識向上が不可欠です。
企業でコンプライアンス違反が起きる主な原因

コンプライアンス違反は、個人のモラルだけでなく、組織の仕組みや風土も大きく影響します。
「不正のトライアングル」や「割れ窓理論」といった考え方は、不正がなぜ起きるのかを理解するヒントになります。
社員の知識や意識の不足も、違反の土壌となる点に注意が必要です。
不正を生み出す組織環境と心理要因
不正のトライアングルとは、「動機」「機会」「正当化」の3つの要素がそろうことで、不正が起きやすくなるという理論です。
例えば、業績への強いプレッシャー(動機)を抱え、社内のチェック体制が不十分(機会)な状況で、「これくらいなら問題ないだろう」(正当化)といった意識が重なると、不正が生じやすい状況となります。
割れ窓理論は、小さなルール違反や秩序の乱れを放置すると、やがて大きな問題を引き起こすという考え方です。
例えば、些細なルール違反が見逃され続けると、組織全体に「違反しても問題ない」という空気が生まれ、不正のハードルが下がってしまいます。
組織として不正を許さない姿勢と、早期の対応が重要といえます。
法令や倫理に対する知識・意識の不足
社員が法令や社内ルールの内容を正しく理解していなかったり、倫理観が曖昧だったりすると、無自覚な違反が起きやすくなります。
知識不足やモラルの低さは、コンプライアンス違反の大きな要因です。
定期的な教育や啓発が欠かせません。
企業がコンプライアンス対応で取り組むべきこと
コンプライアンスを維持するためには、個人の意識だけでなく、組織としての仕組みづくりが不可欠です。
体制の整備やルールの明文化、研修による教育など、企業全体で取り組むべきことは多岐にわたります。
コンプライアンス推進のための体制を整備する
社内でコンプライアンスを推進するには、担当部署や相談窓口の設置など、組織的な体制づくりが重要です。
不正の兆候を早期に察知する仕組みや、社員が安心して相談できる環境があれば、違反の未然防止にもつながります。
経営層の関与も不可欠な要素です。
企業としての方針と行動基準を明確にする
コンプライアンスを形だけの取り組みにしないためには、企業としての方針や行動基準を明文化し、社員に周知することが必要です。
就業規則や行動規範、業務マニュアルを整備することで、判断に迷った際の拠りどころとなり、組織内の意識統一にもつながります。
コンプライアンス研修を行う
コンプライアンス研修は、社員一人ひとりの意識を高めるうえで欠かせません。
例えば、弊社が提供する「実践コンプライアンス研修シリーズ」では、法令やモラルに関する基礎知識に加え、ハラスメントやメンタルヘルスなど幅広いテーマを取り上げています。
管理職向けには、違反発生時の対応や未然防止に向けたリスクマネジメント、部下の変化に気づくための視点など、現場で求められる対応力を養う内容が中心です。
組織の健全性を維持するためにも、こうした研修を通じて知識と行動力の両面を育むことが重要といえるでしょう。
まとめ
コンプライアンスとは、法令を守ることにとどまらず、企業が法律や内規等の基本的ルールを守って活動することを指します。
コンプライアンス遵守に向けた取り組みは、企業としての社会的責任を果たし、信用を維持するうえで欠かせません。
コンプライアンスを推進するためには、個人の意識だけでなく、体制の整備や行動基準の明確化、継続的な研修といった組織的な取り組みが求められます。全社的にコンプライアンスへの理解と実行力を高めていくことが、企業価値の向上につながるでしょう。
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)