特集
リーダー育成施策に経験をどのように盛り込んでいくべきか
組織的な「成長経験デザイン」の考え方とポイント
- 公開日:2016/12/19
- 更新日:2024/03/25
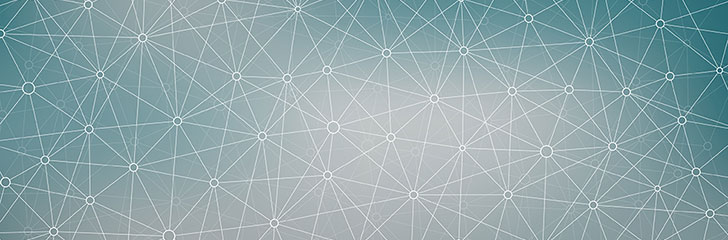
次世代リーダー育成をはじめとする次の経営・事業を担う人材育成の方法論や施策について悩む企業は多い。経営人材育成に求められるスピードが高まっている一方で育成の方法が確立されていないのが実状だ。
そこで今回は、リーダーの成長に最も寄与する“経験”を育成施策にどのように盛り込んでいくべきかに着目し、論じてみたい。
- 目次
- リーダーの成長に最も寄与するのは仕事経験
- 人材の成長において重要な“経験”を組織的な育成施策に反映できているケースは少ない
- 成長に必要な経験の明確化と意図的な経験付与を検討する観点をもつことが重要
- チャレンジを支援する周囲の関わり
- モニタリングの仕組みを整備し継続性を担保する
リーダーの成長に最も寄与するのは仕事経験
事業を担うリーダーの育成に関しては多くの会社で問題視されている。リーダー育成に関する研究でも仕事経験の人材育成への寄与は7割といわれている。
弊社が2012年に実施した「経営人材育成実態調査」では、経営人材育成(以降、事業を担うリーダーの育成)は、「意図的に育てていくことが必要」であり、「仕事経験が重要である」と約8割の企業が回答している。
人材の成長において重要な“経験”を組織的な育成施策に反映できているケースは少ない
では重要であると認識されている “経験”を育成施策につなげるには何に取り組む必要があるのか。
ここでは、過去の日本企業における “経験”の積ませ方・方法が昨今の環境変化の影響によって難しくなっている要因から考えていきたい。
現在の事業リーダーが若手・中堅社員の頃というのは、今と比較すると多くの業界がまだ成長局面もしくは未成熟であり、比較的まとまった仕事が任され(任さざるを得ない)、成功/失敗経験を積むなかで、能力開発が行われてきた。また職能的な人事制度を背景にローテーションによって幅広い仕事経験を積むことも容易だった。
一方、現在は事業を取り巻く環境変化が厳しくなるなか、そういった仕事を任される機会も少なくなり、かつ専門分化が進み、スペシャリスト育成が重視されるようになった結果、以前のようなローテーションも行われにくくなっている。
実際、各社の事業責任者クラスに対してご自身が成長した経験についてインタビューをすると、以下のような話が挙がることが多い。
・ とにかく人手が足らず、今では考えられないような案件を若手の時代にリーダーとして任された。上司は任せっぱなしで自分でやるしかないと思った。
・ 新しい技術で社内に誰も有識者がおらず「お前やってみろ」と任され、誰にも聞けない状況でとにかく自分で調べて、動き回って、試作品完成にこぎつけた。
・ 今では到底承認されない体制で新規事業の推進に七転八倒した。
そしてこのようなエピソードに代表されるような仕事をやりきることを通じて、仕事に対するスタンスを形成し、自信を高め、リーダーとしての素養を獲得している。
一方で、後人の育成について、皆さんが口を揃えておっしゃるのは、「今は事業環境の変化によって失敗が許されない状況になっている。故に相応の体制を整えた上で仕事の分担を明確にする必要があり、過去のような幅広い経験を積ませる機会を用意することが難しい」ということである。
このように過去は比較的余裕があり、意図せずとも良質な仕事経験を積むことができたが、現在は機会そのものが少なくなっている。
そこで、これまで属人的・偶発的に行われてきた“経験による育成”を、これからは意図して設計していくことが必要になる。しかし、そもそも各企業において、どのような経験が人の成長に寄与するのか、明確になっていないことが大半である。その結果、各現場での考え方に則り個別にさまざまな取り組みがなされているものの、組織的な育成施策として行われていることは、多くない。
成長に必要な経験の明確化と意図的な経験付与を検討する観点をもつことが重要
こうした現状を踏まえると、“経験を基点とした人材育成”を進めていくための第一歩は、成長に必要な経験を明確化することである。各社固有の必要な経験があり、それを明らかにすることは当然重要であるが、弊社では先行研究やこれまでの支援事例を元に、ひとつの仮説として「リーダー育成に必要な8つの経験」をまとめている。
「8つの経験」は基本的にチャレンジングな課題を遂行するなかで得られるものである。その経験を通じて知識・スキルを高めたり、事業を担うリーダーとしてのリーダーシップを形成していくものとして定義している(図表1)。
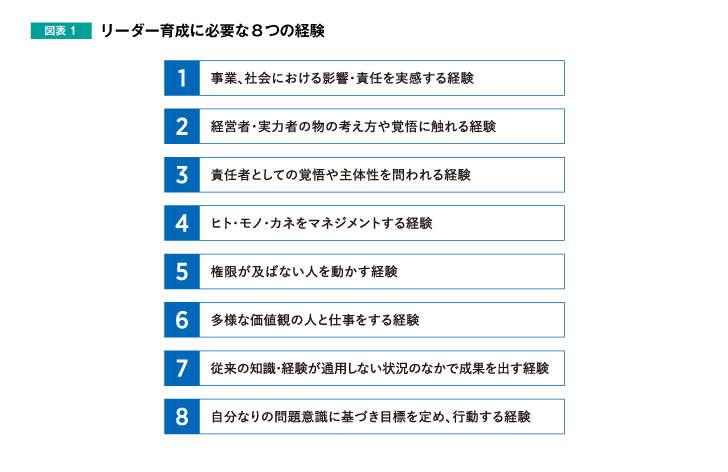
仮にこれを成長に必要な経験とした場合に、次に課題となるのが、「どのような仕事によって経験を積む機会を創出するか」である。
弊社では、“経験機会の創出”を大きく2つの観点から検討することが有効であると考えている(図表2)。
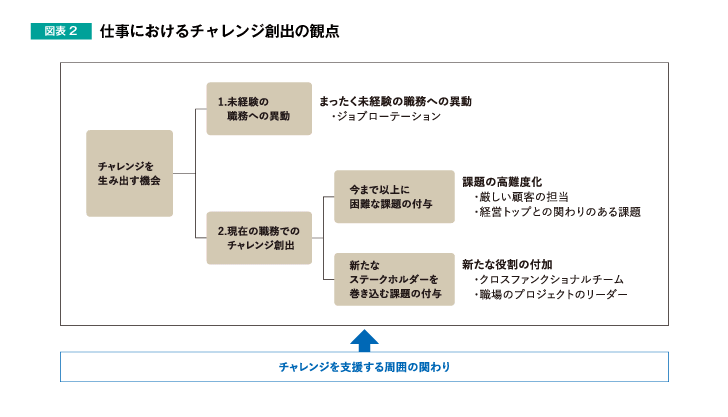
1.未経験の職務への異動
リーダー候補人材を育成していく上では、多様な職種を経験させることで獲得される知識・スキルの幅を広げることも必要となる。職種によって獲得される知識・スキルは異なる。例えば営業と経営企画では、業務遂行上求められるスキルは異なる。営業は、顧客対応力、折衝力が主要スキルであるのに対して経営企画では分析力、構想力といった具合である。因みに「8つの経験」に照らすと、「事業、社会における影響・責任を実感する経験」は顧客接点を担う職務で経験しやすく、「経営者・実力者の物の考え方や覚悟に触れる経験」は経営企画や人事などコーポレートスタッフ部門で経験しやすいといえる。
このように、各社の主要な仕事を挙げ、そこから獲得される知識・スキルを整理した上で、ローテーションによって、「8つの経験」を積ませることが可能になる。
2.現在の職務でのチャレンジ創出
また、ローテーションすることが難しい場合には、現在担っている仕事のなかで、困難な状況を伴う職務を付与することで、育成機会を作り出すことができる。具体的には以下2つの観点で検討するとよい。
■今まで以上に困難な課題の付与
同じ職務のなかでもミッションによって課題の難易度は異なる。例えば営業という職務のなかで攻略困難な顧客群を担当させる、高い要望があり、かつ対応において緻密さが求められる仕事の責任者を担当させるなどが該当する。
■新たなステークホルダーを巻き込む課題の付与
ステークホルダーが変化する課題も、困難な状況を作り出すことにつながる。例えば、全社の重要なプロジェクトのメンバーにアサインすることや、コーポレートスタッフに経営トップの意思決定をサポートするような情報収集・分析示唆だしを主体者となって取り組ませることなどが該当する。
チャレンジを支援する周囲の関わり
なお、これらの機会によって本人が成長するには、周囲の支援が有効となる。そこで、与えられた機会を、有意義な経験とするためのサポートを検討する。
職務が変わったり、困難な状況に置かれると、その人材は渦中にはまってしまい、場合によっては、課題を達成できないままつぶれてしまうリスクもある。そうはならなくとも、その経験からその後に活きる気づきを得られない場合もある。
そこで、人が関わることで内省を促したり、サポートすることが必要となる。
これは、事前に関わり方を精緻に定義しておくことは現実的ではないが、その候補者に誰がどのように関わるかということは、検討しておくとよい。
モニタリングの仕組みを整備し継続性を担保する
これまで経験付与の観点をお伝えしたが、継続的にその結果を振り返り次の育成につなげていくためには、仕組みの整備や育成の基本的な考え方を浸透させていく必要がある。その施策例として2つを挙げる。
1.人材開発委員会の設置
経験を基点にした育成に継続的に取り組んでいくためには、定期的に育成に関して議論する場が重要である。その場の1つとして、人材開発委員会が考えられる。人材開発委員会では、どの候補人材がどのようなステータス(能力/発揮しているパフォーマンス)か確認し、成長課題を克服していくために必要な経験(職務のアサインメントやOJT)を議論する。人材開発委員会で議論する前提となる候補人材の情報については、現場上司からの情報に加えてタレントマネジメントシステムによる情報を活用することも有効である。
人材開発委員会を運用していく上でのポイントについては図表3のとおりとなる。
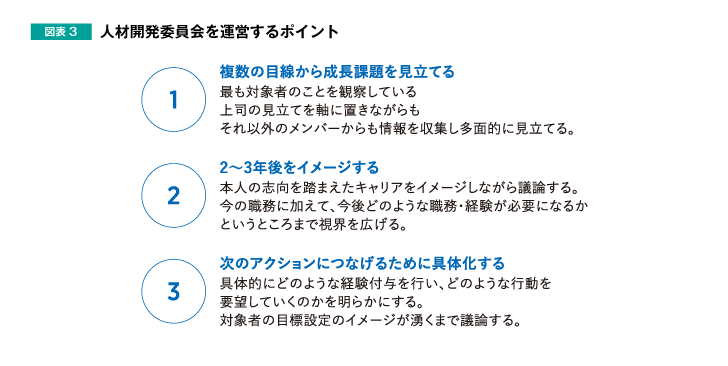
2.“経験による人材育成”の考え方の現場への浸透
人材開発委員会で決定されたことを実行していくためには現場のリーダーであるミドルマネジャーの理解・協力が不可欠である。その理解を深めるためにはミドルマネジャー自身が「自分も過去の経験によって今がある」ということを思い出し、実感することが最も効果的である。
そのような場をワークショップ形式で実施することをお勧めしている。
誌面の都合上詳細は割愛するが、半日~1日程度をかけてミドルマネジャー自身の過去の経験を職務×困難な状況(チャレンジ)×人の関わりの観点からたな卸しし、そこで身に付けたことを関連付け、整理するワークを行う。
これを通じて、成長したきっかけとなったメモリアルワークや周囲からのサポート経験が整理され、自身の部下育成のヒントにもなり得る。
またこのワークの情報を整理すれば自社に必要な経験に関する情報も収集できる。
以上、経験を通じた人材育成に関する主だったポイントをご紹介させていただいた。
変化が激しく、必要な人材を予測することが難しい昨今の状況を踏まえると、チャレンジや修羅場など良質な経験を積んだ人材を育成することが、企業の変化対応を機敏に進めていく原動力となり得る。
本記事が人材育成に携わる皆様のヒントになれば幸いである。
【text:HR企画統括部 リサーチ&デザイン部 マネジャー 谷川聡一朗】
※記事の内容および所属等は掲載時点のものとなります。
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.44 特集2「組織的な「成長経験デザイン」の考え方とポイント」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
*事業を担うリーダーを計画的に育てる体制をつくる「成長経験デザインコンサルティング」特設ページを公開中です。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

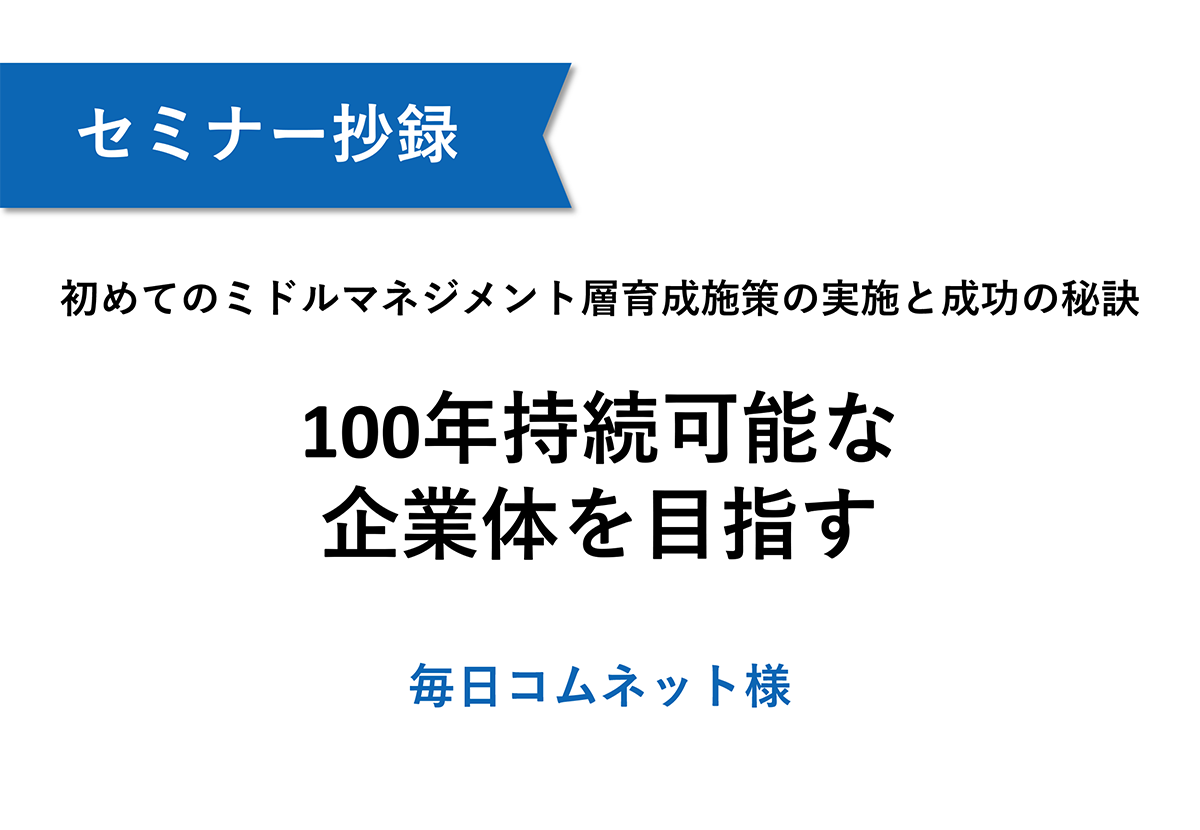









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で