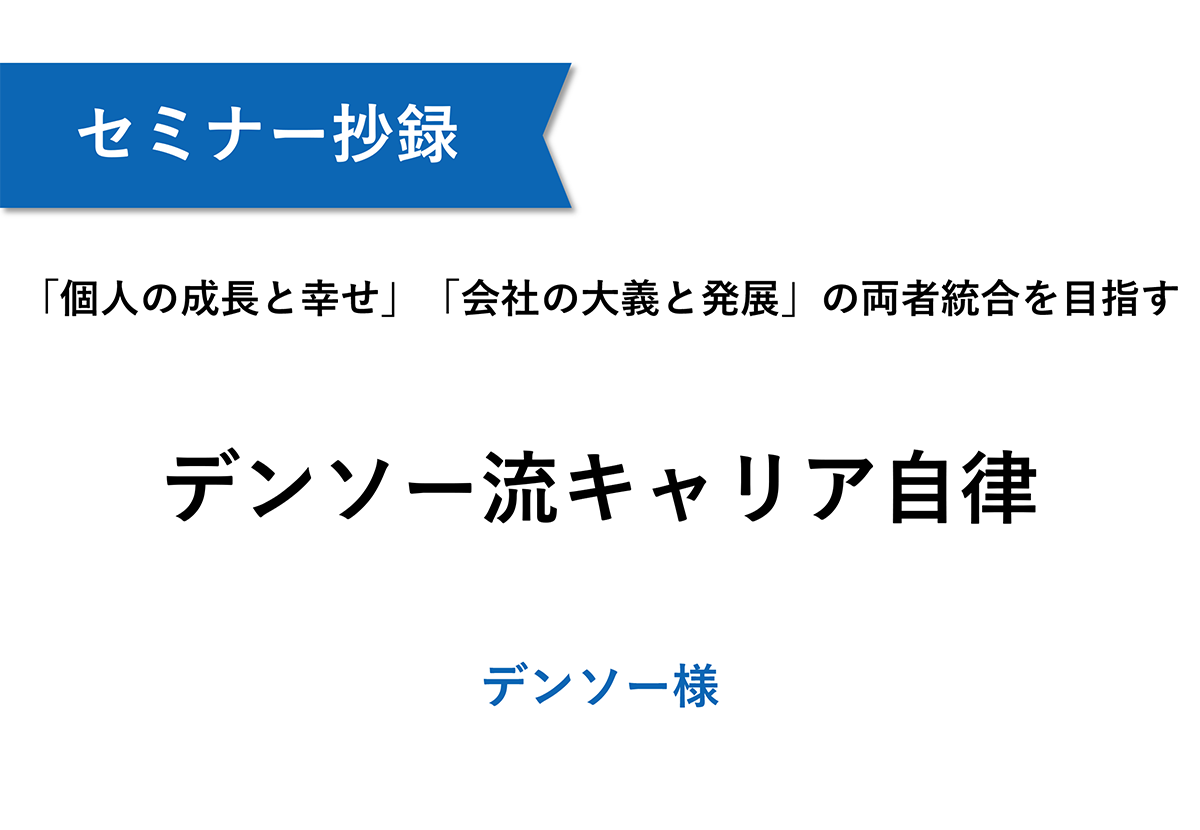特集
境界を越える経験は何をもたらすのか
越境による学びとそのメカニズム
- 公開日:2016/12/05
- 更新日:2024/03/25

企業の人材・組織領域において「越境」という言葉を耳にするようになった。人が境界を越えるとき、越境者本人、周囲や所属組織、社会に、どのような学びや変化がもたらされるのか。
越境(boundary crossing)に関連する学術的議論は、特に1990年代から、経営組織論、心理学、教育学、言語教育、哲学などの複数の分野で盛んになったが、近年、そのフォーカスは強まっている*1。本稿では、越境論の背景と、企業人の学びに関連する学術研究を概観する。
越境とは
越境という用語が最低限意味するところは「何かの境界を越えること」であり「異なるコミュニティや状況間をまたぐ(横断する)という行為や事態」である*2。境界はどこにでも存在する。個人や集団がそこに「境界がある」と感じればそれが境界であり、境界を越える活動はすべて越境である。
企業組織においては、その成り立ちの上で多数の境界が生成される。就業規則や組織文化を共有することにより組織の内と外の境界が意識されることで、メンバーの行動の予測やコミュニケーションが容易になりマネジメントのコストが下げられる。分業を行い組織内に境界を設けることで、注意を払うべき環境が単純化され、意思決定が容易になる。しかし、環境変化にそぐわない過剰適応が生じる場合などには、強固な組織境界は必ずしも組織に利益をもたらさない*3。
近年、越境という概念への注目が高まる背景はまさしくこの点に関係している。社会環境が大きく変化するなかでイノベーションの必要性が叫ばれ、組織や部門、専門性や職能間の境界を越えて変革や創造を起こしていくことが期待されている。また、転職や新事業の立ち上げ、職場外のワークショップや勉強会への参加など、共通の関心やテーマのもとに多様な人が繋がり、文脈を横断しながら生きることが市民権を得てきている*1。
しかし、越境は簡単ではない。異質な文脈やコミュニティの境界を乗り越える難しさや、どのように乗り越えるか、そこで人やコミュニティに生じる変化などが、多岐にわたる越境研究における共通の関心といえよう。
学びが生じるメカニズム
■越境論における学習観
越境における学びの理論の発展には、「人が学ぶとはどういうことか」という学習観の変化が関連しており、今日の越境研究は図表1のような理論あるいは学習観をベースに展開されているという*4*5*6。越境的な共同実践において他者や環境に働きかけ、助けられ、異なるコミュニティへの参加を深めていくなかでの全人的な変容を学びと捉えている。
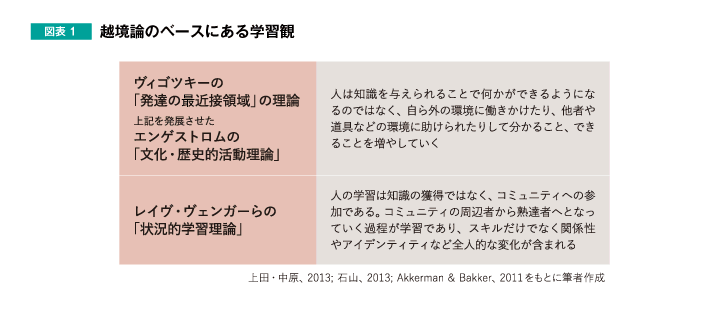
■水平的学習
エンゲストロムの越境論から「水平的学習」と「ノットワーキング」について紹介しよう。エンゲストロムは、行為を「アタリマエ」化していく〈熟達化〉のプロセスを「垂直的学習」と呼ぶ一方、越境的な共同実践を通じて「アタリマエ」の意識が変わる〈異化〉のプロセスを「水平的学習」として論じた(図表2)。長岡(2015)は、近年ワークプレイスラーニングとして議論されるような現場経験を通じた学習が、実は垂直的学習のみを指しており、「経営的文脈には、他者との関わりのなかで自分自身を異化することに繋がる実践活動を、学習と結びつけて理解するための適切な視点が欠如していた」と指摘する*7。
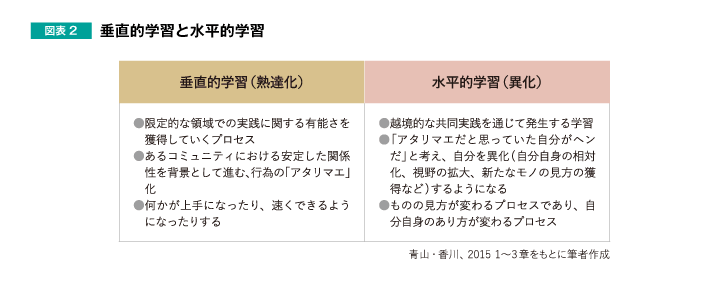
■ノットワーキング
またエンゲストロムは、越境に特徴的な、毎回異なるメンバーにそのつど結び目を結うような協働を「交渉によるノットワーキング」と呼んでおり、その書籍の原題は“From Team to Knots”(チームから結び目へ)である*8。青山(2015)が「固定的なチームから、その場での協働という新しいスタイルへと、働き方が変わりつつあるという見方が背景にある」と指摘する*2ように、越境は新しい協働の関係性を学び、生み出す機会とも捉えられている。
越境が企業人にもたらす学び
このように越境は、既存の組織や仕事への過剰適応を防ぎ、協働のあり方を変えていく機会となると考えられる。中原(2012)は、「個人が所属する組織の境界を往還しつつ、自分の仕事・業務に関連する内容について学習・内省すること」を越境学習と呼び*9、企業人の学習をOJTとOff-JTの二元論で捉えるのではなく、業務経験や職場の他者を通じた多様な学びをデザインすること、その際、社外の経験も重要な機会であることを論じている。
越境が企業人にもたらす効能についての研究事例を紹介しよう。
荒木(2007)は職場外の勉強会への越境が個人のキャリアの確立に影響を与えており、多様なメンバーが共同で解を出すような活動において、専門領域と長期的キャリアの関係についての内省が生じるためと考察している*10。
石山(2013)は、越境先の勉強会での学びを自社に持ち帰り応用するプロセス(ブローカリング)において、(1)専門性、(2)ノットワーキングスキル(関係性を結ぶ)、(3)共同体スキル(共同体の運営に貢献する)、(4)還流スキル(反発を織り込みつつ学びを自社に展開する)、を学ぶことを明らかにしている*5。
藤澤・香川(2015)・藤澤(2016)は、ビジネス/ソーシャルの越境経験がもたらす、自己や会社を異化する内省が、ジョブ・クラフティングと呼ばれる仕事の境界変更(役割変革)を促進し、仕事の有意味感を高めることを示した(図表3)*11*12。
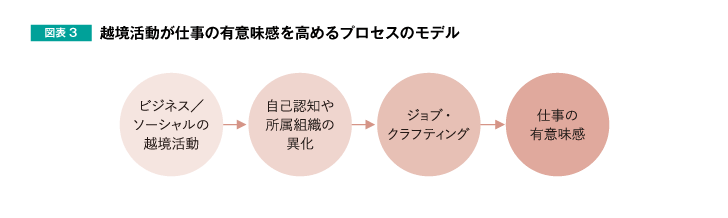
いずれも越境による水平的学習が、個人のキャリアや本業に影響を及ぼすことを示しており、異質な実践における協働に参加することが鍵となるようだ。
*1 香川秀太・青山征彦編著(2015)『越境する対話と学び: 異質な人・組織・コミュニティをつなぐ』 序章、 新曜社
*2 青山征彦(2015)「越境と活動理論のことはじめ」 *1
第1章、 新曜社
*3 桑田耕太郎・田尾雅夫(1998)『組織論』 有斐閣
*4 上田信行・中原淳(2013)『プレイフル・ラーニング―ワークショップの源流と学びの未来』 三省堂
*5 石山 恒貴(2013)『組織内専門人材のキャリアと学習: 組織を越境する新しい人材像』 日本生産性本部生産性労働情報センター
*6 Akkerman, S. F. & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational research, 81(2), 132-169.
*7 長岡健(2015)「経営組織における水平的学習への越境論アプローチ」 *1 第3章、 新曜社
*8 Engeström, Y. (2008). From Teams to Knots (山住勝広・山住勝利・蓮見二郎訳『ノットワークする活動理論: チームから結び目へ』 新曜社、 2013)
*9 中原淳(2012). 経営学習論: 人材育成を科学する.東京大学出版会
*10 荒木淳子(2007)「企業で働く個人の 『キャリアの確立』を促す学習環境に関する研究: 実践共同体への参加に着目して」日本教育工学会論文誌、 31(1)、 15-27.
*11 藤澤理恵・香川秀太(2015)「本業外の社会貢献活動(プロボノ)への参加が促進する組織再社会化―変革的役割志向に着目して―」経営行動科学学会 第18回大会
*12 藤澤理恵(2016)「ビジネス/ソーシャルの越境経験が、仕事の有意味感を高める役割変革に及ぼす影響―ジョブ・クラフティング・モデルに基づく検討―」経営行動科学学会 第19回大会
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
客員研究員
藤澤 理恵
リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。
“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。
経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)