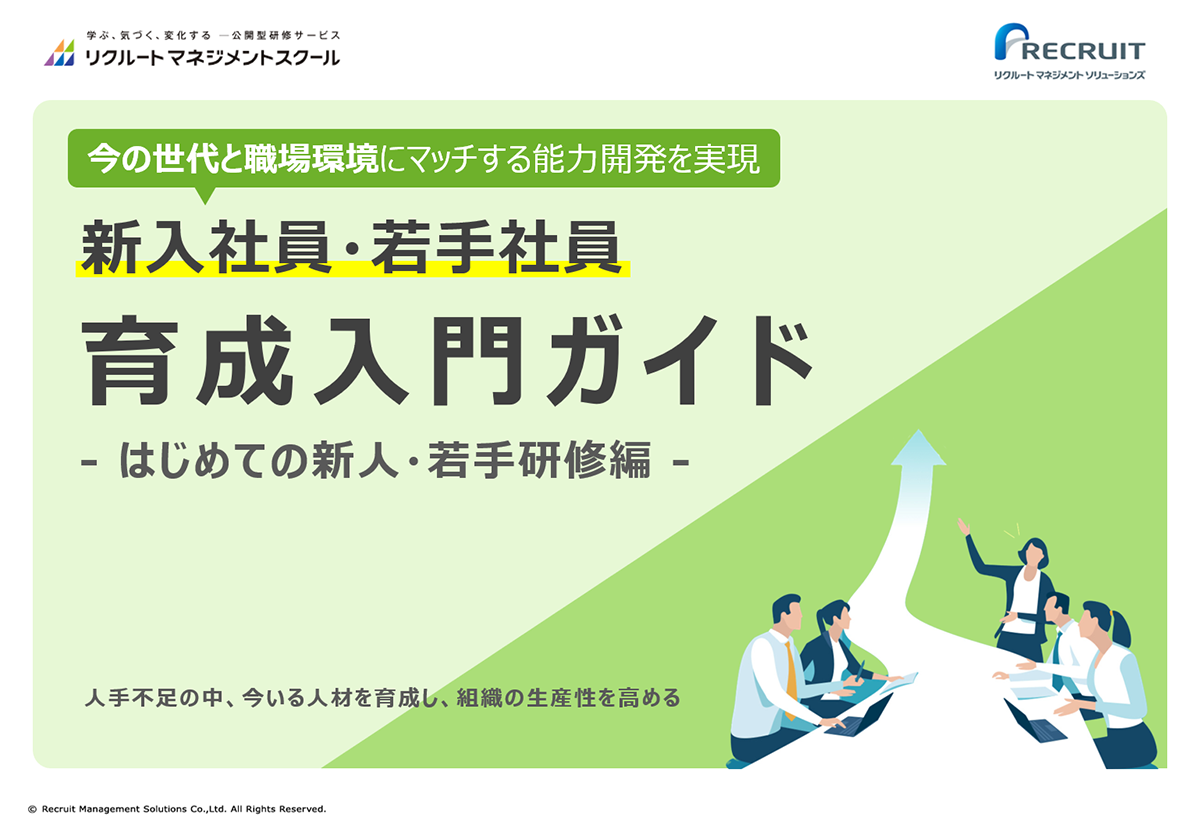連載・コラム
【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
- 公開日:2025/05/12
- 更新日:2025/08/05

トップダウンの育成が機能しなくなりつつある昨今において、「若手育成の難しさ」が大きな課題となっています。育成においてもダイバーシティや対話が求められるなかで、現場にどのようにダイバーシティを浸透させ、向き合っていけばいいのでしょうか。
今回は、大学院大学至善館で次世代の育成に携わられている枝廣淳子氏をお迎えし、「ダイバーシティ実現を目指すなかでの、若手との向き合い方」についてお話を伺いました。
対談メンバー
●枝廣 淳子氏(大学院大学至善館教授)
●武石 美有紀(リクルートマネジメントソリューションズ 研究員)
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
多様性あふれる時代だからこそ、チームでの育成が重要

武石:「育成担当者1人で若手を育てるのは、もう限界だ」――さまざまな企業様とお話しするなかで、最近は特にこういった声をいただきます。変化が激しいビジネス環境で自分の仕事も忙しく、育成に割く時間がない。リモートワークでお互いのコミュニケーションも難しいのに、1on1でのオーダーメイドな育成が求められる……など、さまざまな要因において育成担当者様が板挟みになっていると感じています。
だからこそ弊社としても、若手の育成をワンオペではなく組織ぐるみで、対話や多様性を大切にしながら進めていくことをお薦めしています。共感いただくことも多い一方で、「対話やダイバーシティ的な関わりは時間がかかるので、むしろ育成の効率が悪くなってしまうのではないか」というご意見をいただくこともあります。若手の育成を早く進めたいからこそ、なかなか育成モデルを変えられない。企業様のこういったジレンマについて、枝廣様はどのようにお考えでしょうか。
枝廣:難しい問題ですよね。今までの育成モデルは学校教育も含めて、“スキルや知識を手渡しして、均一に能力を底上げする”ことを目指す、トップダウン型のモデルでした。一方で、スキルや知識を手渡しすればこなせるような仕事は、AIなどでまかなえてしまう時代になりつつあります。だからこそ若手一人ひとりの多様性をふまえた教育方針に変えていかないといけませんし、多様性に対応するためにもチームで育てていくことが好ましいと感じています。
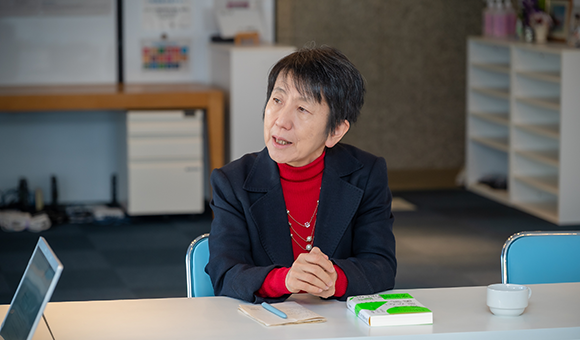
ただ、ずっとダイバーシティではない環境で働いてきた組織からすると、「今までのやり方でも問題は起きなかった」という意識が根強く残っている可能性も高いです。「今までの育成方法だとちょっとうまくいかないな。おかしいな」と察していらっしゃるものの、ダイバーシティや対話が本当に組織の力になると、ピンと来ていないケースも多いのだと思っています。
武石:そういった意識が変わるタイミングというのは、どのような時でしょうか。
枝廣:やはりデータや成功事例などがあると、イメージがつきやすいと思います。
武石:本当にそうですね。データですと、弊社から「職場における新入社員育成の実態調査」を発表しました。回答結果を見ると、上司を含めた職場メンバーの協力がなされていた職場は、新入社員の成長にとどまらず、育成担当者や職場全体にも大きなリターンがある可能性が示唆されました。
また、成功事例も集まってきています。例えば株式会社ヤクルト本社様は、新人にとどまらず、職場でメンバー育成が自走する、強固な組織づくりを掲げ実践。数年で結果も出てきています。今後も参考データや企業様の成功事例の発信に取り組んでいきたいと考えています。
枝廣:引き続き頑張っていただきたいです。
あとはビジネスの経験を通して、多様性に対する意識が変わることも珍しくありません。新しい市場、新しいビジネスモデルがどこにあるのかを考えたり、自分の技術やスキルと結べそうなものを社会課題の中から探ったりする過程で、社会の多様性に目を向ける時が来るはずです。
ビジネスの育成の場でも、「育てるのではなく育つもの」というマインドが人を生かす

武石:ダイバーシティの可能性というお話が出ましたが、昨今はあらゆるところで「多様性は大事」という認識が広まっていますよね。私自身も多様性の大切さは感じているのですが、心に余裕がない時は「多様性ってちょっと、面倒かも……」と立ち止まってしまうことがあります。こういう気持ちには、どう向き合ったらいいのでしょうか。
枝廣:基本的に多様性って手間や時間がかかるものなんです。早く進めようと思ったら、多様じゃない方がずっと楽ですよ。
だからこそ「どんな時も多様性を大事にしましょう!」と強いるのではなくて、「自分とちょっと違う人の言葉も聞こうかな」と思えるくらいの環境を整えることが大事です。タイムプレッシャーがあるなかでも広い心を持ちましょうというのは、心の修行になってしまいますから。
武石:確かに。やはりそういった“心の余裕”をつくる意味でも、職場全体で繋がって、組織ぐるみでお互いに補い合える仕組みをつくっていくことが重要なのではないかと、あらためて思いました。
枝廣:そうですね。昔と比べても求められる多様性の度合いが全然違うので、1人で全部カバーしていくのは難しいです。なので、やはり業務でも育成でも、チームでカバーしていくメリットは大きいと思います。

ただ育成に関しては、「しっかりと育てなければ」と、気負う必要はないと感じています。教育論的な話になりますが、「子どもは育てるのか育つのか」と問われたら、私は「育つものだ」と考えているんですね。
育成の在り方として、外から引っ張ったり、伝え教えたりすることがすべてだという価値観もあります。本人が空っぽの受け皿のような扱いをしてしまうのですね。ですが、その方法では子どもの主体性を削いでしまう可能性もあります。子どもは「育てるのではなく育つもの」。大人は子どもの「育ちたい」という気持ちを邪魔しないことも大切です。職場での育成においても、人が「育ちたい」と思う気持ちを生かせるかどうかが重要なのではないでしょうか。
武石:とても共感します。弊社でも一人ひとりが意欲や可能性を持っている前提で、若手に「教える」だけではなく、若手からも「学ぶ」スタンスが大切だと考えています
(参考:Z世代と共に創る未来 ~異質さに学び組織をアップデートする)。
若手が持つ「育ちたい」という気持ちを大切にして育成を行うには、どのようなことを意識すればいいのでしょうか。
枝廣:1つの方法として、「ここまでにこれだけ育成する」という育成目標に対して、1つの尺度で測るのではなく複数の尺度を持てるといいのではないでしょうか。例えば営業現場で、「アポイントを取る力はまだ足りないけれど、お客様の話を親身に聞き、共感する力が上がった」というケースがあります。後者の共感力の向上も育成の成果ですよね。アポイント件数や売上のような数値で測りやすい尺度も大切ですが、それだけでは測りきれないものもあります。いくつかの尺度をつくり、そのなかの1つでも良い評価として残るものがあれば、新人の可能性や意欲を引き出すことに繋がりますし、育成担当者にとっても育成の効果を感じられ、励みになるでしょう。
後編に続く
後編では、若手社員との対話の質を高めるための具体的なポイントに迫ります。「業務の進捗どう?」で終わらせずに、より深いコミュニケーションを生み出すにはどうすればよいのか。対話の質を向上させる「ネガティブ・ケイパビリティ」の活用法や、ジェネレーションギャップを乗り越えるための「5分だけ」ルールなど、実践的なヒントをお届けします。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
若手社員向けの研修をご検討の方は、若手社員研修特集ページをご覧ください。
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)