インタビュー
東京女子大学 正木郁太郎氏
感謝と称賛は個人にも組織にもポジティブに働く
- 公開日:2025/09/22
- 更新日:2025/09/22
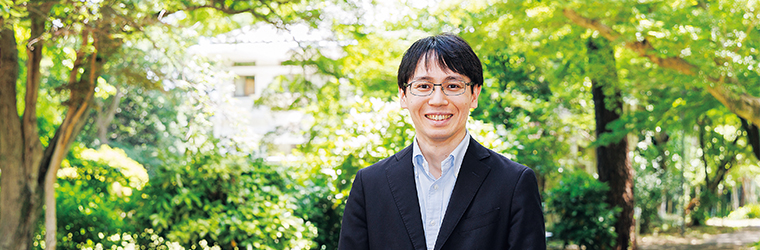
上司が部下に「ありがとう」と感謝したり、部下を「素晴らしい」と称賛したりするフィードバックには、ポジティブな効果があるのだろうか。感謝と称賛の効果を研究する正木郁太郎氏は「ある」と答える。具体的にはどのような効果があり、企業はどうしたらよいのか。
- 目次
- 職場における感謝と称賛を研究する出発点
- 感謝と称賛には3 つのポジティブな効果がある
- 感謝の効果と称賛の効果の共通点と異なる点
- グローバル企業には感謝と称賛のトレーニングを行うものも
- 特にテレワーク環境では感謝と称賛を増やした方がよい
- 感謝・称賛のためのツールやイベントにも効果がある
職場における感謝と称賛を研究する出発点
私は博士課程で、多くの企業の皆さんの協力を得ながら「ダイバーシティ&インクルージョン」に関する研究をしました。その際、企業の皆さんに「自社のダイバーシティ&インクルージョンを実現するために、私たちは明日から何をしたらよいですか?」とよく問われたのですが、その時点では皆さんに渡せるヒントがありませんでした。
そこで、多くの人が明日から実行できるテーマを探していたときに見つかったのが、「感謝」でした。感謝なら、誰でもすぐに簡単に実行できます。感謝の言葉は、ダイバーシティ&インクルージョンの実現に役立つのではないか。この問いが、職場における感謝と称賛を研究する出発点となりました。今回は、先行研究と私の研究から、現状分かっていることを端的にお伝えします。
感謝と称賛には3 つのポジティブな効果がある
職場の皆さんが、周囲に「ありがとう」などと感謝を伝えたり、「素晴らしい」「見事な活躍でした」などと称賛したりすることには、3つのポジティブな効果があることが分かっています。
1つ目に、感謝や称賛には、誰かのため、何かのために行動したい、自ら積極的に行動を起こしたい、といった気持ちを高め、「利他的行動」や「主体的行動」を促す効果があります。2つ目に、職場内の信頼関係、チームワークの良さ、親密さなどを高め、「集団の関係性」を良くする効果があります。特にダイバーシティが高い状況下で、感謝と称賛の習慣が根づいて「関係性が良い」組織では、従業員の「組織愛着」が高まることも分かっています。3つ目に、職場における「多様なウェルビーイングやポジティブな考え方」、職場に対する「前向きな態度」を促す効果があります。
このように感謝と称賛は、行動、関係性、考え方・態度のいずれにもプラスに働きます。また2つ目の効果で分かるとおり、感謝と称賛は個人だけでなく、組織にも良い影響を及ぼします。例えば、上司から部下へのフィードバックの土台には信頼関係が必要です。信頼関係がなければ、部下は上司に耳を傾けなかったり、その言葉をネガティブに解釈したりしかねません。日頃の感謝・称賛によって上司・部下の信頼関係が高まっていれば、上司のフィードバックは間違いなく部下に伝わりやすくなります。感謝と称賛は、このように職場にポジティブな影響を与えていくのです。
さらに面白いことに、感謝と称賛は、される側だけでなく、する側にもポジティブな効果があることが判明しました。感謝や称賛をされた人に良い効果があるのは想像しやすいでしょう。しかし実は、した人にも同様の効果があるのです。感謝と称賛をすることで、相手の良いところや、自分に恩を与えてくれた「仲間」に目が向きやすいためだと考えられています。
それから、職場の人たちが、仲間の感謝を「目撃する」ことにも良い効果があります。感謝を伝えている様子を見ることで、この人たちは信頼してもよいという判断を下し、つながりを増やす効果があります。それが組織改善につながっていく可能性も十分にあります。以上が、職場における感謝と称賛の効果について分かっていることの大枠です。ただし、感謝や称賛だけで、会社全体を大きく変えられるわけではありません。プラスになるのは確かですが、革命的な効果があるわけではないことも事実です。
感謝の効果と称賛の効果の共通点と異なる点
この説明を聞き、感謝の効果と称賛の効果はまったく同じなのかと気になる人もいるでしょう。実は、少なくとも職場では、両者の効果に大きな違いはないのですが、多少の違いはあります。
1つ目に、日本社会では、称賛の方が感謝よりもハードルの高い行為です。そのため、称賛はされるよりもする方がポジティブな効果が出やすいことが分かっています。とはいえ、簡単なのは感謝ですから、まずは「ありがとう」から始め、少しずつ感謝と称賛を増やしていくことをお薦めします。
2つ目に、感謝は称賛よりも「お返し」が起こりやすいと考えられます。称賛は必ずしも「お返ししよう」となるわけではありませんが、感謝は関係性に深く根差したコミュニケーションで、相手にお返ししたい気持ちが高まりやすいのです。
3つ目に、感謝には特に悪い面はありませんが、称賛にはネガティブな作用もあり得ます。例えば、上司がある部下を称賛している光景を目撃した他の部下が、嫉妬する可能性が考えられます。まだ調査結果は得られていませんが、要注意です。
グローバル企業には感謝と称賛のトレーニングを行うものも
以上の研究成果を踏まえて、企業の皆さんへの具体的なヒントをいくつかお伝えします。
第1に、私が過去に調査や講演で関わった企業のうち、特にグローバル展開に積極的な企業のなかには、感謝と称賛の習慣を重視するものも複数ありました。関連するトレーニングや全社イベントなどで推進をするほか、調査結果で感謝と称賛の得点が他社より高く出た例もあります。グローバル企業は、言葉にしないと伝わらないと考える文化と、高い人的流動性、個性の尊重を前提としています。そのため、相手の長所を認め合い、高め合うことを重視しているようです。
対して、日本の職場は人的流動性が低く、旧知の間柄が多い傾向があります。そうした職場は感謝や称賛を頻繁に伝えなくてもよいと考えがちです。また、感謝や称賛を恥ずかしいと感じる人も少なくありません。そのため日本には、感謝・称賛を習慣とする職場が比較的少ないのです。
しかし最近は、日本企業も変わってきています。ダイバーシティ&インクルージョンを実現したい、そのために感謝と称賛の習慣を職場に根づかせたいと考える企業の皆さんには、こうした取り組みが大いに参考になるはずです。
特にテレワーク環境では感謝と称賛を増やした方がよい
第2に、特に「テレワーク環境」では、感謝と称賛を意識的に増やした方がよいでしょう。また新人比率が高まっている職場や、新結成のチームなどでも感謝・称賛の習慣づけをお薦めします。なぜなら、言葉を使わないと伝わらないテレワーク環境や、既存のつながりが少ない職場では、感謝や称賛のプラス効果が出やすいからです。先ほど例に挙げたグローバル企業と同じメカニズムです。
その際、リアクションを早めることも肝要です。やり取りの間隔が空くと、人はどうしても相手の意図を誤って推測しがちです。上司の皆さんは、感謝や称賛をできるだけリアルタイムで、具体的に部下に伝えるとよいでしょう。また、ツールの使い分けもポイントです。感謝や称賛は、チャットツールよりも、電話やオンライン会議を通じて生の声で伝えた方が、誤解なく伝わるかもしれません。
それから、時には雑談も交わした方がよいです。業務だけの関係性では、いざというときに「ありがとう」や「素晴らしい」といった言葉を伝えにくいからです。人は感情的な生きものです。テレワークは業務上のやり取りだけに終始しがちなので、ドライな関係性になりすぎないように注意した方がよいと思います。
感謝・称賛のためのツールやイベントにも効果がある
第3に、感謝・称賛のための「ツール」や「イベント」にも効果があります。ツールのメリットは、「誤解やズレが生まれにくい」ことです。ツールを使えば、相手の感謝や称賛を嫌みだと思う人はほとんどいないはずです。ただ、導入にコストと手間ひまがかかる点は注意が必要です。なお、デジタルツールには利点もありますが、紙のカードで感謝の言葉を送り合うことも十分に可能です。
また、感謝・称賛のイベントにも感謝・称賛文化の醸成効果があります。企業が感謝・称賛を増やすためにできる工夫はいくつもあるのです。
【text:米川青馬 photo:伊藤 誠】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.79 特集1「成長と信頼につながるフィードバック」より抜粋・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
正木郁太郎(まさきいくたろう)氏
東京女子大学 現代教養学部 心理学科 准教授
2017年東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。東京女子大学専任講師などを経て、2024年より現職。著書に『感謝と称賛』『職場における性別ダイバーシティの心理的影響』(ともに単著・東京大学出版会)、『多元的無知』(共著・東京大学出版会)などがある。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












