インタビュー
名古屋大学医学部附属病院 木村武司氏
「学習者中心」の視点がフィードバックの効果を高める
- 公開日:2025/09/08
- 更新日:2025/09/08
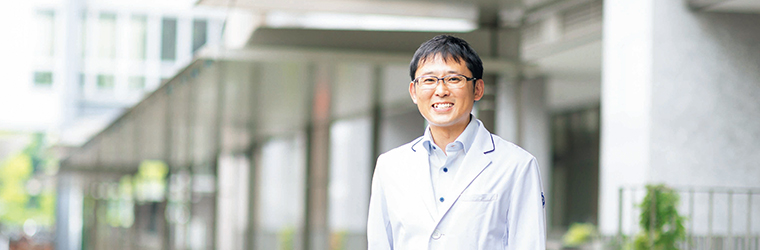
木村武司氏は、医学教育の観点からフィードバックを研究している。医学教育のなかで、フィードバックに関する議論はどのように変遷してきたのか。医療現場では今、どのようなフィードバックが効果的で、何が重要なポイントだと考えられているのか。詳しく伺った。
- 目次
- フィードバックは医学教育でも重要なもの
- 2010 年以前は指導者中心のモデルが一般的だった
- 学習者中心モデルには「観察」と「信頼関係」が必要
- 学習者の状態や気持ちをくみ取ってフィードバックする
- 研修医を萎縮させないコミュニケーションも大切
- フィードバックリテラシーの早期向上も重要ポイント
フィードバックは医学教育でも重要なもの
私は医学部を卒業した後、研修医を経て、千葉県の亀田総合病院で専攻医として経験を積み、安房地域医療センターでスタッフとして働きました。亀田総合病院と安房地域医療センターには教育熱心な文化が根づいており、私も次第に研修医の教育や指導をする立場になっていきました。そのなかで、苦労する後輩や挫折する後輩が少なくないことが気になり、どうすればもっと上手に指導できるのだろうと考えるようになったのです。
そこで私は、2017年に京都大学の「現場で働く指導医のための医学教育学プログラム(FCME)」を受講しました。現在は、名古屋大学医学部と名古屋大学医学部附属病院でFCMEの運営者として働きながら、医学教育学を研究しています。
企業と同じように、医学教育でもフィードバックは重要なポイントの1つです。今回は医学教育の観点から、フィードバックの変遷や効果的なフィードバックについてお話しします。
2010 年以前は指導者中心のモデルが一般的だった
医学教育の世界では、2010年以前は「指導者中心」の伝統的なフィードバックモデルが一般的でした。当時は「指導医が学習者(若手医師や医学生)にどう教えるか」に着目したモデルのニーズが高かったのです。その象徴が、5マイクロスキルとサンドイッチ・フィードバックです。どちらも1990年前後に医学教育へ開発や導入がなされました。
「5マイクロスキル」は1分間指導医モデルとも呼ばれ、フィードバックを短時間かつ簡便に行えることを意識して作られています。① 学習者に自分の考えを述べてもらう。② 学習者にその考えの根拠を述べてもらう。③ 一般論について指導者側から述べる。④ 今回学習者ができた内容について褒める。⑤ 今後改善すべきと考えられる誤りを正す。以上の5ステップでフィードバックする方法です。「サンドイッチ・フィードバック」はよりシンプルに、「称賛→批判→称賛」という形で批判の前後に称賛を挟む手法です。
こうした指導者中心のモデルは、処方的で医師が受け入れやすいこともあり、多くの指導医に広まりましたが、私はその効果には懐疑的です。もちろん、この種のモデルにもフィードバックの頻度や量が増えるなど、一定の効果はあります。しかし、指導者からの一方向的なアプローチのため、フィードバックの内容が学習者の行動につながらないことが多いのです。大切なのは、指導医の正しいアドバイスが研修医によく伝わって、行動変化や成長につながることです。指導者中心モデルは、その面で効果に限界があります。指導者はその限界を理解しておくべきです。
学習者中心モデルには「観察」と「信頼関係」が必要
2010年頃から、学習者への影響により目を向けた研究が増えてきました。そのなかから、R2C2モデルをはじめとする「学習者中心」のフィードバックモデルが登場してきました。
「R2C2モデル」は、次の4ステップでモデル化されています。① 学習者の文脈に配慮して関係性を築く。② フィードバック内容に対する学習者の反応を確認する。③ フィードバック内容の理解を明確にする。④ コーチングで実現可能な目標と行動計画を設定する。
このモデルにおける指導者は、学習者の内省を促すファシリテーターでもあります。学習者が萎縮することなくフィードバックを受け入れ、パフォーマンスや診療を向上できるよう促進する役割を担っているのです。つまり、R2C2モデルでは、指導者から学習者への一方向性の「指導」ではなく、双方向性の「対話」へと、フィードバックの捉え直しが起こっているわけです。
こうした学習者中心のフィードバックをする際に、指導者が大切にした方がよいことが2つあります。1つは、「学習者のパフォーマンスをよく見ること」です。パフォーマンスの観察がフィードバックのベースになります。それを見ずに対話するのは至難の業です。ですから私は、指導医の皆さんに、学習者のパフォーマンスを丁寧に観察してくださいとよく伝えるようにしています。
もう1つは、指導者と学習者が「常日頃から良い関係でいること」です。R2C2モデルに「学習者の文脈に配慮して関係性を築く」というステップがあるとおり、学習者中心のフィードバックには両者の信頼関係が欠かせません。
指導者の皆さんは、ぜひ日常的に学習者に声をかけたり、挨拶したり、雑談を交わしたりと、学習者を気遣っているサインを出してください。そうした地道な関係性づくりが、いざというときに利いてきます。大事なことを伝えるときや、厳しいことを言わなければならないときに、関係性次第でフィードバックの受け入れが大きく変わってくるのです。
学習者の状態や気持ちをくみ取ってフィードバックする
学習者中心のフィードバックをすることは、学習者の個々人に合ったフィードバックをするということです。分かりやすい例を1つ挙げます。手術の際、初心者研修医には、手術中の細かなフィードバックが効果を上げる可能性が高いです。初心者の場合、一つひとつの手術プロセスの理解や習熟が不足していることが多いからです。指導医が手術中にタイムリーにフィードバックする方が、初心者はパフォーマンスの向上を実感しやすいのです。
しかし、ある程度習熟した若手医師には、手術後にフィードバックの時間を用意したり、手術後の着替えの時間を活用して後からまとめてフィードバックしたりする方が、効果が高まる傾向があります。なぜなら、彼らは手術のプロセス全体を振り返り、つながりを意識してスキルを向上させていく段階にあるからです。手術全体を振り返りながら、「今回はあの選択がベストだった」と褒めたり、「あのときはこうする方法もあったのでは」と別の選択肢を提案したりすることが、彼らのためになるわけです。
このように学習者の状態や気持ちなどをくみ取った上でフィードバックするのが、学習者中心のフィードバックです。
研修医を萎縮させないコミュニケーションも大切
また、学習者の感情面で私が重視しているのは「研修医を萎縮させないコミュニケーション」です。当然ながら、医療現場では医療安全や患者安全が最優先です。しかし一方で、どのような名医も最初は初心者であり、経験を積まない限りは良い医師は育ちません。その時期の過度な緊張感は、研修医を萎縮させ、研修医が診察や手術を恐れたり避けたりするような事態を招きかねません。それでは医学教育はうまくいかないのです。
私自身が若手時代についた指導医は、「責任は私がとるから、自由に診療にあたってください」というタイプの人でした。最初は驚きや戸惑いもありましたが、存分にチャレンジできると共に、任されることで責任感も芽生えてきたことを覚えています。指導者がこのようにサポートしてくれると、学習者は安心してチャレンジしやすくなります。ですから私は、研修医が萎縮せず、モチベーションに火がつくようなフィードバックやコミュニケーションを心がけています。不謹慎にならない程度に緊張を解くような言葉をかけたり、勇気づけたりするのです。こうした学習者中心の視点がフィードバックの効果を高めます。
フィードバックリテラシーの早期向上も重要ポイント
学習者中心に加えて、最近は「フィードバックリテラシー」にも注目が集まっています。
フィードバックリテラシーとは、仕事や学習を改善するためにフィードバックを認識し、理解し、生成し、行動する学習者の「フィードバックを生かす」能力のことです。極端に言えば、研修医のフィードバックリテラシーが高ければ、指導医のフィードバックに多少の問題があっても十分に伝わります。もっと根本的なことを言えば、リテラシーが高まれば、学習能力そのものが高まります。ですから、学習者のリテラシー向上は非常に大切なポイントです。
私は今、医学部の学生たちに授業でフィードバックリテラシーを教えています。学部で臨床実習に入る前から、指導医のフィードバックをどう受け取ればよいかを学んでもらっているのです。このように早期から学習者のリテラシーを高めることが肝要だと考えています。
さらに、指導医のフィードバックスキルの向上も必要です。指導医には、フィードバックに対する研修医の反応から学びを得て、より良いフィードバックを追求してもらいたいと思います。
現在の医療業界は働き方改革の真っ最中で、指導医が若手への指導にかける時間をこれ以上増やせないのが現状です。だからこそ、一つひとつのフィードバックの質を高めていくことが欠かせません。また、フィードバックを含めた育成環境の整備は、病院にとっては採用などにも大きなプラスになります。ですから、医学教育におけるフィードバックの重要性は、今後ますます増していくでしょう。最近はテクノロジー活用も盛んに議論されており、AIを活用し、人とAIのフィードバックがブレンドされながら学習者を育てる未来もあり得ると考えています。
しかし、フィードバックに関しては、学習者中心とリテラシー向上がポイントであることは変わらないでしょう。この2点を押さえながら、今後もより良い医学教育を追求したいと思います。
【text:米川青馬 photo:角田貴美】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.79 特集1「成長と信頼につながるフィードバック」より抜粋・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
木村武司(きむらたけし)氏
名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター病院助教(副センター長)
福島県立医科大学卒業後、研修医、専攻医、安房地域医療センタースタッフを経験。2019年から京都大学医学研究科医学教育・国際化推進センターで大学院生として学びながら、京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター特定病院助教を務めた。2022年より現職。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












