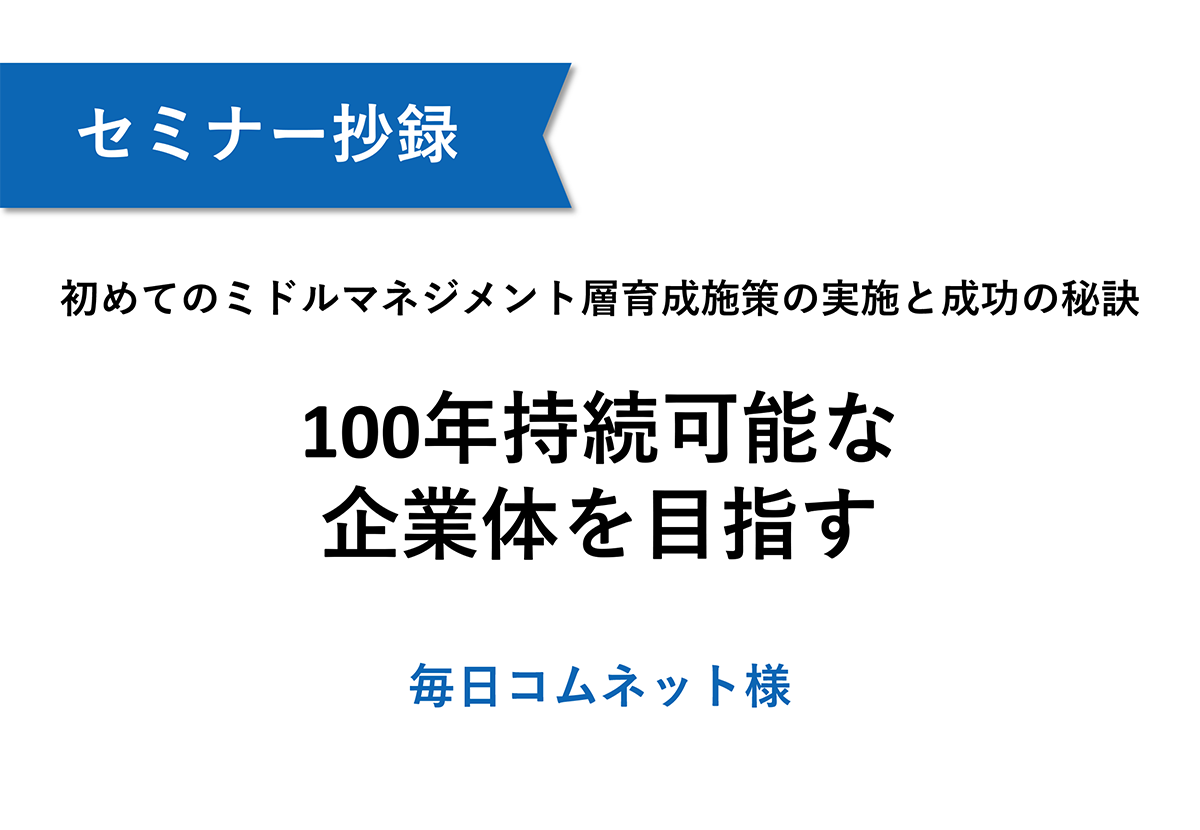インタビュー
社会を変えるリーダー
こたえのない学校 代表理事 藤原さと氏
- 公開日:2025/04/28
- 更新日:2025/07/17
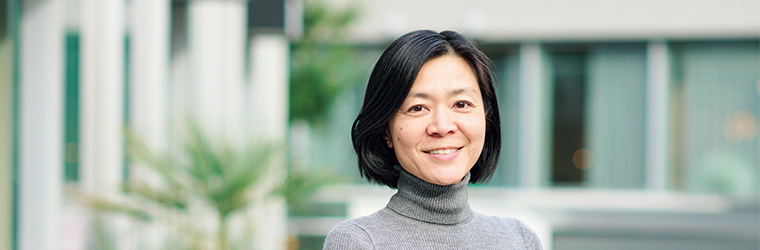
政治も経済も社会も、世界はますます混迷の度を深めている。かつてのような、誰もが分かる“正解”が見えにくい時代、正解の提示と伝達に力を入れてきた学校教育も変わるべきではないだろうか。探究をキーワードに、次代を担う子どもたちの新しい学びを模索する一般社団法人こたえのない学校の代表理事、藤原さと氏に、その活動内容とこれまでのキャリアを聞いた。
「探究を探究する」プログラム
現行の学習指導要領は、2020年度から日本の小中高の教育現場に順次導入された。この改定で多用されているのが「探究」という言葉だ。「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、知識の習得や活用だけではなく、探究が学びの1つの軸になったのである。
そうしたなか、非営利の民間団体であるこたえのない学校が「探究を探究する」をテーマに、2016年からスタートさせたLearning Creators’ Lab(以下、LCL)というプログラムが注目を集めている。
毎年、約8カ月をかけ、受講生たちが4、5名のチームを組み、各自の探究プロジェクトを開発、実施していく。受講生は現役の教員や教育関係者が多い。性別、私立公立の別、年代、教科の専門などは考慮するものの、選考はせず、申し込み順だ。定員は36名で実際の学校のクラスの人数に近く、「自分がクラスの子どもだったら」という気分をもてるようにしている。
チームはくじ引きで決める
2024年はミヒャエル・エンデの『モモ』を参考にした「星の時間」をテーマに、3月から11月にかけて開催された。理論編の講師は探究学習を実践してきた実務家や研究者が担当し、オンラインにて月1回のペースでワークショップを行う。
7月には東京の奥地、檜原村で1泊2日の合宿があり、古民家に宿泊。そこでチームがくじ引きで結成され、11月に行われるリアルの場での最終発表に向け、アルムナイ(卒業生)がメンターとなり、プランを練り上げていった。
藤原氏が話す。「くじ引きで決めたのに、中学校の理科の先生、高校の物理の先生、大学で航空宇宙分野を学んだ中学校の先生、課題解決型学習で有名な小学校の先生という4名が偶然、チームとなり、『“光”で生徒が自走する授業をつくる』というプロジェクトに挑みました。LCLは探究がテーマなので、ここまで本気に「授業」をやったケースは珍しい。30年後に温泉を掘ることをテーマにしたチームもあります。途中から、自分たちが温泉なんだと訳の分からないことを言い出して(笑)」
この研修の特徴についてはこう述べる。「各自のマインドが変容すること。探究学習のノウハウをつかみに来たのだけれど、気がついたら、探究する教育者としてのあり方が問われるんです」
初期の頃は手探りだった。研修中、ある受講生が怒り出した。「こんな中途半端な研修は見たことがない」と。「先生はピカピカに整備してから授業を送り出すんですが、私は企業出身なので、プロトタイプでいいでしょうと。そうしたら、他の受講生が『いや、これは自分たちが作る研修なんだから、いいんじゃないか』と言い出した。そんなふうに、ヘンテコな研修を受講生が面白がるようになったんです」
8期を終え、卒業生は多様な活動をしている。同じチームのアルムナイ同士で東京の世田谷にオルタナティブ・スクール(公教育とは異なるもう1つの学校)を作った例があるし、合宿で活用した檜原村の古民家も環境再生の団体と組み、山の再生を図るアルムナイが所有、合宿にも協力している。
娘の保育園の父母会長就任が転機
藤原氏は慶應義塾大学出身。考古学者に憧れ、最初は文学部に所属した。大学1年生のとき、お金を貯めてパキスタンに行ったものの、仏像に見入る研究者の顔を見て「こんな情熱は私にはない」と諦め、法学部政治学科に移る。現地で貧富の格差や難民キャンプの様子に心を奪われたからだ。
大学を卒業すると日本政策金融公庫で小規模事業者向け融資の仕事に従事した後、米国の大学院に留学し公共政策学を学んだ。帰国後はソニーに在籍、戦略部門で海外企業との共同開発や新規事業立ち上げなどさまざまなプロジェクトに携わる。同社を辞めたのは、子どもの出産に際して体調不良になったことがきっかけだった。
その後、娘が保育園に入り、その父母会長になったのが大きな転機だった。「私は典型的なワーキングマザーで、仕事も多忙でした。じゃんけんに負けて会長になったとき、面倒なことになったと思いましたが、意外に楽しいものでした。仕事中心の日々のなかで子育てに向き合ってみようと思い、地域での子どもの学びをどう支援したらいいか、考えるようになりました」
子どもが小学校に入る頃、学校での学び方や授業、テスト、通知表について違和感を覚えた。「学校には常に答えがあり、いかに素早く、しかも多くそこにたどり着けるかが生徒の評価の基準になります。ところが社会に出るとそこに答えはありません。それなのに、学校はなぜ答えのあることばかりにこだわっているのだろう。そんな疑問をママ友と話しているうちに出てきたのが、『こたえのない学校』というアイディアだったのです」
その後、探究という言葉に出合い、探究学習の専門家に話を聞きながら、2014年から小学生向けのキャリア教育型の探究プログラムを作る。同年、こたえのない学校という組織も立ち上げた。
探究プログラムのテーマはテクノロジー、医療、ビジネス、アートなどで、参加した子どもはプログラムの最後にびっくりするような“作品”を作り上げたが、2016年から教育者育成に徐々に軸足を移した。
具体的には先述したLCLや、心理的に安全な学習環境を作る「社会性と情動の学習」、「インクルーシブ教育」を学ぶカリキュラムなどで、企業人や行政職員などを含め、毎年100名ほどの社会人を受け入れている。その他、藤原氏は教育委員会や学校、企業向けの研修にも関わり、助言も行っている。
探究と人間の学び
そもそも探究とは何だろうか。辞書にはこうある。「物事の真の姿をさぐって見きわめること」(広辞苑)。
藤原氏いわく、「探究には歴史と系譜があります」。古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの著作『ニコマコス倫理学』に早くも「探究」という言葉が頻出しているという。「18世紀に近代教育の古典『エミール』を著したルソーは大人に教えてもらうだけではなく、子どもたち自身が学ぶ力をもっていると主張します。その流れを受け、ペスタロッチ、フレーベル、モンテッソーリといった新しい教育の唱導者が現れました。探究という言葉が近代教育のなかで使われたのは米国が最初で、19世紀に生まれたプラグマティズムという思想が大きな背景にありました。探究は今になって突然出てきたものではありません。その歴史をよく理解し、良い形で吸収、実践し、次代につなげていくことが必要です」
人間の学びに対する考え方には歴史的な変遷があるという。永続主義、本質主義、進歩主義、実存主義、社会改造主義などで、前の2つは学び手への知識の「伝達」に重きを置くのに対し、後の3つは学び手自らが知識を「構成」していく立場をとる。
永続主義、本質主義が学び手は「知る」前は無力だと捉えるのに対し、進歩主義、実存主義、社会改造主義は学び手がもともともつ「学ぶ力」を信頼する。「社会改造主義の考え方が私は好きなんです。今の社会はマジョリティが作ってきたもので、完璧なものではありません。だとしたら、私たちはそれを疑い、いい方に変えていく主体になり得るんです。そのための社会的変革を促すものが知識なのです。もちろん、探究する学びが正しくて、伝達する学びが間違っているわけではありません。調和のとれた総体的な学びを経験するにはどちらも重要です」
障がいのある子どもと海でサーフィン
藤原氏の活動の対象は広がり、2021年には、障がいや病気の有無、国籍や人種、宗教、性別といったさまざまな違いを超え、子どもたちが同じ環境で一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」と探究学習を融合させたFOX Labをスタートさせた。同教育の研究者や実践者に学ぶ一方で、実践活動もある。海岸環境の保護を目的とする国際NGOと連携し、重度の障がいのある子どもがプロのサーファーと一緒に湘南の海岸でサーフィンを楽しむ1DAY海キャンプである。「インクルーシブ教育の文脈でも、知識・技能供与の側面が非常に大きい。それが大切なことは分かるんですが、私はそこに探究というアプローチを入れていきたいんです。この10年余り、探究という言葉を中核に置いて活動してきましたが、正直いってその本質はまだつかめていません。それこそ探究しがいのある魅惑的な言葉です」
好きな言葉は、“日本のマザー・テレサ”とも呼ばれた福祉活動家、佐藤初女の「限りなく透明に凛として生きる」だという。「故人ですが、素敵な方です。私が体調を崩したとき、大変お世話になりました。初女さんのようなおばあちゃんになりたいとずっと思っているんです」
【text:荻野 進介 photo:山﨑 祥和】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.77 連載「Message from TOP 社会を変えるリーダー」より抜粋・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
藤原 さと(ふじわら さと)氏
一般社団法人 こたえのない学校 代表理事
慶應義塾大学法学部政治学科卒業。コーネル大学大学院修士(公共政策)。日本政策金融公庫、ソニーの本社経営企画管理・戦略部門などを経て、2014年、こたえのない学校設立。著書に『協働する探究のデザイン』(平凡社)など。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)