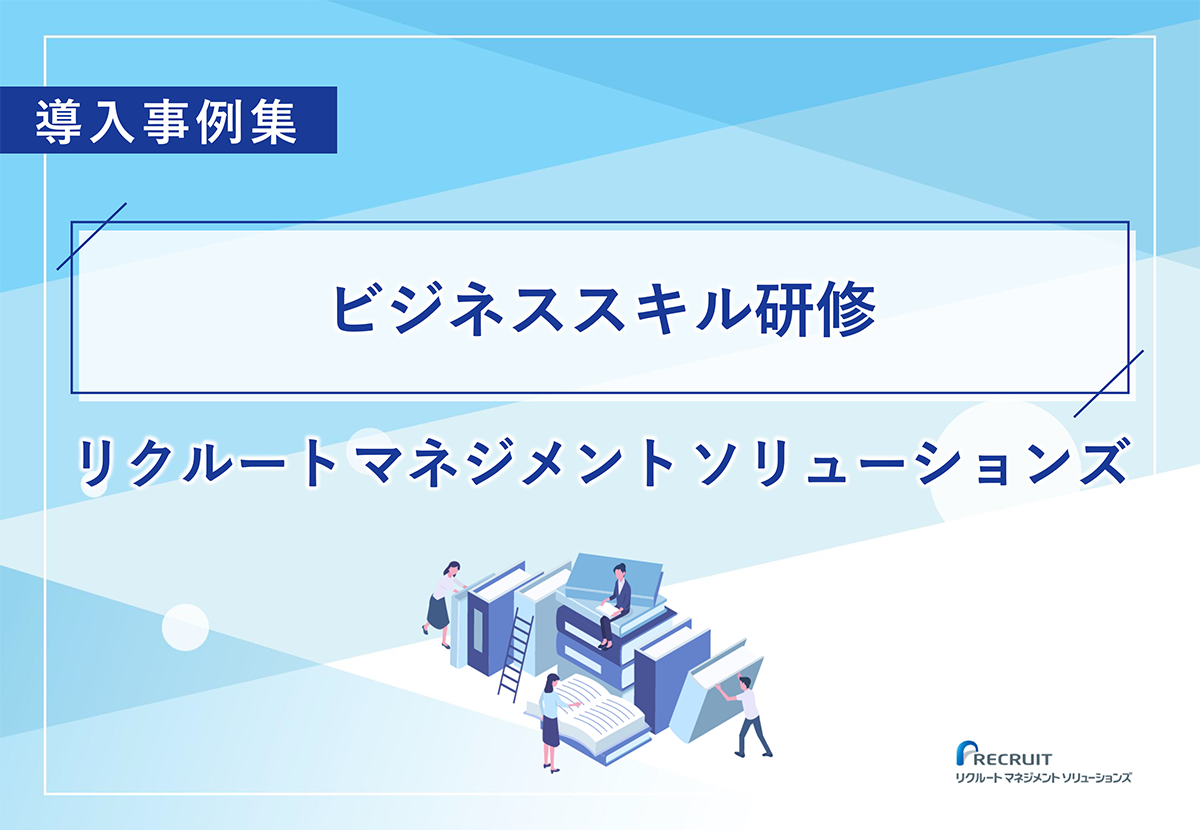- 公開日:2025/03/24
- 更新日:2025/07/17

人工知能学会元会長の松原仁氏(京都橘大学 工学部 情報工学科 教授)は、日本のAI研究を長くリードしてきた。特に、AIに小説を創作させる「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」で有名だ。松原氏に、AIが社会にどのような変化を起こすのか、AIがもたらす新しい学びの可能性と課題は何かを伺った。
- 目次
- 急激なAIの発達に不安を覚えるのは自然なこと
- AIが人間を完全に上回ったとき人間はAIを受け入れる
- 言語の壁をやすやすと越える「リアルタイム音声翻訳アプリ」
- 日常的に生成AIに触れて「AIリテラシー」を高めよう
- AIは人間や企業の「差別化」を難しくするツールでもある
急激なAIの発達に不安を覚えるのは自然なこと
私は1981年に東京大学大学院に入り、人工知能の研究を始めました。若い皆さんは知らないと思いますが、人工知能研究には過去2回の「冬の時代」があり、そのときには人工知能はもうダメだといわれました。私が研究を始めたのは1回目の冬が終わりかけた頃で、周囲からは人工知能の道に進むことを止められました。
しかし、今やAIは驚異的なブームを迎えています。これはAI研究の第一人者、ジェフリー・ヒントンでさえ予測できなかったことです。ChatGPTの開発者たちも、ChatGPTがこれほど人間とうまく対話できるようになるとは思っていなかったそうです。AIの発達や実用化は、私たち研究者の想定を超える速さで進んでいるのです。
このAIの発達スピードを見て、不安を覚えるのは自然なことです。私のもとには、さまざまな人たちが「AIをどう活用し、どう対応したらよいでしょうか?」と相談にやってきます。今日は、そうした場でよく話すことをお伝えします。
AIが人間を完全に上回ったとき人間はAIを受け入れる
企業の皆さんが最も心配していることの1つは「AIが人間の仕事を代替すること」でしょう。これに関しては「別にAIに限ったことではない」と答えています。18世紀に蒸気機関が発明されて以来、進歩したテクノロジーは必ず人間の仕事を代替してきました。AIもその一種と考えれば、何も不思議ではありません。他のテクノロジーと同じように、AIも私たちの仕事を代替するのです。
ただAIは、レベルの高い知的労働を代替する点が従来のテクノロジーと大きく異なります。人間は優れた知性によって自然界のトップに君臨した生きものです。ですから、AIに知性トップの座を脅かされるのが怖いのは当然のことです。
この不安に対して、私は「時が解決します。AIの発達に早く慣れましょう」と伝えるようにしています。分かりやすい例が、将棋です。
私は長い間、将棋AIを研究してきました。将棋AIが弱かった頃は、プロ棋士も将棋ファンも私たちを温かく見守ってくれました。ところが将棋AIが強くなってくると、軋轢が生まれ、私たちへの風当たりが強くなりました。プロ棋士の皆さんは、自分たちの仕事がAIに奪われるのではないかと不安になり、将棋ファンの皆さんは、プロ棋士がAIに負ける姿を見たくなかったからです。
その後、将棋AIの強さはプロ棋士を追い抜きました。2017年には、AIが当時の現役名人・佐藤天彦さんに勝利しました。将棋ファンなら誰もがよく分かっていることですが、現在の将棋AIは藤井聡太さんよりも明らかに強い存在です。
今や、将棋界はAIの圧倒的な強さにすっかり慣れています。将棋AIがどれだけ強くても、誰もが藤井さんを天才と称賛しています。藤井さんやプロ棋士の多くが、将棋AIを積極活用して実力を磨いています。さらに将棋ファンは、将棋AIがリアルタイムに形勢判断する「評価値」を見ることで、将棋観戦をより楽しめるようになりました。
AIが人間を完全に上回ったとき、人間はこのようにAIを受け入れるのです。今後は他分野でも同じようなことが次々に起こるに違いありません。
言語の壁をやすやすと越える「リアルタイム音声翻訳アプリ」
実は、科学やビジネスや芸術の世界では、将棋界と同様の事態がすでに起こりつつあります。
例えば、「Sakana AI」という会社があります。Google社の著名なAI研究者たちが日本に移り住んで設立したAI開発の新興企業で、日本発の画期的なAIサービスを次々に提供し始めています。その1つに、論文のアブストラクト(要約文)から論文を書くAIサービスがあります。私は人工知能研究を始めた頃、論文のアブストラクトを書いたら、AIが論文をすべて書いてくれる世界を夢見ていました。彼らはそれを実現しつつあります。
AIの発展が特に進んでいる領域の1つが、翻訳です。生成AIは、もはやTOEICで満点に近い点数をとれるまでになっています。もう少ししたら、AIリアルタイム音声翻訳アプリが完成し、世の中に広まるでしょう。そうすれば、私たちは言語の壁をやすやすと越えられるようになります。
AIは芸術の世界でも優秀です。私は、AIに小説を創作させる「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」を主宰してきました。本プロジェクトでAIが執筆した小説は、過去に星新一賞の一次審査を通過しています。AIは小説も書けるようになってきたのです。それだけでなく絵を描くことも、作曲することもできます。
日常的に生成AIに触れて「AIリテラシー」を高めよう
生成AIは今後飛躍的に高度化し、あらゆる領域で多くの仕事を代替するようになります。私たちはさまざまなシーンでAIと共存する必要があるのです。その際、私は次の3つの能力がポイントになると考えています。「AIリテラシー」「コミュニケーション力」「考えて選ぶ力」の3つです。
「AIリテラシー」とは、AIと付き合う際の知恵やノウハウのことです。例えば、最近「生成AIのウソ」が注目されています。確かに生成AIは、事実と違う情報を語ることがあります。AIは人間と違い、それが事実かどうかを判断できませんから、厳密にいえばウソをついているわけではありません。間違いとは知らずに、堂々と正しい文章のなかに間違いを紛れ込ませることがあるのです。この「ウソ」を見分けるのは難しく、見方によっては人間のウソ以上に困りものかもしれません。
しかしこの問題は、複数の生成AIを使えば、ほとんど解決できます。いくつかの生成AIに同じ質問を投げかければよいのです。すべてのAIの答えが同じなら、正しい確率が高いと見てよいでしょう。どれかが違うことを言った場合には疑ってかかればよいのです。このようにAIの性質をよく理解して、上手に使いこなすことが大切です。
生成AIを使いこなすコツの1つは、「質問の深掘り」です。生成AIは曖昧な質問をすると、曖昧な答えしか返してくれません。ところが、その曖昧な答えに対して、「具体的にはどういうこと?」「その言葉の意味を教えて」などと、さらに深掘りする質問を投げかけると、詳しく説明してくれるのです。こうやってAIと何度もやり取りすると、生成AIの回答も磨かれていきます。
こうしたAIリテラシーの向上に最も効果的なのは、日常的に生成AIに触れることです。よく考えれば、人間も不正確な情報を話したり、曖昧な答えをしたりすることは珍しくありません。AIはそんな人間と同じようなものだと思えばよいのです。こうした性質や特徴に慣れるには、毎日のように生成AIを使うのが一番の早道です。
現在、多くの日本企業や官公庁が、生成AIのウソ・情報漏洩・著作権侵害などのリスクを気にして、生成AIの導入を躊躇しています。しかし、それでは従業員の皆さんはいつまでもAIリテラシーを高められません。早期導入をお薦めします。それができないようなら、せめて「プライベートでAIに触れましょう」と奨励することを勧めます。
AIは人間や企業の「差別化」を難しくするツールでもある
生成AIの長所の1つは、感情を気にする必要がないことです。人間が嫌がるようなこと、例えば同じ質問を繰り返すようなことをしても、AIは決して怒りません。AIが相手だと、そうしたことを気にせずに気楽に質問できるのです。
人間相手のコミュニケーションは、そうはいきません。人間は感情の生きものですから、例えば相手の考えが間違っているときはやんわりと否定するような心づかいが求められます。これが2つ目の重要な能力「コミュニケーション力」です。
どれだけAIを上手に使いこなせても、周囲の人間とコミュニケーションがとれなければ、仕事にはなりません。当然ながら、この社会では今後も人間との対話が欠かせないのです。ですから私は学生たちに、大学時代にコミュニケーション力を磨いておこうと伝えつづけています。
3つ目の大事な能力は、「考えて選ぶ力」です。AIは、全人類の標準的能力を一定レベルまで一気に高めてくれるツールです。見方を変えれば、AIは、人間や企業の「差別化」を難しくするツールでもあるのです。今後、AIの普及と同時に、多くの企業やビジネスパーソンが、自らの差別化ポイントを再考することになるでしょう。
私が、多くの人の差別化ポイントとなりそうだと考えているのが「考えて選ぶ力」です。これは膨大な情報のなかから、自分に必要な情報がどれかを主体的に考え、選び取る力です。さらにいえば、どの行動を優先すべきかを主体的に考え、実行に移す力です。AIと人間が共存する時代には、考えて選ぶ力さえあれば、あとはAIが力強くサポートしてくれるでしょう。だからこそ、この力があるかないかで差がつくのです。
考えて選ぶ力を鍛える上で役立つのが、「読書」です。本を一冊読んで、そこに何が書いてあるかを考える訓練が、考えて選ぶ力の基礎力となるのです。最近は若い人を中心に読書の習慣がなくなりつつあります。だからこそ、私は読書量が人の能力や人生を一層大きく左右するようになるのではないかと考えています。ですから、私はことあるごとに、学生たちに「本を読みましょう」と伝えています。社会人の皆さんも、同様に読書習慣を身につけることをお薦めします。
AI、ロボットとの融合によって、ある人は不可能と思われていたことを克服し、またある人は可能性のフロンティアに挑むでしょう。未来では、そうした新たな人類「ポスト・ヒューマン」によるまったく新しい社会が生まれていくと私は考えています。皆さんも、ポスト・ヒューマンを目指す第一歩として、3つの能力の向上から始めてみてはいかがでしょうか。
【text:米川 青馬 photo:角田 貴美】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.77 特集「テクノロジーで変わる職場の学び」より抜粋・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
松原 仁(まつばら ひとし)氏
京都橘大学 工学部 情報工学科 教授
京都橘大学情報学教育研究センター長
1986年東京大学大学院情報工学専攻博士課程修了。通商産業省工業技術院電子技術総合研究所(現・産業技術総合研究所)、公立はこだて未来大学教授、東京大学教授を経て、2024年から現職。『AIに心は宿るのか』(集英社インターナショナル)など著書多数。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)