- 公開日:2023/10/02
- 更新日:2024/05/16

障害者雇用とインクルージョンを考えるにあたっては、日本の障害者雇用制度の観点から考える必要がある。その背景にある問題意識は何か。企業が解決していくべき課題は何か。厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課課長(取材時) 小野寺徳子氏に詳しくお話を伺った。
アセスメントを強化して一般企業で働く障害者を増やす
日本は、民間企業に法定雇用率以上の障害者を雇用する義務を課しています。この場合の障害者とは、障害者手帳を持っている身体障害者・知的障害者・精神障害者のことを指します。一方で、ハローワークはもっと広い範囲で障害者支援を行っています。障害者手帳を持っていない人々、例えば「病院でおそらく自閉症だと診断されました」といった人々の就労支援もしているのです。私たちはどちらも障害者雇用と捉えています。
2016年から、障害者雇用促進法では企業が障害者を雇用するにあたり、障害者一人ひとりへの「合理的配慮」の提供を義務化しています。合理的配慮とは、それぞれの障害特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。例えば、光の刺激が得意でない人は、仕事中もずっとサングラスを掛けることを理解した上で雇用してもらう必要があります。同様に、耳の聴こえない人には周囲に筆談をお願いしたり、疲れやすい人には休憩時間を設けてもらったりすることがあります。
問題は、障害者本人が自分にどのような配慮が必要かを十分に理解できていないケースがあることです。自己理解が不足していると、必要な配慮を受けられず、実力を発揮できなかったり、障害が悪化したりすることが少なくありません。
そこで私たちは、2022年12月に障害者総合支援法を改正し、「就労選択支援制度」の創設を決めました。就労選択支援とは、就労アセスメントを活用した支援です。就労を希望する障害者が就労支援サービスと協力して、自分はどのような職種や労働条件で働きたいのか、どのような能力・適性があるのか、就職後にどういった合理的配慮が必要なのかなどを評価・整理することです。
現在は特別支援学校の卒業生のうち、30%ほどは一般企業に就職しますが、すぐに一般企業に就職するのが難しい30%ほどの皆さんは、就労系障害福祉サービスを活用しています。就労選択支援を強化すれば、働く自信をつけ、思いきって一般企業にチャレンジする障害者が増えるのではないかと考えています。特別支援学校から一般企業に就職する人々、就労系障害福祉サービスから一般企業に移行する人々が増え、より多くの皆さんが適切な合理的配慮を受けながら、企業で活躍することを期待しています。
また、働いている最中に精神障害となった人々のなかには、本当は休憩などの配慮が必要なのに、自分は配慮などなくても働けると思い込んでいるケースが見られます。そのためにかえって精神障害を悪化させることがよくあるのです。そうした人々にも就労選択支援を活用し、自己理解を深めてもらえたらと考えています。
親会社やグループ会社でも障害者が働くことが望ましい
もう1つの新制度として、2024年4月から「障害者雇用相談援助助成金」(仮称)が始まります。障害者雇用に係るノウハウを有するコンサルタント会社や地域のNPO法人などに助成金を支払い、1年間にわたって、企業に伴走型の障害者雇用コンサルティングをしてもらう取り組みです。具体的には、障害者雇用に関する課題の洗い出し、障害者に適した仕事の切り出し、障害者の受け入れに必要な組織マインドセット変革などのコンサルティングを行います。
この助成金の特徴は、特例子会社に対しても、親会社やグループ関連会社への障害者の転籍・出向を実現することで助成金の支給対象としていることです。
私たちは、法定雇用率が上がるなかで特例子会社だけが肥大していくことを懸念しています。本来は、特例子会社だけでなく、親会社やグループ会社にも障害者が在籍し、障害者雇用が法人全体に広がっていく状態が望ましいのです。この助成金は、障害者雇用のノウハウが十分でない中小企業などに対して取り組みの裾野を広げていくだけではなく、障害者雇用のインクルージョンの理想形を目指すための制度でもあります。
障害者雇用は社会貢献に限らず経営戦略として優れている
私たちが企業の皆さんに障害者雇用を勧めるのは、法定雇用率のみの達成や単なる社会貢献のためだけではありません。障害者雇用が経営戦略につながるものであるからです。
例えば、とある農業法人では、実に興味深い障害者雇用に取り組んでいます。この農園は年に1人、その年に特別支援学校のなかで最重度と思われる生徒さんだけを雇用し続けています。そして、その人にどのような仕事をお願いし、どう働いてもらえばよいかを社員全員で考えています。その人に働いてもらうためには、作業工程をより丁寧に整えたり、機械に工夫をしたりする必要があります。その生徒さんがしっかり働けるようになることで、結果的に組織全体の労働生産性が高まったり、労働環境がより良くなったりして、経営改革が進むのです。
同じように障害者を戦力化し、ビジネスを伸ばしている会社が、実は地域に多くあります。なぜなら障害を特性と捉え、一人ひとりの際立った特性に適した仕事を切り出せば、むしろ一般の労働者以上に能力を発揮し戦力になるからです。例えば、発達障害の皆さんはゲームのデバッグ(ゲーム開発中に不具合を発見する仕事)が得意なことが多く、優秀なデバッガーになる可能性が高いといわれています。また、ある警備会社は精神障害者の慎重さや生真面目さといった特性を生かし、雇用することで、事故率を大幅に下げることに成功しています。精神障害者には、臨機応変な対応は難しいのですが、定型的な警備業務には向いているのです。
ある大企業は、視覚障害の人たちを、電話だけで営業を完結する「通信営業職」として雇用して高評価を得ています。この通信営業職を企画したのは、視覚障害のある人事部スタッフです。人事が視覚障害者の強みを熟知していたからこそ生み出せたポジションなのです。
もちろん、これらの企業はより良い障害者雇用にたどり着くまでに、多くの失敗と試行錯誤を経験し、それらを乗り越えるための話し合いを重ねています。しかし、その試行錯誤や話し合いこそが成功の鍵であり、障害者雇用に取り組む醍醐味なのです。
障害者にとって良い職場は、全員にとって良い職場です。多くの障害者は一生懸命に仕事に取り組みます。その姿を見て感動し、襟を正す社員が多いという話もよく耳にします。障害者はできることが少ない、雇う上で負担が大きいと感じている会社は、障害者に接する機会が少なく、よく知らないだけです。まず1人でもよいので障害者を雇用し、一緒に働き、過ごす時間をもってみてください。それが障害者インクルージョンの第一歩です。
【text:米川 青馬 photo:伊藤 誠】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.71 特集1「障害者雇用・就労から考えるインクルージョン」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
小野寺 徳子(おのでら のりこ)氏
厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 課長(取材時)
早稲田大学卒業後、障害児の集団療育の現場で指導員として1年間勤務した後、1990年労働省(当時)に入省。山梨労働局職業安定部長、埼玉労働局職業安定部長、ハローワークサービス推進室長、首席職業指導官を歴任し2019年7月より現職(取材時)。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


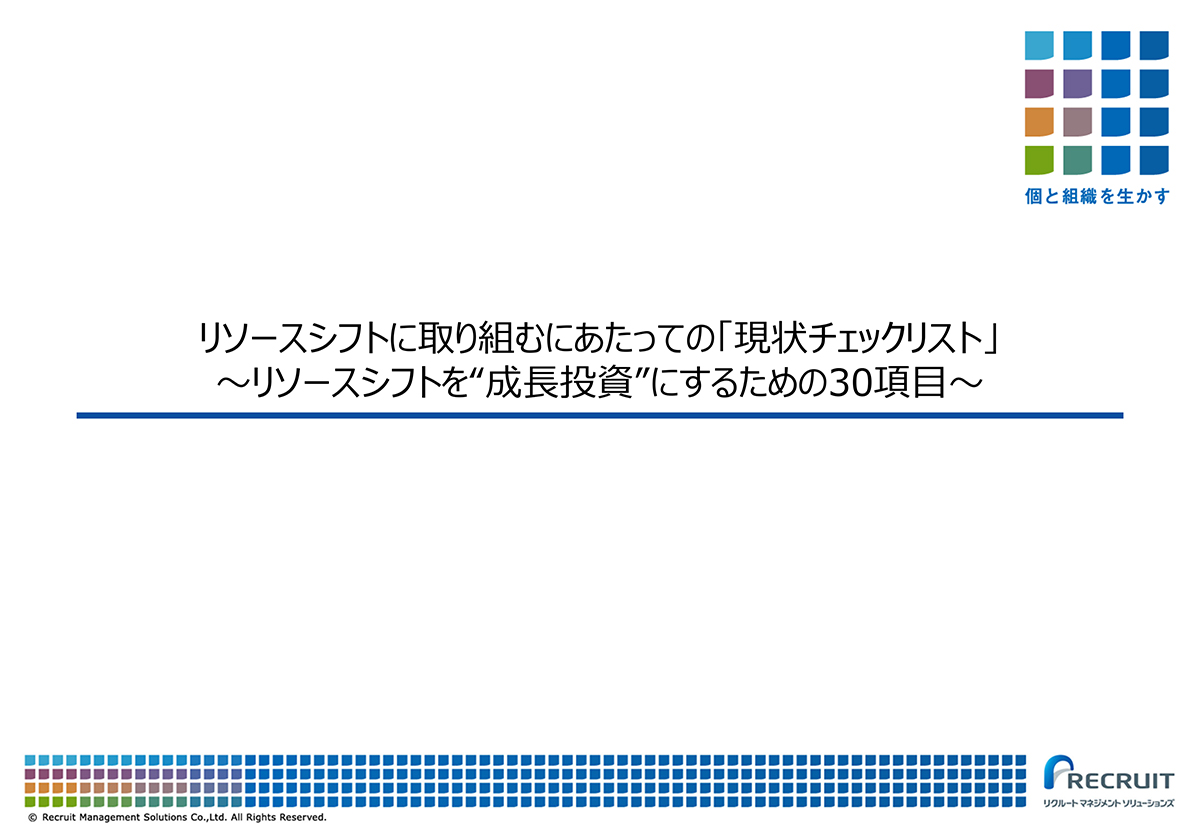











 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で