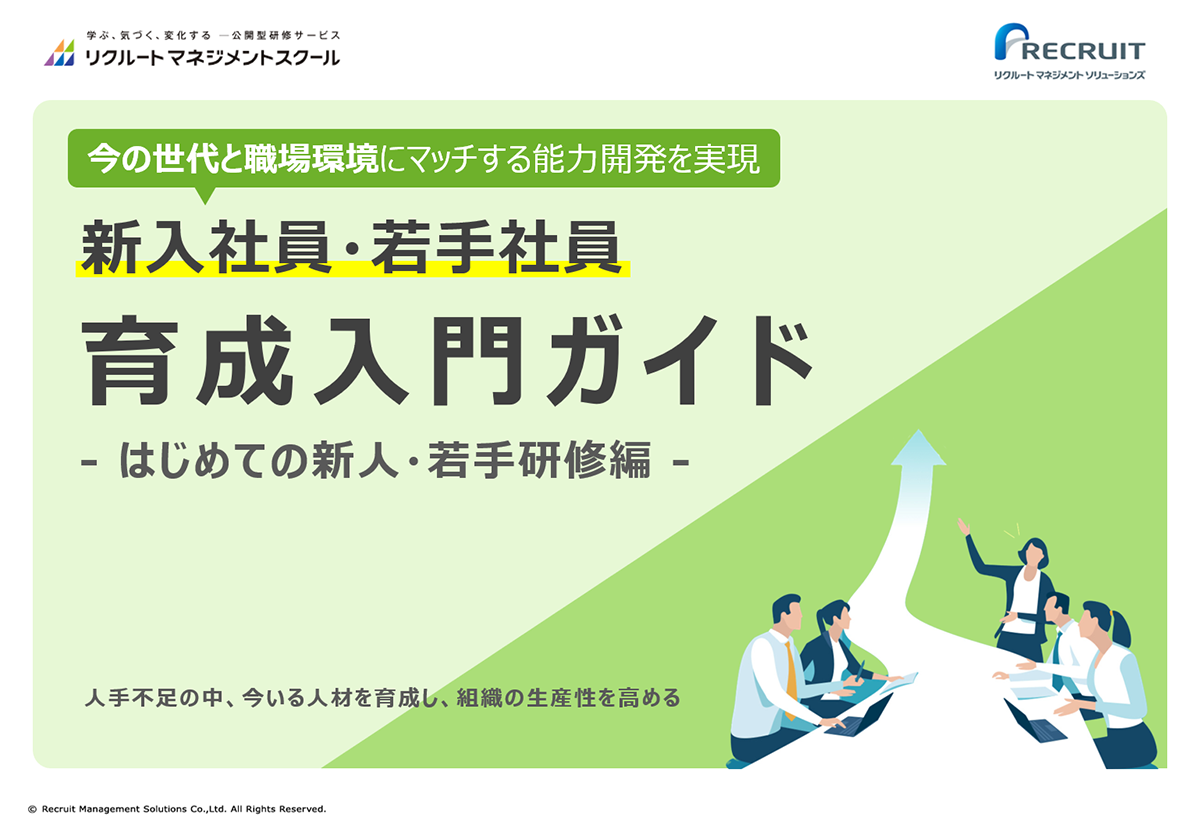インタビュー
立教大学 中原 淳氏
オンボーディングには個人の頑張りと職場の働きかけの両方が大切だ
- 公開日:2021/09/13
- 更新日:2024/05/17

中原淳氏は、1万2000人の大規模調査を経て2021年に出版した『転職学』* の冒頭で、、自分自身がオンボーディングに苦労した体験談を綴っている。『転職学』で転職を科学した中原氏は、新人・若手のオンボーディングについてどう考えているのだろうか。
* 中原 淳・小林祐児・パーソル総合研究所(2021).働くみんなの必修講義 転職学 人生が豊かになる科学的なキャリア行動とは KADOKAWA
- 目次
- 転職時には学び直しの期間、オンボーディング期間が必要
- 個人はソーシャルスキルを発揮 組織は4つの支援を行うべし
- 知識やスキルは想像以上にポータブルではない
- 今の新人は現状に最も早く適応しているが不安は大きい
転職時には学び直しの期間、オンボーディング期間が必要
2018年、43歳の私は東京大学を辞し、9人の助教・研究員・事務スタッフたちと共に、研究室ごと立教大学へと移籍しました。
立教大学は、すばらしい研究環境・教育環境を私たちに提供してくれました。ところが数カ月後、学生の前で板書をする私の右手は震えるようになってしまったのです。原因は、立教大学にはありません。そうではなく、私は、かつての大学では、大学院での指導がメインで、主に大学院生、社会人を教えてきたのです。しかし、立教大学では、20代の学部生に教えるようになった。移籍当初、私は、学部生への教え方や、関わり方を習熟できていなかったのです。恐らく、ここから精神的なプレッシャーを感じていたのでしょう。右手が震えて、それを隠しながら授業をしていました。これが私のオンボーディングの苦い経験です。
『転職学』は自身のこうした経験を踏まえ、転職には「ラーニング思考=学び直し」が重要だ、というスタンスで書いた本です。私の場合で言えば、私は「教え方」を再学習しなければならなかった。
日本では転職者の即戦力神話がはびこっており、最近は新人のジョブ型雇用も話題になっています。会社としては入社すぐに活躍してほしいわけですが、現実的には難しい。転職時には学び直しの期間、オンボーディング期間が必要です。
オンボーディングはベテランも新人・若手も基本は同じで、個人の学び直しや主体的な行動が欠かせません。一方で、オンボーディングには職場の働きかけも必要です。個人の頑張りと職場の働きかけの両方がなければ、オンボーディングはなかなかうまくいかないのです。
個人はソーシャルスキルを発揮 組織は4つの支援を行うべし
まずは個人の頑張りについてです。新卒者もベテラン転職者も、オンボーディングの際には孤独にならないために、周囲と積極的にコミュニケーションをとることをお勧めします。
その際に発揮していただきたいのが、あいさつや会議・会話を始めるための「関係開始スキル」、相手の立場を考えて真面目な態度で接する「関係維持スキル」、不愉快な思いをしたときにはっきりと伝える「主張性スキル」です。この3つのスキルを磨けば、職場での関係づくりは必ずうまくなります。ソーシャルスキルは生得的な性格ではなく、獲得できる技術です。
また、就職・転職の際、忘れない方がよいのは、「学び直しが必要だ」という心構えです。これまでの経験から得た学びを捨てる「アンラーニング(学習棄却)」も、新たな職場になじむ上で欠かせないことの1つです。
一方で、職場側には「4つの支援」が求められます。
第一は、仕事や振る舞いについてアドバイスする「メンタリング支援」、第二は、職場で「誰が・何を・知っているか」を教える「ネットワーキング支援」です。第三は、振り返りや気づきを促す「フィードバック支援」で、第四は、安心や心理的な安全を提供する「セーフティネット支援」です。転職者がこの4つの支援を受けているかどうかで、なじみの早さやジョブ・パフォーマンスが大きく変わってきます。私の場合で言えば、同僚には大変恵まれたと思います。多くの支援を同僚から得ることができました。シンドイ時期も、彼らの支えやサポートで何とか乗り越えられましたので、感謝しています。
なお、リモートワークでは、ちょっとした隙間時間に話す「隙間のコミュニケーション」、観察して学ぶような「察しのコミュニケーション」、飲み会を開いたりする「祝祭的なコミュニケーション」、部門を超えた「部門間連携コミュニケーション」の4つのコミュニケーションが失われがちです。オンボーディングでは、マネジャーは、これらを補完する工夫をするとよいでしょう。例えば、Zoom会議が終わった後、マネジャーと新人の2人だけが残り、少し会議の振り返りをするといった取り組みに効果があるはずです。
知識やスキルは想像以上にポータブルではない
なぜオンボーディングには、個人の頑張りと職場の働きかけの両方が必要なのでしょうか。
大きな理由は、知識やスキルは、世間で思われているよりもポータブルではないからです。前職の知識やスキルが、新たな職場では想像以上に役に立たないケースが多いのです。知識・スキルには領域固有性や文脈依存性があるからです。
私がまさにそうでした。教えることにはそれなりの自信があり、新たな大学でも問題ないと思っていましたが、それをうまく転用できませんでした。教える対象が大学院生・社会人学生から、学部生に変わったからです。やってみてはじめて分かったのですが、大学院生に教えるのと学部生に教えるのでは、まったく話が異なるのです。
大学院生・社会人学生に教えるときは内容の細部を省略できるのですが、学部生は知識や社会人経験がありませんから、彼らが何を分かっていないかに寄り添い、学問の入り口まで連れてくる必要があります。当初、私はそのことを理解せず、今までどおりに教えていました。当然ながら、学部生たちは私の言っていることが分からず、口をポカンと開けるばかりでした。私はなぜ彼らの反応が悪いのか分からないまま、しばらく1人で空回りしていました。そうしたら、右手が震えるようになったのです。
私は、この時点で間違いに気づき、格好つけるのを止めました。学生たちが、人材開発・組織開発のなかで学びたいテーマを選び、それを発表し合い、それについて、私がコメントしたり、補足したりする教え方に転換しました。私は、新たな教え方を学び直しました。これまでの教え方を、アンラーニングしたわけです。そうしたら徐々にうまく回るようになりました。幸い1年間ほどで、右手の震えもなくなりました。最初は苦労しましたが、私は転職に大満足しています。
今の新人は現状に最も早く適応しているが不安は大きい
私が見る限りでは、職場のオンボーディング支援の善しあしには相当の差があります。上手な職場は、マネジャーが中心となり、ウェルカムメッセージ、キーパーソンの紹介、歓迎会やランチ会などを丁寧にやっていますが、離職率が高い会社ではほとんど行われていません。離職率が高いと、採用や育成のコストが無駄になり、職場メンバーの気持ちも落ち込みます。離職率を下げたいなら、地道なオンボーディング支援に力を入れるべきです。
また、離職率の高い会社で起こりがちなのが、「面接と現場のズレ」です。面接官の話と現場の状態の間にズレがあると、入社者のモチベーションが下がり、オンボーディングが一気に難しくなります。これを防ぐ有効手段は、現場マネジャーが面接プロセスに入ることです。現場メンバーが面接官の1人になると、さらに良いでしょう。
最後に、私のゼミの卒業生たちの声を届けます。新人として就職した彼らは今、「コロナ禍の新卒入社、かわいそうだね」と言われるたびに腹が立つそうです。コロナ禍以前の働き方を経験しているわけではないので、そういうことで同情してほしくない、ということです。一方で、先輩たちと同じように働けているかどうかを大変気にしています。
恐らく現状のリモートワークに最も早く適応しているのは、新人・若手の彼らです。決してかわいそうな存在ではありません。ただ、彼らの不安が大きいのも事実です。彼らの適応と不安を気にかけながらオンボーディングを支援していただけたら、きっと大きな戦力になるはずです。
【text :米川青馬】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.63 特集1「変わるオンボーディング」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
中原 淳(なかはらじゅん)
立教大学 経営学部 教授 立教大学大学院 経営学研究科
リーダーシップ開発コース 主査
東京大学教育学部卒業。大阪大学大学院人間科学研究科、メディア教育開発センター(現放送大学)、マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学准教授などを経て、2018年より現職。『経営学習論』(東京大学出版会)、『組織開発の探究』(ダイヤモンド社)など著書多数。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)