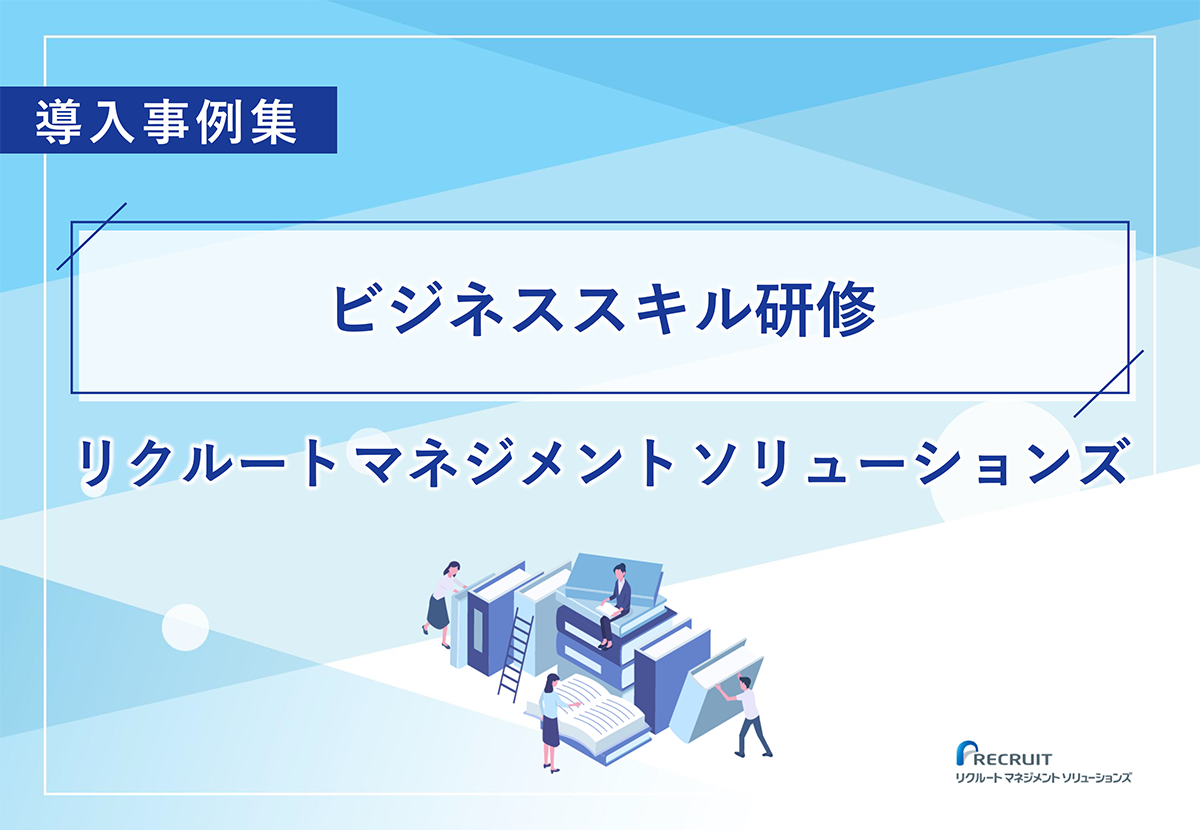インタビュー
上智大学 杉谷陽子氏
対面とオンラインの長所・短所を知り上手に組み合わせればいい
- 公開日:2020/12/21
- 更新日:2024/05/21

今後、オンライン会議システムはビジネスで欠かせないものになるだろう。では、対面コミュニケーションは必要なくなるのだろうか。果たしてオンラインだけで、職場内の信頼を構築できるのだろうか。対面とオンラインの情報伝達の違いに詳しい杉谷陽子氏にお話を伺った。
対面はメール・チャットよりも道具的情報が伝わりにくい
今でこそ、メールやチャットはごく当たり前のものになりましたが、これらが普及した2000年代以前は、メールなどのインターネットを介したコミュニケーションへの懐疑的な見方が強くありました。最も丁寧で言いたいことが伝わりやすいのは対面コミュニケーションだ。メールやチャットは対面に比べると意思疎通が難しく、対面で話せないときに仕方なく使うツールだ。こうした認識が一般的でした。しかし私は、その考え方に疑問をもっていました。実は、対面よりもメールやチャットの方が、情報伝達において有利な場面があるのではないか、と感じていたのです。そこで、対面とメール・チャットの情報伝達の違いを比較する実験を行いました。
実験の結果、2つのことが分かりました。
(1)対面コミュニケーションの方が、メール・チャットよりも情報の伝え手の満足度が高かった。つまり、主観的には、対面の方が相手に情報が伝わった、理解してくれたと感じやすい。
(2)しかし、メール・チャットの方が、対面よりも情報理解度テストの正答率が高かった。つまり、メール・チャットの方が、情報が相手に正確に伝わり、理解が深まりやすい。
まとめると、対面コミュニケーションは伝え手の満足度はより高いが、情報は伝わりにくく、メール・チャットは伝え手の満足度は高くないが、情報はより伝わりやすいのです。
なお、ここでいう情報とは、「道具的情報(論理や手順などの説明)」や「事実」のことです。こうした情報に関しては、対面よりもメール・チャットの方が詳細まで正確に伝わるのです。仕事の具体的なシーンでいえば、ある場所への道順や今日の会議の議題、提案内容とその根拠などは、メールで送付したり、チャットで伝えたりした方が、間違いが少なくなります。
対して、後で詳しく説明しますが、喜怒哀楽などの「感情的情報」は、やはり対面の方がメール・チャットよりもよく伝わります。
なお、私が研究したときは、Zoom、Teamsなどのオンライン会議システムがまだ存在していませんでしたが、オンライン会議はメール・チャットよりは対面に近いものの、対面と比較すれば、物理的な「場」を共有していない点などにおいてメール・チャットと同様の特徴をもつと位置づけられます。
非言語的な手がかりは脳に負荷をかける
なぜこうした違いがあるかといえば、対面コミュニケーションでは「非言語的な手がかり」が豊富に伝わる一方で、メール・チャットではほとんど伝わらないからです。
非言語的な手がかりとは、言葉以外のコミュニケーションの要素、例えば、表情やジェスチャー、声の調子などのことです。これらは、時に言葉の意味を正反対に変えてしまうほど、感情的情報を強く伝えます。例えば、相手が「今日はつまらなかった」と言ったとしても、笑顔で言ったのなら、親しみを込めたユーモアと解釈できるでしょう。反対に怒った顔をしていたら、本当につまらなかったと思っているのでしょう。そうした意味を的確に見極めるには、非言語的な手がかりに注意しなければなりません。対面コミュニケーションにおいて、表情やジェスチャーは重要な要素です。
だからこそ、非言語的な手がかりは、脳にそれなりの負荷をかけると考えられます。対面コミュニケーションでは、話す側も聞く側も、自分の表情や身ぶり手ぶりなどに気をつけながら、相手の表情や身ぶり手ぶりにも気を配っているのです。反対にメールやチャットは、そうした情報が欠けている分だけ脳の負荷が少なく、言葉の理解、道具的情報や事実の理解に集中しやすいというわけです。
では、オンライン会議の非言語的な手がかりはどうかといえば、やはり対面とメール・チャットの中間に位置づけられると思われます。詳しく説明すると、「対面→オンライン会議→電話→チャット→メール」の順に、非言語的な手がかりが少なくなります。オンライン会議でも、ある程度の非言語的な手がかりは伝わりますが、現状では対面に及びません。
誠実な意図を確かめるのは対面の方が向いている
では、今後のビジネスコミュニケーションはどうしたらよいのでしょうか。私の結論は、「対面とオンラインの長所・短所を知り、上手に組み合わせればいい」というものです。
2020年前半は、大学同様、コロナ禍によって多くの企業がオンライン中心で業務を進めてきたと伺っています。きっとそのなかで実感していると思いますが、オンライン会議やメール・チャットだけでも、日々の業務の多くは問題なく進められるはずです。なぜなら、説明したとおり、オンラインの方が対面よりも、むしろ道具的情報や事実を詳細まで正確に伝えやすいからです。業務の多くは道具的情報でできており、オンラインはそれらの情報を扱うのに適しているのです。
ただし、だからといって、対面コミュニケーションが必要ない、というわけではありません。感情的情報を伝えたいときには、対面で会議をした方がよいと思います。
なかでも、対面コミュニケーションが最も効果を発揮すると思われるのは、「誠実な意図への信頼」を確立したいときです。社会心理学では、信頼は、相手の「能力」への信頼と「誠実な意図」への信頼からなるといわれてきました。能力への信頼が、この人は能力が十分あるから安心して仕事を任せられる、という信頼であるのに対し、誠実な意図への信頼は、この相手は誠実だから不正や裏切りをしないだろう、という信頼です。この信頼を確かめるには、表情・しぐさなどの非言語的な手がかりが重要になりますから、対面の方がオンラインよりも優位性があるでしょう。また、対面でコミュニケーションすると、相手と分かり合えたという「伝達感」が得られます。これも誠実な意図への信頼の醸成におおいに役立つはずです。
例えば、新人社員が、上司や同僚と一度も会わずに、スムーズにチームに入っていくのはかなり難しいことだと思います。少なくとも上司とは何度か対面で話し合い、誠実な意図への信頼を確かめ合い、高め合う必要があるでしょう。そうしたコミュニケーションを省略して、すべてオンラインで進めるのはあまりお薦めできません。また、定期的な面談や業務の進捗確認なども、上司と部下ができれば対面で、最低でもオンライン会議でお互いの顔をしっかりと確認しながら行った方が、効果が上がるはずです。
もう1つの信頼である「能力への信頼」は、道具的情報と深く結びついており、オンラインでも十分に確かめたり深めたりすることが可能でしょう。実際、今の仕事現場では、初対面の相手とメールやチャットのやり取りだけで取引や業務を進めることも多々あるはずです。メール・チャットだけでも、相手の仕事ぶり、能力の高さ、熱心さなどは十分伝わってきますから、相手の能力が信頼に値するかどうかを判断することはできるのです。
もっといえば、対面の場合、相手の見かけや様子が良いために能力が高いと勘違いしてしまう、という誤解が生じる可能性もあります。そのことを考慮すれば、非言語的手がかりの乏しいオンラインの方が、能力について適切な判断ができるかもしれない、とさえ思われます。
以上をまとめると、基本的な業務はオンライン中心で進めてもかまいませんが、少なくとも誠実な意図への信頼を醸成する際には、上司が対面コミュニケーションを積極的に活用することをお薦めします。こうやって対面とオンラインを上手に組み合わせることが、コミュニケーションを円滑に進める上でとても大事なことです。
【text:米川青馬】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.60 特集1「リモート時代の職場の信頼」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
杉谷 陽子(すぎや ようこ)氏
上智大学 経済学部経営学科 教授・経営学科長
2008年一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。同年、上智大学経済 学部経営学科助教。同准教授を経て2019年より現職。専門は消費者心理学、社会心理学、マーケティング論。著書に『消費者行動の心理学』(分担執筆・北大路書房)などがある。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)