インタビュー
早稲田大学 島田陽一氏
労働法から見る越境 副業の全面禁止は法的に問題あり
- 公開日:2017/02/13
- 更新日:2024/03/22

社外への越境という意味で、最も古くから行われていた活動といえば副業だろう。最近はやや変わりつつあるが、日本企業は副業に寛大とは言い難い状況だ。労働法はこの問題をどう解釈しているのだろうか。早稲田大学 法学部 教授 島田陽一先生にお話を伺った。
就業時間以外の時間の使い方は労働者の自由
会社と社員の間には労働契約関係が成立しています。労働契約とは使用者の指揮監督のもとで労働者が労務を提供し、それに対して会社が報酬を支払う契約のことです。
労働を行うのは就業時間、つまり所定労働時間プラス時間外という形で、枠がはめられています。
それ以外の時間を労働者がどう使うか。つまり、趣味に没頭しようが、家で寝ていようが、ボランティアに夢中になろうが、副業をやろうが、労働者の自由なのです。まずこの大原則を押さえておく必要があります。
農業は副業の王様だった 第二種兼業農家の存在
歴史を振り返ると、日本社会と副業は切っても切れない関係にありました。農業ではなく、もう一方の仕事から主な所得を得ている第二種兼業農家の存在です。いわば農業を副業にしている人たちです。その昔、郵政や国鉄など、現業公務員のなかには田畑を持ち、そこから収入を得ている人たちが相当数いました。
農業だけではありません。実家が商店を営んでいる場合、会社から帰って仕事を手伝う人や、土地持ちでアパート経営をしている人もいるでしょうし、株や投資も、お金儲けという面では副業と同じです。でも、これらが今まで大きな問題とされたことはありません。
では、労働者は副業をし放題なのかといえば、そうではありません。
労働契約の埒外である就業時間以外の時間において、労働者と会社との関係が完全に切れているわけではないからです。契約上の明記はなくても、法原則である「信義誠実の原則」が適用され、労働者は会社の名誉や信用を守り、会社にとって不利益な行為に手を染めず、しかるべき秘密は保持するという義務を負っています。
その結果、「やってはいけない副業」が出てくるわけです。イメージ重視の会社に勤めているのにそれを毀損するような仕事、競業他社での仕事、会社で知り得た情報を利用して行う仕事などがそれにあたります。逆にいえば、それ以外の理由で会社が副業を禁じることはできないと考えるべきです。
翌日の仕事に支障が出るのは何も副業だけではない
では、自分の特技を磨き成し遂げたことが収入につながるケースはどうでしょうか。銀行に勤務しながら、シンガーソングライターとしても活躍した小椋佳さんが典型です。最近はITを利用したアプリ製作やアフィリエイト(成果報酬型広告)で稼ぐ人が増えています。
この場合も、同じように「信義誠実の原則」が適用されるだけで、会社が規制するのは行きすぎです。
「副業をやると、翌日の仕事に差し支えるから禁止している」という人事がいますが、論理的にはおかしなことです。
徹夜で飲み歩いたり、ハードなスポーツをやったりすると、翌日の仕事に支障が出がちです。それらはとやかく言わず、副業だけを目の敵にするのは説得力に欠けます。
副業を全面禁止するのではなく、許可制にし、先に挙げたような、会社が禁止することに合理性があるような内容でない限り、原則、認める。仕事に支障が生じたら、副業を問題視するのではなく、その事実をもって本人の責任を問えばいいことです。
許可の際に働きすぎの防止を注意勧告
ただ、副業には働きすぎという問題がつきまといます。
労働基準法第38条に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とあります。A社で正社員として働き、B社でアルバイトしている人がいると、一日の労働時間の上限は8時間と決まっていますから、A社で6時間働くと、B社での副業は2時間に制限されてしまいます。
それ以上、働いてもらうにはB社が時間外手当を支払わなければなりませんが、それは非現実的でしょう。よほどの人材でない限り、そんな要求は通りません。つまり、副業者に限ればこの条項は有名無実化しています。
従って、副業を許可する際に働きすぎにならないよう、労働者にしっかり伝えるべきでしょう。
もう1つ、自宅と会社の往復途上での事故や怪我という通勤災害の問題もありましたが、こちらは解決しています。
これまでは自宅から最初の会社への経路と、2番目(副業先)の会社から自宅に戻る経路の2つでしか認められていなかったのですが、2005年に労働者災害補償保険法が改正され、最初の会社から副業先に向かう経路上での事故や怪我にも保険給付がなされるようになりました。
【text :荻野進介】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.44 特集1「「越境」の効能」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属・役職等は取材時点のものとなります。
PROFILE
島田陽一(しまだよういち)氏
早稲田大学 法学部 教授
1953年生まれ。75年早稲田大学法学部卒業。83年同大学院法学研究科博士課程修了。83年小樽商科大学講師、84年同助教授、94年同教授。97年早稲田大学法学部教授(現職)。 2004年同大学院法務研究科教授(併任、現職)。2014年より早稲田大学副総長も務める。共著『ケースブック労働法第4版』(有斐閣)、『社会法の再構築』(旬報社)、『条文から学ぶ労働法』(有斐閣)。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


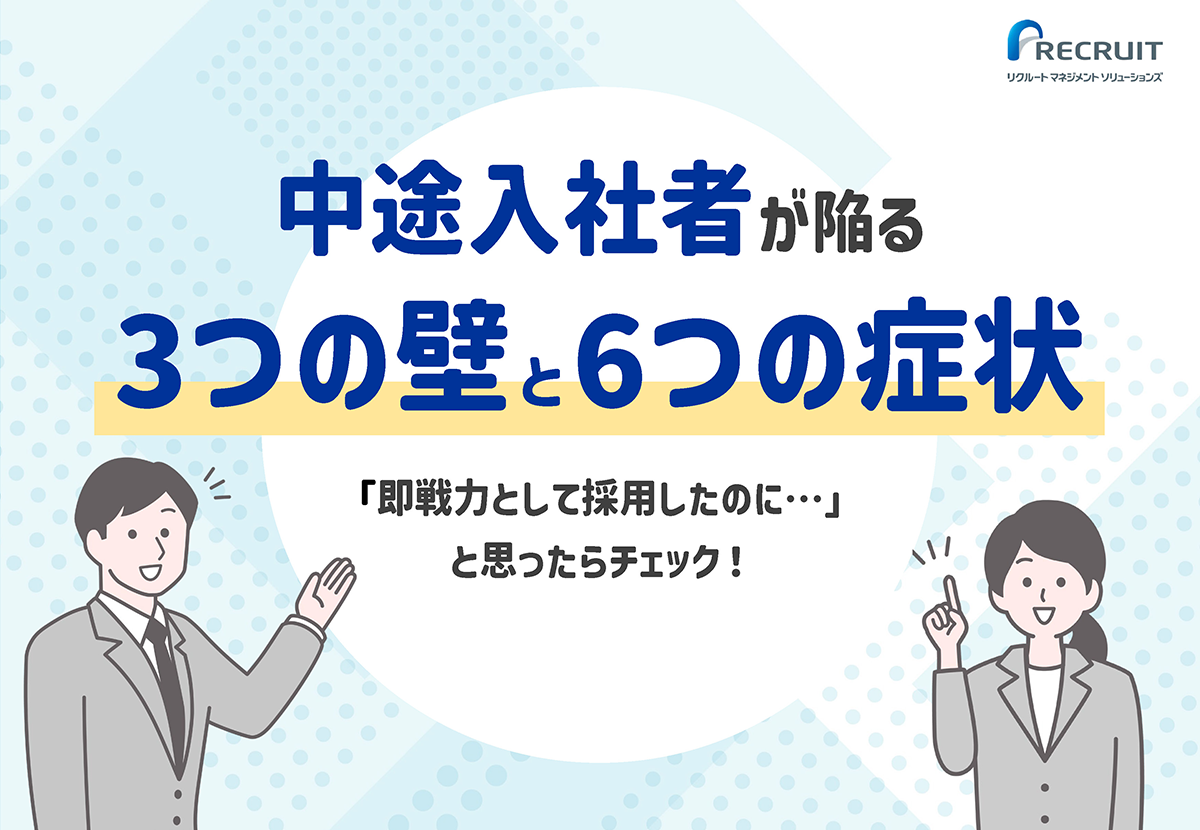
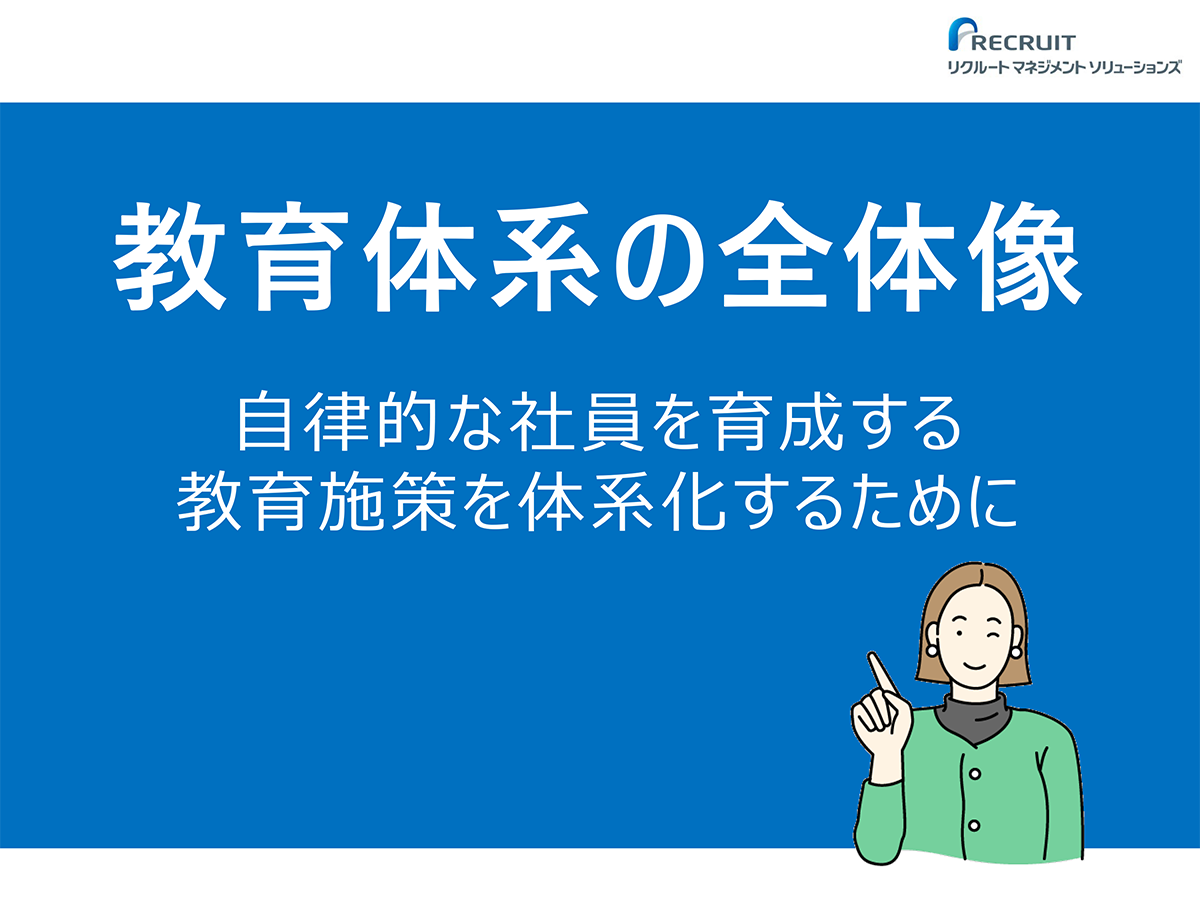
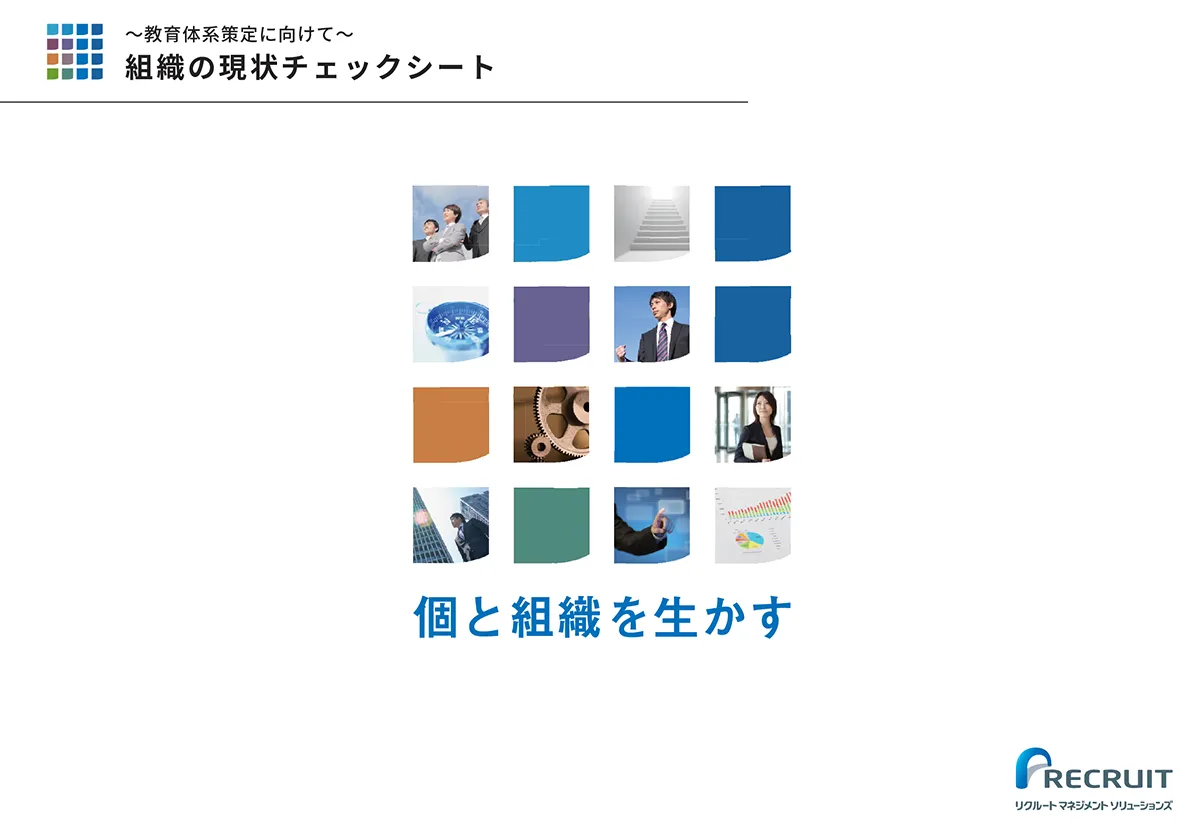









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で