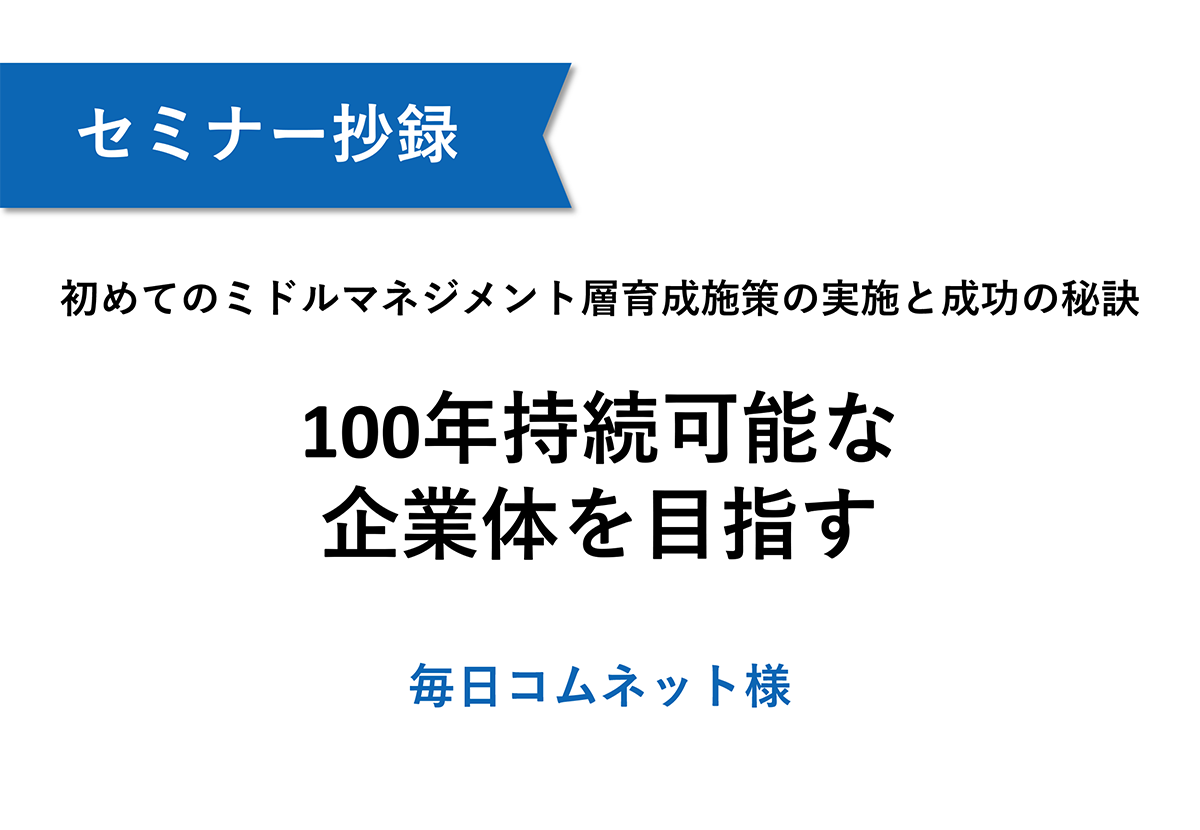インタビュー
「プロ経営者」の育ち方・育て方 第5回
神輿には乗りたくない、財務諸表と現場力で企業の再建を 上山 健二氏
- 公開日:2011/05/25
- 更新日:2025/04/15

このシリーズでは、「プロ経営者」の育ち方・育て方への示唆を得るために、複数企業で経営者としての実績をあげた社長へのインタビューを行っています。今回はその第5回として、ジャック(現カーチスホールディングス)、長崎屋、GABAにて社長職を歴任されている上山健二氏にお話を伺いました。
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第10回
- 多くのすばらしい経営者に直接触れて 織畠 潤一 氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第9回
- 好きなこと、得意なことを伸ばしてBtoCビジネスの変革を 田岡 敬氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第8回
- 「為せば成る」を原点に、志と行動力が結果を生む 秋元 征紘氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第7回
- 学びを実践しながら、自己に対する厳しさを持ち徹底的にやり抜く 池本 克之氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第6回
- 合理的・合目的的な意思決定と人とのつながりを大切に 平松 庚三氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第5回
- 神輿には乗りたくない、財務諸表と現場力で企業の再建を 上山 健二氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第4回
- アメリカ本社での5年間の経験が経営観の礎に 村上 憲郎氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第3回
- 自分を深く知ることによって、経営者としてぶれない軸をもつ 河田 卓氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第2回
- ベストパフォーマンスを出すために学び続ける 山田 修氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第1回
- 32歳のときに45歳で社長になるという目標を 新 将命 氏
- 目次
- 経営者になる覚悟 ~いずれ日本にも経営者の人材流通マーケットが
- 日々の鍛錬 ~MBA留学と修羅場経験の連続
- 主観的業績 ~最もタフだったジャックの最後の1年半を乗り越えたこと
- 強み・弱み ~絶対あきらめない、ぶれない頑固もの
- 理想の経営者 ~自分に対する厳しさをもった規律のある人
経営者になる覚悟 ~いずれ日本にも経営者の人材流通マーケットが
― まず、上山さんが経営者になる覚悟をいつどのように決めたのかについてお伺いします。2007年の「Road to CEO」の記事で、おばあ様のお話や、経営者に会いたくて都銀を選んだということを拝見しました。
そうですね、大阪で自転車屋をやっていた祖母に「商売人に向いている」と言われたことが結構心に残っていたというのは確かにありましたが、実際銀行を就職先に選んだ時に、経営者になる覚悟をしていたかと言えば、そこまでの覚悟は当然していませんでした。ただ、いちばん経営者に会える職業は何だろうという考えはもっていました。大学4年の夏に最後にもう1社と住友銀行とで迷った時には、どちらが社長に会えるかを結構考え、都市銀行のほうが経営者に会えると思ったんです。また、大学では野球部にいたのですが、OBで住友銀行に行った人が当時いなかったんですね。他の銀行に就職した先輩方からも誘っていただいたのですが、自分が異端的だなと思うところなんですけれど、先輩の多いところに行って東大野球部OBのOne of them となるよりは、初めてというほうが面白いと思って住友銀行に行きました。
― 銀行に入られて、どこかのタイミングで「自分は経営者になるんだな」と思われたのですか?
銀行からミシガン大学のMBAに留学させてもらった時には、向こうの人たちは前の会社を辞めて来ていますから、できる人ほど自分でスタートアップしようとか、優秀な人ほど自分の会社を経営したいという意識の強い人が多いのを目の当たりにしました。そこですごく刺激を受けたのですが、自分は銀行から派遣してもらっていたので、すぐ辞めて外に飛び出すというようなことはその頃は全く考えていませんでした。会社に恩返しをしようという思いで帰って来たんです。
留学から帰って来て約2年半は新橋でバブル崩壊後の法人営業をやって、その後企画部に移りました。予算セクション、MOF担(銀行側の大蔵省担当)のサブ、IRなどを経験しました。IR担当の時には、頭取と打ち合わせする機会などもあって、こういう世界もあるのだと勉強になりました。その当時、企画部長が常務取締役で、私とはちょうど入行が20年違いました。常務ですから雲の上の人なんですけれど、その方ですら経営会議の1票を持っていなかったんですね。その時単純に思ったことは、あと20年経って万が一出世させてもらったとしてもまだ銀行の経営に直接タッチする立場になれないんだな、ということでした。今の体力・気力の充実している時に、もっと経営者に近いところで生きていけたらいいなと思い始めました。
それは頭取、部長など偉い人だけを見て思ったわけではありませんでした。本部に行くと各年次のトップの人が数人ずついるので、年次ごとのトップが必ず年功序列になっているのが如実にわかるんです。もちろん仕事のできる人がたくさんいるんですけれど、40代にさしかかってくると、自分がこの組織で執行役員になるには、という発想にだんだん切り替わっていくようでした。そのためにはどうしても、失敗しないように生きていこうと思うようになるんです。図抜けて優秀な人だけがたまに突出して異端的な発言をしたりしていましたが、だいたい角が取れてきます。それを見ていたら、10年、15年後の自分が想像つかなかったですね。とんがっていましたから。言いたいこと言って、怒られて、でも銀行のためになることを自分は言っているんだと思っていましたから。
その頃、新橋で法人営業をしていた時に新規先として取引をとったジャックから声がかかったんです。それもたまたま店頭公開の祝電を私が打ったのがきっかけでした。将来のことをちょうど考えていた時だったので、どうしようかと思った結果飛び出しました。飛び出したきっかけも、たまたま4月の新人研修の講師を命ぜられて、辞意を表明せざるをえなくなったからでした。前途洋洋たる気持ちをもった新人の前に講師として立って、1ヶ月間、こんなに素晴らしい仕事だからがんばれよという話をする仕事です。私としてはそれをやったら絶対辞められないと思ったので、とっさの判断で誰にも相談せずに辞めることを口にしてしまいました。
― いろいろな偶然が重なったのですね。
企画部に異動する前に、日比谷と新橋で外回りをやっていましたから、数百名の社長に会っていました。パパママショップの社長さんから上場企業の社長まで、いろんな人を見ていますよね。この方みたいにはなかなかなれないだろうなと尊敬する人もいるし、まあ自分もこれくらいのことはできるなとか、もっとうまくできるなと思える人もいました。そんな時に、銀行という大企業で働いているよりも、こういう仕事のほうが面白そうだなと思ったことは多々ありました。いろいろな局面で思いが募ってきていたというのは事実です。
ただ、転職する時の覚悟は今から思うとまったく甘いです。展望を全く描けずに辞めていました。自分はもともと営業マンの時もそうでしたし、今のGABAの来年度予算などを考える時もそうですが、結構ストーリー立てるんですよね。1個1個、これをこうやったら、こうなって、こうなるんじゃないかなというところまで、1本の道を作って、その通りに進んでいけた時が何度かありました。1本こう細い道が光って見えるみたいな感じで。そういうふうにするのがたぶん好きなんですけれど、最初の転職の時はそこまでシナリオを作ったりストーリーを作ったりする前に飛び出してしまいました。だから今から思うと考えも浅かったなあと思うし、怖くもなります。
― ジャックに転職した時には、どれくらいそこで勤めようと思っていたのですか?ずっと勤めるつもりだったのですか?
それは思っていないですね。オーナー企業の雇われ副社長として、大して株も持たずに入っていますから、前職では直接経営にタッチしていなかった自分がそれをできるようになれば、かなりの勢いでかなりのことを吸収できるんじゃないかという漠然とした期待をもって入りました。10年以上勤めるようなそんなイメージはもっていなかったですね。ただ、3年でとか5年でとか、そういう期限を自分で作って入ったというわけでもないです。
次は自分のビジネスを立ち上げるのか、あるいは職業経営者的な道を歩むのか、それはわからなかったですけれど、銀行を辞める時に思ったことは、経営者の人材流通マーケットで生きていく経営者になれる可能性があるんだったら挑戦したいということでした。日本の経済界ってアメリカの何十年か後を行っていると昔から言われていて、日本の経営者の人材マーケットは当時なかったですが、アメリカには厳然とあって、アメリカのみならず欧米にも一定規模の経営者の人材流通マーケットがあって、経営者として一定の成果を出して生きていく人たちがいる。そういう世界が日本にも必ず来るだろうという楽観的な思いがあって、自分も挑戦したいと思いました。だから、自分の会社を立ち上げるか、職業経営者の道に行くのかわからないけれども、銀行を辞めたというわけです。MBAに行っている時、向こうの大手のCEOはだいたい生え抜きはおらず、あの頃でジャック・ウェルチくらいでした。それを見ていてこういう世界が日本にくるかもしれないと、アメリカほど活発でないかもしれないけれど、日本にもそういうニーズが出てくる可能性があると思ったのです。
日々の鍛錬 ~MBA留学と修羅場経験の連続
― 経営者になろうと思われた時に、その頃から始められた日々の鍛錬というものはあったのでしょうか?
大学時代は、経営財務のゼミ以外は単位をとって卒業させてもらうために試験を受けていたような学生だったので、自分のアカデミックなバックグラウンドに全く自信がなく銀行に入ってしまっていました。ですから、銀行に入ってからは、全銀協の通信教育も全部やりましたし、証券アナリストの通信教育もやって、夜、独身寮で結構勉強はしました。その時点では経営というよりは、銀行員として通用する素養は身につけようということで必死にやっていました。営業として結果を出さないと銀行では認めてもらえないと思っていたので、結果につながるためにはどうしたらいいかを毎日考えていました。
あとはMBAに行かせてもらうためにいろいろ画策をしましたね。支店長に頼み込んで、その方のおかげで行けたようなものです。ふつう3年目で内示が出て4年目に行くんですけれど、3年目に内示をもらえなかったのであきらめていたら、4年目に内示があって、5年目に滑りこませてくれたんです。それはすごくラッキーでした。当時は、MBAをとってくればオールマイティなのではないかという幻想があったんですね。だから留学させてほしいということを強烈にアピールして、人事調査でもボールペンでふつうは書くところを蛍光ペンでアンダーライン引いたりして。それで行かせてもらいました。
― 経営者になった後に、何らか継続してされていることはありますか?
振り返ると、何かを意識して自分を鍛えるということはなかった気がします。銀行を辞めて移ってからというもの、ジャックと長崎屋の時にはとにかく休んでないんですよ。GABAも平日忙しいので結局土日どちらか出社することはありますが、それでも長崎屋の時の比ではないですね。長崎屋の時は、土曜日は全部出ていましたし、日曜日も何かあれば出ていましたから。特に長崎屋は更生会社でしたから、待ったなしというか断崖絶壁で毎日生きているようなものなので、意識して何かをするというよりも、何かをせざるをえなくて、という感じでした。その前のジャックも最初は成長企業の調子の良い部門の担当だったのでそうでもなかったんですけれど、オーナー会長が横領事件を起こした後からは、何かを意識して自分を鍛えるというよりは、荒波にもまれていました。
主観的業績 ~最もタフだったジャックの最後の1年半を乗り越えたこと
― これまでの経験のなかで、主観的に自分としてはこれはやれたなという仕事は何ですか?
自分がいちばんこれはやれたなと思うのは、ジャックがつぶれなかったことです。現預金が240億円あると思って銀行はジャックに金を貸していたんですね。借入金が130億円あったんですよ。しかし、実際には現預金は40億円しかなかったという状況で、銀行に返済を待ってもらいながら商売して、キャッシュフローをプラスにすることでなんとか回せるぎりぎりの状態でした。その少し前に大型の小売店舗を複数出店していましたので、仕入れが先行して資金繰りは少し大変だった。そこへもってきて、あるはずの現預金が実際200億すっとんでいたんですよ。だからこれはやばいなと、真っ青でした。そこで逃げないおまえがばかだと言う人も当然いるんですけれど、自分としてはそこで辞めても自分には何も残らないし、ただそんな会社に転職してばかなやつだなで終わって次の展望が開けないで辞めるのも癪に障ったので、辞めるということは考えなかったです。ただ、民事再生の記者会見で頭を下げている夢は何度も見ました。そこから、オーナー一族から担保として取った自社株を何とか他社に譲渡できる道筋まで作れたのですが、あの局面でそれができた人はジャックには自分しかいなかっただろうと思います。オーナー会長が横領事件で逮捕されるに至るプロセスも含めて、尋常でないことが多すぎてあまり比較もできないですけれど、自分としては今までの社会人経験の中でいちばんタフだった状況で、なんとかそれを乗り越えられたというのがジャックの最後の1年半でした。あれよりも厳しいことはもう絶対ないと思っています。実際、長崎屋も更生会社ですから倒産した後で、自分が行ったのは負債を棒引きしてもらった後だから、ある意味前向きなんですよね。でも、競争が激しくもともと商売のきつい小売業だから、そんなリスクの高いところに行って、と人からはよく言われましたけれど、生きている店舗が何店舗かあってそこでの運営なので、ジャックの最後の1年半に比べれば大したことないなと思えて、長崎屋にも行けました。
― 複数企業で社長をやられてみて、ご自身で得意とするフェーズ、業種、規模などがあるのか、ないのか、そのあたりはいかがですか?
得意とするフェーズは、どこでも大丈夫と言いたいところですが、圧倒的に建て直し期に自信があります。そこしか自信がまだないです。業種や規模は関係ないと思います。全業種をやったわけではないので偉そうなことは言えませんが、ビジネスというのは、いろいろあっても結果は全部BSとP/L、キャッシュフロー計算書に表われます。そこに全ての問題が集約されていると思いますし、実際集約されていますから、BSとP/Lがあれば十分です。だから業種はあまり関係ないと自分では思っています。規模も100倍するか10倍するか、いろいろあるとは思いますけれど、BSの中身と言うのはそれほど変わらないと思います。
― 外から入ってくる時に、DAY1から何をするかということについては、自分の中ではどの会社に行く時でもこういうふうにやろうというのは決まっているのですか?
会社の状況によって変わりますが、いちばん大事なのは最初に幹部社員を集めてオフィシャルな場で話をするタイミングです。それはどの会社でも共通で、それをいつやるか、どういう内容にするかは入ってから決めます。長崎屋の時は、筆頭株主(更生会社のスポンサー)であるキョウデンの橋本会長と相談して、入社してから1ヵ月半後にやりました。その時も橋本さんはお手並み拝見という感じで、社長をさせるつもりだけれどまだ社長にするとは公言しないので、社長室長としてプレゼンしろと、数ヶ月やってやれそうだったら社長にすると言われていました。GABAは規模も長崎屋よりかなり小さいし、事前に有報は見ていたので数字を見るのにもそこまで時間はかかりませんでした。ですので、11月1日に専務執行役員として入社して1週間後に、3週間後の11月21日にやることを決めて実施しました。何よりもその一発目が大事です。長崎屋の場合は更生会社ですから、過去の悪いところを指摘しても仕方ない。債権者に泣いてもらって膿が出た後ですから、前向きな話、今後の商売の考え方について話しました。GABAの場合は、生きている会社で、上場企業で業績が悪くなってきているので、それをV字回復させなくてはいけないですよね。従業員に会社の何が(どこが)悪いのかという認識があまり伝わっていなかったので、単純に今のGABAはこういう状況ですというのをP/L、BSの推移を見せて、問題点を共有して、売上は伸びているものの、利益とキャッシュが悪化しているということを理解させました。まずやるべきことは徹底した経費削減で1年でP/Lを建て直すことですという話をしました。それができれば絶対によくなる、そのかわり厳しいよと、使ってた経費も使えなくなるからね、と。
一発目の会議で、どこまで皆に「こいつまともそうだな、こいつの言っているようにやればよくなるな」と感じてもらえるか、で勝負が決まると思っています。100%こちらを向かせるのは絶対無理です。必ず「何言っているんだ、こいつ」と斜に構えている人が2、3割はいると思っておいたほうがいい。「この人まともだな」と思ってくれる人をその斜に構えている人よりも多い人数確保することが大事なんですね。2、3割が「上山ってやつの言うことはまだ信用できねえ、こいつ俺たちの首をただ切ろうとしているだけなんじゃないか」「本当にこの人に付いて行っていいのだろうか」などと思いますから、それよりも多い人数をこちらに向かせることに集中します。もちろん言っている中身にロジックがないと皆納得しないですから、そこにも集中して、どんな人が聞いても反対より賛成が多いという状況を作れるようにします。真ん中でどっちつかずの人が3、4割いたとしても、賛成のほうが反対より多ければ賛成のほうに感化されますから、それは気にしません。
― それはどこで学んだことですか?
ジャックで大事件が起こった後に、若い社員に日頃の商売を頑張ってもらわざるをえなかったんですね。車の買い取りや販売など、炎天下、真夏、真冬、雨の日も外で一生懸命働いている人たちの仕事は変わらないので、皆が頑張ってくれているからこの会社はぎりぎりもっているんだと。だからそこはお願いすると。社長になる直前も含めて、店も回って、それを事あるごとに話しました。そこでやっぱり学んだんです。会社というのは現場の本業がしっかりまわっていないと絶対もたないです。現場の本業がしっかりまわっている状態にすることが何よりも大事なので、そのためには、やはり同じ目線で語りかけてわかってもらうしかない、というのをその頃学びました。
長崎屋でも同じですね。私はど素人ですから、まともなことをまず言って、現場に行ってびっくりさせないといけないので、赤いエプロンを付けて誰よりも長く売り場にいるんです。それをやらないと絶対信用してくれない。GABAでも同じです。スクールは営業時間が長くてシフトを組んでいるのですが、夏休みの時期などにはどうしても手薄な店が出てきます。そうすると本社に応援要員のSOSを出せる仕組みがあって、私も空いていたら行きます。カウンセラーとして働きます。特に個人のお客さま向けのサービスをやる会社ではそういうことをやる必要があると思っています。個人のお客さまのニーズや要求は千差万別で、非常に厳しいことが時としてありますから。
― 社長がそこまでやっているんだったら、というので現場からの見方も変わってくるのですね。
長崎屋の時にもイージーオーダー・スーツを売ろうということになって、紹介件数では社員の誰にも負けませんでした。銀行時代の同期とかに電話して、徹底してお願いするんです。そうすると皆、あの人本気だなと思ってくれる。ジャック時代も、紹介件数は誰にも負けたことないですよ。GABAに入ってまだ21カ月ですけれど、22名紹介しました。
口先だけだと絶対見破られます。皆、客商売をしていますから人を見る目が結構あるんです。そうすると、本気で言っていることなのか、口先だけでごまかそうとしていることなのか、すぐ見破ります。だから、そこまでやらないと、という思いはありますよね。
― 建て直しにあたって、他に何か意識していることはありますか?
建て直しにはチームを組んで入ることがよくありますが、私は1人がいいと思っています。なぜかと言うと、経営チームで入るともともと会社にいた人が「被害者」じゃないですけれど、経営チームとそれに対するものということになってしまって、勝手にやってよという感じになる。1人で行くと、1人では何もできないので、そこにいるその会社の人に頑張ってもらわないとどうしようもない。たった1人で丸腰で来たら、皆それを感じますから。そこにいる人に頑張ってもらわないと損だと思います。5人、10人で入っていくとその人件費も含めてコスト負担が増えて、元の会社の人はやる気を失って生産性が落ちてしまう。そうすると、うまくいく再生もうまくいかない気がしてしまうんです。そこで1人で行って、みんなをやる気にして会社をよくする、それでもやらない人には、申し訳ないけれど退職させる、降格させると言ったほうがよいです。やらない人に厳しく言ったほうが、やる気のある人はもっとモチベートされますから。仕事していない人は皆がわかっているので、それは徹底的に指摘するべきなんですね。結果を伴っていない人、口では言ってもやるべきことをやっていない人は必ずいます。人事ですから100%正確にというのは難しいとは思いますけれど、明らかに仕事をしてないのにポストが高い人はだいたいわかるものです。過去に貢献していたという人は難しい部分もありますが、建て直し期は今がそうでないなら必要ないというように割り切るべきだと思います。
強み・弱み ~絶対あきらめない、ぶれない頑固もの
― 業績を支えてきた資質は何ですか?
成功するまで絶対にあきらめないということかなと思います。逆に言うと、あきらめなければ最後には成功する(負けない)ということです。異端なことをやってきただけ、というのはありますが、自分の特徴という意味で言うと、「絶対あきらめない」というところと「ぶれない頑固もの」というところでしょうか。会社を経営する上で、これが正しいことだろうと思ったことはぶらさないです。負けず嫌いであきらめないというのは、子供の頃からそういう性格でした。負けっぱなしだったんですね、中学高校の野球部とか、大学の野球部も。高校2年の時はいいピッチャーがいたので県のベスト16まで勝ったことがありますが、それ以外はほとんど負けっぱなしでした。それは自分の性格形成に影響していると思います。その中で負けず嫌いな性格が染みついたんでしょうね。何とかしてこの状況を変えたいというか、そういう思いばかり強くなっていたという感じはあります。野球部の同期は皆負けず嫌いでした。そうでないと途中で辞めるんですよね。下手だから練習しないといけないので、朝から晩までグラウンドにいました。その時にしつこいというか、あきらめない性格は作られたのだと思います。
― リーダーシップという観点でいうと、学級委員、ガキ大将など、どういう幼少時代、学生時代でしたか?
学級委員になったことはあります。なったことはあるけれど、ガキ大将的ではなかったと思います。どちらかというとガキ大将で偉そうなやつとけんかして負けるとか、やられるとか、そういうことはありました。その頃から徒党を組めない人間だったんですね。つるんでやるのが苦手なんです。自分の言うことを周りの人が聞く、みたいなのは嫌です。私は会社でも社長っぽくないと思っています。GABAに入社して最初席がなかった時にも、営業のいちばん若手の女性の隣の端の席に座って、そこで仕事していました。社長になった後も社長室には入らないで、社長室は会議室にしました。大部屋の一角に机だけあればいいよと。神輿に乗っている的なものが嫌なんです。
― 中・高・大学生と同級生など周囲の人と比べてちょっと人と違うようなところはありますか?
確かにこのような転職をしている人は私しかいないです。証券会社に入って今はベンチャー企業の社長をやっている大学野球部の同期が1人だけいますけれど、他にはいないですね、こんな生き方をしているのは。だから、いったい何の文句があるんだ、と皆に言われる。銀行もあっさり辞めてぽんと外に出てしまったところも確かに他の人とは判断基準が違うのでしょう。自分には何か既成概念的なものに反発したいところがあるようです。中高の時もどうせ野球なんて下手だから勉強してればいいと思われるのが嫌で、野球で負けたくなかった。大学時代も東大の野球部は弱いものだと全国的に思われていますから、何とかひと泡吹かせてやりたい、弱いと思っている人たちを見返してやりたいというのがあったんですね。
― ぶれないことが大事というのは、どこで身に付いたのですか?
ジャックの時の苦境で身に付いたことです。ぶれたら誰も付いてこなくなる気がしました。
― 建て直し期では、短い時間の中で人が付いてきてくれるような信頼関係を作らなくてはいけないですよね。
幹部社員によく言うのは、経営って難しそうに感じるけれど、絶対そうでないんだと。やるべきことをやるべきタイミングでやるべき人がやるだけなんだと。言うべきことを言うべきタイミングで言うべき人が言うんだと。この2点です。それさえ間違えなければ会社の業績は絶対よくなります。人は、どこかでタイミングを間違えたり、今言うのは辞めようと思ったりします。でも、やるべきこと、言うべきことというのは、早いほうがいいことが多いんですよね。間髪おかずに実行したほうがいいです。しかも部下からすると、この人にはこういうことを言ってほしいというタイミングがあります。それを間違えて言わなかったりすると部下ががっくりきます。部下が気づいていないようなことをびしっと言うようなこともあるし、やるべきことをやるべきタイミングで、しかもやるべき人がちゃんとやるのが大事です。それも、公然とやったほうがいいことが多い気がしています。切れるような怒り方をするのはよくないですが、理路整然とミスはミスだったというのは悪くないと思います。そのほうが本人以外の当事者も大きく納得することがありますから。
もちろん、言ったほうがよかったな、と後悔したりすることは何度もあります。特に長崎屋の時には、大事な会議の席上で自分が言うべきことを言わずに後で後悔したということがありました。社員は小売の世界で何十年生きている人なので、素人なりの遠慮というのがあって、そこが難しいところでした。
あと、タイミングという意味でよくあるのは、業績をよくするためにP/Lを改善することの連続のはずなんですけれど、「もうちょっと様子を見てから」というのを経営者はしがちです。様子を見ても悪くしかならないという明白な材料があるにも関わらずそうしてしまうことが多いものです。よくなる可能性があって様子を見るならいいけれど、このデータ見たら悪くしかならないという時でも、もうちょっと様子見てから、という人もいます。様子を見るんだったら、もがいたほうがいいですよね。何かを変えてみて、もがいて奮闘してみて、ダメだったらやめようとスパッとやめたほうがいい。初めてやる業種であまりわからない時にはそういう判断をしがちなんですけれど、後から思うと、もっと早くできたなと思うことはよくあります。
― 弱みについてはどのように認識されていますか?
弱みは、先程のぶれないというところと表裏かもしれませんが、頑固すぎるところでしょうか。いろんな人の言うことをちゃんと聞いているつもりで聞いていないことがあります。初めての業種に入って知らないことばかりなので、自分では聞いているつもりだし、聞かなくてはいけないと思って聞いていても、予め作った自分なりの再建に向けてのストーリーのロジックに、無理やり合わせてしまう意識が働くことを自分で感じることがあります。間違っていたから変えるということも必要です。信条などはぶらしてはいけないところですが、商売の方針や戦術面は変えていいと思います。信条をぶらしまくると誰も付いてこないですが。今みたいな立場だと、筆頭株主から言われてこの会社に来ていて、筆頭株主が6割も株を持っているわけですから、ある程度結果さえ出していれば筆頭株主は私のやりたいようにやらせてくれる立場なんですよね。そういう私がよく社内の人の言うことを聞かずに自分が思うように自分が思うことが全て正しいんだというような経営をやってしまうとかなり独断専行の専制君主的経営になってしまうのでそれは相当まずいと思うんです。そこは自分でそうなってはいけないと思うところですが、振り返るとたまにそうやって自説に持ってきている時があるので、そこがやっぱり弱みで、克服していかないといけないところです。
理想の経営者 ~自分に対する厳しさをもった規律のある人
― この経営者はすばらしい、こうなれたらいいという理想の経営者はいますか?
この人というのはいません。全人格的に存じ上げているわけではないので、わからないからです。ただ、「この人は1人で責任を負って判断しているな」というような方には、共感を覚え、尊敬する部分があります。そういう意味では、規律のある人、ディシプリンをもっている人が好きです。自分に対する厳しさをもっている人でしょうか。経営者ってやりたいようにやろうと思えばやれてしまう可能性のある仕事ですから。たとえば先般、上場企業役員の高額報酬の個別開示が初めて行われて、この会社のトップがこんなにもらっているんだと思うこともありましたが、会社の業績や業界の動向をみると、明らかにディシプリンがないなという人はいます。日本の経営者は甘い人が多いように思えます。大企業の経営者になれば周囲がやってくれますよね、身の周りのことは秘書がやってくれて、会議の資料は部下が作ってくれて、自分は会議に出席して資料を読んでというような人もいっぱいいますから。別にその人でなくてもいいという感じがするんです。その辺を自分で律していると感じられる人は大企業の経営者でも尊敬できる部分があります。
会社の経営というのは何かすれば必ずコストがかかるから、社長であればそこは絶対最小のコストで乗り切れるようにすべきです。同じ目的に到達するのであれば、同じ結果をもたらしてくれるのであれば、その手段の段階、途中の段階では、最小のコストを選ぶべきです。そういう努力をしない経営者は山ほどいます。売上、利益が大きいんだから、ちまちまコストのことを言うな、そんなことをしたら社員が小さくまとまってしまうということを言う人もいるけれど、それは絶対間違いです。会社である以上は、規模が大きかろうが小さかろうが、絶対そこをぶれさせてはいけないと思います。その辺が感じられない経営者は多いです。私が気にし過ぎなのかもしれないけれど、金繰りで苦労しているのでそう思ってしまうんです。支払承認は細かいものでも気になったら確認します。ちょっとでも、ちょっとでも、ということを皆がやれば業績は変わってきます。コストは意思を持ってコントロールできます。売上はこちらがコントロールできないんです、絶対。コントロールできるものをコントロールしないと経営者とは言えないと思うのです。
理想の経営者とは少し違うかもしれませんが、子供の頃からスポーツ一色で、巨人ファンではなかったけれど王さんは好きでした。今でも王さんのコメントは何を聞いても納得できます。人格者で自然と人が付いてくる印象があります。偉そうに、社長だから言うこと聞けというのではなくて、上山の言うことは理にかなっているから一緒に仕事しようと思われるような経営者が理想だと思っています。
インタビューを終えて
上山さんは40代半ばながら、ジャック、長崎屋、GABAとすでに3社目の社長職に就任しておられます。ジャックでは経営再建のみならずオーナー会長の横領事件というショッキングな出来事をも乗り越えて、当初16年かけて更生する予定だった長崎屋では12年前倒しで更生計画を終結させるなど、簡単には想像ができないような修羅場経験の中でも実績をあげてこられました。絶対あきらめない姿勢を基盤とし、営業での数百名もの社長に会った経験、MBA留学での経営知識、経営者としての数々の修羅場経験を通して、ぶれないスタンスに基づいた現場力ある経営手腕に磨きがかかっていかれたのでしょう。
インタビュー当日は、経営再建に関する臨場感あふれるお話から、幼少期から大学時代までの野球のお話まで、ビジネスや経営に対する厳しい姿勢をお持ちである一面と、情熱的で謙虚なお人柄がにじみ出るようなエピソードをたくさんお話してくださいました。
インタビュー:組織行動研究所所長 古野庸一 /文:主任研究員 藤村直子
協力:株式会社 経営者JP 代表取締役社長・CEO 井上 和幸 氏
※本インタビューは2010年8月4日に実施したものです。
PROFILE
上山 健二(かみやま けんじ)氏 株式会社GABA 代表取締役社長

1965年生まれ。1988年東京大学経済学部経済学科卒業。住友銀行(現三井住友銀行)入行後、1992年米国ミシガン大学ビジネススクールに留学、1994年MBA(経営学修士)取得。1999年4月退行。同年5月、中古車買取大手の株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社、6月に取締役副社長、2001年6月に同社代表取締役社長に就任。2002年5月同社退職。同年9月、更生会社株式会社長崎屋に入社し社長室長兼経営企画室長を務める。2003年2月取締役社長室長兼管理本部長に就任。同年3月事業管財人代理兼代表取締役社長に就任し同社の更生手続を指揮する。2006年7月、12年前倒しで更生手続を終結させる。2008年4月に同社を退社、10月に専務執行役員としてGABAに入社。2009年3月より現職。
執筆者
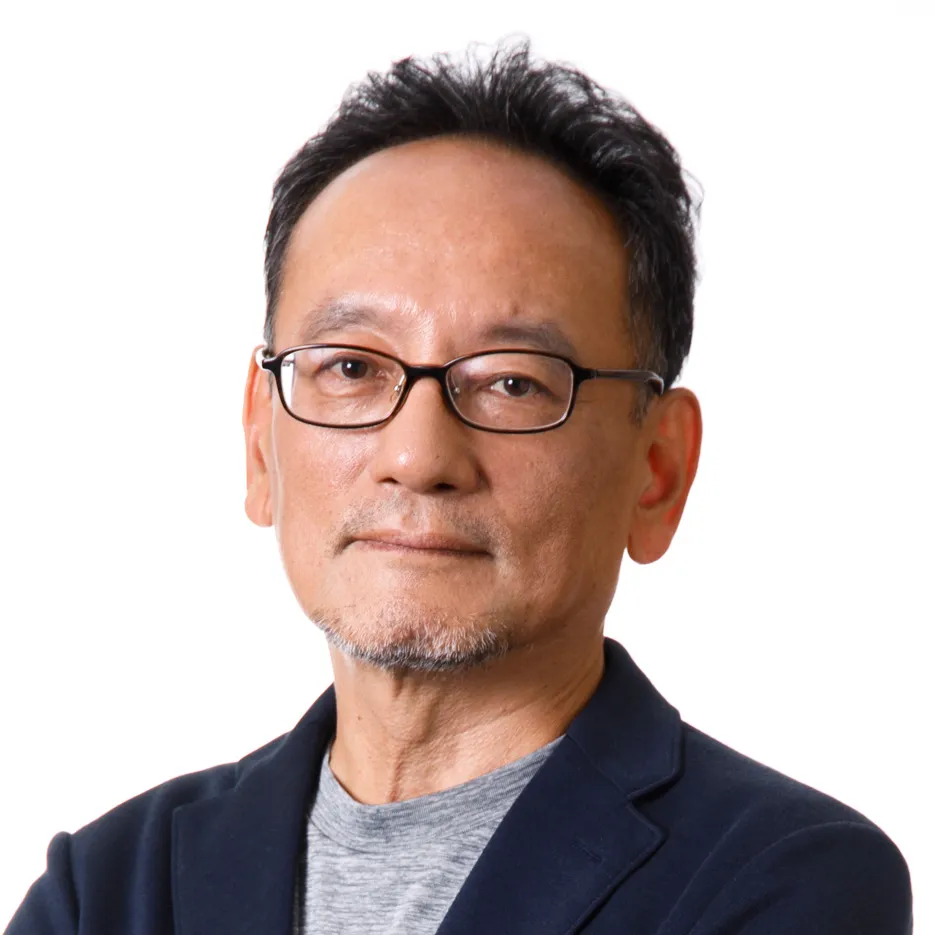
技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
古野 庸一
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社
南カリフォルニア大学でMBA取得
キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事
2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主任研究員
藤村 直子
人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)、リクルートにて人事アセスメントの研究・開発、新規事業企画等に従事した後、人材紹介サービス会社での経営人材キャリア開発支援等を経て、2007年より現職。経験学習と持論形成、中高年のキャリア等に関する調査・研究や、機関誌RMS Messageの企画・編集・調査を行う。
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第10回
- 多くのすばらしい経営者に直接触れて 織畠 潤一 氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第9回
- 好きなこと、得意なことを伸ばしてBtoCビジネスの変革を 田岡 敬氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第8回
- 「為せば成る」を原点に、志と行動力が結果を生む 秋元 征紘氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第7回
- 学びを実践しながら、自己に対する厳しさを持ち徹底的にやり抜く 池本 克之氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第6回
- 合理的・合目的的な意思決定と人とのつながりを大切に 平松 庚三氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第5回
- 神輿には乗りたくない、財務諸表と現場力で企業の再建を 上山 健二氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第4回
- アメリカ本社での5年間の経験が経営観の礎に 村上 憲郎氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第3回
- 自分を深く知ることによって、経営者としてぶれない軸をもつ 河田 卓氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第2回
- ベストパフォーマンスを出すために学び続ける 山田 修氏
- 「プロ経営者」の育ち方・育て方 第1回
- 32歳のときに45歳で社長になるという目標を 新 将命 氏
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)