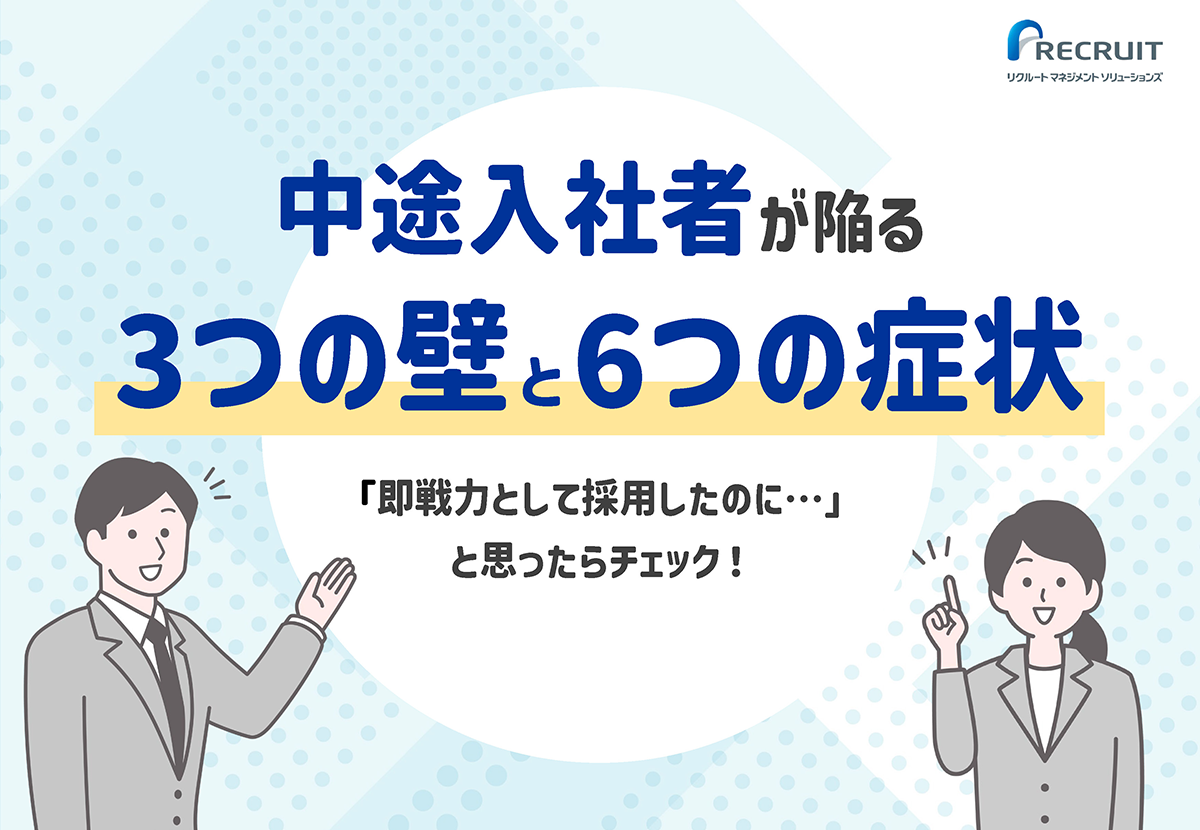- 公開日:2025/10/06
- 更新日:2025/10/10

弊社は2023年4月より、社内公募制度「キャリアプラス」を導入しました。現職を続けながら新しい業務やプロジェクトに挑戦できる本制度について、他社の方々から「どんな制度なのか詳しく知りたい」という声をいただくことも増えています。
そこで、「キャリアプラスをつくった社員たち」と「キャリアプラスを使った社員たち」から、制度の概要や魅力をご紹介します。後編となる今回は、実際にキャリアプラスを経験した3名の弊社社員がお届けします。
- 社内公募制度の魅力に迫る
- 社内“越境”で広がる視界――キャリアプラス利用者が語る実態、効用、そして運用課題【後編】
- 社内公募制度の魅力に迫る
- 「キャリアプラス」はどう生まれた?立ち上げ・運用を担う人事に聞く【前編】
ライトな兼務と周囲の前向きさが、一歩を踏み出すきっかけに

キャリアプラスで担当した仕事
A:私は、主務では中小企業のお客様に対する営業を担当しています。キャリアプラスには2回参加していまして、1回目は研修サポートツールの導入推進、2回目は営業企画に挑戦しました。特に1回目の案件は、新卒の頃からずっと興味があったサービスに近かったので、「これは運命かもしれない。ぜひ私にやらせてください!」と強くアピールしたことを覚えています。
キャリアプラスの期間は基本的に半年間ですが、1回目の配属先での経験がとても有意義だったので、「このまま通常兼務として続けていきたい」という希望も出しました。難しいかもしれないと思っていたのですが、縁あって類似のプロジェクトにアサインしてもらうことができたので、今は主務の営業80%、アサインされたプロジェクト10%、新たなキャリアプラス10%の割合で働いています。
B:キャリアプラスに加えて、通常兼務もしているのはすごいです。私は普段、サービスの企画や開発などを担当していて、キャリアプラスでは社外広報に挑戦しました。個人的に弊社の「個と組織を生かす」というスローガンに共感しているので、広報がどうやってそのマインドを社外の皆様に伝えているのか、また社外から弊社がどのように見えているのか、ずっと興味があったんです。
ただ、本格的な兼務や異動には尻込みしてしまう方だったので、キャリアプラスが始まるまではなかなか勇気を出せませんでした。だからこそ、キャリアプラスの「兼務10%」というライトさが嬉しくて、1期生としてすぐに応募したのを覚えています。
C:私も同じく、キャリアプラス1期生です。前職で社内広報を担当しており、また同じような仕事に挑戦してみたくて応募しました。担当したのは、半期ごとに行われる社員総会の企画と運営です。全社員が集まる規模の大きなイベントなので、前職とはまた違う、インパクトのある経験を積むことができました。
主務では、プロダクト開発部門の一部署でマネジャーを担っており、キャリアプラスの受け入れもしています。Aさんのように、キャリアプラスと通常兼務を並行している人もたまにいますが、やはり「行動力がある人だな」と感心してしまいますね。
A:大変かもしれないとは思ったのですが、人事からも「キャリアプラスをぜひ活用してください!」という熱いメッセージを感じたので、とりあえずやってみようかと(笑)。主務のマネジャーに快く送り出してもらえたので、前向きな気持ちにもなりやすかったです。
B:確かに、制度が始まった頃から「キャリアプラス応募した?」「あの部署、楽しそうだよね」という会話が自然と生まれる雰囲気はありましたね。気持ちを後押しするような社内の雰囲気があったからこそ、応募しやすかったのはあると思います。
メインミッションとキャリアプラスの両立方法
B:キャリアプラスの期間中は、主務をはじめとするメインミッションの時間が90%、キャリアプラスの時間が10%になるように、時間を振り分けながら働きます。平均すると、週半日ほどをキャリアプラスに充てました。例えば私の場合は、週1ペースで社外広報チームの定例会や先輩社員との1on1に参加して、それ以外はスポットで取材対応や打ち合わせ、メディア向けイベントの企画や資料作成などを行いました。
A:平均週半日、というと一見軽そうですが、週や期のどこかで大きく時間を取られることもあるので、主務の繁忙期とかぶってしまうと少し慌ただしくなります。キャリアプラスでは兼務10%というルールに沿って仕事の切り分けをしてもらえますが、10%の業務をきっちり切り分けるのは、参加側から見ても少し難しそうでした。実際には「気持ちの10%」という感覚に近く、週半日をやや超えることもあった印象です。
ただ、自分からキャリアプラスに手を挙げているので、精神的な負担はそれほど重くありませんでした。「このまま営業のキャリアに絞って磨いていっていいのだろうか」という迷いもあったなかで、転職をせずに別のキャリアに挑戦できるメリットが大きかったのだと思います。キャリアプラス先のチームの一員として役割を与えてもらい、成果をきちんと評価していただけたことが、自信にもつながりました。「キャリアプラスだし、これ以上はやらなくてもいいですよ」と変に壁をつくられてしまうよりも、有意義な経験になったと感じています。
▼キャリア自律についてさらに知りたい方はこちら
人事になったら知っておきたい10のこと 〜人事トレンド編〜 第5回
「会社は社員のキャリア自律を支援するべきなのですか?」
参加側・受け入れ側から見る「キャリアプラスで得られたもの」

キャリアプラス参加で得られた「プラス」の効果
A:キャリア形成やリスキリングの機会としてスタートしたキャリアプラスですが、実際に参加してみると、意外な効果を感じることもありました。特に印象に残っているのは、「視野が広がったこと」です。
キャリアプラスで兼務をする前は営業の経験しかなかったので、どうしても営業の立場から物事を見てしまうところがありました。しかし、キャリアプラスをきっかけに開発や企画にかかわったことで、企画から見た営業の姿や、サービスを開発する側の想いなど、これまでとは違う視点に気づけるようになったと感じています。
また、部署によって評価軸が変わることにも気づきました。営業では「売れたかどうか」が大きな評価基準になりますが、例えば企画の場合は「筋が通っている」「新しさがある」「周囲を動かせる」といった、違う観点での評価もありました。思ってもみなかった自分の一面を褒められることもあって、キャリアの新しい可能性を感じることもできました。
B:私も「参加してよかった」と思うことがたくさんありましたが、想像していなかったメリットとしては、主務・兼務ともに、良いシナジー効果が起きたことです。やはり同じ社内であっても、部署が違えば仕事の進め方や振り返り方も違いますし、コミュニケーションの仕方も変わります。兼務先の仕事のやり方を主務側に持ち込んだり、「いいな」と感じた風土を共有したりすることで、お互いの部署のいいところを持ち寄るような好循環も生まれました。
受け入れ側として感じた組織的な変化
C:マネジャーとしてキャリアプラスの方を何名か迎えましたが、組織的なプラスも確かに感じています。普段接点のない部署から来た方は、自分たちにはない考え方やスキルを持ち込んでくださることが多いのです。逆にお互いの考え方を比較するなかで、「自分たちにはこんな強みがあるのか」と気づくことも珍しくありません。キャリアプラスは個のキャリア形成を支える制度ではありますが、組織開発の追い風にもなると感じています。
またマネジャーとして、キャリアプラスは社内の別部署の方に、自分の部署のことを知ってもらうチャンスだとも思っています。私の所属部署は少人数かつグループ所属歴が長い方が多く、メンバーが固定しがちです。ただ、キャリアプラスを通して人材の出入りが増え、部署に興味を持ってくれる方も増えました。兼務期間が終わっても連絡をくれる方もいて、今もメンバーとしてつながりを感じています。
もちろん、キャリアプラスの受け入れを行うと短期的に忙しくなるので、部署によっては利用を見送ることもあると思います。ただ、やはり「自部署に合う人材に出会いたい」「部署に新しい風を入れたい」というマネジャーの気持ちにも応えてくれる制度なので、これからもキャリアプラスは積極的に活用していきたいです。
キャリアプラス制度への「これからの期待」

キャリアプラスの現場で感じた課題と改善策
A:キャリアプラスは私にとって何度も参加したくなる制度ですが、運用において気になる点もあります。あくまで参加側からの意見ですが、ジョブの切り出しが難しそうです。半年という期間でどこまで仕事をお願いするのか、目標をどう設定するのか、半年で成果が出なかった場合の評価をどうするのか――これらが難しく、キャリアプラスの募集を出すハードルになっているという話も聞きます。
営業先のお客様からも、「キャリアプラスのような制度を自社でもやってみたい」という声をよくいただくのですが、やはり仕事の切り出しの難しさや、現場の協力を得られるかどうかを心配されている印象を受けます。Cさんは受け入れを何度も経験されているそうですが、ジョブの切り出し方のコツはあるのでしょうか。
C:ジョブの切り出しは確かに難しいのですが、コツを挙げるなら、「人材活用の選択肢として、常にキャリアプラスを頭の片隅に置いておくこと」でしょうか。チーム内の状況や目標を把握する時に、「どの仕事ならキャリアプラスの方にお任せできるだろう?」と日頃から考えるようにしておくと、切り出せそうなジョブも浮かびやすくなります。キャリアプラスの案件を出すタイミングで、メンバーの意見を聞いてみるのもいいですね。
ただ、一番大切なことは、応募者の期待に沿ったジョブアサインができるかどうかです。キャリアプラスで来てくださった方に、「期待どおりの経験ができた」と思ってもらえるよう、お互いの意見をすり合わせてマッチングの精度を上げることが本当に大切だと思います。
B:マッチングの精度を上げる意識は、参加側も持っておいた方がいい気がします。私もキャリアプラスに応募する前に、興味のある部署のマネジャーと軽く話をしました。キャリアプラスの面接は基本的に部長が担当するので、マネジャーなら選考に影響しない範囲で話ができるかと思って。
そう考えると、先輩訪問とまではいかなくても、選考外で気軽にお互いのニーズを確かめられる機会があると、より安心できるかもしれません。参加先の部署の繁閑期なども、事前に分かると嬉しいですね。
A:やはりキャリアプラスの案件内容を見ただけでは、どんな人を求めている募集なのか、細かいニュアンスが分からないことがあります。私もキャリアプラスに応募する前、募集先の部署にチャットを送ったことがありますが、少し勇気が必要でした。「分からないことはぜひ直接聞いてみてください!」というサポートがあれば、マッチングの精度もさらに上がるのではないかと思います。
C:メンバーを送り出す側の部署からも、何か支援ができるといいですよね。私の部署だと、部下のキャリアプラスのエントリーシートを添削したり、相性がよさそうな部署を一緒に考えたりしています。
B:それ、いいですね。私もやってほしいです(笑)。

参加して感じた、キャリアプラスの“推しポイント”
A:キャリアプラスはまだスタートしてから数年しか経っていない制度なので、「キャリアプラスってどう?」と周りから聞かれることもあります。推しポイントをあえて挙げるとすれば、「自分の可能性に気づけるところ」です。今の部署では分からなかった強みが見えたり、視野が広がったりするところがメリットだと思います。
B:「自社の魅力を再発見できるところ」もいいですね。人脈が広がりますし、「うちの会社ってこんなことまでしているんだ!」と気づくこともあって、会社で働くのが楽しくなる気がします。
C:転職しなくても自分の可能性を広げられるところが、やはり魅力的ですよね。マネジャーという立場ですが、機会があればぜひ2回目のチャレンジをしてみたいです。
社内公募制度をはじめとする人事制度について検討されている方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
■おすすめのサービス
人事制度設計・運用支援コンサルティング
- 社内公募制度の魅力に迫る
- 社内“越境”で広がる視界――キャリアプラス利用者が語る実態、効用、そして運用課題【後編】
- 社内公募制度の魅力に迫る
- 「キャリアプラス」はどう生まれた?立ち上げ・運用を担う人事に聞く【前編】
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)