連載・コラム
可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
ピースなチームは一日にして成らず
- 公開日:2022/01/31
- 更新日:2024/05/17

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。今回は、雑談朝礼や管理職立候補制など、奇策を定着させチームを盛り上げる、ヤッホーブルーイングのマネジメント発明に迫る。 株式会社ヤッホーブルーイング 人事総務ユニット・ユニットディレクター 長岡知之氏にお話を伺った。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
今回のテーマ「心理的安全性」
「心理的安全性(psychological safety)」とは、組織のなかで、自分の考えや気持ちを安心して発言できる状態のことを指します。組織行動の研究者エドモンドソンが1999年に提唱した定義によれば、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」です。 昨今、心理的安全性の高いチームが成果を創出するという話をよく目にしますが、それは決して単に何を言っても許される組織や、仲が良いだけで成果の基準が上がらない「ぬるま湯」組織を作ろうという意味ではありません。エドモンドソンによれば、図表1のとおり「心理的安全」かつ「責任」の高い組織では「学習」が進み(Learning Zone)、高い成果を創出できます。
<図表1>心理的安全と責任のバランスによる4つの組織状態
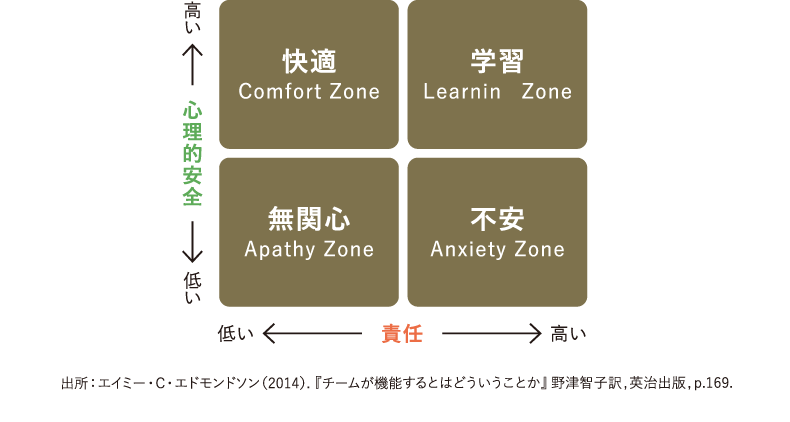
「責任」とは、チームが高いパフォーマンスを出すことに対する、メンバーのコミットメントや責任感を指します。心理的安全の感覚だけでは、楽しく打ち解けるものの高い成果に向けて挑戦をしない快適状態(Comfort Zone)が常態化してしまいます。逆に、「責任」だけが高く「心理的安全」が低ければ、よほど個人プレーで仕事内容が明瞭でない限り、協働で成果を生み出すチームにとって良い状態とはいえません。強い成果圧力のなかで周囲にアイディアを打ち明けたり支援を求めたりすることもできず、不安ばかりが生まれる組織になってしまうことでしょう。たとえ正解の確信がなかろうとも、または仮に役職が高いなどの権限をもたずとも、より良い成果の創出に向けて誰もが等しく言葉を発することができる学習状態を作り出してこそ、組織は強くなります。そのためにリーダーは己の限界を理解し自分も失敗することを率直に伝えていくと共に、メンバーに参加を促し、失敗には制裁ではなくチームでの学習を促すことが重要となるのです。
負のスパイラル、渦中で出会ったチームビルディング講座
荒井:長岡さんはどんな経緯で今のお立場に?
長岡:グループ会社の星野リゾートに新卒で入社し、人事総務の経験を積んだのち、2009年から当社で働いています。現在も人事総務関係の仕事をしています。正式名称は「ヤッホー盛り上げ隊」です。
荒井:何て良いお名前なんでしょう(笑)。今日は御社の組織変革の道のりをお聞きしたいです。
長岡:組織変革のきっかけは地ビールブームですね。ブームが落ち着いて売れなくなると「企画が悪いからだ」などと陰口を言う人も出てきますし、余ったビールを廃棄するなどのマイナスな仕事も多くなりました。どんどん人が辞めて、業務負荷が上がり、さらに辞める……慌てて採用するとミスマッチを起こし、また人が辞める。「これではいけない」と代表の井手が社外のチームビルディング講座を受け、感銘を受けて社内でもチームビルディング講座を始めました。私はその一期生です。
荒井:長岡さんはどうして参加したのですか。
長岡:楽しく仕事ができれば生産性が上がるし、人材の定着にもつながります。負のスパイラルをグッドサイクルに変えていけると思ったのです。
荒井:講座はどのような内容でしたか。
長岡:心理学者タックマンによるチームビルディングにおける4つの発展段階「タックマンモデル」と照らし合わせて、現場のチームの成熟段階と課題を捉えたりして……その上でチームビルディングの成果をメンバーで体感することが目的でした。
荒井:チームで成果を出す原体験を作るのですね。
長岡:日々の業務でメンバーが活躍して「チームビルディング講座を受けると良い影響があるのかも」と思ってもらえることが大事なので、一期生のメンバーを中心に成果を出すことにこだわりました。それと並行して「ニックネーム制」などの施策も全社展開しました。最初はみんな戸惑っていましたね。
荒井:今はすっかり定着していますよね。
長岡:2年、3年かけ「何でそれをやるか」の理由も説明し社内に展開した結果だと思います。スタッフとファン(お客様)が交流する「宴」というイベントでも、ファンの方とニックネームで呼び合っています。ファンの皆様と一緒にクラフトビールで世界平和を実現していきたいので、フラットなコミュニケーションを通じ対等な関係を築いていきたいのです。
絆を深めるコミュニケーションは年輪のように積み重ねるもの
荒井:チームを支えている施策には、他にどのようなものがありますか。
長岡:例えば「雑談朝礼」ですね。始業前に輪になって集まり、必要な業務上の連絡はさっさと終えて、残りの時間で仕事以外の話をします。「昨日、趣味のゴルフに行ってきました」など、たわいもない話を1人1~2分ぐらいで回すのです。そうすると「私も実はゴルフ好きです」といったコミュニケーションの連鎖につながる。これも12年以上、毎日やってきました。始めた当初は「早く仕事に取り掛かって早く帰りたいんだ」という批判もありましたが。
荒井:やる価値があるのだと説明されたのですね。
長岡:そうです。コミュニケーションは年輪のように積み重ねていくものだと我々は考えています。あと、会議の議事録もほぼすべて公開されているのですが、これも当社ならではかもしれません。
荒井:皆さんと共有する前提で議事録を作られているのですか。
長岡:はい。機微情報以外の経営情報はすべて共有していますね。会議の冒頭には「小学生時代の恥ずかしい話」のようなアイスブレイクを入れています。UPされた議事録のアイスブレイクのネタに対して、みんなでコメントを入れたりしていますね(笑)。大事なコミュニケーション機会になっています。
荒井:面白いですね。全員の黒歴史をちょっと披露してしまうみたいな。
長岡:そう。さりげなく自己開示できるわけです。
<図表2>チームビルディングと組織開発の多様な施策群「よなよなエール流 コミュニケーションマップ」
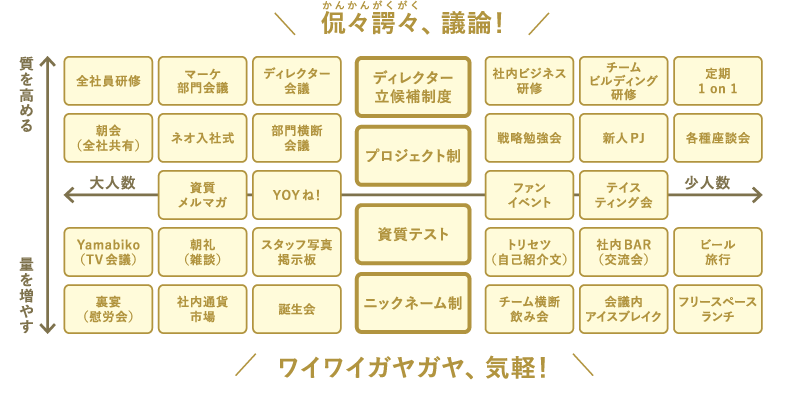
リーダーの選抜は立候補制 メンバーに人事権を委ねる
長岡:新入社員研修の一部にもチームビルディング講座が入っています。「コロナ禍下でヤッホーブルーイングのコミュニケーション施策をより良くする提案をしてください」などのお題で、チームで議論を重ねて提案し、実行するところまでやり遂げる。チームビルディングを体感することがねらいです。研修の最後は笑いあり涙ありの感動的なものになります。
荒井:新人時代から、仲間と共にチームの力や醍醐味を共有できるのは素敵な財産になりそうですね。中途入社の方は前の組織の文化とのギャップに驚かれないですか。
長岡:複数回の面接のなかで、本当に社風に共感してくれていて、チームで成果を出すことを求めている人かどうか確認して採用を進めています。
荒井:カルチャーフィットを大事にしているということですね。さまざまな取り組みを通じて、会社が目に見えて良くなったタイミングはありましたか。
長岡:PDCAを繰り返しながら徐々にという感じですね。毎年Great Place to Work®の「働きがいのある会社」調査に参加しており、5年連続でベストカンパニーにも選ばれました。私たちは世界レベルでも働きがいのある会社になることも視野に入れ、「そのために私たちは何ができるんだろう」と一人ひとりが考えています。だから「経営理念の浸透のために動画でPRしていいですか」と若手が提案してきたりしていますね。
荒井:素晴らしい。組織的な内容だけでなく、事業的な提案も若手から生まれていそうですね。
長岡:もちろんです。自ら手を挙げて新事業のリーダーになることもできます。ユニットディレクター(課長職相当)を立候補制にしているのです。みんなの前で公開プレゼンをして、聞いた人はアンケートに答えて「戦略は妥当か」「この人を推薦したいか」を判断し、投票を通じて人事に参画します。健全な競争のなかで切磋琢磨されていき「こういう事業を立ち上げたい」などと新たな提案が生まれてくるのです。
荒井:どんな観点でリーダーを評価していますか。
長岡:1つ目が戦略の立案、2つ目がその戦略の遂行、3つ目がチームビルディングですね。4つ目が成果への貢献で、事業としての成果を出したかが問われます。プレゼンだけではなく、日頃から一緒に仕事をしているその姿も評価に入ります。
荒井:戦略の妥当性だけでなく、日々の協働のなかで「一緒に働きたいか」を重視しているのですね。立候補制の場合、現リーダーが後任を育てる力学は働くのでしょうか?
長岡:リーダー自身も新しいことにチャレンジしたいでしょうし、組織規模を拡大するなかでチームを円滑に進めるために、チームを分割して新しいリーダーポストを作りたい場合もあります。新しいリーダーの育成は、本人のキャリア上もそうですし、戦略推進においても非常に大事なことですね。
荒井:立候補して選ばれなかった場合は、人事からフィードバックをもらえるのですか。
長岡:結果にかかわらず全員にアンケ―ト結果のフィードバックをしています。今後のために生かしてほしいからです。
荒井:立候補者としては励みになりますよね。
長岡:かなり情熱と時間を割いてやってもらっているから、こちらもできる限り丁寧にやっています。お話ししてきたように「年輪のように積み重ねてきた実績」が当社のチームビルディングの文化につながっています。一部の突き抜けたリーダーや、圧倒的にパフォーマンスが高い人に依存する体制ではなく、会社として継続できる仕組みを、コツコツと育ててきたつもりです。
荒井:お時間も迫ってきたので、最後に1つ聞かせてください。長岡さんが考える組織づくりの次のステップは何ですか。
長岡:「日本でトップクラスの働きがいのある会社」になることです。先ほどお話ししたGreat Place to Work®中規模部門のトップ10にはまだ入ったことがありません。GPTWの上位はサービス業が多いのですが、製造業でも働きがいの高い組織を作れることを証明したい。そのために多様な職種の人がやりがいを感じて、チームで新しい価値を生み出せるようにしたいと考えています。
荒井:多様な人が新しい価値を生み出せるチームへ、さらに発展されていこうとしているのですね。長岡さん、今日はありがとうございました。
【text:外山武史】
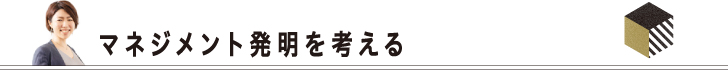
良いチームになるための共体験を作る
ヤッホーブルーイングでは10年以上をかけ(1)心理的安全(2)責任の両者をバランスよく強化し、学習するチームを実現してきました(図表3)。(1)については、その施策の量や種類が多いだけでなく、顧客とも垣根を越えた関係を構築している点も魅力的です。また(2)については、例えば立候補制の施策からは「誰もがチーム経営の主体者である」という強いメッセージを感じます。「戦略は妥当か」「共に働きたいか」という2つの評価軸は同社らしくもあり、人への影響力を通じて成果を上げるリーダーの本質ともいえるでしょう。ビールを片手に仲間と快適ゾーンを楽しんだら、皆で学習ゾーンへと踏み出していく。この体験を全員で積み上げているところに同社の強さを感じます。
<図表3>ヤッホーブルーイングの組織開発の力学
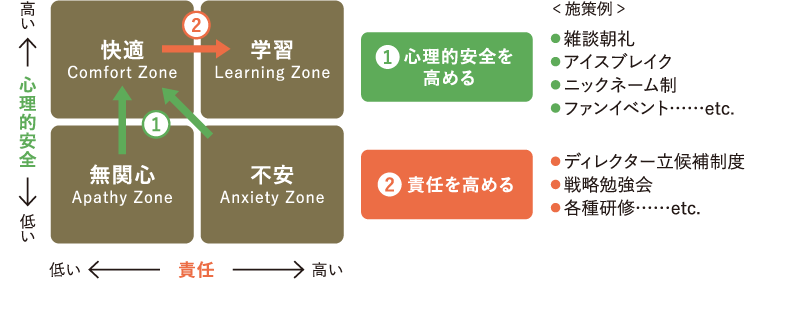
【インタビュアー:荒井理江(HRD統括部)】
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.64連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第10回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
長岡知之(ながおかともゆき)氏
株式会社ヤッホーブルーイング
人事総務ユニット・ユニットディレクター
大学卒業後、星野リゾートに入社。6年間勤務し、人事総務などに従事。2009年に転籍希望が叶ってグループ企業のヤッホーブルーイングに入社。現在は、ヤッホー盛り上げ隊(人事総務)のユニットディレクター。長年にわたりヤッホーブルーイング流のチームビルディングに取り組む。
バックナンバー
第1回 エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る(VOYAGE GROUP)
第2回 マネジャーの仕事をチームに委譲(サイボウズ)
第3回 “Why”から構築するデザイン組織(グッドパッチ)
第4回 マネジャーがいない会社の組織デザイン(ネットプロテクションズ)
第5回 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計(ゆめみ)
第6回 “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀(ヌーラボ)
第7回 「らしさ」と創造的な場をデザインする(Japan Digital Design)
第8回 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」(Ubie)
第9回 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎(ユーザベース)
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












