連載・コラム
可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
- 公開日:2019/11/25
- 更新日:2024/04/04

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。初回は、1999年の創業以来、成長を続ける、VOYAGE GROUP 取締役CTO小賀昌法氏に、エンジニアのモチベーションについて伺った。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
- 目次
- 今回のテーマ「職務満足」
- 評価に対する不満を払拭するため「技術力評価会」を小さく始める
- フィードバックをするときは本人の自律性に訴える言葉を選ぶ
- 小さく始めて失敗と成功を繰り返しプロダクトを育てる文化を作りたい
今回のテーマ「職務満足」
「どのような仕事なら、あなたは意欲がわきますか?」と問われたら、どんな仕事を思い浮かべるでしょうか。安心・安全な仕事、好きな仕事、やりがいのある仕事など、さまざまな観点が思い浮かびます。
今回取り上げたいのは、ハックマンとオルダムによる「職務特性モデル」の観点です。大変有名なこの研究によれば、従業員の意欲が引き出される職務には5つの特徴があります。具体的には、自身のさまざまな能力を発揮でき、一連の流れを見通せて、その重要性を感じることができる仕事を、裁量をもって自律的に、手応えを得ながら進められるようなとき、仕事への意義や責任、成果を実感し満足感が高まるというものです。
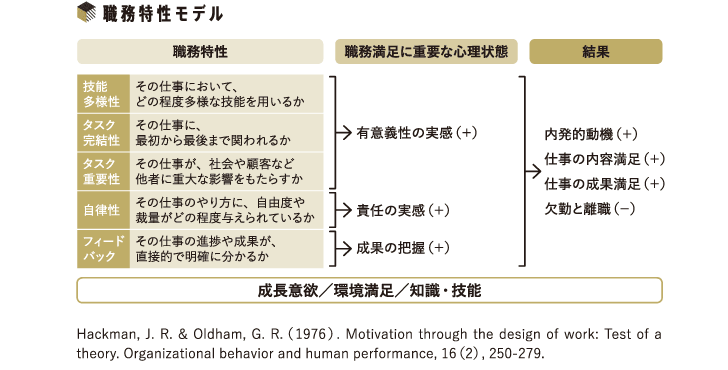
もし、自分の担う仕事が、断片的な単なるタスクでしかなく、重要性も感じられず、自律的な判断もできず、結果のフィードバックも得られなかったら、どうでしょうか。この研究が訴えているのは、組織が分業化していくなかで仕事が断片化することで生じる弊害です。事業拡大により、組織の規模が拡大。組織は機能ごとに分かれ、役割分担が進行し、生産性は向上します。しかしそのとき、仕事の担い手が「この仕事に何の意味が?」「良くしたくとも自分にはどうせ変えられない」と諦めれば、改善も進まず、最悪の場合には組織の弱体化を招くかもしれません。
多くの人に、仕事への醍醐味を感じ続けてもらいたいと思うとき、留意すべきことは何か。今回はエンジニアチームのマネジメントにそのヒントを探ります。
VOYAGE GROUPのCTOとして、技術面から経営課題の解決を後押しする小賀氏。エンジニアをエンジニアが評価する「技術力評価会」をはじめ、働く人の意欲を引き出す「仕組み」が、どんな考えのもとで作られているのか尋ねた。
荒井:今日はエンジニアのモチベーションを高める秘訣を伺いたいと思ってお邪魔しました。
小賀:はい。よろしくお願いします。早速ですが、まず大前提として、2019年の今、エンジニアがどんなことを考えているのか知ることが大事だと思います。エンジニアは世界最高レベルの技術に、簡単にアクセスできます。分かりやすいところでいうと、プログラムのコード。世界の一流企業、例えばGAFAが使っているものに触れて、実際に動かすこともできるんです。だから、多くのエンジニアはグローバルな視点をもっている。憧れの企業は、日本の企業よりもむしろ、GAFAをはじめ、NetflixやAirbnb、Uberだったりします。
荒井:なるほど。世界を見ているのですね。
小賀:ですから、エンジニアがどこを見ているのか理解した上で、自分たちのプロダクトについて考えられるといいですね。「今すぐ太刀打ちできないかもしれないけれど、GAFAなどのいいところは取り入れていこう」というスタンスです。
荒井:もし経営陣や事業の意思決定者が技術面に明るくなかった場合、その考えを理解してもらうにはどうしたらいいのでしょう?
小賀:基本的に、企業のトップは高みを目指しているものです。「GAFAに通用するレベルのエンジニアを育てるため、彼らのモチベーションを高めるような施策を打ちたい」という対話をするといいかもしれませんね。
荒井:それを聞いたら経営陣も燃えますね。
小賀:僕は技術とは、課題解決のための手段の1つだと考えています。だから、“技術だけ”をやりたいエンジニアに対しては「それって何のための技術なんだっけ?」という議論を必ずしているんですよ。世界に目を向けて、新しい技術を学べば、課題解決の引き出しが増えます。エンジニアが定期的に技術を学ぶのは、そのためです。
荒井:新しい技術を試したくなりませんか?
小賀:そのために、小さく失敗することで、成功の道を早く探り当てる「エンジニアリング」の思考が重要です。例えば、ソフトウェアの場合はプログラムのバージョンが適切に管理され、簡単にリリースできる仕組みがあれば、新しい機能をすぐに試せる。そして問題があれば即座にもとに戻すこともできる。その仕組みがあるだけで、新しい技術にチャレンジしやすくなりますよね。
評価に対する不満を払拭するため「技術力評価会」を小さく始める
荒井:小賀さんは現在CTOとして、技術を通じて経営課題の解決を目指されていると思いますが、CTOに就任された2010年頃、最初に小賀さんが取り組まれた課題はどんな内容だったのですか?
小賀:「エンジニアが評価に納得していないこと」でした。ちょうど事業部制になり、事業部のなかにエンジニアが配属されたタイミングでした。事業部長は技術に明るくないことも多いので、評価に対する不満が生まれやすいんですね。そこで私は、半年間の成果の1つについてエンジニアが90分のプレゼンをし、それをエンジニアが評価する「技術力評価会」という制度を提案したのです。それを2、3人から始めて、約2年間で全エンジニアを対象にしました。
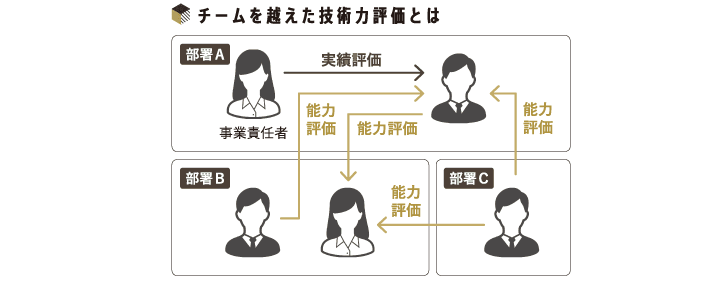
荒井:小さく始めたわけですね。90分間、自分の話をプレゼンテーションするわけですから、抵抗を感じるエンジニアの方もいたのでは?
小賀:みんなやる前は憂鬱だったと言います。けれど、良いフィードバックをもらえるし、終わってみると満足感があると言うんですよね。フィードバックをもらって次につながった経験があると、チャレンジしやすくなります。そういう改善のサイクルを、文化にしたいと考えています。
荒井:フィードバックの仕方にもポイントがあるのでしょうか?
小賀:まず1つは、さまざまな角度から見ることですね。例えば、普段一緒に仕事をしている上司は、実績評価をします。能力評価は、違うチームに所属する「その人よりグレードの高いエンジニア」2人が、「技術力評価会」を通じて見ます。次回は違う人が担当するので2年で8人のエンジニアから能力評価を受けることになるんです。ただし、見る人が多いと、評価にバラつきが生まれます。バラつきをなくすために、最初の300回は私が同席したんです。
荒井:それはすごい!
小賀:いかに良いフィードバックのスキルと文化を醸成していくか。しかし、最初はその意義すら伝わりにくいものです。その仕組みがちゃんと安定して機能するまでは、誰かが責任をもって張りつかないといけません。この制度は、質疑応答のスキルと、文章で分かりやすくフィードバックポイントを伝えるスキルが鍵ですから、「技術力評価会」を経験するとエンジニアの言語化能力も上がります。そして、技術を生かして会社の経営戦略を推進するとき、その伝える能力が生かされるというわけです。
フィードバックをするときは本人の自律性に訴える言葉を選ぶ
荒井:「それは違うよ」というニュアンスのフィードバックをするときはどうされていますか?
小賀:若いエンジニアが何とか自分の好きな技術を使いたいから、ポジティブな面を強調してくることもあるんですよね。「そういう気持ちも分かるよ。うまく取り入れていくのはいいんじゃないの?」というニュアンスで、導いていけるといいなと思っています。チャレンジは奨励しますが、「小さくチャレンジしやすいアーキテクチャーのデザインや、チームのマネジメントのスタイルなども考えてほしい」と併せて伝えています。もしくは「この課題に対してこれがどう役立つんだっけ?」「他の選択肢も考えてみようか」という具合に問いかけることも。選択肢を提示した上で「どれがいい?」と、本人の自律性に訴えかけるコミュニケーションを意識しています。ちなみに、2年前くらいから「技術力評価会」に社外のエンジニアを招き入れています。
荒井:外部の目を入れるわけですね。
小賀:はい。他社のCTOクラスの方や、ある技術分野ではすごく尖った方たちを入れています。
荒井:エンジニアたちから一目置かれている存在ということでしょうか。
小賀:そうです。VOYAGE GROUPの当たり前が、世界の当たり前であると誤解してしまうのは良くないので、あえて違う環境で活躍しているエンジニアを社外の評価者として入れることで、視野を広げられればと思っています。
小さく始めて失敗と成功を繰り返しプロダクトを育てる文化を作りたい
荒井:「技術力評価会」は今も改善を繰り返しているのですね。小賀さん個人は、次の挑戦としてどんなことを考えていますか?
小賀:私は課題があると解決したくなるタイプです。今の状況でいうと、VOYAGE GROUPがサイバー・コミュニケーションズ(CCI)と経営統合してCARTA HOLDINGS(電通グループ)になった経緯があるのですが、私たちの強みである「プロダクトを小さく始めて失敗と成功を繰り返しながら育てる文化」を電通グループの力でもっと加速させられたら面白いと考えています。ただし、パートナーやクライアントが大手になればなるほど、ミスが許されにくい状況になってくるので、そのなかでいかにこれまで培った文化を発展させていくかが課題ですね。
荒井:とても難しそうな課題ですね。
小賀:会社が大きくなると挑戦が難しくなると思われがちですが、「でもGAFAとかNetflixとかアリババとかテンセントとかは、チャレンジしていないんだっけ?」という話なんですよね。
荒井:間違いなく、チャレンジしていますね。
小賀:新しいことにチャレンジしながら、大きな失敗はしないんだけれども前に進んでいけるエンジニアリングマネジメントを、大きな会社と一緒にやっていくことができるか……いや、やっていかなければという気持ちが強いです。
荒井:頼もしいお言葉。小賀さんのチャレンジを応援したいです。
小賀:ありがとうございます。
荒井:最後に改めてエンジニアのモチベーションを高めていくために大事にしてほしいことを、読者へのメッセージとしてお話しいただけますか?
小賀:大きな目標を掲げて、長い目で取り組むことですね。長い目をもつことで、小さな失敗を許容できるようになります。目の前の小さなことに対して心はざわつくのですが、大事なのは大きな目標に近づくことです。そのための小さな失敗やチャレンジを許容する考え方が大事だと思います。
荒井:そうですよね。大きく描いて小さな一歩も大切にということですね。
小賀:時には失敗するので、一歩や二歩退がることもあると思うんです。そんなときは、「このまままっすぐ進んでも目的地に着けなかった。今、正しい道が分かったんだ」とか「分からないことが1つ消えて、不安も減った」という捉え方をしています。だから「長い目をもってゴールに向かっていきましょう」と伝えたいですね。
荒井:「失敗した……!」じゃなくて「正しい道が分かった」と捉えるわけですね。なるほど。エンジニア以外にも通じるアドバイスだと思います。小賀さん、本日はどうもありがとうございました!
【text:外山武史】
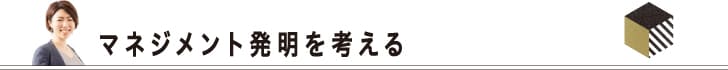
エンジニア職は、スキルや外部労働市場の特性から、自身の成長や新技術試行へのドライブがかかりやすい職種です。先の図でいえば、技能多様性やフィードバック、自律性への欲求が高いと考えられます。今回、VOYAGE GROUPが発明したマネジメント方法を、職務特性理論に照らすと下図のようになります。
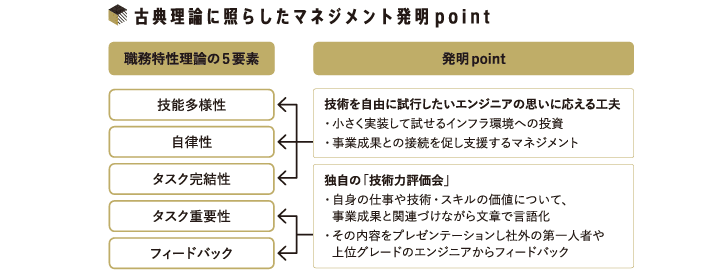
事業観点でより良い方法を自律的に検討させることや、新しい試行をしやすくする仕組みで自律性や技能多様性の欲求に応え、さらに技術力評価会では公平で納得感のあるフィードバックがもらえるだけでなく、仕事の重要性を事業価値から説明する力を磨く機会ともなり、タスク重要性を高めていたといえるでしょう。取り組みの浸透を実現したのは、小賀氏の8年以上にわたる情熱的なリーダーシップと施策への関与です。理論的にも理想的なこの形は、エンジニアという職種に真摯に向き合うことを通じ実践へと昇華されてきたのですね。
【インタビュアー:荒井理江(HRテクノロジー事業開発部)】
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.55連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第1回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
小賀 昌法(こが まさのり)氏
株式会社VOYAGE GROUP 取締役CTO
2010年にECナビ(現VOYAGE GROUP)に入社。CTOとして、エンジニアの採用・育成・評価戦略におけるさまざまな仕掛けを構築・運用し、エンジニア文化の醸成に貢献。また、サービスインフラや社内インフラの構築・運用を手掛けるシステム本部長や情報セキュリティ委員長も兼任。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




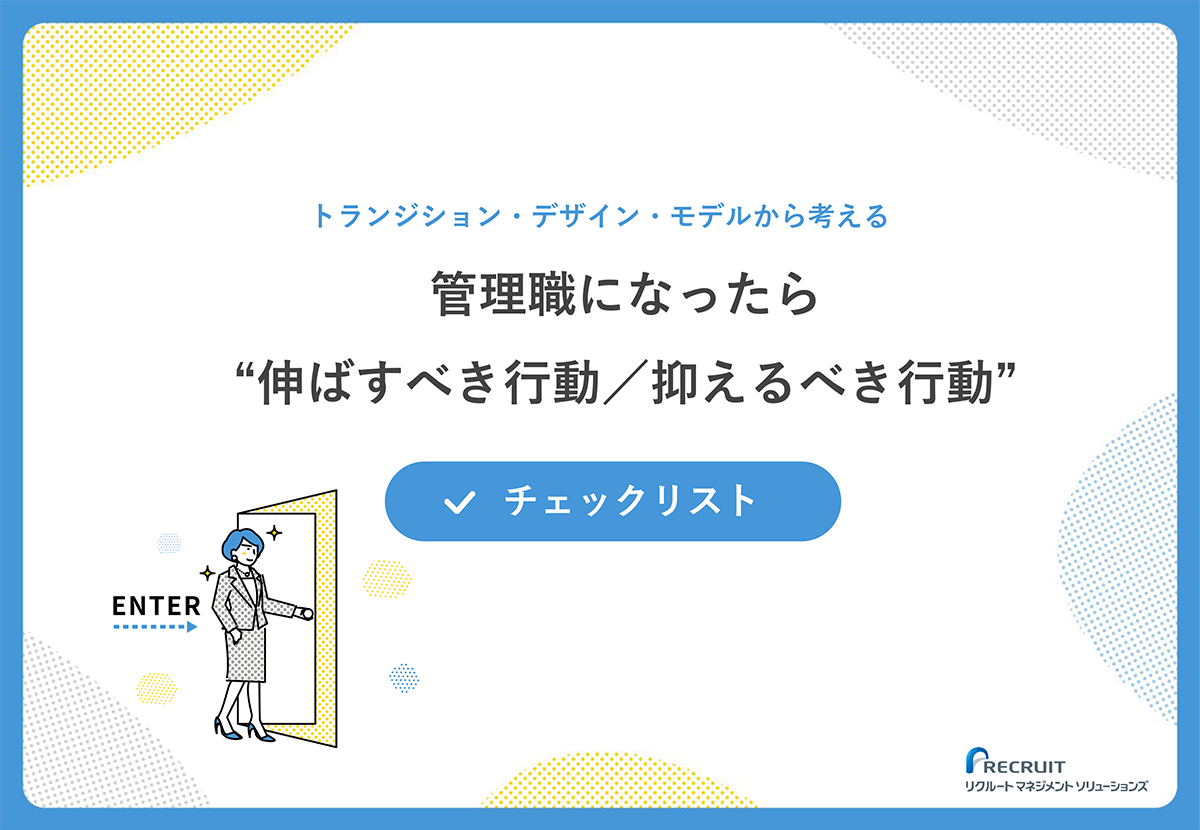









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての