連載・コラム
可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 公開日:2024/07/22
- 更新日:2024/07/22

本連載は、創業から歴史は浅くとも、独自の組織・人材観を掲げ成長する企業や組織に取材し、その「発明」に学ぶインタビューシリーズだ。今回の取材先は、創業100周年を迎えた老舗企業でありながら、しなやかに挑戦を続ける木村石鹸工業。その道のりは一筋縄ではいかなかった。社長就任前からその状況を俯瞰していた4代目社長の木村祥一郎氏に、組織の課題とどのように向き合ってきたのかを聞いた。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
「責任」とは最後までやり抜くことだ
山田:木村さんは大学時代にご学友とIT企業を興されて、副社長をしていたそうですね。
木村:そうなんです。僕は長男なので小さい頃から親父に「お前は4代目の社長だ」と言われて育ったのですが、いつしか「何で人生を親父に決められなきゃいけないんだ?」と疑問に思うようになりまして。親父が石鹸を作ったり、商売したりしている様子がすごくカッコ悪く見えて「こんな世界にいたくない」と思ったんです。大学で京都に出てから家には寄り付かなくなりました。
加茂:そんな過去があったのですね。
木村:親父も諦めて他の人に社長を任せて会長に退いたんですね。でもその間にいろいろと問題が起こって、社員が親父のもとに来て「このままだと全員辞めます」と直談判したそうです。仕方なく親父が社長に戻ることに。でも親父の体調が悪く「どうしようもないから手伝ってほしい」と僕に言ってきたんです。とはいえ、IT企業の仕事があるので、いきなりは戻れません。僕の知り合いの外資系化粧品会社の社長を経験した方が「自分のキャリアの最後に、中小企業の立て直しをしたい」と言っていたので、渡りに船だと思ったんですね。親父とも意気投合して次こそいけるかなと思ったんですが、またしてもうまくいきませんでした。再び親父から相談されて「じゃあ一旦戻るか」と。3年でIT企業に戻るつもりでしたが、実際にやってみると面白いし、会社の状態も良くなったのでIT企業の役職は退任し、木村石鹸の4代目として覚悟を決めました。
山田:社長に就任された頃は、どんな問題があったのでしょうか。
木村:社員が後ろ向きでしたね。ベテランの営業マンに「言った者負けの会社だ」と言われたことがあるんですよ。
山田:言った者勝ちではなく?
木村:営業マンが、あるお客さんの仕事を獲るために、設備投資の提案をしたんですね。投資実行後、実際に受注して大きな仕事になったんですけど、すぐにその会社が外資に買収され、国内の契約が全部見直しに。ウチへの仕事も急遽なくなりました。そのお客さん専用の設備だったので、一時的に無駄になってしまいました。当時の経営者から「どうするんだ。お前が何とかしろ」って言われたことをその営業マンはずっと覚えていたんです。開発チームも商品の開発をなるべくしたくない様子でした。「こういう商品を開発したい」という依頼書を出すと開発チームが審査するんですが、出した書面がほとんどNGで返ってくる。「同じような商品があるから、これは多分売れないと思います」という具合です。営業も社外に相談した方が親身になってもらえるので、社外の開発会社に相談するんですが、自社で開発チームがあるのに社外で開発していたら、そら儲からないですよね。
山田:どうしてそんなことに?
木村:ようするに、経営側から「失敗するな」というメッセージをずっと発せられていたわけです。だから、なるべく失敗したくないので、自分は手を挙げないし、新しいこともやりたくないと。とにかく稟議書が多いのも象徴的でしたね。当時20名の会社なのに5個も6個もハンコが押してある。それっていうのは、自分が責任をとりたくないという姿勢の表れですよね。
加茂:その状況を打開するために、木村さんは何から取り組んだのですか。
木村:最初の3年はとにかく社員と話をしました。不満や心の叫びを引き出して、なるべく対応するようにしていましたね。稟議書に関しても「僕は分からないので、自分で決めてもいいですよ」と伝えていました。すると「責任がとれません」という話が出てきたのです。みんな「責任」の意味をペナルティのようにネガティブに受け止めていたんですね。そのため、当社の「責任」は「自分がやると決めたことを最後までやり抜く意志」と意味づけしたんです。社員には最後までやり抜いてもらう。その代わり金銭的なデメリットやトラブルの謝罪に関しては会社が責任をとる。社員は途中で失敗しようがトラブルを起こそうが、最後まで自分ごととして逃げなければいいんです。逃げなければ、「あの人はちゃんと最後まで責任を果たしてくれる人だ」と信頼される。そういう話を、新人が入るタイミングや朝礼などで繰り返し伝えてきました。「責任というのは、最後までやり遂げることなんだよ」と。次第に社員の意識も変わっていきました。
山田:失われていたチャレンジ精神や主体性が養われていったのですね。
加茂:社員の行動も変わり、稟議書も必要なくなったのでしょうか。
木村:そのとおりです。それに失敗を避けてなるべく開発しない姿勢から、とにかくトライした方がいいという価値観に変わると、今度は失敗が増えるじゃないですか。だから失敗したネタを僕が拾い上げて、社内全体に「こんな面白い失敗があった」ってネタにしたり、メディアにその失敗のネタを語ったりしていました。
加茂:木村石鹸では失敗も称えられるし、ある意味おいしいわけですね。
社員の過去を査定せず社員の未来に投資する
山田:聞くところによると、社員の皆さんの給与は自己申告で決めるそうですね。
木村:そうです。評価制度や賃金制度は、会社から社員に向けてどう働いてほしいのかというメッセージとしては一番強烈だと思っていました。ただ、評価制度の変更はすごく重いので、そう簡単に変えられなくて。しばらくは僕が決めて、「文句があったら言ってきて」という形でやらせてもらっていたんです。でも、これから新卒を入れていこうというときに「全部社長が決めています。文句があれば言ってください」というやり方では厳しいなと。僕らが目指す方向に合致する評価制度がないか探していたらアメリカで「No Rating」が盛り上がっていたんです。
山田:社員をランク付けしない評価制度ですね。
木村:日本で導入支援していた会社があったので、話を聞きにいったら自分が思っていたことがすでに形になっていたんです。「自己申告型給与制度を日本でやっている会社があるんだ」と感動して、導入を支援してもらったんですよ。
山田:多くの企業は公平かつ正確な評価をしようとしますが、そもそも評価をしないということですね。
木村:人が人を正確には評価できないというところからスタートしています。じゃあどうするか。「その人が未来にやろうとしていることに投資できるかどうか」というスタンスで向き合っています。大事なのは、お互いが覚悟を結べるのか。結果ではなく、未来にどんな価値を提供するかに意識を向けています。だから、給与査定というよりも「これからの未来、こうなったらいいよね。じゃあ、これぐらい君に賭けよう」という前向きな対話になるわけです。
加茂:それにしても、社員の創発を待つ姿勢が素晴らしいですね。
木村:待つというより、自分は営業も製造も何もできないので、みんなに任せるしかないんです。ちなみに、僕たちは社員たちの提案を吟味する場を「投資額決定委員会」と呼んでいます。提案を未来に実現できるか吟味をして、どこまで投資できるかを判断する場にしたいからです。「査定」と「投資」では社員の目線が全然違うんですよね。「投資」の場合、提案をどうやって会社に納得させるかという方向に向くので、働き方や目標を立てるときの意識が変わりますし、提案を吟味するマネジャーの意識・目線も変わりました。
山田:全員がどんな価値を生み出したいか考える風土になったのですね。
木村:これは意図していたことではないのですが、「1日何件訪問します」といった個人のパフォーマンスを上げるための内容から、「チーム横断型のプロジェクトで価値を提供します」という具合に、チームで価値を生み出す方向に提案が変化してきました。1日の訪問回数を増やすことに限界があるように、個人のパフォーマンス向上には限界があります。みんなのパフォーマンスを上げていく立場になる方が、未来に大きな価値を生み出せると気づいたからだと思います。
山田:個人単位ではなく組織としてのパフォーマンスを上げて価値を生み出す提案が増えているのですね。
若手が秘密で開発したシャンプーが大ヒット
山田:次の組織課題を挙げるとしたら何ですか。
木村:若い人たちが最前線で、困難なことにチャレンジしていける組織にしたいですね。とにかく若い人たちに活躍してもらって「ベテランは自分の知識と経験を捧げて、若手を輝かせてください」というメッセージを伝えています。自分自身が学生のときに何も知らない状態で起業した経験から、「若いからできない」とか「経験がないから難しい」とかっていうのは、あまりないんじゃないかなと思っていまして。若いからできることもいっぱいありますし。それにベテランの経験や知識が噛み合わさると、イノベーションが起こりやすいと思っているんですよね。僕らはメーカーなので、ユニークな商品を生み出すことが一番のコアだと思っています。ユニークな商品を生み出すには失敗を含めて「トライの回数」が重要であり、勢いに任せて若い人たちがやる方が、トライの回数が増えると思います。「12/JU-NI」というシャンプーが、良い例です。社員が5年ぐらいかけて、みんなにも秘密にしたまま研究を重ねた末に完成したものなんですよ。
山田:えー!そうなんですね。
木村:僕はシャンプー市場なんて競合も多いし絶対ダメだと思っていたんです。でも使ってみたら、めちゃくちゃ良かった。SNSで紹介したら大反響だったので、180人ぐらいのモニターに使ってもらったんですね。すると「早く商品化してほしい」と熱烈なメールやDMが届いたんです。実際に商品化して発売したら、今の自社ブランドのなかで最も売上が大きな商品に。自由に開発できる環境だったからトライしてくれていたんです。
山田:若手が主体的にチャレンジした素敵なエピソードですね。最後に、組織づくりに励んでいる人事担当者にアドバイスをお願いできますか。
木村:いえいえ、僕たちも多くの企業と同じく組織の悩みはありますから。ただ、人間関係の問題はその会社固有の問題であり、その人固有の問題もあるので、セオリーやロジックになびかない方がいいです。それより「生の社員と向き合い、会話する方が見えてくるものがある」と思っています。
【text:外山 武史 photo:角田 貴美】
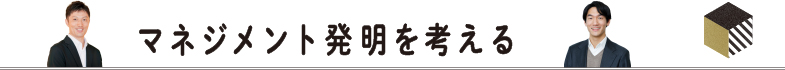
未来を見据え、従業員と互いに覚悟を結び合う経営
身の回りの実験から組織変革を起こす[山田]
自己申告型給与制度や投資額決定委員会などのユニークな制度・仕組みを聞くと、その内容や運用面に目が行きがちですが、ポイントはその手前にあるのだと思いました。まず木村さんは従業員との対話からスタートし、組織で何が起きているのかという背景を捉えたのち、身の回りから稟議書をなくしていくことや、「責任」について直接語ることを通じ、期待する行動や是正したい態度を発信されました。
制度や仕組みを通じ、現場の行動、ひいては組織風土を変えていくためには、身の回りで小さく実験し、反応をもとに改善していくようなアプローチが重要なのだと感じました。
従業員を信じ、支援することがすべての出発点[加茂]
組織運営上、特に余裕がない状況においては、経営・マネジメントが従業員に対して、結果責任の追及や結果の査定のみに焦点を当てることが多いように感じます。そのようにしてしまうと、従業員の創発を削ぎ、組織としてもより窮地に陥ってしまいます。そうではなく、従業員が構想した未来に投資し、諦めずにやりきるよう期待して要望・支援することにより、新たな価値が生まれ、組織も発展していきます。上記を進める上では、「人は皆創造的で能力に満ちあふれており、失敗も許容される環境においては、任せられたことは最後までやりきる存在である」といった人間観が必要のように感じます。
【インタビュアー:加茂 俊究(コンサルティング部)[左]/山田 海(コンサルティング部)[右]】
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.74連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第20回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
木村 祥一郎(きむら しょういちろう)氏
木村石鹸工業株式会社 代表取締役社長
1972年、大阪府八尾市生まれ。同志社大学在学中の1995年に仲間数名とネット検索エンジンを提供する有限会社ジャパンサーチエンジンを立ち上げる。以来18年間、商品開発やマーケティングなどを担当。2013年にIT会社取締役を退任し、家業である木村石鹸工業株式会社へ。2016年9月、4代目社長に就任。
バックナンバー
第15回 内発的動機は報酬に勝る(サービスグラント)
第16回 応援から生まれる挑戦がある(ETIC.)
第17回 未来の大人と共に描く未来(ユーグレナ)
第18回 対話の力で主体的な挑戦を育む(広島県教育委員会)
第19回 80億人の異彩を放つ社会を目指して(ヘラルボニー)
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



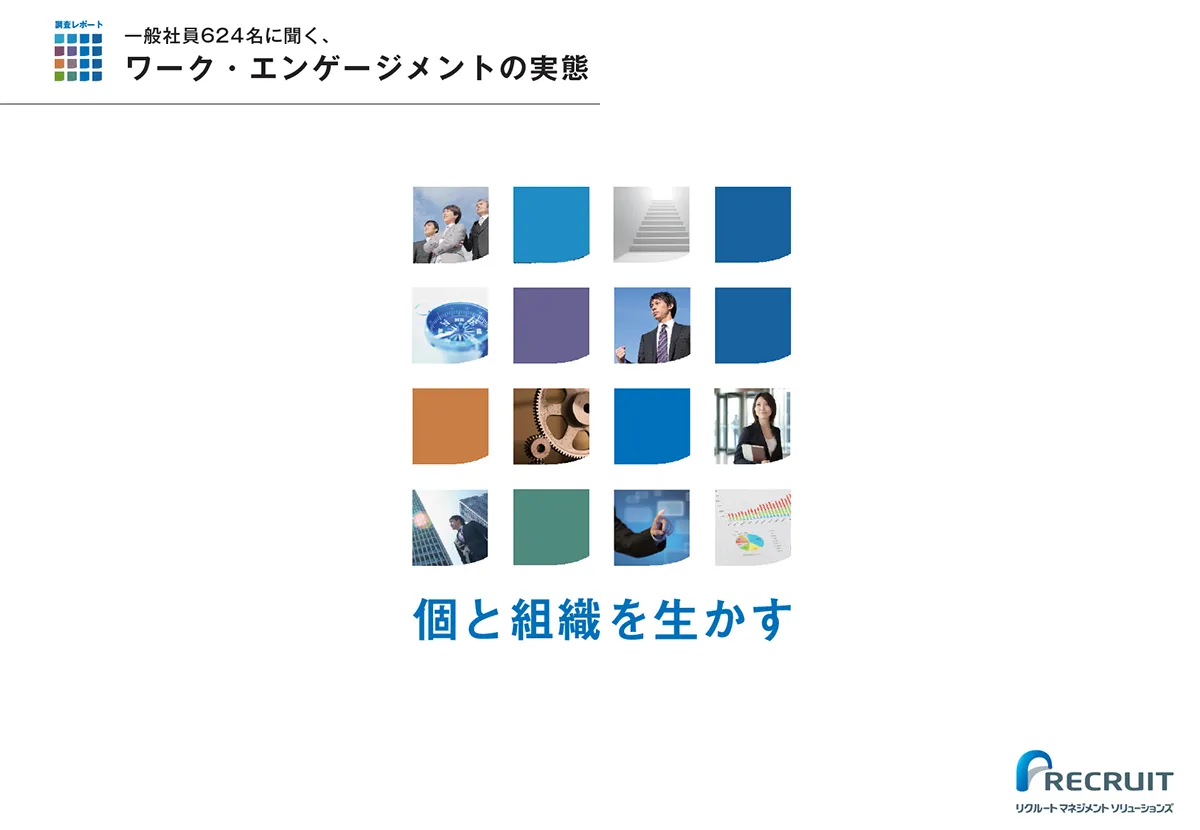
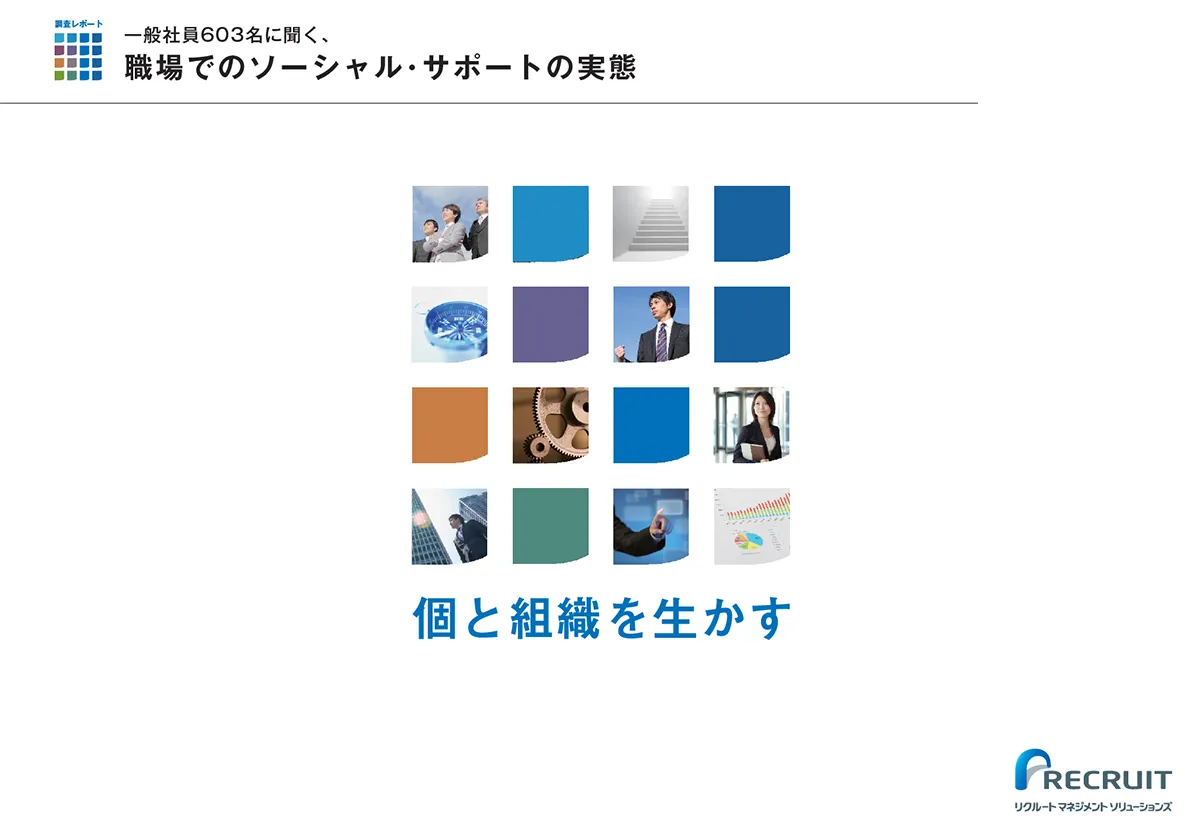









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての