- 公開日:2020/11/02
- 更新日:2024/04/04

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。今回はエンジニア、デザイナー、クリエイターなど志向の異なる人材全員をCEOとして扱う、株式会社ゆめみの発明に迫る。代表取締役 片岡俊行氏にお話を伺った。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
今回のテーマ「連結ピン」
「連結ピン」とは、米国の組織心理学者R.リッカートが提唱した組織とリーダーシップの関係に関する概念です。人と人、人と組織、または組織と組織を有効的に結びつけ、コミュニケーションを円滑化することで組織の意思決定や業務推進を支える、いわば“潤滑油”の役割のこと(図表1)。
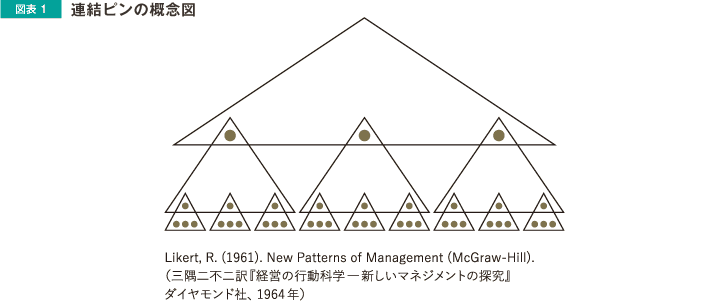
リッカートは、組織マネジメントをシステムと捉えた上で、その特徴が4つに分類されることを1961年に提唱していますが(図表2)、この「連結ピン」としての機能は、特にシステム4、つまり民主主義型システムにおいてその実効性を発揮すると論じています。そして、一般にその役割を担うのが、組織の管理職です。
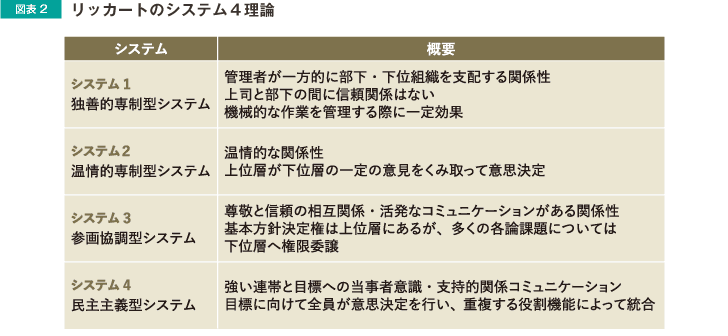
「民主主義型」とは、耳ざわりは良いものの、組織構造が複雑化し、またスピーディな意思決定が求められる昨今において、管理職だけがその連結ピンを担うにはあまりにも負荷が高いことは想像に難くありません。どのように現場の意思決定の質とスピードを維持しながら、全体としての整合性をとっていけばよいのか。独自の組織マネジメント体制を発明された株式会社ゆめみの片岡俊行氏にお話を伺いました。
荒井:さまざまなメディアでゆめみの組織哲学を拝見し、まさに「マネジメント発明」をしていると感じていました。2018年にアジャイル組織を作ると宣言された後の手応えはいかがですか。
片岡:日々新しいチームが生まれたり、人が異動したりと変化していますよ。当社では、全社員が代表取締役権限をもち、自律・分散的に意思決定を行うためのプロリク(Proposal Review Request)(図表3)という仕組みで、意思決定をします。なので、チームの新設や異動も人事ではなく当事者が自ら決定し、組織を変化させています。
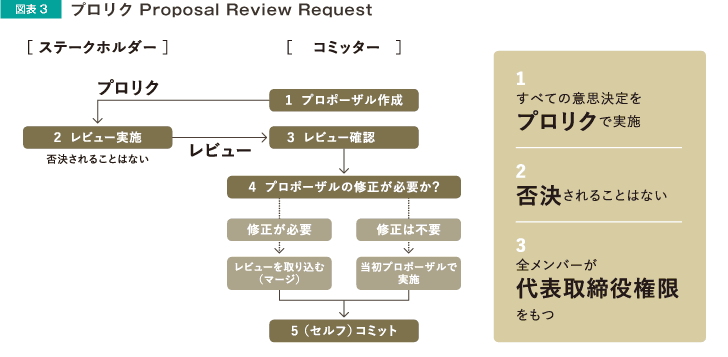
荒井:プロリクでは何を提案してもいいのですか。
片岡:ゆめみでは個人活動からチーム・組織の運営まで、コミッター(決裁権限をもつ人)とコントリビューター(決裁権限をもたない人)からなる形態を採用しています。新卒の1人がコミッターになり、名刺の必要性を感じないから、お客さんに名刺を出さないというマイルールを作ったこともあるのですよ。
荒井:え! それは通ったのですか。
片岡:他のコミッターやコントリビューターは提案を上書きすることはできても否決はできませんので、自ら取り下げなければどんな提案も通ります。
荒井:コントリビューターは、どういう関わり方をしているのですか。
片岡:レビュワーやアドバイザーの役割もありますが、重要なのは「権限がないこと」ですね。Linuxなどのオープンソースコミュニティには、コミッターとコントリビューターがいます。ソースコードを改変できるのはコミッターだけ。最初はみんなコントリビューターからスタートし、実績を出したらコミット権限をもらえるのです。
荒井:オープンソース開発が、組織設計のモデルになっているのですね。
片岡:学生時代の原体験も影響しています。サークルやクラブでは、部長がすべての物事を決めるわけではないですよね。みんなでああだこうだ言ってなんとなく決まっていく。これは、小さな会社も同じような感じだと思います。
荒井:確かにそうですね。ちなみに組織改革のトリガーとなったのはどんなことだったのでしょう。
片岡:実は10年ほど前は、マネジャーに権限が集中してしまって、「負担が重すぎます」という相談もあったのですよ。でも今は、みんなで管理職や人事の苦しい部分を分担している状態だから、肩の力を抜けるようになりました。
荒井:その結果、納得度の高い組織になったと。
片岡:ただし、権限委譲は簡単ではありません。例えば、新任の課長に部長が「任せる」と言ったものの、課長は問題を抱え込んで取り返しのつかない状態で部長に相談に来たとします。すると、「お前には任せられない」という話になり、権限も狭まって信頼関係も崩れる……みたいなことが起こりがちですよね。部長と課長の間で正しく権限委譲を認識し、段階的に委譲する仕組みが必要なのです。
権限委譲の難しさを解消した「二重連結ピン」
荒井:部長が課長に任せすぎるとうまくいかない……ありがちな話だと思います。
片岡:そこで、私たちは「二重連結ピン」という設計を考えました。組織とリーダーシップの関係性を表す概念に「連結ピン(複数の組織をつなぐ役割)」があります。それを二重にするのです。下位組織の組織長が上位組織の構成員であるという関係によって連結されているのが一般的ですが、ゆめみでは上位組織の組織長も下位組織にコントリビューターとして所属します(図表4)。
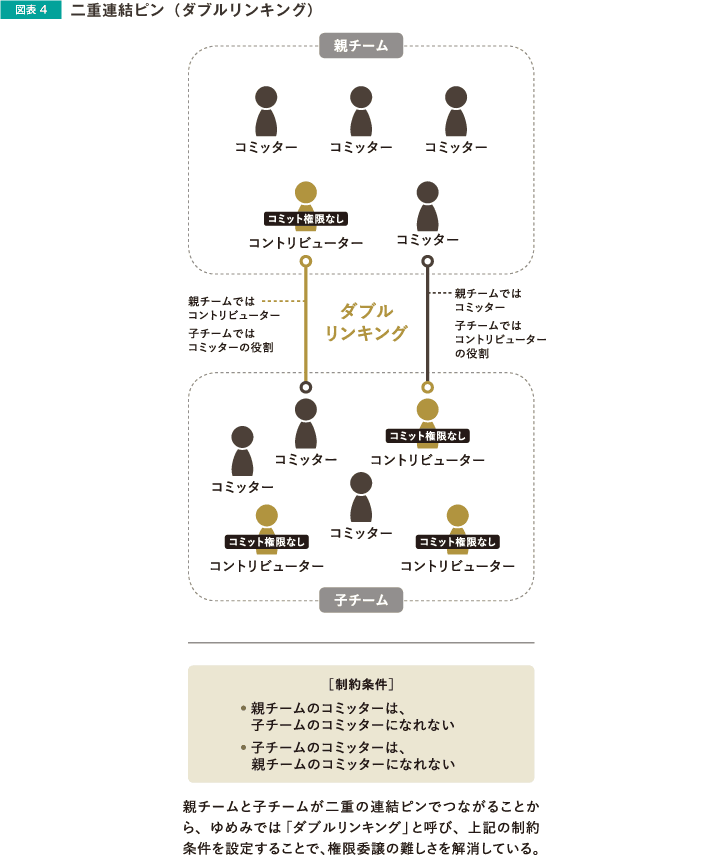
荒井:課に関わり続けるけれど権限はない、と。
片岡:そうです。例えば、マーケティングの戦略を決める上位組織のコミッターは、広報を担う下位組織のコントリビューターになります。下位組織のコミッターは上位組織のコントリビューターになるので、お互いに組織を連結している状態です。上位組織のコミッターはマーケティング戦略の観点から、「その広報戦略は全然マーケティングに沿ってないよ」とアドバイスもできる。しかし、コミットの権限がないので、下位組織のメンバーは「はいはい」と聞くだけ聞けばいい。
荒井:聞き流せるわけですね(笑)。
片岡:日頃から上位組織のコミッターが下位組織のSlackチャンネルでああだこうだ言える環境だから、密なコミュニケーションが生まれるし、それぞれの組織の活動が離れ離れになることもないのです。
自律適応型組織を支える委員会組織とフラクタル構造
片岡:プロリクや二重連結ピンは、チームや個人の権限を独立させながら、その意思決定に外部適応の視点を取り入れて協調を促す仕組みです。もう1つ、チームや組織に長期視点での外部適応を生み出す仕組みとして「委員会組織」があります。チームや組織の問題を発見し、標準化などで効率化を図ったり、新しい手法を開発したり、外部にブランドを形成したりという役割を担い、中長期的に外部環境に適応的な状態にする「組織学習」のための機能です。このように、個人・チーム・組織全体のそれぞれに、短期的・長期的な外部適応の視点が提供され、協調的な意思決定や活動が自律的に選択できることが重要だと思います。さらに、プロリク、二重連結ピン、委員会組織などの仕組みはすべての組織レベルで同じ構造をしており、フラクタル構造(部分と全体が自己相似的な関係)を描いているのです(図表5)。
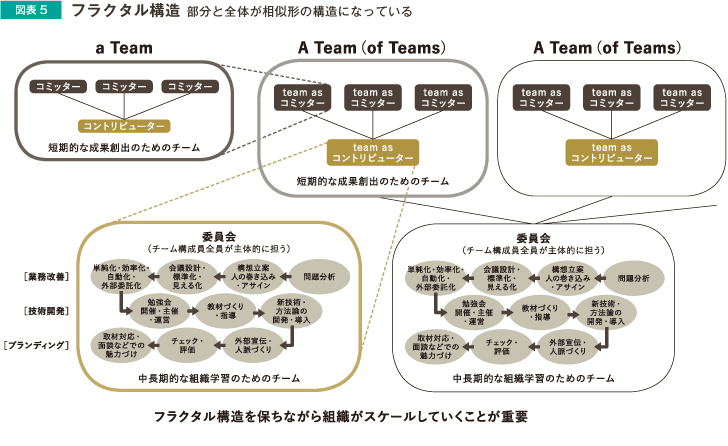
荒井:フラクタルな構造で設計しているから、1000人規模を目指していけるということですね。
片岡:そうです。ただし、課題もあります。現場の状況を観察し、仮説を立てて、組織改革をしてきたのですが、組織が大きくなると隅々まで自分の目で見られなくなるでしょう。私は、一人ひとりがSlackチャンネルで呟いている課題や悩みのすべてに目を通しています。250チャンネルならまだ見られるけど、1000は難しいかなと。
荒井:250チャンネルでも相当すごいです。
片岡:今は私が、ある人の発言を他の人に届くように仲介したり、視座の高い発言をシェアしたりしていますが、これをシステム的に行うために、機械学習によるAIツールを開発しているところです。
荒井:ゆめみのさらなる進化がとても楽しみです。本日はありがとうございました!
【text:外山武史】
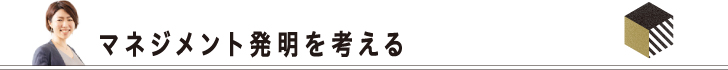
計算された構造が人と組織の自律を生み出す
組織には往々にして、短期視界・個別最適での意思決定に偏る力学が働きます。そのため、長期視界・全体最適へとバランスをとる仕組みを、組織のなかに意図的に仕込む必要があります。従来の組織は、それを管理職が担ってきたわけですが、片岡氏は長期視界・全体最適での外部適合を、「プロリク」と「二重連結ピン」、そして「委員会組織」によって担保させることで、管理職の負担を軽減しながら、組織が自律的に長期視界・全体最適の視点をもって機能するように仕掛けています。
それぞれの機能も非常に興味深いのですが、さらにこれらの仕組みがすべての組織単位において「フラクタル構造」をとることによって、組織規模が拡大したとしても、各組織が長期視界・全体最適の視点をもつことができ、組織の硬直化・官僚化を防いでいけるという点も、非常に面白い発明です。
また、ゆめみの仕組みを運営する上では、有効な意思決定を自律的に行えるリーダーが数多く存在することが重要ですが、「プロリク」や「二重連結ピン」、「フラクタル構造」自体が、そうしたリーダーを育成することにも役立っているといえます。具体的には、意思決定の観点・基準を知ることと、実際に最終的に意思決定する経験を積む貴重な機会となっているわけです。
なお現在は、片岡氏自身が会社全体の連結ピンとして機能されていますが、ゆくゆくはAI はもちろん、この文化のなかで育つリーダーたちによってこの連結ピン機能がフラクタルに担保されていくことでしょう。さらなる展開がとても楽しみです。
【インタビュアー:荒井理江(HRテクノロジー事業開発部)】
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.59連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第5回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
片岡 俊行(かたおか としゆき)氏
株式会社ゆめみ代表取締役
京都大学大学院在学中にゆめみ設立。大手企業向けのデジタルマーケティング支援で関わったインターネットサービスは月間利用者数5000万人規模。デジタル変革のリーディングカンパニーに育てた。現在は「アジャイル組織」を掲げ社内変革の指揮を執る。
バックナンバー
第1回 エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る(VOYAGE GROUP)
第2回 マネジャーの仕事をチームに委譲(サイボウズ)
第3回 “Why”から構築するデザイン組織(グッドパッチ)
第4回 マネジャーがいない会社の組織デザイン(ネットプロテクションズ)
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


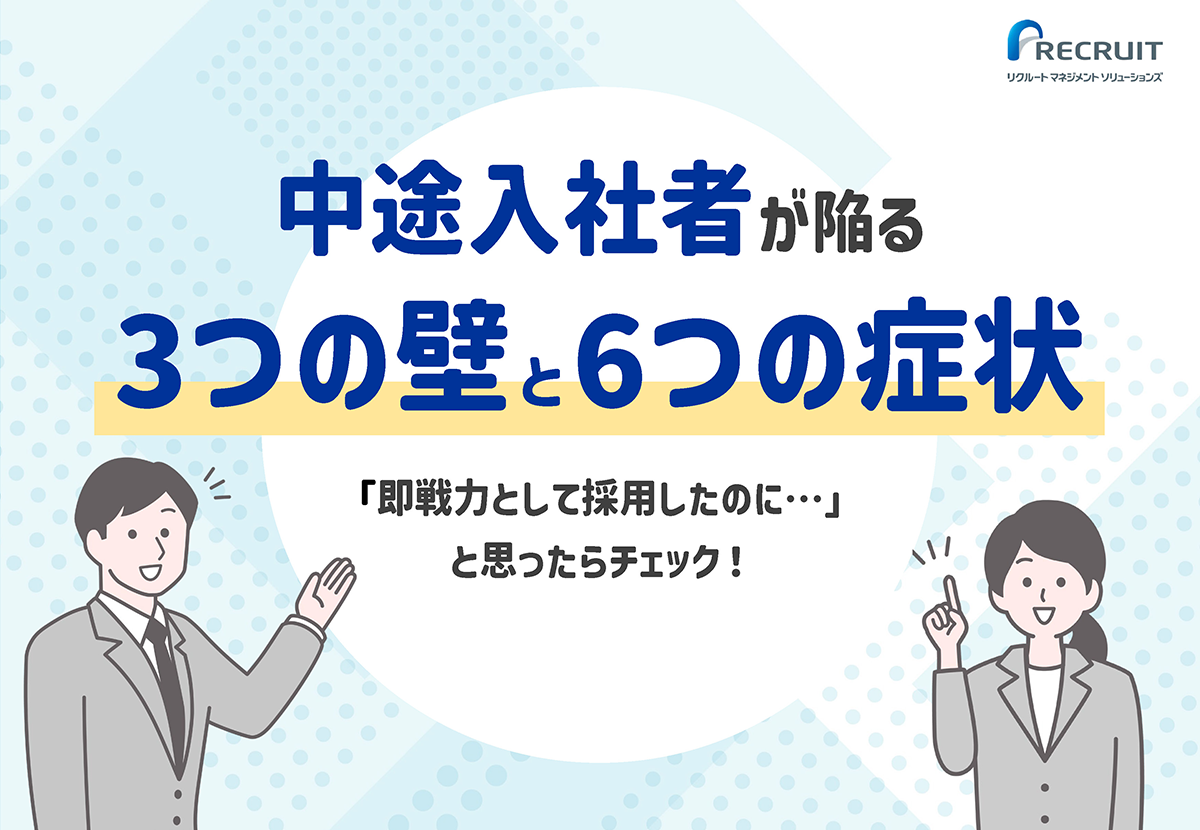
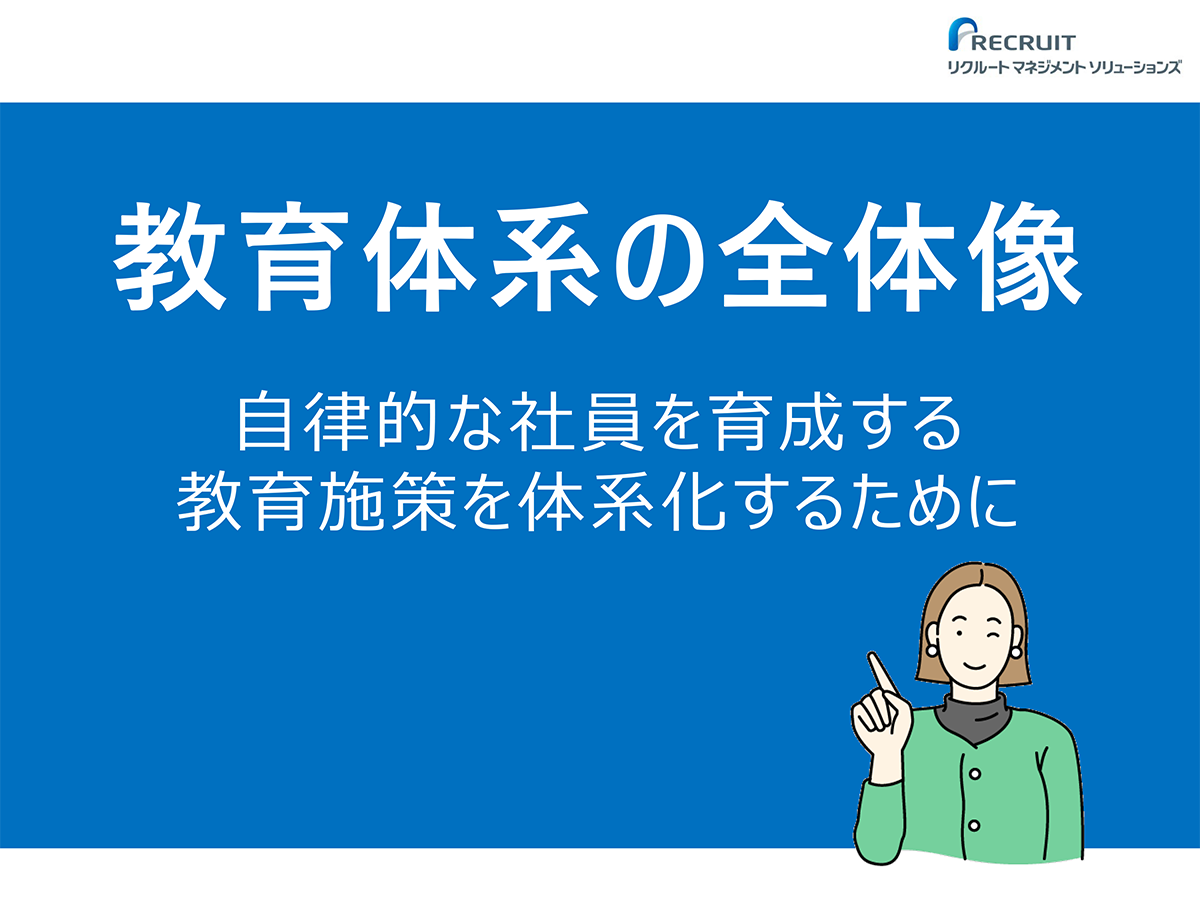
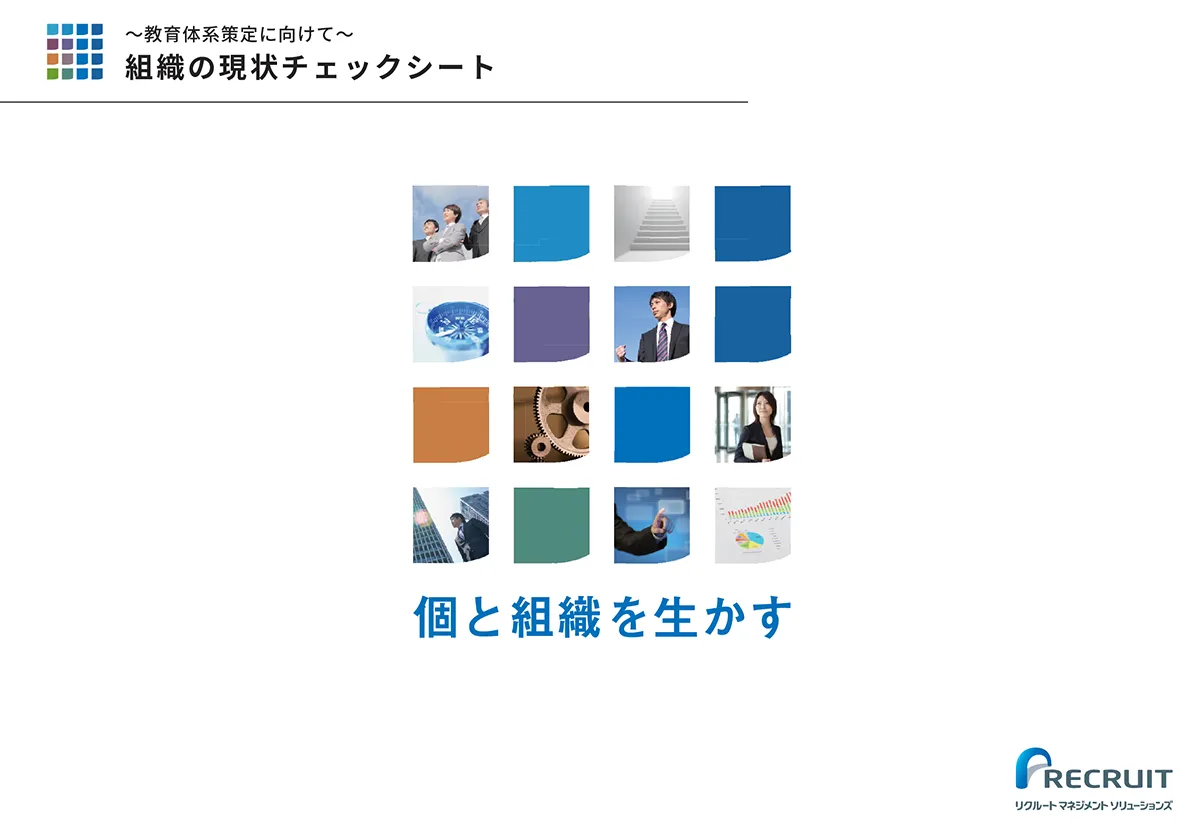









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての