連載・コラム
可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
“Why”から構築するデザイン組織
- 公開日:2020/05/18
- 更新日:2024/04/04

経営学や心理学において古典とされるマネジメント理論は、今日の事業環境においても有効なのだろうか。本連載は、創業から歴史が浅いながらも大きな成長を遂げる企業に、シリーズでインタビューしていく。それら「若い」企業は、現代の人と事業に最適なマネジメント理論を生み出すポテンシャルを秘める。古典の理論を温めつつ、これから急成長に向かう企業から第2、第3 の創業を志す大企業まで広く参考となるような、最新知見を「発明」していきたい。「デザイン組織」を掲げるグッドパッチ代表取締役社長の土屋尚史氏に、「Why」を軸に対等なチームを作るという発明について伺った。
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
- 目次
- 今回のテーマ「自己決定理論」
- デザインの力に気づいた人は多いがその本質を取り入れた組織は少ない
- Whyから考えて本当に必要なものをクライアントと一緒に作る
- デザインはチームで取り組むもの 1つの視点や方向性では磨けない
今回のテーマ「自己決定理論」
やる気に関わる理論枠組みで有名なのは「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」ではないでしょうか。内発的動機づけとは、課題それ自体に喜びや満足をもって取り組んでいる状態を指し、仕事や学習のパフォーマンスが向上することが知られています。一方、外発的動機づけは、罰・報酬などによって突き動かされるような心理状態を指します。
Ryan & Deciが提唱した「自己決定理論」は、この外発的動機づけと、内発的動機づけに、連続性があることを示しました。具体的には、5つの段階で論じています(図表1)。人は任された仕事に対して、一足飛びに「好きだ」「やりたい」(内発的動機づけ)と思えるとは限りません。むしろ最初は、義務的または何らかの罰を避けたい思い(外発的動機づけ)で取り掛かることも多いのではないでしょうか。
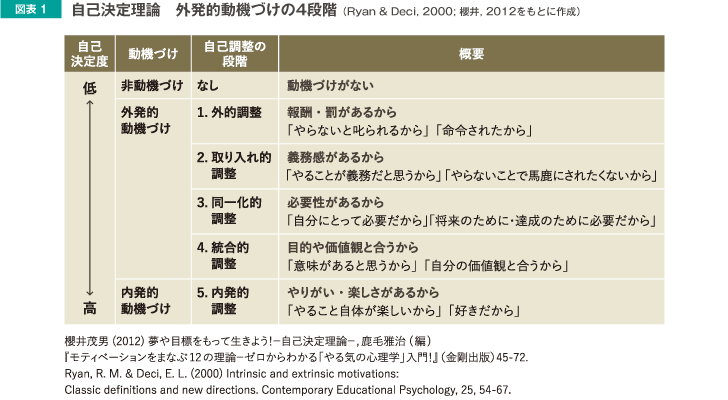
この段階を進めていくために重要なのが、「自己決定感」、つまり自分自身で決めたという感覚をもつことです。やらされているからではなく、自らその仕事を遂行することを選び取っていると思えるかどうか。それには、仕事の意味・価値を自ら言葉にできていることが重要です。この「“なぜ”その仕事をやる意味があるのか?」という問いを社員にも、顧客にも問いかけ、仕事の意義・目的から内発的なエネルギーを生み出し、組織を蘇生させたのが、今回ご紹介するグッドパッチです。
荒井:経済産業省・特許庁が「デザイン経営」を宣言するなど、今、社会からデザインの力が求められています。そのようななか、グッドパッチでは「デザイン組織構築支援」を行っていると聞きました。そもそも「デザイン組織」とはどんな組織ですか。
土屋:いわゆるデザイナー集団ではなく、「デザインの本質」を理解し、実践する集団です。絵を描くことが好き、作品制作が好きで、モノやコトだけに関心を向け、ヒトに関わらない。そういう人はアーティストであって、デザイナーとはいえません。デザインとは本来、企業と人の本質を見つけてつなげていくためのもの。プロダクトやサービスの先にいる相手を想像して、「こういうことをしたら喜ぶよね」とか、相手の体験や感情と向き合って、それを良くするために考えてやっているんです。
荒井:相手ありきのデザインを、グッドパッチでは当たり前にやられているんですね。
土屋: そうです。だからデザインに取り組む前に、クライアントの存在意義やビジョン、哲学のような本質を明確にします。それと同時に、ユーザーのコアニーズを掘り下げる。だからグッドパッチは「Why から考える」をコアバリューにしています。「Why」のなかには、本質や大義、「なぜやるのか」というストーリーが詰まっている。だから必ずみんな「なぜやらないといけないのか」という「Why」からスタートするんですよ。
荒井:上が決めたからやらなきゃ、ではないと。
土屋:上司に対しても「なぜそれをやるのか?」と、仕事の意味を必ず問います。仕事に取り掛かるまで時間がかかって、面倒なコミュニケーションに見えるかもしれません。けれど、「Why」が腹落ちしたら120%やる。相手の期待を超えてやり遂げます。
荒井:言われたからやるのと「Why」が分かった上でやるのとでは全然違うわけですね。
土屋:仕事の意義が腹落ちしていない状態で、「とにかくやれ」と言われても、力が湧いてきませんよね。それにもかかわらず、世の中にはマネジャーが「Why」を伝えない組織が多い。それではデザイナーはもちろん、若者は動かないですよ。
荒井:もはや「Why」なしに若者は動かないですか。
土屋:できる若者ほど社会的意義や目的に共感しないと動かないと思います。
デザインの力に気づいた人は多いがその本質を取り入れた組織は少ない
土屋:AirbnbやUber、Instagram、そして瀕死の状態から20年で時価総額世界一まで上り詰めたAppleも根底にあるのはデザインの力です。今、世界的に「デザインが重要だ」といわれていますが、その本質をつかんでいる人は少ない気がしますね。
荒井:確かに「デザインが大事らしいぞ」で止まってしまっているかもしれません。
土屋:単純に職種としてのデザイナーを集めるのではなく、「本質まで掘り下げる」「人の感情に向き合う」など根底の価値観を揃え、デザイナーのマインドセッ トを組織に入れることが重要だと思いますね。
荒井:グッドパッチのマインドセットはどうやって浸透させたのでしょうか。
土屋:「Whyから考える」は6年ほど前からしていたんですが、自分で考えない「Why待ち」的なメンバーが増えた時期もありました。「Why」って自分で取りに行くことが前提なので待ちじゃダメなんですよ。その一方で、マネジメント層がメンバーの感情に向き合っていなかったこともありました。その結果、組織が崩壊してマネジャーも役員も全員いなくなってしまったんです。だから、改めて「Whyから考える」ことに向き合える人たちと組織を再構築したんですよ。それが組織として強くなるきっかけになりました。仕事を任せられる人が増えたので、私自身は、オペレーション的な仕事はしていないですし、マネジャーたちのマネジメントにもタッチしていません。任せて自由にやらせた方が伸びる人、ある程度細かなフィードバックがいる人など、みんなちゃんと個を見てマネジメントしていますね。
荒井:「Whyから考える」が浸透したことで、任せられる人が増えたんですね。
土屋:ただし、ビジョン、ミッション、バリューの明確化には取り組んでいます。経営の三要素はヒト・モノ・カネといわれていますが、今はお金で動かない人も多いし、マーケットにお金があふれているから、相対的にヒトの価値が上がっていますよね。そこに向き合わないのは経営の怠慢です。
荒井:だから土屋さんは人と向き合い続けているということですね。
Whyから考えて本当に必要なものをクライアントと一緒に作る
土屋:もう1つ、僕の役割として大事なのは「グッドパッチで働く意味」を作り続けることですね。ここ数年は売り手市場なので、みんな働く場所を選べます。だから仕事をいかに魅力的な位置付けにするかが大事。例えば、グッドパッチでは「受託」という言葉を使わないようにしているんです。
荒井:言われたものを作る仕事ではないと。
土屋:そうです。「Why」から考えて、本当に必要なものをクライアントと一緒に作る。だから「クライアントワーク」と呼んでいます。デザイナーたちは納期までに今までできなかったことを実現させるし、クライアントからのフィードバックがあるから成長します。グッドパッチにおいてクライアントワークは人を育てる装置なんですよ。
荒井:「言ったことだけやればいい」というクライアントはいませんか。
土屋:そういう依頼は基本的にお断りしています。僕らがパフォーマンスを出すことができて、企画や戦略から関われる仕事を選んでいます。だから、グッドパッチでクライアントワークをしているデザイナーは、WEBやデザイン系の業界のなかで、最も誇り高く働いていると思いますよ。
荒井:大企業と対等なパートナーシップを組むのは難しくありませんか。
土屋:そもそも「外注」「下請け」という発想の会社とはパートナーシップは組めません。パートナーシップは対等なものだからです。
荒井:古い価値観の企業でも、「この組織を変えたい」という担当者だったらどうでしょうか。
土屋:その熱意を感じて「一緒に仕事をしましょう」ということはあります。そういう意味で担当者の熱量が仕事を請ける基準にもなっていますね。
デザインはチームで取り組むもの 1つの視点や方向性では磨けない
荒井:クライアントの期待を超えるチームはどのように作るのでしょうか。
土屋:必ずプロジェクトのキックオフミーティングをします。2~3時間かけて自己開示をするんです。自分のバックグラウンドを話したり、一番愛しているモノを持ってきてもらったりとか。
荒井:愛しているモノ! 確かにそこに嘘はつけませんからね。
土屋:愛しているモノを選ぶプロセスにも、必ずその人のストーリーがあるじゃないですか。そのなかに、価値観が表れると思っています。
荒井:クライアントワークに取り組む前に、まずチームを作るんですね。
土屋:決して1人に任せることはしません。なぜならデザインはチームでするものだからです。1つの視点、1つの方向性だけだと深く掘れないし、ブラッシュアップできません。フィードバックやディスカッションのなかで深めていくものです。チームで取り組む分、工数は増えますが、それでも、売上も問い合わせも増え続けています。
荒井:チームで取り組んだ方が、品質が上がるということの証明ですね。
土屋:品質を上げるという点に関して言えば、その仕事が、クライアントの存在意義の明確化や、クライアントのミッション・ビジョンにつながっているかも重要です。つながっていないと、その仕事の「Why」が曖昧になってしまいます。だから、必ずクライアントの経営者にプロジェクトの目的や背景、期待をインタビューしています。その上で、ユーザーのコアニーズとフィットするポイントを探す。企業とユーザーの間をつなぐことが、僕らの仕事なんです。
荒井:自社の組織づくりとも重なりますね。
土屋:そのとおりで、マネジャーは「Why」がないまま「誰かに指示する役割」という具合に、役割を誤認してはいけないと思っています。
荒井:クライアントワークもチームマネジメントも構造は同じなんですね。
土屋:そのことをみんな理解しているから、マネジャー志願者が増えています。
荒井:すごい。マネジャーになりたがらない若者が増えているのに。
土屋:マネジャー志願者が増えているのは、会社のビジョン、ミッション、バリューに共感する人だけを採用していることも大きな理由ですね。また、グッドパッチにいると、人への興味が高まるようです。
荒井:みなさんがマネジャーを志望するきっかけは何なのでしょうか。
土屋:みんな1人でできることの限界を知るんじゃないでしょうか。チームの方が大きなインパクトを出せると気づくときがくるんだと思います。会社も同じです。この会社はデザインの力を証明することがミッション。インパクトを起こすにはそれなりの規模が必要だから、人数を増やすと決めていました。
荒井:社会にインパクトを与えるために、仲間を増やして育てていくと。規模を大きくした後は、どんな展開を考えていますか?
土屋:「Why」なしで思考停止状態のまま作られた、使いにくいプロダクトが世の中にたくさんあります。グッドパッチが数千人規模になったとき、どんなインパクトが残せるだろうかと考えていますね。
荒井:素晴らしい社会貢献になりますね!
土屋:ただし、人が成長し続ける環境を用意することが最優先です。グッドパッチを成長意欲の塊みたいな人たちの集団にしたいし、成長の機会を与え続けていきたいですね。
【text:外山武史】
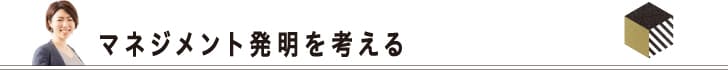
「受託とはいわない」という土屋氏の言葉が表すとおり、同社のデザイナーが目指すのはクライアントと共通の目的をもつ強いチームとなること。そのため、「なぜこの案件をやるのか?」について、共に議論し「統合」させるプロセスは理にかなっています。逆に、かつての「Why待ち」の状態は、「外的調整」や「取り入れ」の段階の発想とも考えられ、顧客と良い関係を結ぶことは難しかったでしょう。同社は、この文化を採用・マネジメント層の見直し、バリューの浸透によって創り上げました(図表2)。さらにこの文化は三者の相互の関係性によって維持・強化されると考えられます。人間に関心をもちメンバーの心に向き合う人をマネジメントに据えた点、意欲ある顧客を選ぶと決めた点は、文化の土台を作る勇気ある重要な意思決定だったといえるのではないでしょうか。
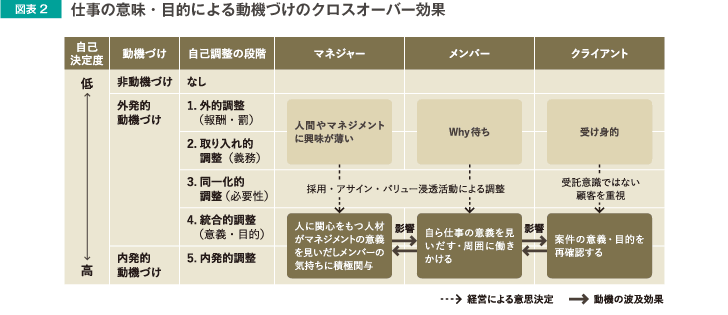
【インタビュアー:荒井理江(HRテクノロジー事業開発部)】
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.57連載「可能性を拓くマネジメント発明会議 連載第3回」より転載・一部修正したものです。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
土屋尚史(つちやなおふみ) 氏
株式会社グッドパッチ 代表取締役社長/CEO
サンフランシスコのbtrax Inc.にてスタートアップの海外進出支援などを経験し、2011年にグッドパッチを設立。UIデザインを強みとするプロダクト開発でスタートアップから大手まで数々の企業を支援。ベルリン、ミュンヘン、パリに進出し、日本とヨーロッパで170人のデザイナーを抱えている。
バックナンバー
第1回 エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る(VOYAGE GROUP)
第2回 マネジャーの仕事をチームに委譲(サイボウズ)
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第20回 木村石鹸工業
- 失敗は栄養 社員を信じ未来に投資
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第19回 ヘラルボニー
- 80億人の異彩を放つ社会を目指して
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第18回 広島県教育委員会
- 対話の力で主体的な挑戦を育む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第17回 ユーグレナ
- 未来の大人と共に描く未来
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第16回 ETIC.
- 応援から生まれる挑戦がある
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第15回 サービスグラント
- 内発的動機は報酬に勝る
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第14回 Gaudiy
- 組織の自律分散と中央集権を使い分ける
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第13回 メタリアル
- VR(バーチャル・リアリティ)オフィスは人類の叡智を解き放つ鍵
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第12回 READYFOR
- 行動原理の異なる、エンジニア組織と事業を「乳化」させる
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第11回 カウシェ
- 希少な優秀人材を副業で巻き込む
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第10回 ヤッホーブルーイング
- ピースなチームは一日にして成らず
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第9回 ユーザベース
- 丹念な言語化文脈の理解が文化醸成の礎
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第8回 Ubie
- 1社複数文化が最適解 文化は「混ぜるな危険」
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第7回 Japan Digital Design
- 「らしさ」と創造的な場をデザインする
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第6回 ヌーラボ
- “協働”を育む多国籍企業のコラボの流儀
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第5回 ゆめみ
- 人が増えても“全員CEO”を貫く組織設計
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第4回 ネットプロテクションズ
- マネジャーがいない会社の組織デザイン
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第3回 グッドパッチ
- “Why”から構築するデザイン組織
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第2回 サイボウズ
- マネジャーの仕事をチームに委譲
- 可能性を拓くマネジメント発明会議 第1回 VOYAGE GROUP
- エンジニアを奮い立たせる仕組みを作る
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



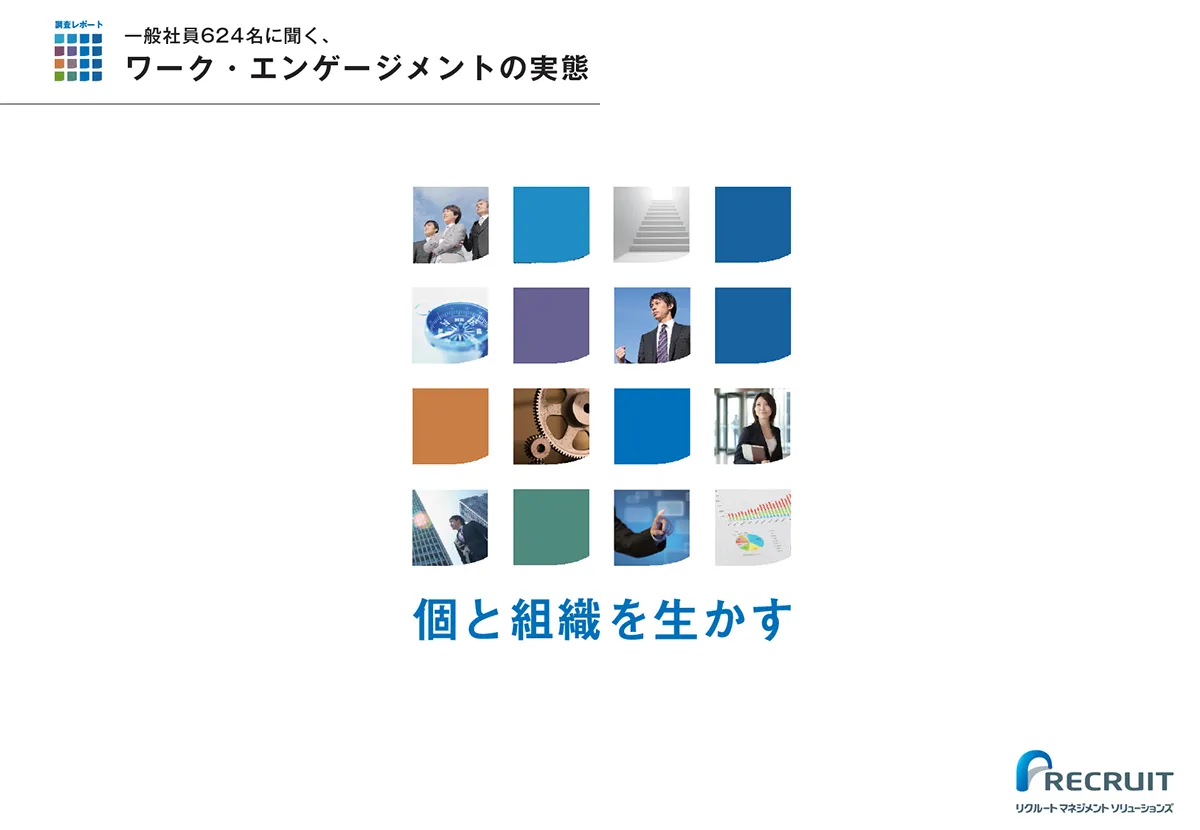
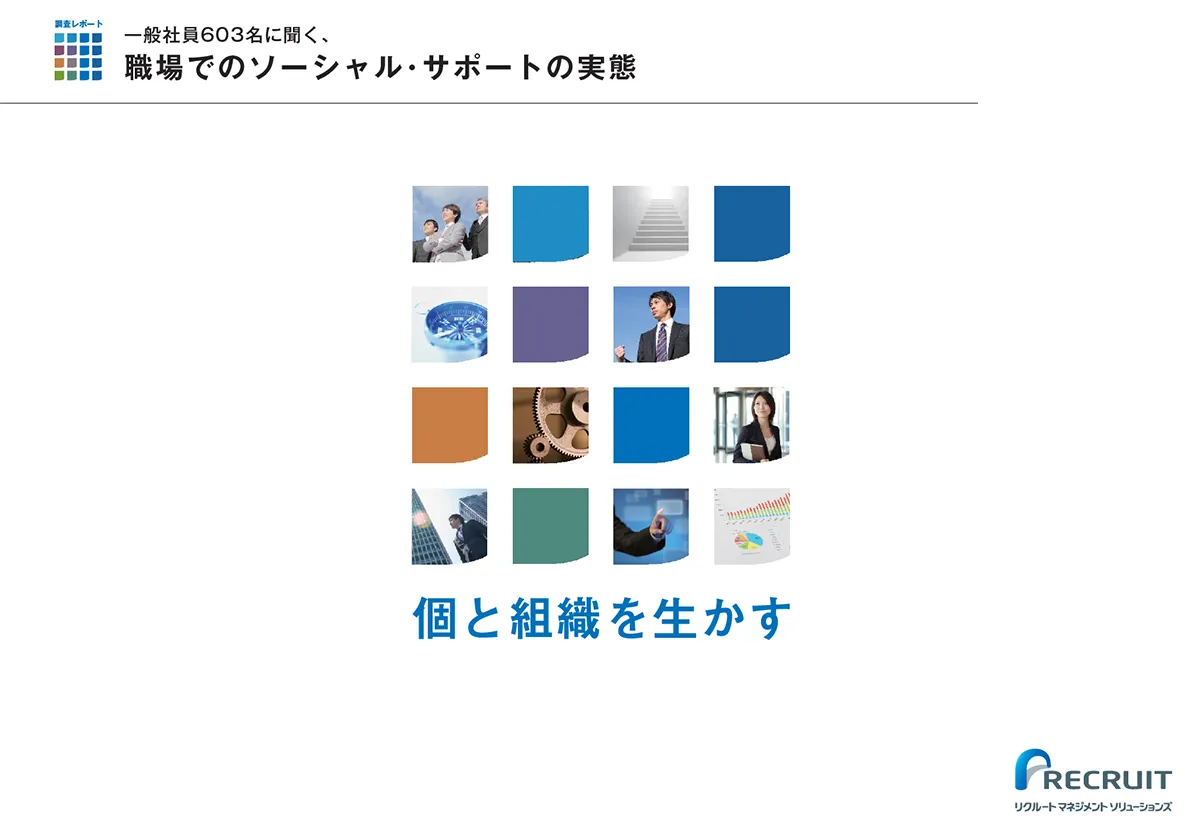









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての