連載・コラム
Pre-On-Postの「三位一体」ではじめてあらわれる研修の効果
現場で生きる研修にするために
- 公開日:2008/09/08
- 更新日:2024/05/16

新入社員から管理職の能力開発支援、組織活性化まで人と組織を生き生きとさせるために行われるさまざまな研修。企業がそれらに求めているのは、研修での気付きや発見が現場での成果(具体的な行動変容)に結び付くことではないでしょうか。弊社が提供したい価値もまさしくそこにあります。そこで今回は、弊社北海道支社の支社長を兼務するトレーナーが、企業とトレーナーの双方の立場から見た効果的な研修のあり方について語ります。新入社員から管理職の能力開発支援、組織活性化まで人と組織を生き生きとさせるために行われるさまざまな研修。企業がそれらに求めているのは、研修での気付きや発見が現場での成果(具体的な行動変容)に結び付くことではないでしょうか。弊社が提供したい価値もまさしくそこにあります。そこで今回は、弊社北海道支社の支社長を兼務するトレーナーが、企業とトレーナーの双方の立場から見た効果的な研修のあり方について語ります。
行動の根っこにある考え方や生き方に軸足を置くからこそ、現場感覚を大切にしたい。
私は現在北海道エリアの責任者(支社長)として日々のマネジメントを行いながら、トレーナーとしても週に1回(2~3日)程度研修の現場に出ています。したがって支社長として、トレーナーとして、さまざまな企業と接し、研修や人材開発に対するいろんなご要望や期待を感じている訳ですが、その中で一番大事なのは現場感覚ではないかと思っています。具体的には「この講師・先生はうちの現場をどこまでわかってやってくれているのか」とか、「受講生は研修で学んだことをどれだけ現場で生かすことができるのか」といったことです。
弊社の研修にはいわゆる知識を取得するだけのものはありません。ビジネスパーソンとしての個人の考え方であるとか人としての生き方であるとか、人間の行動の「根っこ」の部分にある姿勢やスタンスに軸足を置いたプログラムがほとんどなんです。だからこそ、日常の現場感覚を大切にしたいんですよね。プログラム開発時に、営業、トレーナー、そして開発者が一体となって現場の生々しい話をしながら、いつも喧々諤々やっているのもそうした理由からです。

それぞれの担当にも現場への意識が根付いています。
例えば、営業担当者は発注者である企業の人事部門へはもちろん、極力研修の対象者がいらっしゃる現場に出向いて可能な限りのインタビューを行います。「どんな仕事を、どんな思いでしているのか?」「どんなところに喜びを感じ、どんなことで悩んでいるのか?」・・・。これら現場情報をきちんと事前にトレーナーに伝えていきます。
また、実際の研修場面においては、インハウス(特定の企業向け研修)と一般の公開コース(さまざまな企業の受講者が合同で実施する研修)の区別なく、トレーナーも「日頃、仕事の現場ではどうですか? できていますか?」といった現場の状況を問う投げかけを常に行いながら運営するようにしています。そして、日頃できていない点についてはその原因を一緒に考えながら受講生の考え方や生き方にまで掘り下げていく。ここまでやらないと、長年しみついた行動は変わらないんですよ。だからこそトレーナーたちは常に現場を意識しながらプログラムを進めていくのです。
効果を最大限にできるかどうかは、研修の前後がカギ。
現場感覚を重視する弊社の研修が、果たして現場で生きるかどうか。そのカギを握っているのは実は研修前後の職場でのコミュニケーションにあると思っています。
例えば、弊社では受講生の皆さんに研修終了後のアンケートをお願いしているのですが、「研修に期待をしていましたか?」という問いに対する数値は総じて低いんです。確かに日常の業務が忙しい中で研修に送り出される方には、「なんでこの忙しい時期に研修なの?」という思いもあるでしょう。でもそんな中で、上司から研修に向かう自分への期待を感じるメッセージをひと言でももらえていたら、研修に臨む気持ちがまったく違ってくるみたいなんです。
私も上司の立場としてメンバーを研修に送り出すことがありますが、本人の課題や研修との関係などを必ず伝えるようにしています。メンバーが研修から帰ってきた時も同じです。研修をきっかけとして本人に気付きが起こり、何かが湧き上がってくる。そんな時は誰かに話したいし、聞いてほしいものです。そういう気持ちを持ったメンバーに、上司の方からぜひ話しかけてほしいのです。「どんな研修だった?」「どんなふうに感じた?」「どうすればいいと思った?」そんな何気ない問いかけでいいんです。メンバーからはきっといろんなことが溢れ出すでしょう。そんな思いを受け止めて欲しいのです。それだけでメンバーは「よし!頑張ろう」と思うものです。
こうした職場のコミュニケーションは上司と部下との関係をより深め、組織の一体化を促すきっかけにもなります。正直、私が日頃接する北海道の企業では、研修後に上司との面談を設けているケースは非常に少ないんですが、私は研修後の上司面談をぜひ制度化してほしいと思っています。
また弊社ではフォロー研修も積極的に提案しています。研修の場ではわかったつもり、理解したつもり、やる気になったつもりでも、実際の職場では忙しさに流されてなかなか実践できないものです。だからこそフォロー研修をセットで実施することで、こうした課題が解決できる可能性が高まるんです。研修で学んだこと・気づいたことを実践できている受講生とできていない受講生がもう一度話す場をつくることで「なぜ」が生まれ、ノウハウやナレッジを共有することで研修の内容がはじめて腹に落ちる受講生がいるのも事実なんです。

しっかりとした基本や基礎が成長の糧になる。
私は組織における人の成長はPDSのサイクルを回すことで為され、成長のスピードはPDSを回すスピードで決まると思っています。またPDSを回す際に非常に重要だと思うのが、「自律」と「協働」に関する基本や基礎と呼ばれる部分です。なぜなら、成長できない大きな原因の多くは「できてあたりまえのことができていない」「わかっちゃいるけどできない」といった基本や基礎がきちんとできていないことにあるからです。
私が『FBC(新入社員導入研修)』、『SBC(中堅社員基礎研修)』、『MBC(管理者基礎研修)』といった研修が好きなのも、基本や基礎を扱うプログラムであるからなのかもしれませんね。そして、基本や基礎は新入社員に限ったことではなく、ビジネスパーソンを卒業するまでずっと大切なことであり、学ぶ姿勢や成長する姿勢のベースになっていくことだとも思っています。
私自身も基本や基礎を大切にしています。「人と組織を元気にする」仕事を人生最後のライフワークにしたいと思って飛び込んだトレーナーの世界。生まれ故郷である北海道で勤務する機会を得て支社長も兼務することになりましたが、これからも今の自分にとっての基本や基礎とは何かを問いかけながら、それぞれの仕事を通じていつまでも成長し変化し続けていけたらと考えています。
執筆者

人材開発トレーナー
小田嶋 章一
1958年生まれ。大手人材開発・情報出版企業に入社。人事教育・人事測定事業の営業を経て、その後人事部へ異動し主に採用や研修業務を担当。人事課長に昇格後、採用広報の営業課長や販売促進誌の編集長を歴任。優秀経営者賞・マネジャーMVPなどの社内表彰も数多く受賞。エグゼクティブマネジャー昇格後は新規事業のビジネスモデルの構築に貢献。2002年リクルート(現 リクルートマネジメントソリューションズ)のトレーナーに。自動車・食品・電機メーカー始め、金融・商社・不動産・マスコミなど多岐に渡る業界を担当。08年4月より北海道支社の支社長を兼務。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


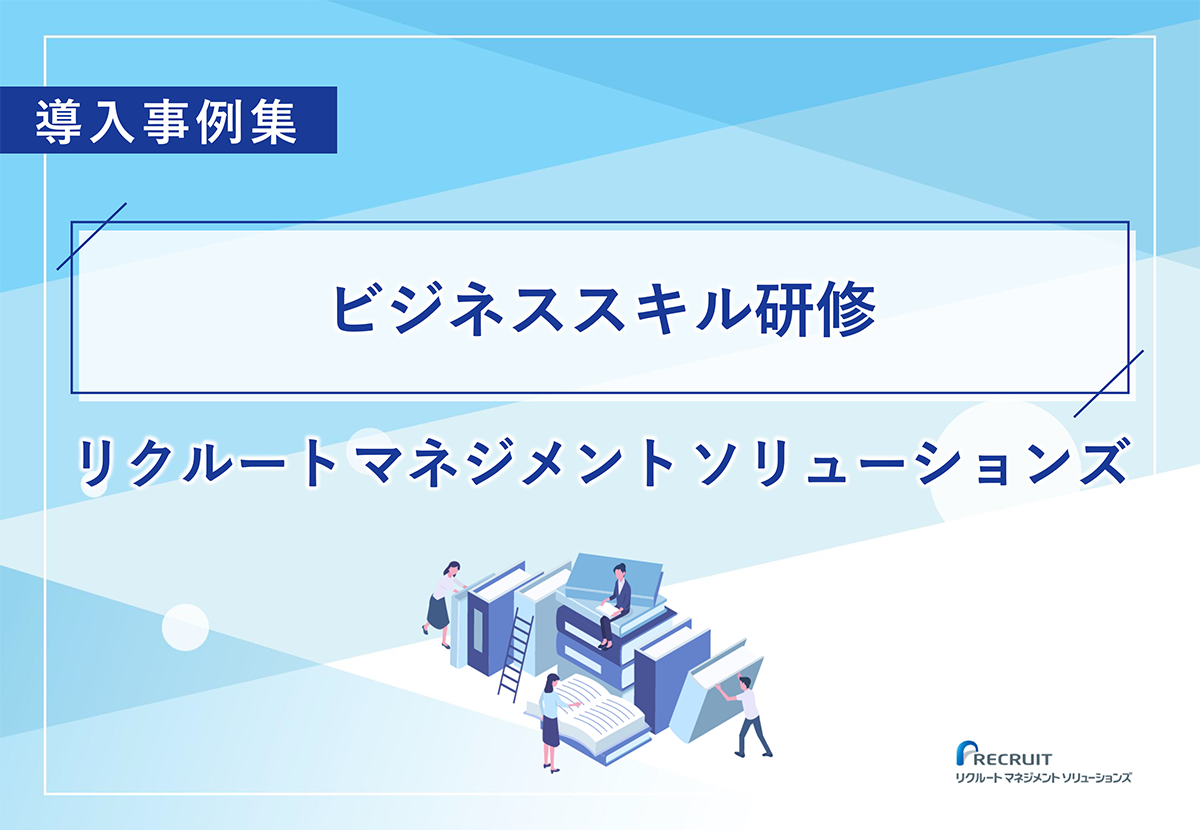









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての