用語集
OKRとは? 企業が使う目標管理の手法を、具体例を用いて解説
- 公開日:2021/04/06
- 更新日:2025/07/15
OKRとは
OKR(Objectives and Key Results)とは、目標設定や目標管理のためのフレームワークの1つです。「達成目標(Objectives)」と、目標のマイルストーンである「主要な成果(Key Results)」という2つの要素を設定し、高頻度で評価することで、効率的な目標達成が可能となる点が特徴といえます。
また、OKRで設定される目標は、企業・部署・個人で連携した内容になるところも特徴です。企業目標に基づいて部署目標や個人目標を設定するため、社員が一丸となって重要課題に取り組める点がメリットといえるでしょう。
人事制度設計と運用のポイントを解説
【無料動画セミナー】自社らしい人事制度の設計と運用定着のポイントはこちら
OKRの基本

OKRでは、まず企業全体の重要な「達成目標」と「主要な成果」を決定します。
次に企業の達成目標とリンクさせながら、チームのOKR、個人のOKRの順に細分化して設定していきます。
企業が求めている結果がチームの目標に、チームが求める結果が個人の目標となり、企業と個人の方向性が統一されます。これにより、スピーディーな目標達成が可能となります。
OKRが注目されている背景
OKRが注目されている背景としては、以下の3点が挙げられます。
- GoogleやIntelといった先駆的な企業での導入実績がある
- チーム間の連携やモチベーション維持に役立つ
- 目まぐるしく変化する市場ニーズにも対応しやすい
OKRはIntelの元会長兼CEOとして知られるアンディ・グローブが提唱して以来、Googleを始めとする有名企業に導入されているフレームワークです。従来はピーター・ドラッカーが提唱したMBOという目標管理制度が主流でしたが、OKRは組織と個人の目標が連動しており、生産性やモチベーションの向上に結びつきやすいことから注目を集めるようになりました。
「目標の設定→マイルストーンの設定→達成度の評価→再設定」のサイクルを早く回し、市場のニーズの変化に対応しやすいところも、注目を集めている理由といえるでしょう。
日本ではまだ身近ではないOKRの導入事例
日本ではまだ身近に感じられないOKRですが、OKRを導入して成果を上げている企業も存在します。ここでは、日本と世界で先駆的にOKRを取り入れた企業をご紹介します。
■GoogleのOKR導入事例
Googleは、OKRの導入に成功している企業の代表例です。インテルに勤めていたジョン・ドーアが2000年代初めGoogleにOKRを紹介したことから運用がスタートしました。
■メルカリ
株式会社メルカリは、まだ日本に情報が少なかった2015年にOKRを導入したことから、日本国内におけるOKRのパイオニアといわれています。
【コラム】ピアレビューとバリューにより機能する評価制度 メルカリ
リモートワークでもOKRの評価サイクルはしっかり回っている
■Chatwork
ビジネスコミュニケーションツール「チャットワーク」の提供元であるChatwork株式会社でも、2017年からOKRを導入しています。
OKR以外の人事評価に関する手法との違い
人事評価の手法としては、すでに多くの企業がMBOやKPIを用いた管理などを導入していますが、OKRは他の手法と何が違うのでしょうか。具体的にそれぞれの特徴と違いを見ていきましょう。
■MBOとOKRの違い
1954年にピーター・ドラッカーが提唱した「MBO(Management by Objectives and Self Control、目標による管理)」は、個人の自主性を尊重しながら達成すべき目標を設定し、業績向上を目指すマネジメント手法です。
■KPI管理とOKRの違い
「KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標)」は、最終目標を達成するために必要なプロセスが適切に実施されているかをチェックするための中間指標のことです。
定量的な目標を定める点でOKRと似ていますが、KPI管理では部署やプロジェクト単位で実現可能な数値を設定し、100%達成を目的とするのに対し、OKRは企業全体で高い目標を掲げ、主要な成果では60~70%の達成率を目指します。
■ノーレーティングとOKRの違い
評価しないという考え方の「ノーレーティング(No Rating)」は、社員を点数やランク付けしないという新しい人事評価です。対話を重視し、目標設定やフィードバックする点は、OKRと共通しています。
しかし、ノーレーティングは上司が部下の仕事ぶりをリアルタイムで把握するために運用される一方で、OKRは報酬などの評価には結びつけず、組織の目標達成を目的とする点で大きく異なります。
■その他の人事評価についての手法
上記のほか、人事評価制度を補完する手法としては「コンピテンシー評価」や「360度評価」などが代表的です。
「コンピテンシー評価」は、業績を上げるための行動特性(コンピテンシー)を基準として、個人の能力を評価する手法です。目標達成のための行動を分析し明確化するため、人事評価だけでなく人材育成にも活用できるというメリットがあります。
「360度評価」は、上司や同僚、部下などさまざまな立場にある複数の人が1人の社員を評価するものです。上司だけの評価よりも多面的な判断になるため、評価に対して本人も納得しやすく、企業への信頼も高まります。
OKRを導入するメリット

OKRを導入することは目標達成のため以外にも、組織にとってさまざまなメリットがあります。
■最重要課題を明確にして共有できる
明確な目標を全員で共有することにより、目的意識と連帯感が生まれ、重要課題に協力して取り組むチームづくりができます。
■仕事の優先順位づけと生産性の向上
優先事項が明らかになることで、重要でない課題との区別ができます。今やるべき仕事に集中できる環境が整うため、社内全体で生産性の向上につながります。
■明確な社内コミュニケーション
OKRを通じて同じ目標と期限に向かって仕事を進めていくため、OKRが社内全体の共通言語となり、役職や部署に関係ないフラットなコミュニケーションが取りやすくなります。
■社員のやる気やエンゲージメントの向上
組織の目標と個人の目標が連動しているため、自分の仕事が会社にどのように影響するのかが分かりやすく、仕事へのやる気やエンゲージメントの向上が期待できます。
OKRの導入・運用方法
OKRを導入する際は、企業全体の目標を設定してから、部署や個人の目標に落とし込んでいくという手順を踏むのが一般的です。具体的な運用の流れを4つのステップに分けてご紹介します。
企業全体のOKRを設定する
はじめに、企業全体としての達成目標(Objectives)と主要な成果(Key Results)を設定します。企業全体のOKRの設定は経営陣などの少数で行うことが多いですが、現場の意見をOKRに反映するためにも、事前に社員や幹部クラスにしっかりとヒアリングを行っておくとよいでしょう。トップダウンではなくボトムアップのOKRを設定することで、企業全体で同じ目標を共有する意識やモチベーションも生まれやすくなります。
なお企業の達成目標は、一般的に「挑戦的なもの」に設定します。あえて達成が難しい目標を設定することで、メンバーの想像力やモチベーションを刺激するきっかけにもなるでしょう。
部署・チームのOKRを設定する
企業のOKRを設定したら、その内容を踏まえて各部署やチームのOKRを設定します。例えば「顧客獲得に向けて、自社史上最もお客様からの反響が大きい新ブランドを立ち上げる」という企業目標を立てた場合、各部署の得意分野を踏まえて「半年以内に業界をリードするブランドチームを立ち上げる」「お客様に褒められるカスタマーサービスをつくる」といった定性的なO(目標)を設定します。さらにKR(主要な成果)で定量的な指針を立てることで、「企業目標を達成するために部署やチームは何をすべきか」を把握しやすくします。
個人のOKRを設定する
企業のOKRと部署・チームのOKRを設定したら、従業員個人にもOKRを設定してもらいます。経営陣からの一方的な目標にならないよう、必要に応じて上司やメンターがサポートし、お互いに納得できる内容に調整することが大切です。
期間終了後に評価を行う
企業、部署、個人のOKRをそれぞれ設定したら、定期的に目標と成果に対して評価を行います。評価のタイミングは企業によって異なりますが、1カ月~四半期ごとのスパンが好ましいでしょう。
OKRの効果の設定方法
OKRには多くのメリットがありますが、最大限の効果を発揮するためには「達成目標(Objectives)」と「主要な成果(Key Results)」を正しく設定することが大切です。
■「達成目標(Objectives)」の設定
「達成目標」では、最初に設定された企業の目標とリンクさせながら、チームや個人の目標を決めていきます。
【達成目標(Objectives)の設定条件】
・四半期など短期間での達成を目指す
・60~70%程度の達成率を見込める目標にする
・企業にとって最重要な課題に取り組む
・チームや個人の目標は企業の達成目標とリンクさせる
達成目標は利益や業績を上げる以外にも、顧客満足度を高める、理想を実現するなど、さまざまな目標が考えられます。最重要で取り組むべき目標を絞り込みましょう。
■「主要な成果(Key Results)」の設定
達成目標に対して3~5個の「主要な成果(Key Results)」を設定します。
【主要な成果(Key Results)の設定条件】
・定量的に計測できる
・難しいが実現可能なもの
例えば、達成目標が「1カ月の売上を過去最高にする」とした場合、主要な成果は「顧客単価を500円アップさせる」「新規購入者のリピート率を20%増加させる」「新商品を10個企画し販売する」など、具体的な数値で結果が示せるものにします。
OKRを効果的に運用する際のポイント
「OKRを導入したけれど、上手く運用できなかった」とならないためにも、OKRを運用するうえで気をつけたいポイントを押さえておきましょう。
■目標設定から結果までを常に公開する
OKRでは、透明性が重要になります。すべての目標から進捗状況、結果までを公開し、経営陣や社員など社内の誰もがアクセスして見られる状態にしておきましょう。
■目標を高く設定し、社員のモチベーションを高める
到達できそうなレベルより少し上の「野心的(ストレッチ)目標」を設定することで、挑戦する意欲やチームで協力して乗り越えようとする気持ちが高まります。
■処遇や昇格・昇進への直接の連動・活用は避ける
OKRでは高い目標を掲げることが大切です。しかし、OKRを評価制度に直結させると、目標未達となり昇格・昇進に響くことを恐れ、個人が設定する目標のレベルが低くなる可能性があります。OKRを評価制度に影響させることは避けた方がよいでしょう。
■定期的にミーティングやフィードバックをする
期限の終わりに成果を確認するのではなく、1週間などの短いスパンで日常的にOKRの進捗状況の確認をし、成果を報告します。失敗や間に合わないことを責めるのではなく、どうしたら目標達成できるかを話し合い、トライアンドエラーを繰り返しながら目標到達を目指していくことが重要です。
職種別のOKRの具体例
最後に、OKRを設定する時のポイントを職種別にまとめました。目標(O)と達成指標(KR)の具体例も併せてご紹介します。
営業
営業職の役目は、顧客との接点を通じて企業の売上、組織全体の成長につなげることです。よってO(Objectives)は、「成長市場での存在感を高める」「契約更新率を向上させる」といった、顧客獲得に絡んだ目標にするとよいでしょう。KRに具体的な目標数値を入れることで業務の指針が明白になり、パフォーマンスも上がりやすくなります。
営業職のOKRの例
■Objective
新規顧客を積極的に開拓し、売上拡大を目指す
■Key Results
四半期で新規顧客を15社獲得する
新規商談の月間平均数を20件に増やす
マーケティング
マーケティング職は「自社の商品やサービスを必要としている人に知ってもらい、選んでもらう仕組みを作ること」を担うポジションです。そのためOKRにおいても、「誰にどう伝えるか」「どうやって購買意欲を高めるか」といった役割に直結するOKRを設定するとよいでしょう。
マーケティング職のOKR例
■Objective
ターゲット市場でのブランド認知を高める
■Key Results
月間WEBサイト訪問者数を50%増加させる
イベント後のアンケートで「ブランドを知っていた」と回答する割合を70%にする
人事
人事は企業において、採用活動や人材育成、組織開発、社員満足度の向上などを担うポジションです。よってOKRにおいても、改善を図りたい企業課題に対して設定を行います。
社員満足度に関するOKRの例
■Objective
社員満足度を向上させ、離職率を低下させる
■Key Results
離職率を前年比で10%減少させる
社員の福利厚生利用率を20%向上させる
製造部門
製造部門におけるOKRは、生産効率の向上、品質の改善、安全性の強化、コスト削減など、製造プロセスや業務全般の最適化を目指すものが多いです。
製造部門のOKRの例
■Objective
製品品質を向上させ、顧客満足度を高める
■Key Results
生産ラインでの不良品発生率を2%以下にする
品質チェックの精度を向上させるための研修受講率100%を達成する
おわりに
OKRはIT業界だけでなく、BMWやサムスン、ディズニーなどの企業でも実施されており、医療や教育など多種多様な分野に広がっています。OKRについて正しい運用方法を身につけ、組織の目標達成に活用してみてはいかがでしょうか。
目標管理については、以下の研修で詳しく解説しています。
目標や評価を軸にマネジメントの質を高め、個人の成長と組織の成果創出を実現する
評価者研修・目標設定研修
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



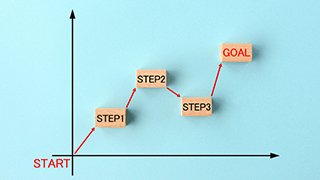













 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての